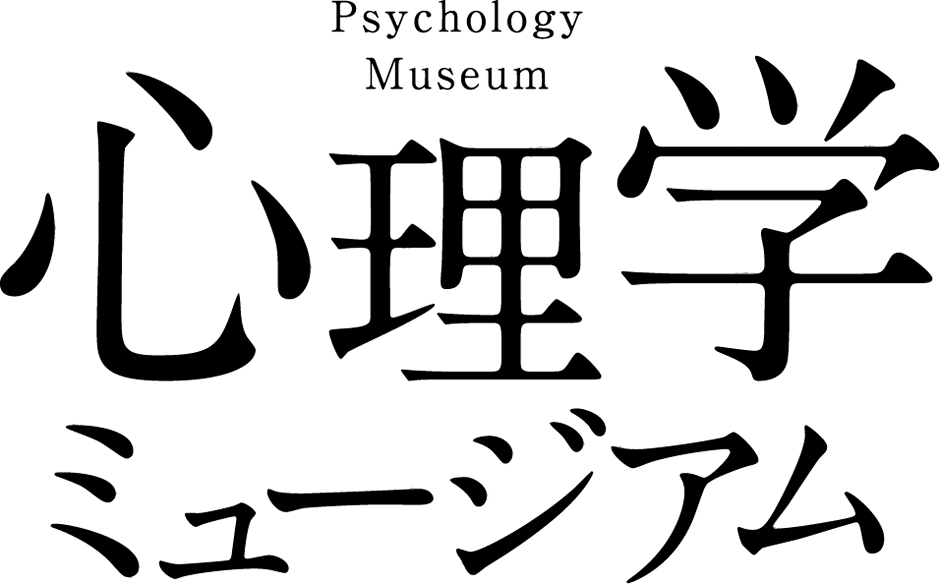辻 敬一郎先生
動画は抜粋です。インタビュー全文は下記からご覧ください。
辻 敬一郎先生の略歴
・名古屋大学、視空間知覚、動物実験、視覚的陥穴、スンクス
・1959年、名古屋大学文学部卒業。1964年、同大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程単位取得退学。文学部では横瀬善正教授、教育学研究科では續有恒教授の指導を受け、1979年「奥行視に関する実験的研究」により文学博士。
・名古屋大学文学部教授・同副総長、中京大学心理学部教授、日本心理学会理事長などを歴任。実験・比較心理学を専攻。
・インタビュウでは、平面図形の奥行視に始まり、ラットの迷路探索行動、ヒヨコ・サルの視覚的陥穴反応、スンクスのキャラヴァンやドメスティケーション(家畜化)過程の行動変性、乳幼児の落差知覚・高所恐怖など、幅広く豊富な研究歴を聴かせていただきました。
日時:2015年9月24日(木)
場所:日本心理学会第79回大会会場(名古屋国際会議場)
インタビュアー:小泉晋一(共栄大学)、高砂美樹(東京国際大学)
場所:日本心理学会第79回大会会場(名古屋国際会議場)
§ 専攻決定以前
インタビュアー(以下、「イン」と略) 大学入学当時のことから伺いましょうか
辻 名古屋大学入学が1955年4月です。終戦から10年で世情は安定してきましたが、周囲にはまだ困窮生活を送っている仲間が少なくありませんでした。闇市で血を売って授業に出てくる同級生や身内を戦禍で失って天涯孤独になった友人がいました。
教育制度改革に伴って、高等教育は一般教育(教養課程)と専門教育(専門課程)を二本柱とするようになりました。入学すると最初の2年が教養課程で、その後に専門課程に進むという方式でした。
一般教育については、後に評価が分かれるのですが、個々の学問分野やその体系にふれることができたという点で貴重な機会になったと思います。というのも、そのカリキュラムが、心理学・政治学・物理学というように分野を単位にした授業で構成されていたからです。つまり「学問分野型」(discipline-oriented)でした。しかも、学部・専攻の如何にかかわらず共通に履修要件が定められていたのもよかったと思います。人文・社会・自然の3系列それぞれ12単位、外国語8単位、保健体育4単位を取らなくてはならず、さらに文学部志望者には外国語3科目16単位が課せられていました。このようなハードな条件でしたが、こういう形で「専攻に非ざる専門」に触れる機会があったことで学生の「教養」が培われたと思っています。
先ほど申しませんでしたが、新制大学発足にあたっては、旧制の高等学校・高等専門学校が旧来の大学に併合されました。名大の場合、名古屋帝国大学と第八高等学校・岡崎高等師範学校が合体したのでした。縁あって入学から10年後の1964年4月、教養部に職を得るのですが、「一般教育としての心理学とはなにか」を模索するうち、専攻学生以外を対象にする授業がすなわち一般教育なのだと考えるようになりました。そうならば、概論を講じる必要もなかろうと割り切り、1セメスターを通して「学習心理学」だけを講じたり、専門書を抜粋したテキストを演習に用いたりしました。これが予想以上に好評で、「初めて大学らしい授業だった」「心理学の性格にふれた」などと言ってくれました。
話を元に戻しますと、入学して1年ほど経って、それまで自分の視界になかった心理学に出逢うことになります。
イン その前、篠山(ささやま)から名古屋大学文学部を志望されたのはどういう理由だったのでしょうか?
辻 出身高校は「兵庫県立篠山高等学校」(現在の篠山鳳鳴高等学校)です。伝統学校ですが、当時のクラスでは伝統に縛られない自由な雰囲気があり、生徒がそれぞれ個性を発揮する一方、社会思想や哲学に対する憧れから背伸びした議論をしていました。私自身は、中学時代から天文気象に興味があって部活に熱中し、高校でも理化部に所属して活動を続けていましたから、理学部進学が念頭にありましたし、周囲でもそう思われていたようです。しかし、高校在学中に社会科学への関心が芽生え、受験の直前まで天文学か社会学かの選択に迷っていました。
文学部か理学部かの選択肢など考えられないと思われるかもしれませんが、かつていくつかの大学には文理学部がありました。扱う事象が人文か自然かを問わず基礎科学を担う組織ですから、文系・理系の二分法に比べれば奇妙ではないはずです。
クラス担任が物理担当の先生だったこともあって理学部進学を勧めてもらいましたが、家族は天文学に進むことに賛成ではなかったようです。幼いころ病弱だった私の健康を心配してくれたのでしょうが、祖母などは「人様が寝ているときに起きているような仕事」と反対していたようです。
自分の中では、社会科学に“揺さぶられる”ような気分が強まり、地域社会の閉鎖性や住民の意識を歴史社会学的観点で解き明かすという問題意識が膨らんでいきました。それによって閉塞感から解き放たれるという期待が漠然とあったのかもしれません。名大には理論社会学の本田喜代治教授とジンメル研究者の阿閉(あとじ)吉男(よしお)助教授らがおられました。父の親友の大学教授が名大を勧めてくださいました。じつは、国民学校2年の夏に篠山に疎開するまで名古屋に住んでいましたし、叔父の家に下宿できるということもありました。もしかすると、この一件には親父の画策があったのかもしれませんね。
§ 心理学との出逢い
イン 心理学ではなく社会学志望だったのですね?
辻 入学の時点では心理学の存在すら知りませんでした。一般教育の授業科目に心理学があることを知っても関心がなく、受講しませんでした。出逢いはまったくの偶然に訪れました。偶々、自分が受けていた授業が休講になって教室で早弁していたとき、隣室から講義が聞こえてきました。八高(旧制の第八高等学校)時代のおんぼろ校舎ですから音が筒抜けです。その授業、村上英治助教授担当の心理学講義でした。声の大きなことでも知られた先生ですから壁越しでもノートが取れるほどでしたが、たしか知覚の話だったと記憶しています。
これがきっかけになり、自分で心理学書を求めて読んでみました。大脇義一先生の『心理学概論』(培風館)で、意識・行動の実験科学という点が新鮮でした。進路を決める際の選択肢にあった理学部志向が甦ってきて、さらに心理実験法も独習しました。並行して『物理実験法』を読んだのもプラスになったようです。
村上先生は後々いつも「俺の影響で辻は心理に替わった」と言われましたが、先生から単位はいただいていないのです。しかし、聴講、正しくは盗聴して専攻を鞍替えしたのですから大きな影響を与えていただいたのはその通りで、学恩を忘れることができません。
志望の社会学については、勉強していくうちに自分との相性に疑問を抱くようになりました。心理学の方法論に魅かれるのと逆に、社会学の方法論に違和感めいたものがありました。ドグマティックではないものの、自分にはなじまないという感じだったと思います。
§ 心理学教室
辻 当時、文学部心理学講座は横瀬善正教授・内山道明講師に蛭川栄・市川典義両助手という教官構成で、横瀬先生が私の指導教官でした。ただ先生は健康が優れず授業を休まれることがしばしばあり、それを補うように、内山先生のリーダーシップの下スタッフ・院生・学部生で活発な議論が行われていました。総勢20名ほどのこじんまりした教室で、学部生は学年2~3名、そこに他大学からの編入者があるという状態でした。こうした雰囲気の中で日常的に学んだものが授業以上に大きかったというのが実感です。
教室の一員になると、さっそく先輩から被験者を頼まれます。断るわけにもいきませんから、授業以外は専ら被験者を務める時間でしたが、この経験も心理学実験について考える上にも、あるいはまた自分の課題研究を進めるのにもずいぶん役立ちました。
イン そのあたりをもうすこしご説明いただけませんか?
辻 教室では横瀬先生が提唱した視覚場の理論、通称「横瀬の場」の実証研究が進められていました。横瀬先生は、色と形という視覚の二大テーマのうち形の研究が立ち遅れていることを痛感され、輪郭を構成する線分を荷電体とみなし場の概念を導入して形の問題に迫るという独創的な構想を立てられ、教室ではその実証研究が鋭意進められていました。その姿に接するうち、新参の私たちもその“チーム”の一員となっていきました。
今にして想えば、1950年代半ばから60年代にかけて、我が国の心理学界は活況を呈していました。すくなくとも私が接した基礎心理学領域では、大学・教室ごとに学風が違っていて、立場や理論をめぐる論争が盛んでした。現在のような専門別学会や目的別協会が組織されている状況とはまったく違い、当時は日本心理学会のほかには、発足まもない教育心理学会と応用心理学会しかなかったと記憶しています。いずれにせよ、学会大会に参加するのは一大事でした。知覚研究領域では、横瀬の場理論のほか、東北大学の本川弘一教授(生理学)の「網膜誘導場」や東京教育大学の小保内虎夫教授らによる「感応理論」が提唱され、それぞれ検証実験が行われていて、大会は成果発表の大舞台だったわけです。図表を手書きした掛図を筒状にして担いで会場に向かう姿は戦に臨む武将たちを髣髴とさせるものがありました。私たちはさながら下級武士としてそれに従ったのでした。
イン 卒論のテーマは?]
辻 こういう教室のムードに刺激され、自分も実験を始めたいと考えるようになりました。学部に進んでまもない時期です。心理学に鞍替えした動機が心という現象のおもしろさにあったわけではなく、むしろその研究方法に魅かれたのでしたから、実験法が適用できるならばどんなテーマでもよかったわけですが、視空間知覚・奥行視をテーマに選びました。
心理学書には、奥行視の手がかりとなりうる要因が羅列されているだけで、要因の発生や相互関係など肝腎なことは書かれていませんでした。生意気にも、そのような学問状況に不満を感じたものです。それがこのテーマに取り組む動機で、場理論的アプローチが有望だという気がしていました。
指導教授の横瀬先生も賛成してくださいました。ただ、出発点で先生と進め方について考えの違いがありました。先生は刺激に立体を用いて、その周囲の場の強さを測定するものと期待されていたようですが、私の念頭には平面図形を刺激にすることしかありませんでした。それと言うのも、外界はすべて二次元の網膜像に還元されて再び三次に復元されるわけだから二次元から出発していいのではないか、しかも平面図形の場合は生理解剖的諸要因の関与がなく単純な条件で現象分析ができるのも利点だろう、とそう考えたのです。卒論では種々の図形についてデータを収集し、まずまず計画どおり、視えの遠近と場強の対応関係を明らかにすることができました。これが卒業研究です。
§ 教育学研究科教育心理学専攻
イン 大学院は教育学研究科だったのですね?
辻 そうです。講座化されはしたもののまだ文学研究科に心理学専攻が設置されていませんでした。一方、新制度になって発足した教育学部には教育心理学専攻の修士・博士課程が設けられていて、教室の先輩も教育学研究科教育心理学専攻に進んでいました。
教育心理学専攻は、社会・職業、人格・発達、学習・教育、数理・統計の4講座編成でした。学部では知覚心理学しか学んでいませんでしたので、初めて諸領域から成る心理学の“実像”にふれる機会であり、どの授業も新鮮でした。ですから課程修了要件の単位数をはるかに超えて履修しました。
大学院に入っても、実験や作業は相変わらず文学部の心理学教室で続けていましたから、その点では学部時代の延長でした。変わったのは指導教官です。横瀬先生は教育学研究科専任ではないため指導教官になっていただけず、新たに續有恒教授にお願いすることになりました。續先生は、『心理学研究』に掲載された「近さについて」の論文にあるように知覚研究を手がけておられましたが、新制度になって東北大学教育学部に赴任されたのち名大に来られました。
ちょっと脱線しますが、新制度の教育学部は教育学・教育心理学の研究を行うという趣旨で旧制帝国大学など数校に設置されたもので、旧師範学校の併合によって発足した初等中等教育教員養成系の学部(学芸学部)とは性格を異にしていました。新しい組織ということもあって、先生方はこの新設学部の使命や将来を非常に強く意識されていたようで、今にして思えば、教育心理学が最も色濃く出ていた時期でした。續先生のようにそれまでの研究歴から一転して新領域の先導役を担うという立場に転向された先生方が他にもおられたのではないでしょうか。
續先生が私の指導教官になってくださることは申し合わされていたようです。それまでの経緯もあって横瀬先生に配慮なさっていたとみえ、修論研究について細かいことはほとんどおっしゃいませんでした。演習の時間、最新の実験データを出しても、それについてはなんのコメントも出されません。院生仲間から実験式の当てはめがよくないなどの批判が出るのを聴いておられ、議論が終わるころになって、「それで?」とポツンと言われるのです。強烈な一撃でしたね。この寸評によって、二手・三手先を見通す態度の重要性を学びました。
§ 当時の学問状況
辻 ここで当時の学術状況を振り返ってみますと、学史を飾った学派運動が終息し、それぞれの学派に連なる人たちが自説の支えとしていた対象領域が、ゲシュタルト学派なら知覚、行動主義なら学習という具合にそれぞれ継承されていくわけですね。学派運動を経たのち領域分化が進むという経過でした。
高砂さんが精しくご存知でしょうが、日本で心理生理学が芽生え始めるのもこの時期でした。生体電気増幅装置が心理学教室にも導入されはじめ、EEG・ECG・EMGなどの同時記録により心理現象との対応が追究されていました。名大文学部に脳波計が導入されたのがたしか1959年だったと思います。私が修士1年でしたが、研究実績のある先輩格の教室を見学してくるように横瀬先生から命じられ、1週間ほど東京に滞在して東京学芸大学・東大教育学部・東京教育大学などを訪ねたことを憶えています。当時、日大では山岡淳先生が中心で精力的に研究を進めておられ、そのときは日程の都合で見学できずじまいでしたが、先生には以来、機会あるごとにご指導をいただきました。
横瀬先生は「脳波研究が進むと知覚の内省報告など無用になるし、閾値測定も波形をみれば可能になる」と仰言って、その成果に期待しておられましたが、学界では、脳活動の研究への期待が大きかった時期です。
他方、ゲシュタルト学派の流れを汲む知覚研究が支配的だった日本の実験心理学界に、学習研究が入ってきました。そして、知覚研究と学習研究が実験心理学の二本柱となり、教室ごとにそのいずれかを担って独自の学風を築いていきました。学派運動の時代は終わりましたが、実験心理学も理論志向的ではありました。先ほど紹介した知覚領域における論争がその例ですが、私自身、そういう風潮の中でブラックボックスの中身をめぐる思考を鍛えられたように思います。
§ 博士課程における転向
イン 博士課程に進まれるのですね?
辻 そうです。博士課程と言っても、当時の院生にとって学位は縁遠いものでした。研究成果が蓄積され学界で評価されて初めて論文提出の許しが出るので、ふつう厄歳ちかくなって準備を始めたものです。博士学位のことを「足の裏の米粒」と称していました。「取っても食えないが、取らなければ気持ちが悪い」という自虐めいた表現です。学位はあくまで結果であってそれ自体を目的とした活動など考えられませんでした。ちなみに私の場合、学位取得は1979年、42歳でした。
イン 後期に行かれた頃は比較的ウェルカムな感じですか?
辻 いつ頃からか旧来の修士課程・博士課程を博士前期課程・博士後期課程と呼ぶようになりましたね。少なくとも私たちのころ修士課程と博士課程は連続していませんでした。妙な喩えですが、現在の両課程を同じ建物の1階と2階とすれば、当時は別棟にあったというほどの違いではないでしょうか。修士課程から博士課程に進む場合、まず“お伺い”を立てるのが常識とされ、とうてい「行きます」「受けます」の雰囲気ではありませんでした。
卒論では視えの遠近しか扱えなかったのに対し、修士研究では、観察者から図形の面までの視えの距離を測定することができるようになり、場強との対応をいっそう精細に実証することができました。また、視えの大きさ-距離関係も明らかになり、大きさの恒常との現象的類似も実証できました。そういうことで修士論文を通してもらいました。しかし、指導教官には「それで?」と言われつづけてきましたから、博士課程への進学については自信がありませんでしたが、結局3名進学が許されました。うち2名が教育学部出身、文学部からは私ひとりでした。
イン 博士課程でも續先生が指導教官だったのですか?
辻 引き続き續先生が指導教官を引き受けてくださいました。基本的には修士論文で示した方向に沿った展開を考えていました。それまで扱ったよりも大規模な空間について、その視えの距離と場強との関係式を求め、その所見から視空間構造を明らかにしようという構想です。
ところが、予期しなかった壁に突き当たります。ひとつは測定手続きに関する問題です。使用中の装置では刺激図形(奥行視図形)と視えの距離を測る枠組とは独立であることを前提にしています。量推定法など他の手続きに比べて判断も容易で、すくなくともそれまでのデータ収集にあたっては問題を生じていなかったのですが、街路の写真を呈示すると、モノサシであるはずの枠組がその空間に影響されてしまうのです。
もうひとつ、こちらは理論的な問題でした。平面図形の奥行視では、画像的手がかりしか作用しませんね。眼球調節・輻輳・網膜非対応・運動視差などの手がかりはすべて剥奪されているわけです。操作・移動などの行動とは切り離された視空間の研究にどのような意義があるのかと自問すると不安が募りました。奥行視の場理論的研究としての意義づけは可能かもしれませんが、行動論的知覚研究としては疑問が残りました。
進学を認めていただきながら、ここで袋小路に入ります。一転してそれまでの勢いがなくなったことが周囲に判ったようです。今にして想えば、意欲減退の典型だったのではないでしょうか。
イン その期間どう過ごされたのですか?
辻 気分転換というわけでもありませんが、この時期の“埋草”となったのが、脳波に関する共同研究でした。テーマは「視覚現象と脳波の関係」です。視覚現象は目を開けた状態で起きるのにそうするとα波が消えてしまいます。当時はα波のブロッキングが唯一の指標でしたから、α波が豊富に出現している状態でなければ反応が明らかにできません。というわけで残像や心像のように閉眼条件で測定できるものに限られていました。
その後、1960年代に入りますと事象関連電位を指標として研究の幅が広がりますが、私自身は心理生理学とは距離を置くようになります。主な理由は、心理事象の背後にあるメカニズムを心理モデルの形で探らずに生理過程に還元するというアプローチに魅力を感じなくなったからです。ここで浮かび上がってきたのが意識や行動の「発生」的研究の方向性です。発生を論じるには心理と生理との相関ではなく、時間軸上の行動と行動との関係をとらえることが必要です。ここに来て機構論から発生論へと、またしても“転向”することになりました。1960年代後半のことです。
挫折によって空虚な時期を過ごすことになりますが、そこを埋めようとする力が自分の中で問題意識の“再体制化”を生み出したとも言えそうです。
§ 動物行動研究
イン 動物行動研究に手を着けられたのには、いつ、どういうきっかけがあったのでしょうか?
辻 1963年の夏、短期研修団の一員として2か月間アメリカに滞在しました。その間に国内各地1万2千キロを車でめぐったのですが、途中は大学の寮に泊まり施設見学をしました。ボストンではハーヴァードの心理学教室を訪ねる機会がありました。なにしろ知覚研究以外の事情には疎かったものですからスティーヴンス教授の名前しか知りません。あいにく先生が不在で、帰ろうとしていましたらスキナーの実験室を見て行くように言われ、院生に引き合わせてくれました。案内された実験室にはスキナー・ボックスがズラッと並び、隣室の累積記録装置に打ち出されていましたが、その光景に圧倒されました。被験体はハトだったのでしょうが、ボックスには蓋がしてあってその姿が見えません。どこから動物を見るのか? この素朴な疑問を投げかけると、返ってきたのは「私たちは動物を見ない、データを読むのだ」という答でした。動物実験にまったく無知だったせいもあり、この言葉を感心して聞いたのでした。
イン それが動物実験のきっかけですか?
辻 このことがあって1年後ですね。1964年4月、教養部心理学教室に文部技官教務員という職で採用されました。阿部芳(よし)甫(すけ)教授と村上英治助教授がおられました。村上先生のことは私の転専攻に関連してすこしお話しました。阿部先生は東大では桑田芳蔵先生の門下で卒業後は体育研究所技官を経て旧制の第八高等学校に赴任され、新制の名大教養部におられました。先生は1年後に停年を迎えられるという時期でしたが、動物実験のきっかけを与えていただきました。
教務員の仕事は、先生方の講義のための掛図の作成、実習授業のインストラクション、書籍・備品の発注、会議の記録作成などなどでしたが、両先生とも私の研究環境について細かく気を遣ってくださったので、落ち着いて勉強ができました。そんなある日、格納室の備品を整理していて、T型迷路と木製の飼育箱を見つけました。阿部先生が以前に使用されたもので、永年そのまま放置されていたのでした。
それを見て、「動物実験もわるくないな」と、そう思ったとき、あのスキナーの実験室の光景が甦りました。彼らの行動分析では動物を直接観察することはない。ならば、ゼロから出発する私は徹底した観察から出発してみよう、そう思ったのです。テーマの選択にも偶然がはたらきました。
ラットはある精神科病院で譲り受けました。その病院でリハビリ作業のひとつとして維持繁殖していた近交系10頭です。偶々眼にしたのが潜在学習に関するSeward論文でした。読んでみて「潜在的」とされる点に疑問が湧き、T型迷路内で被験体が示す行動を逐一観察することになりました。ただ、当時まだ市販のビデオがありませんでした。8ミリ・シネですと一巻4~5分の映像しか収められません。1頭あたり30分、10頭、しかもそれを何日も撮るというわけにはいきません。コマ落としにすると間の行動が抜け落ちてしまいます。眼に留まったのがテープレコーダでした。それに行動観察を逐一吹きこみ、後に再生して分析することにしました。行動を“撮る”のではなく“録る”という方法です。
この行動記録法の場合、あらかじめ個々の行動を記号化した目録を作成しようと考えましたが、実施してみるとむしろ“生”の言葉のままがいいと判りました。こうして行動のシーケンスをとらえると、報酬が導入されていない間にも環境探索の様相に明らかな変化がみられました。その所見をまとめた「迷路探索行動の実験的分析」が最初の動物実験論文です。
当初やむをえず採用した行動収録法でしたが、こうして観察経験を重ねるうち自分の「観察眼」が磨かれていき、画像の収録・解析技術が進んでも欠かせない、確かな技法として定着しました。画像収録・解析技術が進んだのちも私にはこの行動描写が欠かせません。ですから動物実験を始める人にはこの“実況放送”から始めてもらっていましたが、ビデオが普及するとそれで済ませればいいと考える人が多くなりました。残念なことです。
こうして、ヒトを対象にした知覚研究から動物を対象とする行動研究へとシフトすることになりました。今回またしても転向です。
イン 有難うございました。予定した時間が来てしまいましたので、続きは日を改めて伺うことにしたいと思います
【第2回インタビュウ】
日本心理学会 心理学者 オーラルヒストリー
日時:2016年2月19日(金)
場所:公益社団法人日本心理学会 事務局
インタビュイー:辻 敬一郎先生
インタビュアー:高砂 美樹(東京国際大学)、小泉晋一(共栄大学)、吉村 浩一(法政大学)
イン 前回は時間が限られて途中になってしまいましたので、本日あらためて時間を設けました。よろしくお願いいたします。
前回は時間を大幅超過した上、途中までしかお話できずに終わってしまいました。こうして再びセッティングしていただくことになりご迷惑をおかけします。今回は続きをお話したいと思います。こちらこそよろしくお願いいたします。
§ 教養部から文学部に配置換
イン 名大で文学部に移られますね?
辻 1974年4月、文学部心理学第二講座助教授に配置換になります。教養部にはちょうど10年間在籍しました。教務員として採用されたとき教官2名だった心理学教室ですが、この間に助手1名を含み5名の教官を擁するまでになりました。
当時、教養部はいくつかの重大な問題に直面していました。とりわけ70年代の学園闘争は忘れられません。名大の場合、終わってみればさほど大きな改革とはなりませんでしたが、若手教官の一人として得た経験は大きなものでした。一般教育と専門教育の関係について問い続けた末に、前回申したように「専攻に非ざる専門は教養」という見解にたどりつきました。その後、平成に入ってカリキュラム大綱化や組織改編により一般教育が大きく縮小あるいは変貌してしまったことを残念に思ってきましたし、その想いは大学を離れた今も変わりません。
文学部に移ることになったのは、心理学第二講座増設にともなう人事です。永年の構想が実現して第二講座設置が認可されたのは確か1971年だったと思います。それまでは意識、とりわけ知覚の研究を軸に運営されてきた第一講座に対して、新たに行動研究を推進する目的をもつ講座として発足しました。そして、初代教授に前田恒先生が着任され、2年後に私が助教授として加わりました。第一講座が横瀬教授・内山助教授、第二講座が前田教授と私、助手3名を加えスタッフ7名でした。講座は二つでも一体的な教室運営を行うというのが当時の基本方針でした。後年、私が退職するまでこの方針が堅持され、意識・行動の統合をめざすという課題を掲げて研究を進めることができました。
有難いことに、第二講座設置後まもなく動物実験施設の申請が通りました。先に着任しておられた前田教授の依頼を承け、文献を参照し動物管理・実験の経験も加えて設計したのが「心理学実験動物舎」です。途中で事務局から何度か図面の描き直しを求められ、そのたびに身を切る思いでしたが、管理・飼育繁殖・実験・解析に必要な最小の作業スペースを確保できました。そこには自分の団地住まいの“知恵”も生かされました。
§ 行動論的知覚研究
辻 卒研に始まった視空間知覚のテーマについては、前回お話したような問題に遭遇して一時期すこし距離をおいていました。しかし、60年代半ば動物行動を手がけるようになったのをきっかけに、そのアプローチや基本構想に変化が生じました。平面図形の奥行視は、視空間意識の中では対象操作や移動などの行動と無縁な、いわば背景的・画像的空間であり、その成立に関与する手がかりも限定されたものでしかありません。視覚場理論の枠組に据えたアプローチとしてはそれなりに意義のあるものでしたが、あの挫折以来、満足できないものを感じていました。そこに偶然が起きます。
NHK教育テレビ番組「高校理科:生物」のうち動物行動を扱う5コマ分の監修と出演の依頼が来ました。そのシリーズの一つ、生得的行動の紹介にWalk,R.D & Gibson,E.J.の「ヴィジュアル・クリフ」(視覚的断崖;visual cliff)実験を取り上げてデモをしました。番組そのものはうまく行きましたが、この装置を使って彼らが書いた論文の内容、特に装置の構造や被験体の選定には重大な難点があることに気づきました。この頃、同じように視空間知覚を研究テーマにしていた林部敬吉さん(後の静岡大学教授)と原政敏さん(後の朝日大学教授)と輪読会をやっていて、私たちの意見をまとめて彼らに送りました。今のようにメイルでというわけにはいかず、タイプで打ったコメントを郵送したのですが、返事を貰えませんでした。
それならばというわけで、独自に考案したのが「ヴィジュアル・ピットフォール」(視覚的陥穴:visual pitfall)です。この装置は、光学的落差を設けた点ではクリフと基本的に同じですが、クリフ実験が落差の有無に対する選好を反応としてとらえるのに対し、移動の自由度を高めて被験体の種に応じて落差の配置を変えることができるようにした点など改良を施した装置・技法です。
イン 被験体はヒヨコだったのですか?
辻 最初のシリーズではニワトリのヒナを対象にしました。先行研究に対する批判だったのですが、彼らの場合、ラットのような非視覚性動物を被験体としているのですね。その点、ニワトリはPortmann,A.の言う「巣立つもの」(離巣性)で、孵化時点で視覚にもとづく自立的な移動・採餌が可能です。落差への対処が生存にとって決定的な意味をもっています。幸い、大学の近くに孵化場があり、鑑別して不用になったオスびなを譲り受けて使いましたから、研究費もほとんどかからずに済みました。これは有難かったですね。
系統発生的にみてこの種では視神経が完全交叉していますから、網膜非対応の手がかりを考慮する必要がなく、その点でも分析がしやすいわけです。ヒナの片眼を一時的に遮蔽すると視野の広さがほぼ半分になります。するとヒナは欠損した視野を補うために頭部を大きく動かし、その結果、運動視差の効果が高まって落差の検知が処置しない場合と変わらないレベルに維持されました。
こうして、発生上の基本となる奥行距離情報は運動視差によって得られることが確証できたのです。しかし、この知見をふまえて複数の要因が関与するようになる過程、つまり手がかりの豊富化過程を明らかにする場合、さらに高い系統発生段階にある動物種を対象にする必要が生じてきます。そこで、一足飛びにニホンザルを被験体に選びました。ニホンザルの仔は出生時点で自立移動が可能ですから私たちの実験目的にも適していますし、視空間知覚に関与する要因がヒトとほぼ同じだろうとも推測できます。実験にあたっては、運動視差・両眼視差・肌理密度の3種を取り上げ、それらが個体発生上どのように手がかりとしてはたらくようになるかを週単位で追跡しました。
幸い、京都大学霊長類研究所が名古屋市の北、犬山にありますので、施設の共同利用を認めていただき、装置を運搬して出生直後から最長で約1年間、毎週観察を行ったのです。松沢哲郎さんが当時研究所助手をしておられてずいぶん支援してくださったおかげで、実験は順調に運びました。各要因の効果を検出するためにいくつかのノウハウを得たことも想い出します。両眼視差を無効にする方法として、片方の眼に一時的にオクルーダを装着することにし、コンタクトレンズのメーカーに協力を仰ぎました。最初は「視力増進のために製品を出しているのに目隠しするものを造れというのか」とお叱りを受けましたが、事情を説明しますとご理解いただき、前代未聞の遮蔽用コンタクトが誕生しました。これを試してみますと、私たちの心配をよそに赤ん坊ザルはすぐ脱着に慣れました。肌理密度の効果をしらべるにあたってもアイディアが生まれました。こういうところが共同研究の強みですね。
この実験は3年ほど続き、運動視差が出生時から作用し、生後3月齢ころになって画像要因つまり肌理密度が有効な手がかりとしてはたらくようになるという新しい知見を得ることに成功したのです。その一方、両眼視差についてはさほど関与しないという結果になりました。それについては、私たちの技法が移動・探索という活動事態を設定していることに関係しているかもしれませんが、他の研究者の報告でも同じような所見が出ています。さらに、落差事態において生じる注視・体動など視覚-運動系反応を分析したところ、手がかり機能の発達の基礎にある知覚-運動機能の発達も明らかにできました。
細部に立ち入った説明になりましたが、こうして実験開始から10年ほどで漸く視空間知覚の手がかり機能の「発生」を解き明かすことに成功したのです。
イン 視空間研究に縦軸、時間軸を入れたというわけですね?
辻 おっしゃるとおりです。視空間知覚の問題を、行動と関連づけ発生論的視点で解明することができ、ささやかながら達成感が得られました。関連することをお話しておきますと、手がかり機能の発生を扱う私たちに対し、個々の手がかりの距離特性を検討するというアプローチを当時NHK基礎研におられた長田昌次郎さんが発表しておられます。こうして、1970~80年代に視空間知覚の実証研究が我が国で進められたということをご記憶いただきたいと思います。
イン この間、他にもエピソードがあったのではないでしょうか?
辻 今こうして振り返りますと、いろいろ浮かんできますね。眼科や視能訓練関係の方から依頼があってピットフォール・テストを両眼視機能不全の施術前後で比較するとか、1歳半の定期検診に組み入れるなどしました。ダウン症候群のお子さんの場合、落差の知覚やその恐怖にはなんら問題がないのですが、落差を避けて移動するという課題を処理するのに手間取りました。その一方、落差を怖がる様子がまったくなくてそこに侵入するというケースが僅かながらありました。子どもが怖がると母親は恥ずかしがり、落差を気にしないと安心されますが、私には後者の例が気に懸りました。残念ながらフォロウアップできずじまいでしたが、知覚と情動の本来的な結びつきに不全が生じている可能性が考えられたからです。
それから暫くして、それと関連のありそうな問題に出逢うことになります。それが高層住宅における幼い子どもの転落事故です。60年代に入ると経済発展とともに都市への人口集中が盛んになり、それに呼応して高層集合住宅の建築ラッシュとなりました。それから十数年して起きた現象です。落差という形で視空間を扱ってきた私には無縁とは思えない問題でした。そこで並行して転落事故の調査を行いました。事故の原因として、全体のおよそ2/3にあたる事例が高所で喚起される恐怖の減弱によるものであることを突きとめました。この所見を発表したところ、フロアで聴いておられた報道関係の方が「高所平気症」というキャッチイな見出しで紹介してくださいました。それ以降この所見の追試が行われ確認が得られています。私自身は、転落という行動は本来的な知覚と情動のリンケージが緩んで両者が乖離した結果だとみなしています。
後年、科研費の補助を得て、「空間性感情の様態と発生に関する総合的研究」と題する研究プロジェクトを立ち上げ、そこでは基礎系と臨床系の研究者の参加を得ていくつかの新たな成果を得ることができました。もちろん残された課題はたくさんありますので、今後も継続していきたいと考えているところです。
この課題を意識するようになって、「滑り台」に注目しました。それを体験することによって高所慣れに歯止めをかけることができるのではないかという予想です。ヴィジュアル・ピットフォールを遊具として使用することも考えられ、基礎研究用に考案した装置の新たな使途になりうる可能性も捨てきれないでいるわけです。
イン そのあたりのことは何処かにまとめておられるのですか?
辻 じつはそれができていません。ちょうど学内外の仕事が増えた時期と重なり、資料収集も中途半端なままであることを反省しています。
§ 家畜育種学教室との連携
イン マウスの系統比較もなさっていますね?
辻 70年代に入ると、農学部家畜育種学教室との交流が始まり、近交系マウスの系統比較による行動遺伝的分析を手がけることになります。きっかけは、心理学への転専攻を考えていた学部生の海老原史樹文さんに行動遺伝学を紹介し、海老原さんがそれに関連した課題で卒研を行うにあたり助言者として加わることになったことです。60年代に始まった行動遺伝学では、研究者の多くが学習行動を取り上げていましたが、学習成績には感受特性・動機づけ・運動機能など多くの要因が関与するので行動と遺伝子との一義的な対応を求めることが困難だと感じていました。
そこで、先例のない活動リズムに着目したのでした。実験者としての海老原さんの力量が高かったので、卒研と修士研究を通じて興味ある事実が明らかになり、日周活動リズムという行動形質を規定する主導遺伝子を同定することに成功しました。海老原さんは、その後、三菱生命科学研究所で川村浩先生のご指導の下、生物リズム発現機構に関して注目すべき成果を収め、第一線の国際的研究者として現在も活躍なさっています。
この出逢いが機縁となり、私たち心理学教室でも80年代半ばまでおよそ10年間、いくつかの行動の系統比較が行われ、またそれと並行して両教室の連携によって実験動物としての近交系マウスの行動特性検定の知見が蓄積されました。
イン スンクスとのかかわりはどういうきっかけで始まったのでしょうか?
辻 先にも申しましたように、私の動物行動研究はゼロから出発していますが、当初から心理学における動物実験の在り方、特に対象とする動物種の偏り、いわゆる「ラット・サイコロジー」に疑問を抱いていました。そして、現状を改めるには、系統発生を視野に収めた種の選定が必要だと強く感じていたのです。育種学教室との交流・連携が深まる中で、そのことを近藤教授にお話したところ、実験動物として新たに開発されたスンクスを対象にしてはどうかとの助言をいただきました。
スンクスとは、食虫目トガリネズミ科ジネズミ亜科に属するジャコウネズミ(Suncus murinus)の野生個体を起源とし継代繁殖された、“名大ブランド”の実験動物です。
私の求めていたものとピッタリだと判り、1979年秋に導入して以来およそ四半世紀にわたってその行動研究を進めました。幸い、教室でほぼ毎年、学部生・院生が関連の課題に取り組んでくれましたし、並行して「ドメスティケーションに伴う行動変性」という包括的テーマを掲げ、生息地におけるフィールドワークや野生個体の継代繁殖でも協力体制ができました。私が学部長・副総長の職にある間も継続できたのは、そのおかげです。教室の力を実感し、感謝の念を禁じえません。
§ 名大で行われたプロジェクト
辻 名大では学生・教官として45年間を過ごしました。学生としては、教養部・文学部・大学院教育学研究科に、また教官としては教養部・文学部に籍をおきましたし、その間、医学部・農学部・工学部・環境医学研究所など学内他部局との交流・連携の機会も少なくありませんでした。ですから他にもいろいろ想い浮かぶことがあります。その一つ、これは私自身が関わったことではないのですが、我が国の研究プロジェクトとしては他に例をみないものですのでご紹介しておきます。
それは1950年代に米国の財団から当時として多額の資金助成を得て行われた「日本人研究」です。このプロジェクトは、医学部精神医学教室の村松常雄教授を代表者とし、精神医学・心理学・社会学の研究者により構成されたチームで数年にわたり行われた大がかりなフィールドワークでした。心理学では、村上英治・丸井文男・秋谷たつ子・関根忠直の諸先生をはじめ、協力者として星野命・詫摩武俊先生らも東京から参加されていました。心理学チームは心理検査を担当し、その中でTAT名大版の開発やロールシャッハ・テストの分析法の改善などが行われました。その成果が『日本人-文化とパーソナリティの実証的研究-』(村松常雄編、黎明書房、1962年)として出版されています。
その一環として継続されていたTAT分析の基準作成には、博士課程在籍当時に加わったことを憶えていますが、このような大規模な研究が当時行われていたことをぜひお伝えしておきたいと思います。学史的にも意義あるこのプロジェクトを資料として保存するべく、在職中に学内の資料センター・図書館や拠点だった医学部精神医学教室に照会したのですが、残念ながら関連する資料は残されていませんでしたし、当時のことを知る人にも会えませんでした。もうすこし早く手を着けておくべきだったと後悔した次第です。
§ 中京大学心理学部
イン 名大から中京大学へ移られますね?
辻 名大を停年退職した後は自由の身でそれまで叶わなかった海外生活を送るという人生設計を立てていたのですが、すぐ近くにキャンパスのある中京大学の心理学部発足にあたりお誘いを受けました。中京とは古くからご縁があり、文学部心理学科設置当初から非常勤で実習や講義を担当していましたので、ご厚意を受けてお世話になることに決めました。6年間在職し、カリキュラムの設計や大学院生選抜の在り方など、あらためて教員として学ぶことが多くありました。初代研究科長を仰せつかり、研究科共通の必修科目として学史・学論を担当した経験も貴重でした。
中京では個々の教員ごとに指導学生をもつというゼミ方式でした。名大では第一・第二講座の教官が一体となって教室として教育研究活動を進めていましたので、当初その運営方式に戸惑いました。その上、日心や基礎心の代表者を務めていて名古屋を離れることも多く、授業や学生指導に専念することが難しい時期でもありました。しかし、学生諸君が私たちのゼミのモットーとした「自立と自律」の精神を酌んでくれて、国立とは別のよさを実感できました。
§ 海外研究者との交流
イン スンクスの研究は名大を停年退職されたのちも続くのですか?
辻 1980年代に入り、スンクスの行動研究の成果が挙がり始めますと、その発表の場として欧州の行動生物学者の集まり、例えば国際動物行動学会議(International Ethological Conference;IEC)や動物行動集会(Animal Behaviour Meeting)に参加の機会が増えます。また、ドイツ語圏エソロジストの研究集会、欧州若手研究者のセミナーなどに招かれて講演するなどの交流も深まっていきましたが、スイス・ロザンヌ大学のフォゲルさん(Prof. Peter Vogel;理学部生態進化教室教授)との出逢いは大きな出来事でした。90年代に何度か彼の研究室を訪ねるうち共同研究の話がまとまり、名大で停年を迎えるとロザンヌに滞在、半年あまりトガリネズミの行動の異種間比較を行いました。
名大在職の最後の数年間は全学の管理運営に関わり、大学院重点化や組織改編、迫っていた法人化への対応などに取り組んでいましたので、ロザンヌでは、職務から解放されて学生時代以来久しぶりに実験三昧の日々を過ごしました。作業を終えて日付が変わる頃に帰途につくのですが、眼下のレマン湖の黒々とした湖面の向こうに瞬く対岸のフランス・エイヴィアンの幻想的な灯りに疲れを忘れたものです。
生態学・発生学者のフォゲルさんと私とは相互に“越境”しあいながら、それぞれのアプローチの特徴・意義について理解を深めることができました。特に、心理学における発生的アプローチと生態研究との補完的関係を認識できたことは大きな果実だったと思います。そんな彼との付き合いももう叶いません。昨年1月、訃報が娘さんの一人から届きました。その衝撃は今も治まっていません。
§ 学会運営
イン 日本心理学会と日本基礎心理学会の理事長を務められましたね?
辻 はい、基礎心は1999年から2期6年、日心は2003年から1期2年でした。他に、日心理事長1年には日心連(日本心理学諸学会連合)の代表も兼ねていました。それぞれ問題を抱え、けっして平穏無事とは言えない時期でした。
基礎心では会員減少が懸念され、学会誌編集の見直しや高校生向け講座の開催など活性化のための方策をあれこれ考えました。日心のほうにも、組織改変・定款改定、公開事業の拡充、欧文誌の委託などのほかにも多くの課題がありました。
イン 国資格化の問題もそうですね?
辻 2003年だったと思いますが、主として医療分野に従事する専門実務者の国資格化を実現すべく関係諸団体による「医療心理士国家資格制度推進協議会」を発足させ、心理学・医学医療など関係団体の参加を得て、代表者として資格内容の検討や養成カリキュラムの策定、国会議員への要望などに努めました。当初、日本心理臨床学会や日本臨床心理士資格認定協会の方たちは、すでに実効を挙げている民間資格との関係もあり、また国資格となった場合に上位規定の医事法制による活動の制約を懸念され、様子を見ておられたようです。そのため最初のころは私たちが専ら要請する形だったのですが、その中で私は一貫して広い職能に関わる包括的な資格を念頭において活動していました。
イン 漸く実現しましたね?
辻 2004年に議員立法の形で上程された案が審議直前になって郵政民営化解散の煽りでいったん“お蔵入り”になりました。その時点で推進協議会会長を後任の日心理事長に委ねて退いたのですが、その時点ではすぐ再提出になるものと期待していました。しかし、どういう経緯かは存知ませんが、その後10年の歳月を経て漸く実現となりました。まずは同慶の至りです。
この上は、社会的評価に堪える人材を養成しなければなりませんが、そのために学界挙げて教育水準の向上を図る必要があると思います。徒に実務に走るのではなく、心理学の広範な学識をもち、他の職能との連携に役立つ基盤を整備していただきたいというのが私の切なる願いです。
§ 研究遍歴の総括
辻 今年(2016年)は心理学を専攻してちょうど60年の節目に当たります。あれこれ自分の探索をたどってきましたが、まとめをしたいと思います。
冒頭に申しましたように、理学部と文学部の選択肢から文学部を選び、志望の社会学から心理学に転専攻し、研究の過程で機構論から発生論へ、知覚研究から行動研究へと、何度も“転向”を重ねてきました。出身高校の校是は「一以貫之」でしたので、それに背くようではありますが、自分としてはそのたび新たな展望が開けたように思います。しかも、転向が可能になったのは環境のおかげだと強く感じるのです。高校では、その校風と時代に援けられました。放課後には化学実験や天体観測に熱中しましたし、図書館の書庫で研究書を読んだりもしていました。そういう経験を通じ、単一の問題にも多様な観点から迫ることができることを理解できたのは大きな収穫でした。
学史的にみて1950~60年代、心理学界では学派期の“空気”が残る一方、既存領域分化と領域統合が同時進行していました。
学部在学中は専ら知覚実験心理学に浸りきった生活でしたが、大学院で教育心理学専攻に所属して同学の多様な領域に接し、自分の視界が広がりました。最初の職場が教養部だったこともプラスになりました。60年代末から70年代半ば学園を揺るがせた波を受け、教官は自分たちに課せられた問題に日夜取り組みましたが、その中で「教養とは専攻に非ざる専門である」と考え、他分野への“越境”を怖れなくなりました。「自由闊達」を旨とする名大の学風も幸いしました。教育研究上の連携についてはお話しましたが、遡れば学部在学時にも卒研の助言を求めて医学部眼科教授室に伺ったり、院生当時は生理学や精神医学の人たちと輪読会を続けたりしたことも“人見知り”の性格を変える一因となったように思います。
イン 羨ましいことですね
辻 近ごろは資格や学位の取得が直近の課題になり、若い人たちがこういう“探訪”をしづらい状況にあるようで残念です。「こうすれば面白い」と判っても、それを一時お預けにしなければならないのは気の毒です。今の若い人たちにとって学位は“免許証”ですから取らなきゃ食えない、切実な問題ですよね。その点、私たちの時代にはある意味の“開き直り”ができました。博士号は「足の裏の米粒」でしたからね。
教員としては、教養部・文学部、そして中京大学心理学部に所属しましたが、それぞれの職場で得られたものも貴重でした。
さらにまた国内の研究活動に加え、もう一つの“越境体験”である海外生活を通じても多くのことを与えられました。当時の仲間が相次いで他界して寂しくなりましたが、彼らと共有してきた課題の達成に向けて努力していきたいと思っています。
§ 付言
辻 今回、このような機会を与えていただき、おかげで自分のささやかな遍歴を振り返ることができました。ただ、オーラルヒストリイにおける当事者の立場を経験するのが初めてでしたから、テープを起こしてくださった文面に眼を通しますと話し言葉の冗長さ・曖昧さや無駄な繰り返しが目立ちました。そこで、かなり大幅に削除し、全体を再構成させていただきました。これではオーラルではないとお叱りを受けそうですが、面接者・編集委員の方々のご寛容をお願いする次第です。
インタビュアー(以下、「イン」と略) 大学入学当時のことから伺いましょうか
辻 名古屋大学入学が1955年4月です。終戦から10年で世情は安定してきましたが、周囲にはまだ困窮生活を送っている仲間が少なくありませんでした。闇市で血を売って授業に出てくる同級生や身内を戦禍で失って天涯孤独になった友人がいました。
教育制度改革に伴って、高等教育は一般教育(教養課程)と専門教育(専門課程)を二本柱とするようになりました。入学すると最初の2年が教養課程で、その後に専門課程に進むという方式でした。
一般教育については、後に評価が分かれるのですが、個々の学問分野やその体系にふれることができたという点で貴重な機会になったと思います。というのも、そのカリキュラムが、心理学・政治学・物理学というように分野を単位にした授業で構成されていたからです。つまり「学問分野型」(discipline-oriented)でした。しかも、学部・専攻の如何にかかわらず共通に履修要件が定められていたのもよかったと思います。人文・社会・自然の3系列それぞれ12単位、外国語8単位、保健体育4単位を取らなくてはならず、さらに文学部志望者には外国語3科目16単位が課せられていました。このようなハードな条件でしたが、こういう形で「専攻に非ざる専門」に触れる機会があったことで学生の「教養」が培われたと思っています。
先ほど申しませんでしたが、新制大学発足にあたっては、旧制の高等学校・高等専門学校が旧来の大学に併合されました。名大の場合、名古屋帝国大学と第八高等学校・岡崎高等師範学校が合体したのでした。縁あって入学から10年後の1964年4月、教養部に職を得るのですが、「一般教育としての心理学とはなにか」を模索するうち、専攻学生以外を対象にする授業がすなわち一般教育なのだと考えるようになりました。そうならば、概論を講じる必要もなかろうと割り切り、1セメスターを通して「学習心理学」だけを講じたり、専門書を抜粋したテキストを演習に用いたりしました。これが予想以上に好評で、「初めて大学らしい授業だった」「心理学の性格にふれた」などと言ってくれました。
話を元に戻しますと、入学して1年ほど経って、それまで自分の視界になかった心理学に出逢うことになります。
イン その前、篠山(ささやま)から名古屋大学文学部を志望されたのはどういう理由だったのでしょうか?
辻 出身高校は「兵庫県立篠山高等学校」(現在の篠山鳳鳴高等学校)です。伝統学校ですが、当時のクラスでは伝統に縛られない自由な雰囲気があり、生徒がそれぞれ個性を発揮する一方、社会思想や哲学に対する憧れから背伸びした議論をしていました。私自身は、中学時代から天文気象に興味があって部活に熱中し、高校でも理化部に所属して活動を続けていましたから、理学部進学が念頭にありましたし、周囲でもそう思われていたようです。しかし、高校在学中に社会科学への関心が芽生え、受験の直前まで天文学か社会学かの選択に迷っていました。
文学部か理学部かの選択肢など考えられないと思われるかもしれませんが、かつていくつかの大学には文理学部がありました。扱う事象が人文か自然かを問わず基礎科学を担う組織ですから、文系・理系の二分法に比べれば奇妙ではないはずです。
クラス担任が物理担当の先生だったこともあって理学部進学を勧めてもらいましたが、家族は天文学に進むことに賛成ではなかったようです。幼いころ病弱だった私の健康を心配してくれたのでしょうが、祖母などは「人様が寝ているときに起きているような仕事」と反対していたようです。
自分の中では、社会科学に“揺さぶられる”ような気分が強まり、地域社会の閉鎖性や住民の意識を歴史社会学的観点で解き明かすという問題意識が膨らんでいきました。それによって閉塞感から解き放たれるという期待が漠然とあったのかもしれません。名大には理論社会学の本田喜代治教授とジンメル研究者の阿閉(あとじ)吉男(よしお)助教授らがおられました。父の親友の大学教授が名大を勧めてくださいました。じつは、国民学校2年の夏に篠山に疎開するまで名古屋に住んでいましたし、叔父の家に下宿できるということもありました。もしかすると、この一件には親父の画策があったのかもしれませんね。
§ 心理学との出逢い
イン 心理学ではなく社会学志望だったのですね?
辻 入学の時点では心理学の存在すら知りませんでした。一般教育の授業科目に心理学があることを知っても関心がなく、受講しませんでした。出逢いはまったくの偶然に訪れました。偶々、自分が受けていた授業が休講になって教室で早弁していたとき、隣室から講義が聞こえてきました。八高(旧制の第八高等学校)時代のおんぼろ校舎ですから音が筒抜けです。その授業、村上英治助教授担当の心理学講義でした。声の大きなことでも知られた先生ですから壁越しでもノートが取れるほどでしたが、たしか知覚の話だったと記憶しています。
これがきっかけになり、自分で心理学書を求めて読んでみました。大脇義一先生の『心理学概論』(培風館)で、意識・行動の実験科学という点が新鮮でした。進路を決める際の選択肢にあった理学部志向が甦ってきて、さらに心理実験法も独習しました。並行して『物理実験法』を読んだのもプラスになったようです。
村上先生は後々いつも「俺の影響で辻は心理に替わった」と言われましたが、先生から単位はいただいていないのです。しかし、聴講、正しくは盗聴して専攻を鞍替えしたのですから大きな影響を与えていただいたのはその通りで、学恩を忘れることができません。
志望の社会学については、勉強していくうちに自分との相性に疑問を抱くようになりました。心理学の方法論に魅かれるのと逆に、社会学の方法論に違和感めいたものがありました。ドグマティックではないものの、自分にはなじまないという感じだったと思います。
§ 心理学教室
辻 当時、文学部心理学講座は横瀬善正教授・内山道明講師に蛭川栄・市川典義両助手という教官構成で、横瀬先生が私の指導教官でした。ただ先生は健康が優れず授業を休まれることがしばしばあり、それを補うように、内山先生のリーダーシップの下スタッフ・院生・学部生で活発な議論が行われていました。総勢20名ほどのこじんまりした教室で、学部生は学年2~3名、そこに他大学からの編入者があるという状態でした。こうした雰囲気の中で日常的に学んだものが授業以上に大きかったというのが実感です。
教室の一員になると、さっそく先輩から被験者を頼まれます。断るわけにもいきませんから、授業以外は専ら被験者を務める時間でしたが、この経験も心理学実験について考える上にも、あるいはまた自分の課題研究を進めるのにもずいぶん役立ちました。
イン そのあたりをもうすこしご説明いただけませんか?
辻 教室では横瀬先生が提唱した視覚場の理論、通称「横瀬の場」の実証研究が進められていました。横瀬先生は、色と形という視覚の二大テーマのうち形の研究が立ち遅れていることを痛感され、輪郭を構成する線分を荷電体とみなし場の概念を導入して形の問題に迫るという独創的な構想を立てられ、教室ではその実証研究が鋭意進められていました。その姿に接するうち、新参の私たちもその“チーム”の一員となっていきました。
今にして想えば、1950年代半ばから60年代にかけて、我が国の心理学界は活況を呈していました。すくなくとも私が接した基礎心理学領域では、大学・教室ごとに学風が違っていて、立場や理論をめぐる論争が盛んでした。現在のような専門別学会や目的別協会が組織されている状況とはまったく違い、当時は日本心理学会のほかには、発足まもない教育心理学会と応用心理学会しかなかったと記憶しています。いずれにせよ、学会大会に参加するのは一大事でした。知覚研究領域では、横瀬の場理論のほか、東北大学の本川弘一教授(生理学)の「網膜誘導場」や東京教育大学の小保内虎夫教授らによる「感応理論」が提唱され、それぞれ検証実験が行われていて、大会は成果発表の大舞台だったわけです。図表を手書きした掛図を筒状にして担いで会場に向かう姿は戦に臨む武将たちを髣髴とさせるものがありました。私たちはさながら下級武士としてそれに従ったのでした。
イン 卒論のテーマは?]
辻 こういう教室のムードに刺激され、自分も実験を始めたいと考えるようになりました。学部に進んでまもない時期です。心理学に鞍替えした動機が心という現象のおもしろさにあったわけではなく、むしろその研究方法に魅かれたのでしたから、実験法が適用できるならばどんなテーマでもよかったわけですが、視空間知覚・奥行視をテーマに選びました。
心理学書には、奥行視の手がかりとなりうる要因が羅列されているだけで、要因の発生や相互関係など肝腎なことは書かれていませんでした。生意気にも、そのような学問状況に不満を感じたものです。それがこのテーマに取り組む動機で、場理論的アプローチが有望だという気がしていました。
指導教授の横瀬先生も賛成してくださいました。ただ、出発点で先生と進め方について考えの違いがありました。先生は刺激に立体を用いて、その周囲の場の強さを測定するものと期待されていたようですが、私の念頭には平面図形を刺激にすることしかありませんでした。それと言うのも、外界はすべて二次元の網膜像に還元されて再び三次に復元されるわけだから二次元から出発していいのではないか、しかも平面図形の場合は生理解剖的諸要因の関与がなく単純な条件で現象分析ができるのも利点だろう、とそう考えたのです。卒論では種々の図形についてデータを収集し、まずまず計画どおり、視えの遠近と場強の対応関係を明らかにすることができました。これが卒業研究です。
§ 教育学研究科教育心理学専攻
イン 大学院は教育学研究科だったのですね?
辻 そうです。講座化されはしたもののまだ文学研究科に心理学専攻が設置されていませんでした。一方、新制度になって発足した教育学部には教育心理学専攻の修士・博士課程が設けられていて、教室の先輩も教育学研究科教育心理学専攻に進んでいました。
教育心理学専攻は、社会・職業、人格・発達、学習・教育、数理・統計の4講座編成でした。学部では知覚心理学しか学んでいませんでしたので、初めて諸領域から成る心理学の“実像”にふれる機会であり、どの授業も新鮮でした。ですから課程修了要件の単位数をはるかに超えて履修しました。
大学院に入っても、実験や作業は相変わらず文学部の心理学教室で続けていましたから、その点では学部時代の延長でした。変わったのは指導教官です。横瀬先生は教育学研究科専任ではないため指導教官になっていただけず、新たに續有恒教授にお願いすることになりました。續先生は、『心理学研究』に掲載された「近さについて」の論文にあるように知覚研究を手がけておられましたが、新制度になって東北大学教育学部に赴任されたのち名大に来られました。
ちょっと脱線しますが、新制度の教育学部は教育学・教育心理学の研究を行うという趣旨で旧制帝国大学など数校に設置されたもので、旧師範学校の併合によって発足した初等中等教育教員養成系の学部(学芸学部)とは性格を異にしていました。新しい組織ということもあって、先生方はこの新設学部の使命や将来を非常に強く意識されていたようで、今にして思えば、教育心理学が最も色濃く出ていた時期でした。續先生のようにそれまでの研究歴から一転して新領域の先導役を担うという立場に転向された先生方が他にもおられたのではないでしょうか。
續先生が私の指導教官になってくださることは申し合わされていたようです。それまでの経緯もあって横瀬先生に配慮なさっていたとみえ、修論研究について細かいことはほとんどおっしゃいませんでした。演習の時間、最新の実験データを出しても、それについてはなんのコメントも出されません。院生仲間から実験式の当てはめがよくないなどの批判が出るのを聴いておられ、議論が終わるころになって、「それで?」とポツンと言われるのです。強烈な一撃でしたね。この寸評によって、二手・三手先を見通す態度の重要性を学びました。
§ 当時の学問状況
辻 ここで当時の学術状況を振り返ってみますと、学史を飾った学派運動が終息し、それぞれの学派に連なる人たちが自説の支えとしていた対象領域が、ゲシュタルト学派なら知覚、行動主義なら学習という具合にそれぞれ継承されていくわけですね。学派運動を経たのち領域分化が進むという経過でした。
高砂さんが精しくご存知でしょうが、日本で心理生理学が芽生え始めるのもこの時期でした。生体電気増幅装置が心理学教室にも導入されはじめ、EEG・ECG・EMGなどの同時記録により心理現象との対応が追究されていました。名大文学部に脳波計が導入されたのがたしか1959年だったと思います。私が修士1年でしたが、研究実績のある先輩格の教室を見学してくるように横瀬先生から命じられ、1週間ほど東京に滞在して東京学芸大学・東大教育学部・東京教育大学などを訪ねたことを憶えています。当時、日大では山岡淳先生が中心で精力的に研究を進めておられ、そのときは日程の都合で見学できずじまいでしたが、先生には以来、機会あるごとにご指導をいただきました。
横瀬先生は「脳波研究が進むと知覚の内省報告など無用になるし、閾値測定も波形をみれば可能になる」と仰言って、その成果に期待しておられましたが、学界では、脳活動の研究への期待が大きかった時期です。
他方、ゲシュタルト学派の流れを汲む知覚研究が支配的だった日本の実験心理学界に、学習研究が入ってきました。そして、知覚研究と学習研究が実験心理学の二本柱となり、教室ごとにそのいずれかを担って独自の学風を築いていきました。学派運動の時代は終わりましたが、実験心理学も理論志向的ではありました。先ほど紹介した知覚領域における論争がその例ですが、私自身、そういう風潮の中でブラックボックスの中身をめぐる思考を鍛えられたように思います。
§ 博士課程における転向
イン 博士課程に進まれるのですね?
辻 そうです。博士課程と言っても、当時の院生にとって学位は縁遠いものでした。研究成果が蓄積され学界で評価されて初めて論文提出の許しが出るので、ふつう厄歳ちかくなって準備を始めたものです。博士学位のことを「足の裏の米粒」と称していました。「取っても食えないが、取らなければ気持ちが悪い」という自虐めいた表現です。学位はあくまで結果であってそれ自体を目的とした活動など考えられませんでした。ちなみに私の場合、学位取得は1979年、42歳でした。
イン 後期に行かれた頃は比較的ウェルカムな感じですか?
辻 いつ頃からか旧来の修士課程・博士課程を博士前期課程・博士後期課程と呼ぶようになりましたね。少なくとも私たちのころ修士課程と博士課程は連続していませんでした。妙な喩えですが、現在の両課程を同じ建物の1階と2階とすれば、当時は別棟にあったというほどの違いではないでしょうか。修士課程から博士課程に進む場合、まず“お伺い”を立てるのが常識とされ、とうてい「行きます」「受けます」の雰囲気ではありませんでした。
卒論では視えの遠近しか扱えなかったのに対し、修士研究では、観察者から図形の面までの視えの距離を測定することができるようになり、場強との対応をいっそう精細に実証することができました。また、視えの大きさ-距離関係も明らかになり、大きさの恒常との現象的類似も実証できました。そういうことで修士論文を通してもらいました。しかし、指導教官には「それで?」と言われつづけてきましたから、博士課程への進学については自信がありませんでしたが、結局3名進学が許されました。うち2名が教育学部出身、文学部からは私ひとりでした。
イン 博士課程でも續先生が指導教官だったのですか?
辻 引き続き續先生が指導教官を引き受けてくださいました。基本的には修士論文で示した方向に沿った展開を考えていました。それまで扱ったよりも大規模な空間について、その視えの距離と場強との関係式を求め、その所見から視空間構造を明らかにしようという構想です。
ところが、予期しなかった壁に突き当たります。ひとつは測定手続きに関する問題です。使用中の装置では刺激図形(奥行視図形)と視えの距離を測る枠組とは独立であることを前提にしています。量推定法など他の手続きに比べて判断も容易で、すくなくともそれまでのデータ収集にあたっては問題を生じていなかったのですが、街路の写真を呈示すると、モノサシであるはずの枠組がその空間に影響されてしまうのです。
もうひとつ、こちらは理論的な問題でした。平面図形の奥行視では、画像的手がかりしか作用しませんね。眼球調節・輻輳・網膜非対応・運動視差などの手がかりはすべて剥奪されているわけです。操作・移動などの行動とは切り離された視空間の研究にどのような意義があるのかと自問すると不安が募りました。奥行視の場理論的研究としての意義づけは可能かもしれませんが、行動論的知覚研究としては疑問が残りました。
進学を認めていただきながら、ここで袋小路に入ります。一転してそれまでの勢いがなくなったことが周囲に判ったようです。今にして想えば、意欲減退の典型だったのではないでしょうか。
イン その期間どう過ごされたのですか?
辻 気分転換というわけでもありませんが、この時期の“埋草”となったのが、脳波に関する共同研究でした。テーマは「視覚現象と脳波の関係」です。視覚現象は目を開けた状態で起きるのにそうするとα波が消えてしまいます。当時はα波のブロッキングが唯一の指標でしたから、α波が豊富に出現している状態でなければ反応が明らかにできません。というわけで残像や心像のように閉眼条件で測定できるものに限られていました。
その後、1960年代に入りますと事象関連電位を指標として研究の幅が広がりますが、私自身は心理生理学とは距離を置くようになります。主な理由は、心理事象の背後にあるメカニズムを心理モデルの形で探らずに生理過程に還元するというアプローチに魅力を感じなくなったからです。ここで浮かび上がってきたのが意識や行動の「発生」的研究の方向性です。発生を論じるには心理と生理との相関ではなく、時間軸上の行動と行動との関係をとらえることが必要です。ここに来て機構論から発生論へと、またしても“転向”することになりました。1960年代後半のことです。
挫折によって空虚な時期を過ごすことになりますが、そこを埋めようとする力が自分の中で問題意識の“再体制化”を生み出したとも言えそうです。
§ 動物行動研究
イン 動物行動研究に手を着けられたのには、いつ、どういうきっかけがあったのでしょうか?
辻 1963年の夏、短期研修団の一員として2か月間アメリカに滞在しました。その間に国内各地1万2千キロを車でめぐったのですが、途中は大学の寮に泊まり施設見学をしました。ボストンではハーヴァードの心理学教室を訪ねる機会がありました。なにしろ知覚研究以外の事情には疎かったものですからスティーヴンス教授の名前しか知りません。あいにく先生が不在で、帰ろうとしていましたらスキナーの実験室を見て行くように言われ、院生に引き合わせてくれました。案内された実験室にはスキナー・ボックスがズラッと並び、隣室の累積記録装置に打ち出されていましたが、その光景に圧倒されました。被験体はハトだったのでしょうが、ボックスには蓋がしてあってその姿が見えません。どこから動物を見るのか? この素朴な疑問を投げかけると、返ってきたのは「私たちは動物を見ない、データを読むのだ」という答でした。動物実験にまったく無知だったせいもあり、この言葉を感心して聞いたのでした。
イン それが動物実験のきっかけですか?
辻 このことがあって1年後ですね。1964年4月、教養部心理学教室に文部技官教務員という職で採用されました。阿部芳(よし)甫(すけ)教授と村上英治助教授がおられました。村上先生のことは私の転専攻に関連してすこしお話しました。阿部先生は東大では桑田芳蔵先生の門下で卒業後は体育研究所技官を経て旧制の第八高等学校に赴任され、新制の名大教養部におられました。先生は1年後に停年を迎えられるという時期でしたが、動物実験のきっかけを与えていただきました。
教務員の仕事は、先生方の講義のための掛図の作成、実習授業のインストラクション、書籍・備品の発注、会議の記録作成などなどでしたが、両先生とも私の研究環境について細かく気を遣ってくださったので、落ち着いて勉強ができました。そんなある日、格納室の備品を整理していて、T型迷路と木製の飼育箱を見つけました。阿部先生が以前に使用されたもので、永年そのまま放置されていたのでした。
それを見て、「動物実験もわるくないな」と、そう思ったとき、あのスキナーの実験室の光景が甦りました。彼らの行動分析では動物を直接観察することはない。ならば、ゼロから出発する私は徹底した観察から出発してみよう、そう思ったのです。テーマの選択にも偶然がはたらきました。
ラットはある精神科病院で譲り受けました。その病院でリハビリ作業のひとつとして維持繁殖していた近交系10頭です。偶々眼にしたのが潜在学習に関するSeward論文でした。読んでみて「潜在的」とされる点に疑問が湧き、T型迷路内で被験体が示す行動を逐一観察することになりました。ただ、当時まだ市販のビデオがありませんでした。8ミリ・シネですと一巻4~5分の映像しか収められません。1頭あたり30分、10頭、しかもそれを何日も撮るというわけにはいきません。コマ落としにすると間の行動が抜け落ちてしまいます。眼に留まったのがテープレコーダでした。それに行動観察を逐一吹きこみ、後に再生して分析することにしました。行動を“撮る”のではなく“録る”という方法です。
この行動記録法の場合、あらかじめ個々の行動を記号化した目録を作成しようと考えましたが、実施してみるとむしろ“生”の言葉のままがいいと判りました。こうして行動のシーケンスをとらえると、報酬が導入されていない間にも環境探索の様相に明らかな変化がみられました。その所見をまとめた「迷路探索行動の実験的分析」が最初の動物実験論文です。
当初やむをえず採用した行動収録法でしたが、こうして観察経験を重ねるうち自分の「観察眼」が磨かれていき、画像の収録・解析技術が進んでも欠かせない、確かな技法として定着しました。画像収録・解析技術が進んだのちも私にはこの行動描写が欠かせません。ですから動物実験を始める人にはこの“実況放送”から始めてもらっていましたが、ビデオが普及するとそれで済ませればいいと考える人が多くなりました。残念なことです。
こうして、ヒトを対象にした知覚研究から動物を対象とする行動研究へとシフトすることになりました。今回またしても転向です。
イン 有難うございました。予定した時間が来てしまいましたので、続きは日を改めて伺うことにしたいと思います
【第2回インタビュウ】
日本心理学会 心理学者 オーラルヒストリー
日時:2016年2月19日(金)
場所:公益社団法人日本心理学会 事務局
インタビュイー:辻 敬一郎先生
インタビュアー:高砂 美樹(東京国際大学)、小泉晋一(共栄大学)、吉村 浩一(法政大学)
イン 前回は時間が限られて途中になってしまいましたので、本日あらためて時間を設けました。よろしくお願いいたします。
前回は時間を大幅超過した上、途中までしかお話できずに終わってしまいました。こうして再びセッティングしていただくことになりご迷惑をおかけします。今回は続きをお話したいと思います。こちらこそよろしくお願いいたします。
§ 教養部から文学部に配置換
イン 名大で文学部に移られますね?
辻 1974年4月、文学部心理学第二講座助教授に配置換になります。教養部にはちょうど10年間在籍しました。教務員として採用されたとき教官2名だった心理学教室ですが、この間に助手1名を含み5名の教官を擁するまでになりました。
当時、教養部はいくつかの重大な問題に直面していました。とりわけ70年代の学園闘争は忘れられません。名大の場合、終わってみればさほど大きな改革とはなりませんでしたが、若手教官の一人として得た経験は大きなものでした。一般教育と専門教育の関係について問い続けた末に、前回申したように「専攻に非ざる専門は教養」という見解にたどりつきました。その後、平成に入ってカリキュラム大綱化や組織改編により一般教育が大きく縮小あるいは変貌してしまったことを残念に思ってきましたし、その想いは大学を離れた今も変わりません。
文学部に移ることになったのは、心理学第二講座増設にともなう人事です。永年の構想が実現して第二講座設置が認可されたのは確か1971年だったと思います。それまでは意識、とりわけ知覚の研究を軸に運営されてきた第一講座に対して、新たに行動研究を推進する目的をもつ講座として発足しました。そして、初代教授に前田恒先生が着任され、2年後に私が助教授として加わりました。第一講座が横瀬教授・内山助教授、第二講座が前田教授と私、助手3名を加えスタッフ7名でした。講座は二つでも一体的な教室運営を行うというのが当時の基本方針でした。後年、私が退職するまでこの方針が堅持され、意識・行動の統合をめざすという課題を掲げて研究を進めることができました。
有難いことに、第二講座設置後まもなく動物実験施設の申請が通りました。先に着任しておられた前田教授の依頼を承け、文献を参照し動物管理・実験の経験も加えて設計したのが「心理学実験動物舎」です。途中で事務局から何度か図面の描き直しを求められ、そのたびに身を切る思いでしたが、管理・飼育繁殖・実験・解析に必要な最小の作業スペースを確保できました。そこには自分の団地住まいの“知恵”も生かされました。
§ 行動論的知覚研究
辻 卒研に始まった視空間知覚のテーマについては、前回お話したような問題に遭遇して一時期すこし距離をおいていました。しかし、60年代半ば動物行動を手がけるようになったのをきっかけに、そのアプローチや基本構想に変化が生じました。平面図形の奥行視は、視空間意識の中では対象操作や移動などの行動と無縁な、いわば背景的・画像的空間であり、その成立に関与する手がかりも限定されたものでしかありません。視覚場理論の枠組に据えたアプローチとしてはそれなりに意義のあるものでしたが、あの挫折以来、満足できないものを感じていました。そこに偶然が起きます。
NHK教育テレビ番組「高校理科:生物」のうち動物行動を扱う5コマ分の監修と出演の依頼が来ました。そのシリーズの一つ、生得的行動の紹介にWalk,R.D & Gibson,E.J.の「ヴィジュアル・クリフ」(視覚的断崖;visual cliff)実験を取り上げてデモをしました。番組そのものはうまく行きましたが、この装置を使って彼らが書いた論文の内容、特に装置の構造や被験体の選定には重大な難点があることに気づきました。この頃、同じように視空間知覚を研究テーマにしていた林部敬吉さん(後の静岡大学教授)と原政敏さん(後の朝日大学教授)と輪読会をやっていて、私たちの意見をまとめて彼らに送りました。今のようにメイルでというわけにはいかず、タイプで打ったコメントを郵送したのですが、返事を貰えませんでした。
それならばというわけで、独自に考案したのが「ヴィジュアル・ピットフォール」(視覚的陥穴:visual pitfall)です。この装置は、光学的落差を設けた点ではクリフと基本的に同じですが、クリフ実験が落差の有無に対する選好を反応としてとらえるのに対し、移動の自由度を高めて被験体の種に応じて落差の配置を変えることができるようにした点など改良を施した装置・技法です。
イン 被験体はヒヨコだったのですか?
辻 最初のシリーズではニワトリのヒナを対象にしました。先行研究に対する批判だったのですが、彼らの場合、ラットのような非視覚性動物を被験体としているのですね。その点、ニワトリはPortmann,A.の言う「巣立つもの」(離巣性)で、孵化時点で視覚にもとづく自立的な移動・採餌が可能です。落差への対処が生存にとって決定的な意味をもっています。幸い、大学の近くに孵化場があり、鑑別して不用になったオスびなを譲り受けて使いましたから、研究費もほとんどかからずに済みました。これは有難かったですね。
系統発生的にみてこの種では視神経が完全交叉していますから、網膜非対応の手がかりを考慮する必要がなく、その点でも分析がしやすいわけです。ヒナの片眼を一時的に遮蔽すると視野の広さがほぼ半分になります。するとヒナは欠損した視野を補うために頭部を大きく動かし、その結果、運動視差の効果が高まって落差の検知が処置しない場合と変わらないレベルに維持されました。
こうして、発生上の基本となる奥行距離情報は運動視差によって得られることが確証できたのです。しかし、この知見をふまえて複数の要因が関与するようになる過程、つまり手がかりの豊富化過程を明らかにする場合、さらに高い系統発生段階にある動物種を対象にする必要が生じてきます。そこで、一足飛びにニホンザルを被験体に選びました。ニホンザルの仔は出生時点で自立移動が可能ですから私たちの実験目的にも適していますし、視空間知覚に関与する要因がヒトとほぼ同じだろうとも推測できます。実験にあたっては、運動視差・両眼視差・肌理密度の3種を取り上げ、それらが個体発生上どのように手がかりとしてはたらくようになるかを週単位で追跡しました。
幸い、京都大学霊長類研究所が名古屋市の北、犬山にありますので、施設の共同利用を認めていただき、装置を運搬して出生直後から最長で約1年間、毎週観察を行ったのです。松沢哲郎さんが当時研究所助手をしておられてずいぶん支援してくださったおかげで、実験は順調に運びました。各要因の効果を検出するためにいくつかのノウハウを得たことも想い出します。両眼視差を無効にする方法として、片方の眼に一時的にオクルーダを装着することにし、コンタクトレンズのメーカーに協力を仰ぎました。最初は「視力増進のために製品を出しているのに目隠しするものを造れというのか」とお叱りを受けましたが、事情を説明しますとご理解いただき、前代未聞の遮蔽用コンタクトが誕生しました。これを試してみますと、私たちの心配をよそに赤ん坊ザルはすぐ脱着に慣れました。肌理密度の効果をしらべるにあたってもアイディアが生まれました。こういうところが共同研究の強みですね。
この実験は3年ほど続き、運動視差が出生時から作用し、生後3月齢ころになって画像要因つまり肌理密度が有効な手がかりとしてはたらくようになるという新しい知見を得ることに成功したのです。その一方、両眼視差についてはさほど関与しないという結果になりました。それについては、私たちの技法が移動・探索という活動事態を設定していることに関係しているかもしれませんが、他の研究者の報告でも同じような所見が出ています。さらに、落差事態において生じる注視・体動など視覚-運動系反応を分析したところ、手がかり機能の発達の基礎にある知覚-運動機能の発達も明らかにできました。
細部に立ち入った説明になりましたが、こうして実験開始から10年ほどで漸く視空間知覚の手がかり機能の「発生」を解き明かすことに成功したのです。
イン 視空間研究に縦軸、時間軸を入れたというわけですね?
辻 おっしゃるとおりです。視空間知覚の問題を、行動と関連づけ発生論的視点で解明することができ、ささやかながら達成感が得られました。関連することをお話しておきますと、手がかり機能の発生を扱う私たちに対し、個々の手がかりの距離特性を検討するというアプローチを当時NHK基礎研におられた長田昌次郎さんが発表しておられます。こうして、1970~80年代に視空間知覚の実証研究が我が国で進められたということをご記憶いただきたいと思います。
イン この間、他にもエピソードがあったのではないでしょうか?
辻 今こうして振り返りますと、いろいろ浮かんできますね。眼科や視能訓練関係の方から依頼があってピットフォール・テストを両眼視機能不全の施術前後で比較するとか、1歳半の定期検診に組み入れるなどしました。ダウン症候群のお子さんの場合、落差の知覚やその恐怖にはなんら問題がないのですが、落差を避けて移動するという課題を処理するのに手間取りました。その一方、落差を怖がる様子がまったくなくてそこに侵入するというケースが僅かながらありました。子どもが怖がると母親は恥ずかしがり、落差を気にしないと安心されますが、私には後者の例が気に懸りました。残念ながらフォロウアップできずじまいでしたが、知覚と情動の本来的な結びつきに不全が生じている可能性が考えられたからです。
それから暫くして、それと関連のありそうな問題に出逢うことになります。それが高層住宅における幼い子どもの転落事故です。60年代に入ると経済発展とともに都市への人口集中が盛んになり、それに呼応して高層集合住宅の建築ラッシュとなりました。それから十数年して起きた現象です。落差という形で視空間を扱ってきた私には無縁とは思えない問題でした。そこで並行して転落事故の調査を行いました。事故の原因として、全体のおよそ2/3にあたる事例が高所で喚起される恐怖の減弱によるものであることを突きとめました。この所見を発表したところ、フロアで聴いておられた報道関係の方が「高所平気症」というキャッチイな見出しで紹介してくださいました。それ以降この所見の追試が行われ確認が得られています。私自身は、転落という行動は本来的な知覚と情動のリンケージが緩んで両者が乖離した結果だとみなしています。
後年、科研費の補助を得て、「空間性感情の様態と発生に関する総合的研究」と題する研究プロジェクトを立ち上げ、そこでは基礎系と臨床系の研究者の参加を得ていくつかの新たな成果を得ることができました。もちろん残された課題はたくさんありますので、今後も継続していきたいと考えているところです。
この課題を意識するようになって、「滑り台」に注目しました。それを体験することによって高所慣れに歯止めをかけることができるのではないかという予想です。ヴィジュアル・ピットフォールを遊具として使用することも考えられ、基礎研究用に考案した装置の新たな使途になりうる可能性も捨てきれないでいるわけです。
イン そのあたりのことは何処かにまとめておられるのですか?
辻 じつはそれができていません。ちょうど学内外の仕事が増えた時期と重なり、資料収集も中途半端なままであることを反省しています。
§ 家畜育種学教室との連携
イン マウスの系統比較もなさっていますね?
辻 70年代に入ると、農学部家畜育種学教室との交流が始まり、近交系マウスの系統比較による行動遺伝的分析を手がけることになります。きっかけは、心理学への転専攻を考えていた学部生の海老原史樹文さんに行動遺伝学を紹介し、海老原さんがそれに関連した課題で卒研を行うにあたり助言者として加わることになったことです。60年代に始まった行動遺伝学では、研究者の多くが学習行動を取り上げていましたが、学習成績には感受特性・動機づけ・運動機能など多くの要因が関与するので行動と遺伝子との一義的な対応を求めることが困難だと感じていました。
そこで、先例のない活動リズムに着目したのでした。実験者としての海老原さんの力量が高かったので、卒研と修士研究を通じて興味ある事実が明らかになり、日周活動リズムという行動形質を規定する主導遺伝子を同定することに成功しました。海老原さんは、その後、三菱生命科学研究所で川村浩先生のご指導の下、生物リズム発現機構に関して注目すべき成果を収め、第一線の国際的研究者として現在も活躍なさっています。
この出逢いが機縁となり、私たち心理学教室でも80年代半ばまでおよそ10年間、いくつかの行動の系統比較が行われ、またそれと並行して両教室の連携によって実験動物としての近交系マウスの行動特性検定の知見が蓄積されました。
イン スンクスとのかかわりはどういうきっかけで始まったのでしょうか?
辻 先にも申しましたように、私の動物行動研究はゼロから出発していますが、当初から心理学における動物実験の在り方、特に対象とする動物種の偏り、いわゆる「ラット・サイコロジー」に疑問を抱いていました。そして、現状を改めるには、系統発生を視野に収めた種の選定が必要だと強く感じていたのです。育種学教室との交流・連携が深まる中で、そのことを近藤教授にお話したところ、実験動物として新たに開発されたスンクスを対象にしてはどうかとの助言をいただきました。
スンクスとは、食虫目トガリネズミ科ジネズミ亜科に属するジャコウネズミ(Suncus murinus)の野生個体を起源とし継代繁殖された、“名大ブランド”の実験動物です。
私の求めていたものとピッタリだと判り、1979年秋に導入して以来およそ四半世紀にわたってその行動研究を進めました。幸い、教室でほぼ毎年、学部生・院生が関連の課題に取り組んでくれましたし、並行して「ドメスティケーションに伴う行動変性」という包括的テーマを掲げ、生息地におけるフィールドワークや野生個体の継代繁殖でも協力体制ができました。私が学部長・副総長の職にある間も継続できたのは、そのおかげです。教室の力を実感し、感謝の念を禁じえません。
§ 名大で行われたプロジェクト
辻 名大では学生・教官として45年間を過ごしました。学生としては、教養部・文学部・大学院教育学研究科に、また教官としては教養部・文学部に籍をおきましたし、その間、医学部・農学部・工学部・環境医学研究所など学内他部局との交流・連携の機会も少なくありませんでした。ですから他にもいろいろ想い浮かぶことがあります。その一つ、これは私自身が関わったことではないのですが、我が国の研究プロジェクトとしては他に例をみないものですのでご紹介しておきます。
それは1950年代に米国の財団から当時として多額の資金助成を得て行われた「日本人研究」です。このプロジェクトは、医学部精神医学教室の村松常雄教授を代表者とし、精神医学・心理学・社会学の研究者により構成されたチームで数年にわたり行われた大がかりなフィールドワークでした。心理学では、村上英治・丸井文男・秋谷たつ子・関根忠直の諸先生をはじめ、協力者として星野命・詫摩武俊先生らも東京から参加されていました。心理学チームは心理検査を担当し、その中でTAT名大版の開発やロールシャッハ・テストの分析法の改善などが行われました。その成果が『日本人-文化とパーソナリティの実証的研究-』(村松常雄編、黎明書房、1962年)として出版されています。
その一環として継続されていたTAT分析の基準作成には、博士課程在籍当時に加わったことを憶えていますが、このような大規模な研究が当時行われていたことをぜひお伝えしておきたいと思います。学史的にも意義あるこのプロジェクトを資料として保存するべく、在職中に学内の資料センター・図書館や拠点だった医学部精神医学教室に照会したのですが、残念ながら関連する資料は残されていませんでしたし、当時のことを知る人にも会えませんでした。もうすこし早く手を着けておくべきだったと後悔した次第です。
§ 中京大学心理学部
イン 名大から中京大学へ移られますね?
辻 名大を停年退職した後は自由の身でそれまで叶わなかった海外生活を送るという人生設計を立てていたのですが、すぐ近くにキャンパスのある中京大学の心理学部発足にあたりお誘いを受けました。中京とは古くからご縁があり、文学部心理学科設置当初から非常勤で実習や講義を担当していましたので、ご厚意を受けてお世話になることに決めました。6年間在職し、カリキュラムの設計や大学院生選抜の在り方など、あらためて教員として学ぶことが多くありました。初代研究科長を仰せつかり、研究科共通の必修科目として学史・学論を担当した経験も貴重でした。
中京では個々の教員ごとに指導学生をもつというゼミ方式でした。名大では第一・第二講座の教官が一体となって教室として教育研究活動を進めていましたので、当初その運営方式に戸惑いました。その上、日心や基礎心の代表者を務めていて名古屋を離れることも多く、授業や学生指導に専念することが難しい時期でもありました。しかし、学生諸君が私たちのゼミのモットーとした「自立と自律」の精神を酌んでくれて、国立とは別のよさを実感できました。
§ 海外研究者との交流
イン スンクスの研究は名大を停年退職されたのちも続くのですか?
辻 1980年代に入り、スンクスの行動研究の成果が挙がり始めますと、その発表の場として欧州の行動生物学者の集まり、例えば国際動物行動学会議(International Ethological Conference;IEC)や動物行動集会(Animal Behaviour Meeting)に参加の機会が増えます。また、ドイツ語圏エソロジストの研究集会、欧州若手研究者のセミナーなどに招かれて講演するなどの交流も深まっていきましたが、スイス・ロザンヌ大学のフォゲルさん(Prof. Peter Vogel;理学部生態進化教室教授)との出逢いは大きな出来事でした。90年代に何度か彼の研究室を訪ねるうち共同研究の話がまとまり、名大で停年を迎えるとロザンヌに滞在、半年あまりトガリネズミの行動の異種間比較を行いました。
名大在職の最後の数年間は全学の管理運営に関わり、大学院重点化や組織改編、迫っていた法人化への対応などに取り組んでいましたので、ロザンヌでは、職務から解放されて学生時代以来久しぶりに実験三昧の日々を過ごしました。作業を終えて日付が変わる頃に帰途につくのですが、眼下のレマン湖の黒々とした湖面の向こうに瞬く対岸のフランス・エイヴィアンの幻想的な灯りに疲れを忘れたものです。
生態学・発生学者のフォゲルさんと私とは相互に“越境”しあいながら、それぞれのアプローチの特徴・意義について理解を深めることができました。特に、心理学における発生的アプローチと生態研究との補完的関係を認識できたことは大きな果実だったと思います。そんな彼との付き合いももう叶いません。昨年1月、訃報が娘さんの一人から届きました。その衝撃は今も治まっていません。
§ 学会運営
イン 日本心理学会と日本基礎心理学会の理事長を務められましたね?
辻 はい、基礎心は1999年から2期6年、日心は2003年から1期2年でした。他に、日心理事長1年には日心連(日本心理学諸学会連合)の代表も兼ねていました。それぞれ問題を抱え、けっして平穏無事とは言えない時期でした。
基礎心では会員減少が懸念され、学会誌編集の見直しや高校生向け講座の開催など活性化のための方策をあれこれ考えました。日心のほうにも、組織改変・定款改定、公開事業の拡充、欧文誌の委託などのほかにも多くの課題がありました。
イン 国資格化の問題もそうですね?
辻 2003年だったと思いますが、主として医療分野に従事する専門実務者の国資格化を実現すべく関係諸団体による「医療心理士国家資格制度推進協議会」を発足させ、心理学・医学医療など関係団体の参加を得て、代表者として資格内容の検討や養成カリキュラムの策定、国会議員への要望などに努めました。当初、日本心理臨床学会や日本臨床心理士資格認定協会の方たちは、すでに実効を挙げている民間資格との関係もあり、また国資格となった場合に上位規定の医事法制による活動の制約を懸念され、様子を見ておられたようです。そのため最初のころは私たちが専ら要請する形だったのですが、その中で私は一貫して広い職能に関わる包括的な資格を念頭において活動していました。
イン 漸く実現しましたね?
辻 2004年に議員立法の形で上程された案が審議直前になって郵政民営化解散の煽りでいったん“お蔵入り”になりました。その時点で推進協議会会長を後任の日心理事長に委ねて退いたのですが、その時点ではすぐ再提出になるものと期待していました。しかし、どういう経緯かは存知ませんが、その後10年の歳月を経て漸く実現となりました。まずは同慶の至りです。
この上は、社会的評価に堪える人材を養成しなければなりませんが、そのために学界挙げて教育水準の向上を図る必要があると思います。徒に実務に走るのではなく、心理学の広範な学識をもち、他の職能との連携に役立つ基盤を整備していただきたいというのが私の切なる願いです。
§ 研究遍歴の総括
辻 今年(2016年)は心理学を専攻してちょうど60年の節目に当たります。あれこれ自分の探索をたどってきましたが、まとめをしたいと思います。
冒頭に申しましたように、理学部と文学部の選択肢から文学部を選び、志望の社会学から心理学に転専攻し、研究の過程で機構論から発生論へ、知覚研究から行動研究へと、何度も“転向”を重ねてきました。出身高校の校是は「一以貫之」でしたので、それに背くようではありますが、自分としてはそのたび新たな展望が開けたように思います。しかも、転向が可能になったのは環境のおかげだと強く感じるのです。高校では、その校風と時代に援けられました。放課後には化学実験や天体観測に熱中しましたし、図書館の書庫で研究書を読んだりもしていました。そういう経験を通じ、単一の問題にも多様な観点から迫ることができることを理解できたのは大きな収穫でした。
学史的にみて1950~60年代、心理学界では学派期の“空気”が残る一方、既存領域分化と領域統合が同時進行していました。
学部在学中は専ら知覚実験心理学に浸りきった生活でしたが、大学院で教育心理学専攻に所属して同学の多様な領域に接し、自分の視界が広がりました。最初の職場が教養部だったこともプラスになりました。60年代末から70年代半ば学園を揺るがせた波を受け、教官は自分たちに課せられた問題に日夜取り組みましたが、その中で「教養とは専攻に非ざる専門である」と考え、他分野への“越境”を怖れなくなりました。「自由闊達」を旨とする名大の学風も幸いしました。教育研究上の連携についてはお話しましたが、遡れば学部在学時にも卒研の助言を求めて医学部眼科教授室に伺ったり、院生当時は生理学や精神医学の人たちと輪読会を続けたりしたことも“人見知り”の性格を変える一因となったように思います。
イン 羨ましいことですね
辻 近ごろは資格や学位の取得が直近の課題になり、若い人たちがこういう“探訪”をしづらい状況にあるようで残念です。「こうすれば面白い」と判っても、それを一時お預けにしなければならないのは気の毒です。今の若い人たちにとって学位は“免許証”ですから取らなきゃ食えない、切実な問題ですよね。その点、私たちの時代にはある意味の“開き直り”ができました。博士号は「足の裏の米粒」でしたからね。
教員としては、教養部・文学部、そして中京大学心理学部に所属しましたが、それぞれの職場で得られたものも貴重でした。
さらにまた国内の研究活動に加え、もう一つの“越境体験”である海外生活を通じても多くのことを与えられました。当時の仲間が相次いで他界して寂しくなりましたが、彼らと共有してきた課題の達成に向けて努力していきたいと思っています。
§ 付言
辻 今回、このような機会を与えていただき、おかげで自分のささやかな遍歴を振り返ることができました。ただ、オーラルヒストリイにおける当事者の立場を経験するのが初めてでしたから、テープを起こしてくださった文面に眼を通しますと話し言葉の冗長さ・曖昧さや無駄な繰り返しが目立ちました。そこで、かなり大幅に削除し、全体を再構成させていただきました。これではオーラルではないとお叱りを受けそうですが、面接者・編集委員の方々のご寛容をお願いする次第です。