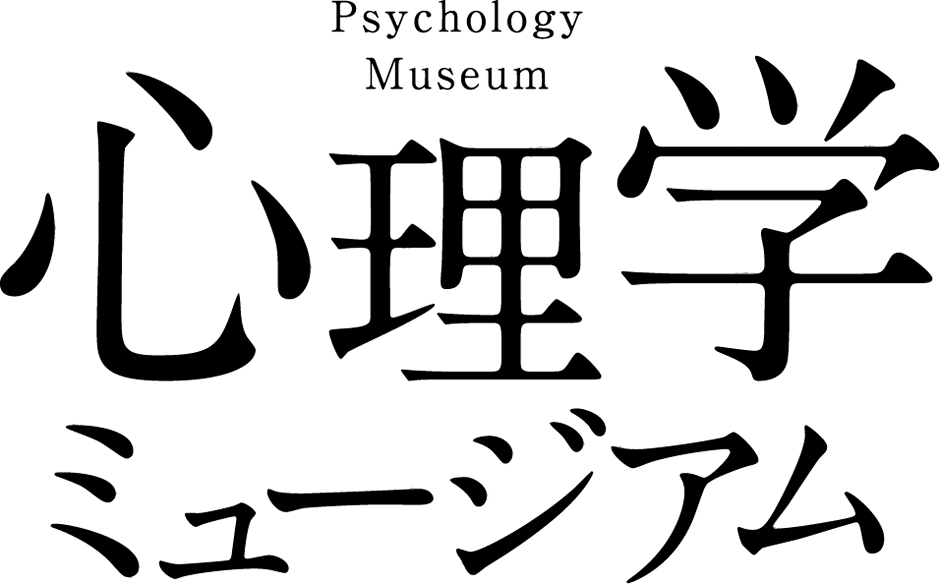鳥居修晃先生
動画は抜粋です。インタビュー全文は下記からご覧ください。
鳥居修晃先生の略歴
・旧制高校理科乙類・東京大学心理学科での授業・労働科学研究所でのアルバイト・サブリミナル広告の委託研究・眼球運動研究・アメリカでの在外研修・先天盲開眼者・感覚代行研究会
・1959年東京大学博士課程修了、東京工大助手、東京農工大学助教授、アメリカミシガン大学眼科学視覚研究所、フロリダ州立大学分子生物物理学研究所へでの在外研修を経て、1991年東大定年退官、2000年聖心女子大学定年退職。博士論文『視野における図一地の形成とその存続に関する研究』
・お話のなかで、先生が学生の頃の東京大学の心理学研究室の様子が生き生きとイメージできました。さまざまなテーマに遭遇しながら、先天盲開眼者研究との出会い、そこから次から次へと新たな発見を積み上げていく様子が伝わってきました。
日時:2016年3月3日(木)
場所:公益社団法人日本心理学会 事務局
インタビュアー:荒川歩(武蔵野美術大学)、小泉晋一(共栄大学)、高砂美樹(東京国際大学)、鈴木朋子(横浜国立大学)
場所:公益社団法人日本心理学会 事務局
インタビュアー(以下、「イン」と略)A 本日は、日本心理学会のオーラルヒストリーにご協力いただきましてありがとうございます。事前にいくつかお伺いしたいポイントはお送りしていますが、それに沿っていただいても、沿っていただかなくても結構です。まず、最初にお送りしたものでいきますと、なぜ心理学を学ぼうと思われたのかということです。いろいろな時代背景等もあり、心理学は、それほど有名ではなかったかと思いますけれども、その中で心理学に出合われたきっかけなどを、お話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
鳥居 では、旧制の高等学校の理科乙類に入った頃から始めます。3年間を高校で過したのは私どもの学年が最後です。新制に切り替わったものですから、私どもの次の年からはもう3年間在学する人たちはいなくなってしまいました。
理科乙類というところは、医学部、そして農学部などの方面に進みたい人が入るコースなのですが、医学部志望の人が多く、ドイツ語が第一外国語だったのです。そのせいで、時間割を見ると、ドイツ語の時間の方が多く、英語には思ったほどの時間が組まれていなかったという記憶があります。
ただ、私はもともと医学部に行くつもりはありませんでした。なぜ理科乙類に進んだかというと、最初に父親に相談したら、「他の学科に行っても就職口はないぞ」と言われ、次に中学の先生に相談したら、「君は理科が不得意だというから、不得意な方をやった方がいい」と言われました。そこで、「では試しに」と思って受けたような次第です。
その頃、読んだ本の中で、心理学に関係しそうなものを挙げるなら、高良武久著『性格学』という本があります。もう一冊はOtto Weiningerの『性と性格』という本で、書棚を探してもどこへ行ったか出てこないのですが、面白く読んだ記憶があります。
理科ですから、授業では、数学、物理学、動物、植物、化学という工合いに、理科系のものが目白押しでしたが、そのようなものの中で文科系と思ったのは、串田孫一先生が講師で来ておられた哲学の授業です。普通、哲学というと、だいたい哲学史でしょうが、串田先生の授業は、例えば「虚栄について」というテーマで1時間、考察を加えるという方式でした。これはあとから考えてみますと、かなり心理学に近いという気がするのですが、受講しているのは大半が医学や農学志望の連中ですから、だんだん受講者が減ってしまい、最後は2人だけになりました。
それから、個人的に少し関係するかなと思うのは、英語の講読テキストで、H. G. Wellsの『タイム・マシン』を楽しく読んだことです。先生が少し訳されては、学生にも、「この先を訳しなさい」という授業でした。細かな内容は覚えていないのですけれども、強く記憶に残ったのは、「threshold」というterm(ターム)でした。そのテキストの後ろに注が出てくるのですが、そこを見ると、「心理学上の術語」と書いてあり、ドイツ語では、「die Schwelle」、それを「識閾」と和訳してありましたね。それから、もう一つ面白かったのは、Darwinの『ビーグル号航海記』です。このようなところが、今思えば心理学に関係した読書の遍歴だったのかも知れません。
さて、いよいよ卒業が近づきましたので受験しなければ、ということになり、医学部を受けるかどうか決めなければなりませんでした。しかし、医学部というところは、人体のいろいろな部位の名称、術語を覚えなくてはならず、あまり暗記が得意ではないので、それは厄介だと思い、また、解剖をやるのが億劫になる出来事があって敬遠したくなりました。その出来事というのは、六高を出て人類学科に入った友人(江原昭善氏)に「脳の解剖をやるから来い」と誘われたのです。彼はどこからか脳を取り出してきて目の前にポンと置き、「ここからここまでは、云々」と領野区分を大まかに説明してくれたのです。彼はその脳を素手で持ち、さらには、「昼になった」と言って、洗いもしないその手でコッペパンをかじり出したのです。そのことを指摘すると、「いや、自分だって、最初はこんなことできなかった。3日ぐらい飯、食えなかったよ」と言っていましたね。そのようなこともあって、医学部はとにかく敬遠し、結局1年待って、文学部を受験しようかと思ったのです。
なぜ文学部かというと、本当は美学科へ行きたかったのです。ところがこれまた、「美学出たって、就職口は何にもない」などと反対されました。「では心理学ではどうかな」と思い付き、志望先を書くよう指示されていましたので、第1志望を心理学、第2志望を美学美術史と書きました。そうしたら、受験後何日かして合格通知が家に来たとき、「心理学」と書いてあったものですから、またおやじに「医学をやっていれば、心理学でも美学でもできないわけじゃないだろう」と反対されたのです。しかし、いまさら医学部受験も面倒だし、受かるどうかも分からないということで心理学に決めてしまいました。
出身大学と出会った先生
かくして、昭和26年、1951年に文学部心理学科に入学したのですが、そのときの主任教授は千輪浩先生で、担当しておられた講義の一つは「心理学概論」でした。先生のもう一つの講義が、「社会心理学の基本問題」でこれも受講することにしました。
さらに、教授のポストに高木貞二先生がおられ、担当されたのは「学習の問題」という講義ではなかったかと思います。当時の私の手帳には、「学習の問題」としか書いてないので不確かですが。2年目に「実験心理学」を受講しているのですが、これは間違いなく高木先生のご担当でした。高木・城戸両先生の『実験心理学提要』という必読の本がありますが、その第1巻のI.を高木先生が書いておられます。先生から、心理学における実験法として精神物理学的測定法を体系的に教えていただいたのです。
その頃海外に出張しておられた助教授の相良守次先生が帰国されて翌年には、「記憶心理学の諸問題」という講義を担当されました。
このほか、学内の講師として増山元三郎先生の「推計学」の授業がありました。これが難しい内容で、次々書かれていく数式を、何しろ文学部の連中ですから、ぽかんとして見ているだけなのです。「これで試験になったらどうしよう」と、みな恐れていたのですが、ノートさえ出せば単位を頂くことができました。しかし、まるで分かっていませんので、推計学に関しては、あとでも言及しますが、いろいろな本で勉強した覚えがあります。
もうお一方、のちに文学部に移られる梅津八三先生ですが、当時はまだ教養学部のご担当で、文学部へは非常勤として来ておられました。1年生のときに、受講したのが「知覚空間の問題」でした。次の1952年(昭和27年)には、「知覚心理学の諸問題」を受講しました。前者の講義の中では、あとでお話しするSendenや、そして梅津先生ご自身が執筆された先天性白内障手術後の視覚に関する論文にも言及されているのですが、これは受講ノートを見るまでもなく覚えていました。
この他に、1年のときには、「実験心理学演習」いわゆる一般実験ないし普通実験という演習があり、むろん必修でした。これは、当時心理学研究室の助手をしておられた瀬谷正敏、東洋、詫摩武俊の諸先生による指導のもとに実施されていました。また、能率研究室という部門が心理学研究室以外にありまして、そこに助手として臼居利朋先生がおられました。さらに特別研究生として水原泰介、大山正、大川信明といった方々が研究室で机を構えておられ、心理学の実験方法に関する具体的な指導をしていただきました。終了後レポートを出し、採点のうえ返してもらいましたので、今でもそのレポートは全部自分の机の中に残してあります。
非常勤の先生として千葉大学の盛永四郎先生が、それは学部のときか大学院のときか、ちょっと不確かなのですが、「ドイツ心理学の発展」というテーマで講義をしてくださいました。これも受講ノートが保存してあります。盛永先生は、5年間ドイツに留学され、Metzgerや、反転図形のRubinのところで研究された方ですから、ドイツ心理学史については通暁しておられたのだと思います。ご専門の視知覚の問題についても、ずいぶん詳しく教えていただきました。
大学院に入ってからも、盛永先生が講師として来ておられて、MetzgerのPsychologie : die Entwicklung ihrer Grundannahmen seit der Einführung des Experimentsという厚い本をテキストとして使いましょうということになったのですが、ドイツ語ですから、だんだん受講生が少なくなってしまい、最後は私1人が残りました。
それから、慶応義塾大学の横山松三郎先生が大学院の非常勤として来ておられました。私の記憶が確かならば、「機能主義と構成主義」というタイトルの講義をしていただいて、心理学の歴史についてずいぶん勉強になりました。
横山先生は、講義を終えられると、5、6人、あるいは7、8人いる聴講生全部を一緒に喫茶店へ連れていってくださって、そこでもいろいろなお話をしてくださったことを覚えています。さあ、帰るという段になると、先生が全部払ってくださるのです。それで皆で「講師料がなくなるのでは…」などと余計な心配をし合った覚えがあります。
さらに、当時東京工大におられた宮城音弥先生が精神疾患に関する講義をされたと思うのですが、受講ノートも見当らずその内容がもはや分からないのです。
1年生のときには、何しろ割とゆとりがありました。それで、文学部の他学科の講義も聴いてみようと思って、美学科の竹内敏雄先生の「文芸のジャンル」と、元教育大の家永三郎先生の「日本近世思想史」、それから、吉田精一先生の「自然主義研究」も聴講しました。その他に、「西洋哲学史概説」、「独文学史概説」などがあったのですがだんだん負担になってきて、全部聴講しおおせたのは、上に挙げた三つの講義、「文芸のジャンル」と「近世思想史」と「自然主義研究」だけです。
先程助手の先生方をご紹介しましたが、その後、吉田正昭先生、確か2年先輩の方ですが上記のどなたかの後任として助手に就いておられます。その次でしたか、教養学部梅津先生の研究室で助手をされていた中島昭美先生が文学部助手として転任してこられました。また金城辰夫さんがこの時期に助手をしておられる筈ですが、どの辺りで活躍されたのか私には分からなくなっています。
吉田先生は山と写真が十八番の方で、私は山歩きにずいぶん同行させてもらいました。後立山連峰のときは吉田さんと私の2人だけでしたが、確か同級の笹本至心君も参加した3人による槍ヶ岳から宇奈月の方までの縦走もありました。南アルプスへも行っています。北アルプスの稜線は、割合高低差が少なく、少し下りてもまたすぐ上がって、またちょっと下りてまたすぐ上がるという工合ですが、南アルプスは、急激に上がって、また急激に下りるという状態の山々が連なり、また山小屋が相互に非常に離れていますから、われわれのような貧弱な体力の者では、とても一日で、たどり着けないこともあるのです。南アルプスのときは私は比較的足が速かったものですから、一番後ろに吉田先生がいて、その前に、初めて山歩きをしたという深田芳郎君がいるのを尻目に先頭切って歩いていったのです。そうしたら途中で、屈強な山歩きの男性が数人下りてきたのに出会って「1人か?」と言うのです。「いや、友達が2人後ろに」、「え? 後ろに? だめだよ、分かれちゃ」と、「1人でばらばらに歩いちゃだめだ」、「このへんでビバークした方がいいんじゃないか」とも言われました。まだ山小屋まではかなりあったのですけれど、吉田さんの決断でその辺りでビバークすることになりました。あとで気がついたのですが、その屈強な人たちは、多分もっと先まで行く予定だったのでしょうが、近くで、やはりテントを張っているのですね。どうやら、われわれが危なっかしいのでチェックしてくれていたのではないかと思います。この辺りで吉田さんが撮影された写真がたくさんわが家にも残っています。以上が公私のさまざまな面にわたって当時研究室でお世話になった方々です。
研究室以外でお世話になった方についても忘れることはできません。それは学部1年の夏休みのことだったと思うのですが、学生が集まる研究室の壁に、統計的な資料の処理に関するアルバイトを国立教育研究所で募集しているという貼り紙が出ていたのです。それで、私は「統計的な処理を勉強するよいチャンス」と思って、先輩の税所篤郎さんと2人で応募し採用されました。
仕事の内容は、あとで知ったのですが、肥田野直先生が担当された、いわゆる進学適性検査に相当する旧制高校受験の際の試験結果の分析でした。私自身もそれを受けているのですが、それらの資料は、全部教育研究所に集められて、保管されてあったらしいのです。それに対してランダム・サンプリングを企画されたのだと思うのですが、肥田野先生のご指示で、何枚かおきに1枚取って、集めたサンプルを処理する下仕事をしました。タイガー計算機を来る日も来る日も回していました。ところがある日そのサンプリングの対象になんと自分の答案が当たってしまったのですね。これは確かではないのですけれども、あとで伺った話では、全国の旧制高校で、何人受けたのかは知りませんが、満点を取った人が二十数名いたということでした。残念ながら、私は、1題、暗号を解かなくてはならない問題を時間切れで解くに至らず、満点ではなかったのを覚えています。
ただ計算機を回すだけでは勉強にならないので、推計学や数理統計学の本を読むことにしました。東京女子大の数学科と津田の数学科のそれぞれ出身という研究所の職員の方たち(榎本富美子さんと二星イセさん)には、ずいぶん助けていただきました。
もう一つは、学部の2年以降のことなのですが、最初八重洲口の国鉄本社内にあり、あとで駒込駅の構内に移った国鉄の労働科学研究室に、アルバイターとして、ずいぶん長く通わせていただきました。このときの研究員として、相馬紀公、清宮栄一、小瀬 輝の諸先生がいらっしゃいました。戦争当時、中目黒に海軍技術研究所という施設があり、私は中学2年のときには勤労動員でそこへ通っていたのですが、正門を入るとすぐ、白い横長の看板がありました。「実験心理学研究室」と書いてあり、左の方へ行くように矢印がしてあったのが今でもありありと目に浮かびます。先程の先生方はまさしくここにおられたらしいのです。要するに海軍が解体されましたから、海軍技術研究所所属の方たちが、その国鉄の労働科学研究室へ移られたのではないかというような気がいたします。
この労働科学研究室でも統計的な処理法に関して、多くのことを教えていただきました。あとで知ったのですが、どなたも東大心理学科出身の先輩だったのです。
インA 大学の心理の学科の授業だけではなくて、あちらこちらに行かれたのですね。
鳥居 そうですね。あの頃は、今と違って、大体、年に3回か4回ぐらいは休講があります。始まるのも4月後半ぐらいで7月に入ると、もう殆ど講義はないという状態ですから、実験でもしていれば別ですけれども、まだ学部では自分の実験というわけにはいかないものですから、とにかく統計法の勉強を、と考えて探しました。
特に、あの頃は、統計がやかましく叫ばれるようになってきた時代なのです。論文を出したくても、統計処理や何%で有意などというような話が載っていなければ通らないという有様の風潮が始まりかけていました。増山先生の推計学は難しいので、臼居先生のご紹介もあって、『医学・生物学のための推計学』(鳥居敏雄・高橋晄正・土肥一郎, 1954, 東大出版会)をまず入手し、少しずつ勉強し始めました。
インA ありがとうございます。そして、「図‐地反転を規定する諸要因の分析」という卒論を書かれたと思うのですが、このテーマを選ばれたきっかけなどはあるのでしょうか。
鳥居 きっかけですか?新制で入学した場合と違って、私は旧制の扱いだったので、2年生のときに、特殊問題研究(卒論の予備実験のようなもの)をしなければいけなかったのです。テーマを考えているとき、梅津先生が書かれた触空間の問題に関わる論文を思い出したのです。臼居先生のお世話で、円盤あるいは、針金をいろいろな大きさ、長さで木の板に貼りつけた実験材料を作ってもらい、それを使って触覚的な大きさや長さの判断を求める一連の実験を試みました。ところが、卒論はこれとは違うテーマでした。このテーマの決定にはある出来事が関係していると思っています。いつのことだったか覚えていないのですが、図-地反転の問題に関連した大山先生の手書きの論文を、「清書」したことがありました。また『Dynamics in Psychology』(1940)というKöhlerの本が、あの頃出ていて、それを読んで以来、図-地とその反転の問題に関心をもっていました。これを卒論のテーマにしようということで、「図-地反転を規定する諸要因の分析」というタイトルで書きました。その際、大山先生が、『千輪浩先生還暦紀念論文集』(1952)に書かれていた「図形残効と反転図形」という論文や、同じ本に掲載されている、当時北大におられて、その後聖心女子大に移ってこられることになる野澤晨先生が書かれた、「図形残効に関する一実験」も、たいへん参考になりました。
インA:それを発表されたのが、心理学研究に大山先生と共著で書かれた『図-地反転の実験的研究』ですね。
鳥居 はい。1955年のことでした。ところがその頃、1949年に出たHebbの『The Organization of Behavior』が視知覚の研究分野に画期的ともいえる影響を及ぼし始めていました。梅津先生のゼミで1年先輩の院生たちが、これを読んでいると知り、同級生と語らって、「読もう」ということになり読み始めました。最初の数章では、Köhlerへの批判やSendenの仕事に関係した問題が扱われていますから、何とか鳩首勉強した覚えがあります。
さて、実は大学院に入って2年目にあたりますが、私にとって新たな経験となることが起こりました。中山書店から『芸術心理学講座』というシリーズが出始めたのです。 5冊ある講座の分冊のうちの一冊が、相良先生編の『芸術と心理』という巻で、この中の「実験心理学」という項目について、書くように、と言われました。もう一つは、宮城音弥先生編集の『芸術と人間』という巻なのですが、ここでは「絵画と生活」について書くようにと指示されました。これらを完成させるまでに、国谷誠朗氏(美術史学科と心理学科卒業)にずい分輔けてもらい、深く感謝しています。すると、梅津先生にあるとき呼ばれて、「芸術心理学に興味があるようだから、これを研究テーマにしたらどうか」と勧められたのです。でも、芸術について実験心理学的に研究するのは容易ではないと考え、もっと先の課題にしようと、ひとまず諦めました。
それから、もう一つは、1957年に平凡社から『心理学事典』が出たことと関連しています。これは、もう大々的なもので、本郷に平凡社の分室(のようなもの)があったのですが、確かそこに藤永保先生が泊まり込んで、項目選定や執筆者の選出などをしておられたようです。われわれ院生もお手伝いに行った覚えがあります。その折、一つは「図-地」、そして、もう一つは「色のあらわれ方」について書くようにと言われました。それらは、もともと盛永先生にお願いしたものだったらしいのですが、先生が、私に回すようにと言われたとのことでした。Rubinの原著と、色のあらわれ方はKatzの原著を、ノートを取りつつ読み返して項目を書いた覚えがあります。この経験もあって、図と地とその反転という問題はこのあとも私の研究テーマの一つになっていきました。
サブリミナル広告の委託研究
これ以外に私が関わったものに、相良先生のところに寄せられた委託研究がありました。実は、当時、サブリミナル広告というものが米国で問題となっていたのです。映画を上映しているときに、ごく短い提示時間で「Eat pop・corn」あるいは「Drink Coca Cola」というメッセージを出したというのです。それを出したことには、観客は気づかなかったというのですが(つまり、閾下だったというわけですが)、それを提示しなかった場合と比べると、売り上げに差が出たというのです。これがちょっとした騒ぎになりました。それで輿論協会が、「サブリミナル広告というようなことが言われているけれども、本当に効果があるのかどうか、実験的に吟味してもらえませんか」という委託研究を相良先生にお願いしてきたのです。相良先生からそのことを伺ったのですが、1人ではできませんので、同級生だった鹿取廣人さんに話しました。それから、当時東京工大の助手をしておられた多湖輝先生が、ミュラー・リヤーの錯視図形の矢羽を閾下で出しても錯視が出るかどうかという実験をしておられたことを思い出して、鹿取さんと2人で多湖さんのところに行き、「相良先生から、こういうお話があるのですが、一緒にやっていただけませんか」ということで、共同実験を開始しました。
いきなり広告効果があるかどうかというのでは飛躍しすぎなので、もう少し地道にやろうと、これは、確か文献があったと思うのですが、顔の表情判断を実験テーマの一つに選びました。
もう一つは、図形の直後再生に及ぼす閾下の命名効果という実験でした。この二種類の実験に関わる結果は、世論協会発行の市場調査に発表したのですが、この冊子が、もう1か月近く探しているのに出てきません。
その後、相良先生のもとに、今度は電通から閾下刺激の効果に関する実験の依頼が来ました。そのため上記のメンバーで電通ではずいぶん実験を重ねました。ある程度成果が出ましたので、「識閾下刺激の効果に関する実験的研究」というタイトルで、1954年の日心23回大会で、相良先生を筆頭にして、多湖さん、渋谷さん(東京女子大卒)、鹿取さん、そして私と、5人の連名で発表しています。
ここで発表した実験の1つは、分割線錯視を使ったものです。これは、二本の線分の間隔が小さいいくつかの線で分割されると、コントロールよりも長く見えるという錯視です。分割する線を閾下で出したらどうなるかという実験でした。この実験の結果は、1962年に相良、鹿取、鳥居の連名で『Japanese Psychological Research』に発表してあります。その他にもいくつか実験があったのですが、いずれもさらに吟味を加える必要があるという結論になっていたと思います。
しかし、やがて、だんだんサブリミナル広告など怪しいのではないかという議論が、アメリカでも行われるようになり、もっと実験を重ねるという意欲は消えてしまったのです。ずっとあとになって、サブリミナルへの関心が復活したようですが…。
ここまでが、大学院在学中の研究にあたるでしょう。
博士論文の提出
私がドクター論文「視野における図-地の形成とその存続に関する研究」を提出したのは1964年、昭和39年のことですが、これは学部を卒業してから、ちょうど10年目にあたります。なぜ、このように時間がかかったか振り返ってみると、その当時の大学院生の間では、ドクターコースが終わってもすぐにドクター論文にはつながらないというような考えがあったのではないか、と思います。ところがあるとき、大学院生や院を卒業した30人ほどが本郷にある学士会館の分館に呼び集められまして、相良先生から「ドクター論文を書くように」とのご指示がありました。そこで、ドクターコースの1期生であるわれわれが走り出さなくてはいけないのではないかと麦島文夫、鹿取廣人の両氏とも話し合って出す決心を固めました。
私が博士論文の第1章で扱ったのは、図と地の形成がどのようなファクターで決まるのかという問題です。これは盛永先生の『類同の法則と視野体制』という、先程の『千輪先生還暦紀念論文集』(1952)に掲載された論考を私なりに発展させようとしたものです。この中でRubinの「横顔と酒杯の図形」について「2つの横顔をそれぞれ異なった色で描く」と「2つの横顔は見えやすくなる」と書いておられる一文をヒントに、その上下の一部をカットした変形図形を作りました。ちなみに「これは酒杯というよりも高坏の方がよい」と、苧阪良二先生から伺った覚えがあります。この左右の横顔を同じ色にした場合、あるいは、同じ明度にした場合、これらを変えた場合などと条件を変えると、一定の条件下では横顔が地になりにくくなるのです。つまり、横顔が、図としてあらわれやすくなるのですね。これは、学会発表もしましたし、『Perceptual and Motor Skills』の編集部から、あるとき手紙が来まして、「無料で載せるから、1ページの論文を書くように」と言ってきたのです。そこで、このときの一部を『Effect of unequality in color upon figure-ground dominance』(1963)というタイトルで書き送った記憶があります。
何日かして北大におられた結城先生が、たまたま研究室にいた私に電話をかけてこられて、「君の書いた論文は、不十分だ。あれだけで論文を書いてはだめだ」とお叱りを受けました。それがご縁になったのかも知れませんが、以後結城先生からは多くのことを教えていただきましたし、先生が北大から中京大学に移られたあとならびに退官されたあとに、先生を囲む研究会を有志と続けました。例えば、八王子セミナーハウスのようなところで、結城先生を囲む、泊まり込みの研究会を実施しております。
博論に戻りますと、第2章では図と地の反転速度が何によって規定されるのかという問題を扱っています。この一部は、『Japanese Psychological Research』(1960)の中に含まれています。
このあと、第3章では、反転と眼球運動の関係を研究課題にしています。このテーマは結城先生が1952年に北大の紀要に書かれた「形と動き」というタイトルの論考および苧阪先生が1970年に大山先生編集の『知覚』(講座心理学)の中で書かれた「眼球運動と形態知覚」という論考の影響を強く受けたものです。その当時、同じような考えを、Luriaが出していて、1975年に、「複雑な対象の視知覚の過程は、複雑な能動的受容活動である」と言っています。視知覚の場合も対象が複雑になるにつれて運動成分の参加が必須となり、それにより触知覚にますます近くなる、というのです。
眼球運動の研究
その頃、アイカメラが研究室に入ってきたのです。最初に入ってきたアイカメラは輸入品のBrandt-Eye-Cameraでした。いわゆる角膜反射法という方式の、調整が厄介なアイカメラです。次に購入されたのが竹井機器による竹井式アイカメラでした。上記の「酒杯-横顔」の変形図形を活用して、例えば「真ん中の視標だけをじっと(30秒間)見ていて、目を動かさないようにしてください」という教示の際の目の動きを撮りました。晴眼成人による凝視時の角膜反射光の軌跡が、微動を伴いつつもほぼ一直線に伸びているのに対して、開眼者の場合には不規則な眼球の動揺を伴うものになることなどを見出しています。
一方、1950年頃から静止網膜像stabilized retinal imageを観察するための装置が登場してきました。その一つは、アメリカの、Riggsたちのもの(Riggs, L. A., Ratliff, F., Cornsweet, J. C., & Cornsweet, T. N. The disappearance of steadily fixated visual test objects. Journal of the Optical Society of America, 1953,43, 495–501.)、もう一つは、PritchardやHebbが考案したもの(Pritchard, R. M., Heron, W., & Hebb, D. O. Visual perception approached by the method of stabilized images. Canadian Journal of Psychology, 1960,14, 67–77.)です。Pritchardの1961年の論文を、私は見逃していたのですが、京大で、苧阪先生がそれを見せてくださったのです。『Scientific American』(204, 72-78.)という雑誌に載った『Stabilized images on the retina』(1961)でした。「では、静止網膜像の装置で、反転図形を見たらどうなるのか」と思い、何とかして、その装置を作ることを計画しました。最初に、Riggsの方式で行こうと思って、本郷3丁目の駅のすぐ近くにあった「コンタクトレンズ東京研究所」を訪ねました。「こういう実験をやりたいのですが」と言いましたら、「それならコンタクトレンズをはめる練習からやらなければだめですよ」と言われて、練習した覚えがあります。当時はずっと長い間はめていてはよくないということでした。装置も、すぐ近くのナルミ商会という光学機械を作る会社に頼んで作ってもらいました。
アメリカ留学による眼球運動研究の中断
静止網膜像研究がうまく行かないうちに、その頃は東大を出て、東京農工大に移ったあとだったのですけれども、アメリカに行く話が飛び出しました。ミシガン大学医学部眼科学の視覚研究室におられた相場覚氏が帰国されるためAlpern教授から、「後釜を」と言われ、鹿取さんに打診があったのです。
少し話が前後してしまうのですが、その頃まだ東大にいた私は先程のナルミ商会で別の光学系の実験装置というのを作ってもらって、いわゆる精神物理学的な研究を当時修士課程の院生だった上村保子さんと共同で始めていたのです。その結果をもとに共著の論文も出しました(『Effects of inducing luminance and area upon the apparent brightness of test field』Japanese Psychological Research,1965)。そのようなバックグラウンドがあったことと、鹿取さんが「自分はいま動けない」ということで、私が行くことになったのです。結局、静止網膜像の研究は、そこでストップしてしまいました。ただアメリカへ行ってから再開可能かとも思ったのです。アメリカに着いてしばらくしてからAlpern先生に、そのことを相談しました。すると「Stabilizedは、とにかく、すごくタフな実験だが、それに耐えられるか」と暗に反対されてしまいました。 Riggsの研究室まで装置を見せてもらいには行きましたものの、静止網膜像については中断したままになりました。
東京工業大学にて
話がとび過ぎましたので、ここで巻き戻すことにします。博論が終わって、最初に就職したのは東京工大の工学部で、1959年の10月からです。
ただ、東京工大には心理学専門の学科はありませんから、一般教育で宮城音弥先生がヘッドの研究室での助手のひとりとしてです。多湖さんが、助手を辞めて千葉大へ移られたので、その後任としてでした。もう1人の助手候補は、私より1歳上の穐山貞登さんで、一高を1年で終えて当時の教育大に進まれた方です。とにかく東京工大では二つの助手のポストの一方は東大から、他方は教育大からそれぞれ採るという方針だったようです。ところが、その時穐山さんは病気のためすぐには応じられず、馬場道夫氏が来られました。その後、病気がよくなった穐山さんが着任されたというわけです。東工大の時代には、穐山さんにずいぶん親密にしていただいて、助手の仕事も研究も一緒に楽しく続けた覚えがあります。何しろ秀才で、あとあとまでも、その交流が色褪せることはありませんでした。
東大での助手と先天盲開眼者との出会い
東工大に移って1年半ほど経った頃、思いがけず東大への移籍という事態が起こりました。1961年5月から文学部の助手として勤務することになったのです。その翌年奇縁とも思えるような大きな研究テーマに出会うことになりました。1961年から、読売新聞社が、開眼手術とその後の治療の資金を援助するという「光のプレゼント運動」を始めたのを知ったのです。そして、間もなく白内障にかかった人が手術を受けて、「あ、見えるようになった」というような新聞記事が出てきました。学部の頃から私は、Sendenの本も、梅津先生の論文も知っていましたから、すぐに新聞社に電話をかけたのです。 そのときの社会部所属の記者で、その後ずっとお付き合いすることになる今村新之助氏がまもなく研究室に来られたので、「少なくとも先天性の白内障の方の場合、手術のあと眼帯が取れるやいなや母の笑っている顔が見えたというようなことはあり得ないでしょう」という状況を紹介したと思います。すると、今村さんは「なるほど。われわれは光のプレゼントはしたけれども視覚のプレゼントはしていないんですね」とすぐさま了解されました。そこで、「視覚のプレゼントとまでいくかどうか分かりませんが、どなたか手術を受けた方を紹介していただけないでしょうか」と依頼してみました。それでは、と紹介された方が、TMさんだったのです。お母さんは、元看護婦さんで、私どもの要請にこたえてTMさんを大学に連れてきてくださることになりました。TMさんと私が実験室で課題などを試みている間に、研究室で、梅津先生は、お母さんと、いろいろ話し合っておられました。帰りぎわ、「お母さん、今日はとても楽しかった」とTMさんに告げておられました。TMさんの方はどうかというと、「帰りにお菓子を買ってくれるので」と言って、それが楽しみでやってきたとのことでした。あのときは、まだ11歳ですからね。
TMさんは、生後1年2ヵ月でハシカにかかって、両眼とも失明し(角膜白斑)、その後の保有(残存)視力は「右眼ゼロ、左眼光覚弁」と記載されています。色は、少し分かったようです。形はどうかというと、白い台紙に、黒い紙から切り抜いた三角、丸、四角をそれぞれ貼りつけたものを用意し、見てもらったのですが、目の前に提示しただけではどんな「形」か分かりませんでした。台紙を手に取って眼前に近づけ、さらに動かしてみたものの、「何カガアル」とは分かったようですが、「名前(形の)ハ分カラナイ」という状態でした[手術後3ヵ月目の最初(1962年7月)の観察記録による]。
この状況がどう伝わったのか分かりませんが、当時の週刊サンケイという雑誌の取材を受けて、その1966年9月5日号に、「全盲の少女、開眼の意外な体験」というタイトルの記事が出たのです。なぜ「意外な体験」かというと、多くの人は、手術後眼帯を取ればすぐ色や形が分かると思うかもしれないが、そうではなかったからというわけでしょう。そこで私は手術を担当された日本医大の樋渡正五先生にお話を伺うことにしました。
医局にお邪魔して樋渡先生から「まず3月16日に虹彩前癒着をはがし、3月24日に全層の角膜移植手術を実施しました」というお話を伺い、さらに手術後に起こり得る問題についても教えていただきました。この場をかりて、先生と眼科学教室のスタッフの方(当時)に厚く御礼を申し上げたいと存じます。
TMさんに会った日から5か月ぐらい経って、MMさんという方を紹介していただきました。生後約10ヵ月で両眼とも失明(角膜軟化症)し12歳(1962年当時)のときに、都立駒込病院眼科部長の山本由記夫先生の執刀で、光覚が残っていた右眼だけの手術を受けました(1962.12.5)。紹介を受けたときMMさんはまだ入院中でしたので、病室で初めてお目にかかったのですが、「手術の前、明るい、暗いは分かった、でも色は分からなかった」と話してくれました。手術の日から6日後に訪ねた際、MMさんが自分の手で眼帯を短かい時間だけはずす場面に立ち会ったのですが、その途端、「まぶしい」と声を上げました。そして「明るさは分かるけど、色は分からない」と言っています。色の名前も全然知らないという状態でした。したがって、MMさんは「先天盲の開眼者は一体どんな色名を、どのような順序で習得していくのか」という疑問に答え得る希有のひとだったのです。
第2に、「開眼手術のあと、その視覚活動は一体どのような順序で進行するのか」という根本問題の一端に初めて答えてくれた(形の弁別活動にまでは到達しなかったものの)開眼者もMMさんだったのです。
視覚活動形成のためのMMさんとの共同実践活動が1966年夏にさしかかったところで、私の関与をしばらく中断せざるを得ない事態となりました。先程言いましたように、滞米研究生活がここにはいり込んできたためです。
アメリカ留学時の経験
この辺りで、アメリカ留学時の出来事について2、3お話ししておきたいと思います。1966年8月末、ミシガン大学の所在地アナーバーに着き、正式にリサーチ・アソシエイトの資格で視覚研究室の一員となった9月初め、研究テーマについてAlpern先生と話し合うことになりました。『心理学ワールド』の62号に、「アナーバー滞在日記からの抜書き」というタイトルですでに書いてありますので、ここでは端折りますが、「ヒトの色覚の型と錐体細胞内の感光色素(ピグメント)との関係に関する研究」というのがそのとき決まったテーマでした。二色型第一(protanopia)と第二(deuteranopia)のピグメントについてはYoung以来の「欠損説」を支持するデータがRushton教授らによりすでに提出されていたのですが、異常三色型の錐体構成とピグメントに関しては当時まだ確証が得られていなかったのです。そのためミステリー・ピグメントなどと呼ばれていたのですが、それらを探り当てる実験を重ねてみようという計画でした。さまざまな色覚型の多くの人たち(主に大学生)が研究室に来てくれたお陰で、開始後1年弱である程度の成果がありました。しかし、「やっと結果が出始めたな」と、Alpern先生が言われますので、大学に在外期間延期を願い出る手紙を送りました。「では、1年だけは待ちましょう」という許可を拝受しました。
2年目の研究がひと段落して、「さて、もう帰らなくては」と思っていた矢先、次の話が舞い込んできたのです。ケンブリッジ大学の生理学の教授だったRushton先生が定年になって、フロリダ州立大学の分子生物物理学研究所に赴任されることになり、Alpern先生のところに、「一緒に仕事をしないか」という誘いがあったようです。フロリダ行きを決心した先生が一緒に行かないかと私に声をかけて下さったというわけです。
私は困惑して農工大に「もう1年、在外期間を延長していただきたいのですが」と手紙で打診してみました。すると、(そのとき私は助教授だったのですが、)「教授会で、君を教授にするという話が出ている。すぐ帰ってくるように」とのこと。しかし、このようなチャンスはもう二度とないだろうと思いましたので、「この際、申し訳ないので辞職します」という辞職願を提出し、そのことを、Alpern先生に報告したのですが、「それは、ちょっと冒険ではないか」と一旦は止められました。しかし結論としては、「止むを得ないな」ということになり、間もなく農工大からは「休職扱いにする」という許可をいただきました。あわただしく引っ越しの準備をして、フロリダの研究所に着任したのは9月8日(1968)のことでした。
『心理学ワールド』の53号の巻頭言に「実証に150年かかる理論」というタイトルで当時のことを若干紹介しましたが、着くとすぐに実験の準備にとりかかりました。散瞳眼による光覚閾の測定がその具体的な仕事です。視角2度の閃光が見えたか否かを報告しなくてはならないため、最初のうちはデータが安定せず、とりわけ桿体視条件下ではその状態が顕著だったようです。装置と閃光判別法とに若干の改良を加えた結果、どうやら順調に進行し始めて、最初の結果をRushton先生の部屋へ持参したのは11月中旬頃だったかと思います。「Good harvest!」と言われたことをよく覚えています。速報をすぐさま、アメリカの科学雑誌『Science』に送ったのだそうです。しかし、 Rushton先生がしばらくしてやって来られて、「却下されたよ。どうもこの国は、われわれ外国人に対して冷たいようだね」と私にだけ言われました。すぐに『Nature』に送り、受理されたというわけです。これは3人の名で提出されていますが、次の『Nature』の論文には眼科医で視覚研究者のMs Anne Fultonも参加しています。
東大へ
1年弱のフロリダでの研究生活を終えて、9月に農工大に戻りました。ところが翌年東大から声がかかり、帰任後日が浅いので、親しくしていただいていた農工大の先生方に事情についてご相談申し上げました。どなたも了解してくださったことを深く感謝申し上げております。
再び開眼後の視覚研究へ
帰国後、何よりもまず中断していた開眼者の方との協同実験を再開することを思い立ちました。先程のMMさん、TMさんを含めて、1971年以降約20年にわたって10人の方にお目にかかることができました。むろん、少しずつ時期がずれているのですが、殆どが日本女子大児童学科助手(当時)だった望月登志子氏との共同プロジェクトとなりました。
1975年には、名古屋大学眼科の市川宏先生とそのとき医局におられた安間哲史先生からHHさんを紹介していただき、共同で観察を続けませんかと誘ってくださったのです。多いときは1週間に1回くらいの頻度で名古屋大学病院に通いました。HHさんについての観察結果は、市川、安間両先生と私どもの共著論文〔『臨床眼科』(1977, 31, 389-399.)など〕になりました。
このあと1980年には、ToMさんとその弟KMさんという先天性白内障の少女、少年に出会いました。お父さんも先天性白内障とのことでした。その当時、たしか東北大の院生で、のちに弘前学院大学教授に就任される佐々木正晴氏が、この機会をつくってくださったのです。一緒に、研究をしませんかということで、私どもは仙台に数え切れないくらい通うことになりました。それ以来、佐々木さんとは、今日までずっと緊密に共同で仕事をしてきています。
なお、10人の中のMMさんだけは、角膜移植ができるような目ではなかったようです。角膜の真ん中が濁っていましたので、本当は、そこを取らなくてはいけないのですが、手術を敢行すると目が壊れてしまうという状態と伺いました。それで虹彩切除という処置を受けたとのことでした。私がアメリカから帰ってきたあと、MMさんの目はまもなく濁ってしまって、視覚に関する課題はそれ以上続けられなくなりました。とはいえ、MMさんとの長期にわたる協同実験で蓄積された資料は、1972年以降に知り合った開眼者の方々(SH、NH、KT、YS、HH、MOの諸兄、諸姉)のための弁別・識別課題とその設定順序を決めるうえで、貴重な指針となりました。
細かい所まで言及している時間はもうありませんので、1974年10月に初めて出会ったYSさんとの2年間にわたる実践研究の成果について要約しておきます。それは、図領域の検出・定位課題から始まって2次元図形の弁別課題に至るまでの中継段階を余すところなく浮かび上がらせてくれました(『サイエンス』1983年7月号, 28-39.)。
詳細は東大出版会の『開眼手術後の視覚世界』(鳥居・望月,2000)に書かせていただきましたが、その際、編集部の伊藤一枝さんに多大なご尽力をいただきました。
立体の弁別と識別
先天盲開眼者が「2次元図形」の次に対面しなくてはならないのは「立体」です。手術を受けた人に、初めて立方体と球を見せたとき、触ることなくそれらを区別できるかどうかという疑問を、Molyneux,W.が、当時(17c)の哲学者John Lockeに宛てた書簡の中で初めて提起したといわれています。以来、これがモリヌー(ときにモリヌークスと表記)問題と呼ばれるようになりました。
さて立体となると、どのように提示するかという問題にぶつかります。台紙の上に立体を落ちないように貼りつけて、それを持ってもらうなどの工夫もしましたが、結局はテーブルの上に並置して身体を少々傾けつつ見てもらうという並の方式をとってきました。この場合それらを上から見たらどうなるか、真横からあるいは斜めからだとどうなるか、つまり視点によって同一対象の見え方が異なるという事態が起こります。これは、開眼者の方にとってまことに厄介ですね。もう一つの難題は、陰影の存在です。ここでのような普通のライトの下で立体をテーブルに置きますと、光の反対側に影ができます。「この黒いもの、これは何ですか」とある開眼者の方にきかれましたので、「では、触ってみたら」と勧めてみました。眼では見えたものが、触ると「ない」ことを体験してもらった、というわけです。それでも、私どもが出会ったどの開眼者も実物と影を「ひとつながり」のものと見てしまって、「実物」を誤認することがよく起こりました。TMさんがあるとき、ふとつぶやいた「どんな小さい物にも影があるんですね。不思議ですね」という言葉は、まことに印象的でした。
物の識別
立体の弁別・識別が錬成試行を経て少しずつ可能になってきた頃を見計って、物(事物、物体、物品)を「類」として、さらに「個物」として特定する課題に移行し始めました。18cのフランスの眼科医Daviel,J.は「白内障の手術を実施した先天盲の患者22人に物を見せたが、それらが何であるかすぐに分かったひとは皆無だった」と述べています。私どもの開眼者の場合にも状況は全く同様でした。
そこで、物の識別とその錬成に関わる試みを上記の何人かの開眼者の方と始めることにしました。
ところが開始早々、どんな類いのものか告げずに身辺の物品を一つだけテーブルの上などに提示するという課題場面の設定方式には重大な難点があることに気づきました。あるとき、運動靴を片方だけ机の上に置いたときのことですが、上記のNHさんがそれに触って分かったあと「こんなところに運動靴なんかあるわけがない。こんなところに運動靴が置かれたって分かるはずがないよ」と言ったのです。このように不用意に採用する「物の識別課題」の方式には問題がある、という趣旨のPalmer(1999)の卓抜な批判もあります。
ここで脳損傷後に物の識別が困難になった方についてご紹介してみましょう。
国立障害者リハビリテーションセンターの山田麗子さん(東京女子大卒業後、聴力言語センターを経て、国立障害者リハビリテーションセンターの心理部門に移った方)と一緒に、同時失認(脳損傷により)と診断されたSさんにある期間お目にかかったことがあります。
同時失認というのは、いろいろ定義があって厄介なのですが、Sさんの場合Luriaの言う同時失認の症状に一番近く、一つの物を見たとき、それしか見えないとのことでした。例えば「刺身が目の前に出されると、その一切れが取れない」と言われるのです。靴などの履物を左右揃えて描いた絵に対しても「二つ出されると分からない、一つだけ出してくれませんか」とのこと。Luriaが実施している方法ですが、紙の上にたくさん黒のドットを打っておき、「ドットの上に、赤鉛筆で印をつけてください」という課題を実施してみました。赤の印が黒から外れてしまうのです。黒を見ると赤が見えない、赤を見ると黒が見えないというわけで、適当な所にポンと打ちますから、多くの赤が黒から外れてしまうのですね。
物体失認の症状を呈した(交通事故による脳挫傷により)Kさんの場合、お目にかかってから半年ぐらいの間は、具体物やその写真、あるいは黒線の描画、動物の模型、プラスチック製の果物などが、ごくごく少数のもの以外、視覚的にも触覚的にも識別できない状態でした。その自覚もなかったようです。上記のものなどを見分ける試行を続けるうちに、半年程も経った頃でしたか、あるとき、「物が分からない。どうも、私は物が分からないようだね」と言われるようになりました。いわゆる「病識」ができたのでしょうか。とにかく、初めのうち「何で、こんなつまんないことやるんだ」と怒っておられました。「こんな子ども相手みたいなこと、なぜやるんだ。この物は何だなんて、そんなこと聞くとは無礼だ」と言われたりしたのですが、山田さんは、よく対応しておられましたね。
あるとき山田さんがたまたま席をはずしてKさんと私の2人だけのときに、ふと思い付いて、手元にあった黒いくしを目の前に置いて、「分かりますか」と尋ねてみたのです。すると「いや、分からない」、「触ってもよいか」とおっしゃるのですが「いや、触るのは少し待ってください」と言って、私がくしを取り、「髪をとかす動作」をしてみたのですね。そうしたら、すぐ「あ、くしだ」というわけです。しばらく間を置き、それを再び机に置いて、「これ、分かりますか」と尋ねたところ、「分からない」とのことでした。物によっては、それが、どのようなときにどのような動作で使われるか、その所作が大事だということを私としては初めて教えられました。
もう一つ例を挙げます。毎日使っているはずなのに、テーブルに置かれた歯ブラシに「分からない」と言われたときの出来事です。山田先生が、それを使って目の前で髪をとくように動かしたところ、「違う」、次に耳掃除の動作をしてみたのですが、これにも「違う」というお答えです。このあと先生が歯磨きの動作をしてみたとたんに、「あ、歯ブラシだ」と見事正解に至りました。
またあるとき、目では分からなかった歯ブラシに触ってすぐ分かったあと「なんだ、歯ブラシじゃないか。こんなところにあるもんじゃない」とKさんに怒られました。「こんなところにあるから、分からないんだ」とその理由について開眼者のNHさんと同じことを言っておられました。物には、用途に応じた、あるべき場所があって、そこにあれば分かるということではないでしょうか。
顔・表情
物と並んで、いやそれ以上に厄介なのは顔ですね。物は近づいて見ることもできますけれど、他人の顔を接近して見るわけにはいかないという社会的な制約があります。それでKTさん(15歳の頃水晶体摘出手術を左眼だけに受けた方)は幼児の顔を観察することを、自分で試み始めたと述べておられます。「笑っている」ときの顔を見て「頬の筋肉が盛り上がるのが分かるようになった」とのこと。来訪時(1974.10)から1年半経った頃には「笑顔は想像がつくようになった」ものの、まだ「悲しそうな顔や怒った顔は想像がつかない」(1976.3)という状況が続いています。当初から「顔を見てそれが誰なのか、どうして分かるのですか」という疑問はずっと抱いておられるようです。このところ、よく似た2人の女性の顔写真を10枚用意し、それらを振り分けるという弁別課題を試みているのですが、今一歩というところでしょうか。
鏡映像とグレゴリー
ここで鏡映像に対して開眼少女MOさんが示した反応とその変遷について、ごくあらましを〔詳細は『先天盲開眼者の視覚世界』(2000, 東大出版会)〕ご紹介しておきます。
MOさんは、左、右眼の角膜移植を何回かにわたって受けているとのことで、「読売光と愛の事業団」(1971年発足)の担当の方から紹介されました(当時14歳)。出会って2ヵ月半経った頃(1989.12)、初めて姿見の前に立ってもらったとき、「何が見えますか」と尋ねてみたのですが「見えない、分からない」としか答えませんでした。しかし、1ヵ月(2回目)以降は、鏡の表面を触ったり、裏側に手を回して探ったり、裏側へ回るというようなことを試みています。だんだん、鏡というものが、自分を映す、自分の顔を映してくれる、外が映っているということも分かってきて、後ろにある物体は前に映っているのだとか、外の中に私がいるとか、そのような報告が、約2年後には現われています。
その経過を、ブリュッセルで国際学会があったとき(1992年:東大定年後、聖心女子大学に在職中)に、ポスター形式で発表したのです。そうしたら、そこにGregory教授(視知覚の研究、開眼後の視覚状況に関する論文でも著名な)が見にきてくれたらしいのです。そのとき、私はポスターの前から離れていて、望月ひとりが立っていたのですが、「何か偉そうな人が来ていろいろ質問された」とあとで言うのです。そして、もちろんポスターだけでは詳細は分かりませんので、英文で細かく書いた報告ノートを持参していましたから、それをお渡ししておいたというわけです。するとそれがGregory著の『Mirrors in Mind』という本の中で引用されていたのです。そこに載せてくれたことを私どもは知らなかったのですが、新曜社の社長堀江洪さんがあるとき電話をかけてくださって、「今度Gregoryの本が出て、先生達の研究が載っているの知ってますか」、「載ってるんですよ。訳しませんか」ということになってしまい、訳すはめになりました。
Gregory教授は、とても博識らしく、扱っている分野も多方面にわたっていますので、鹿取さんと鈴木さんにもお願いして、4人の共訳で『鏡という謎』(2001)を出版してもらいました。編集部の塩浦暲、吉田昌代の両氏のご尽力にも深く感謝しています。
変換視
先程の佐々木さんは、20数年前から、当時宮城教育大に在職中の八木文雄氏と共同で変換視メガネの短期・長期着用実験を続けてきています。さらに視野全体をかくすアイマスクや小視角の穴だけ開けたピンホールメガネの着用実験も実施し始めています。私も視角が3度前後のピンホールメガネで外界(見知らぬ場所)を観察することを、何回か試みてきました。
2010年からは日本大学の佐藤佑介氏がこの共同研究に参加してくれることになりました。お陰で体操競技における視覚の役割について具体的な研究を実施する道が拓けつつあります。「倒立における視野制限の影響」といったテーマの実験はその一例です。
ピンホールの実験には思い出が一つあります。大学院の頃、梅津先生のゼミで、視野の広さは物の見え方に、どのような影響を及ぼすのかという問題で論じ合ったことがあるのです。「視野を、できるだけ縮めて、小さな穴を通して外を見てみるようにしたら、どんなことになりますかね」と先生がふと言われたことを、よく覚えています。「実験してみよう」と思ったのですが、今までそのままになっていました。
脳損傷と視神経低形成
先程は、脳損傷による物体失認あるいは同時失認症状についてご紹介しましたが、そのほか大脳性色覚喪失、半側無視、両眼立体視の欠如、実体鏡視における左右像のズレ、眼球運動の不調、複視、画像などにおけるGestaltの解体、といった諸症状の方々にお目にかかりました。そして、鹿取さん、河内さんおよび助手、院生(当時)の諸兄(木村英司、山本豊、今水寛、山上精次、高橋晃、渡辺武郎、中沢仁の諸氏、順不同)と共同で、それらの症状の軽減・改善に関わる試みを続けてきました。東大教育学部の能智正博さんのご尽力もあって、その一端をまとめることができました。
インA 一昨年本を出された、『認知世界の崩壊と再形成』ですね。
鳥居 そうです、あの本には、以上のほかに先天性の視神経低形成と診断されたKさん(多分光覚盲)に関する1歳4ヵ月から2歳4ヵ月までの1年間の行動記録も含まれています。主に国リハの研究室内での非視覚系による空間行動の観察が含まれています。
なお、このKさんに関しては、事物と形態に対する呼称ならびに操作の活動状況を記録した全体で5年半に及ぶデータが未公刊のままになっています。とにかく多岐にわたる資料のため、今度の本には収めることができませんでした。これらを収録した新しい本の完成を見ずに山田さんが逝去(2007年5月)されたことは、まことに心残りと言うほかありません。
学会での仕事
インA 学会の仕事はいかがでしょうか?
鳥居 日心に関係する仕事ですと、編集委員をたしか2年、そのあと、編集委員長を3年務めています。編集委員長をしているときに、Blackwellという、イギリスの出版社から、「日心で出しているリサーチの出版、印刷を引受けたい」と言ってきたのです。 7月に「ブリュッセルで会いたい」とのことで、心理学会事務局の朝倉和子さん、久野洋子さんと一緒に3人で、EditorのMs Claire Andrewsと会いました。 いろいろ話し合い、出版の条件も聞くなどして、「今度は日本で会いましょう」ということになりました。11月になって、アンドリュースさんとManaging DirectorのRene Olivieri氏が来日し、当時の学士会館分館で会ったのです。細かいことは、もう覚えていないのですが、ともかくこうして最終的にBlackwellからの出版が決定しました。
感覚代行研究会
学会とまでは言えないのですが、感覚代行という名称の研究会設立に関与しています。これは、名大の市川先生、早稲田大学理工学部の大頭仁先生、そのときはまだ研究所に在職中の和気典二さん、それに私の4人で立案したもので、いずれは学会にしようという目標を立てていました。しかし、研究会のまま今日に至っているのですが、毎年1回はシンポジウムを開いてきています。去年の12月で41回目ですから、設立以来ほぼ40年ということになります。これまでに『視覚障害とその代行技術』(1984,名大出版会)という本を出していますから、今度は、40回を記念して第10回以降の論文をまとめた本を出したかったのです。しかし、まだペンディングのままになっています。
視覚に極度の制約がある人たちにとって大きな問題の一つは、自在に出歩くことが厄介な点にあります。感覚代行シンポジウムのお陰で歩行補助用ロボットの研究をしておられる森英雄先生(山梨大学)と知り合いになりました。いわゆる盲導犬ロボットの研究を長年積み重ねてこられたのですが、大学を定年で退職された今も、新しい方式の開発に営々と取り組んでおられます。佐々木さんと私とはアイマスクを着用したり、ピンホールメガネをかけたりした状態で、新式の補助車を押して歩く実験のお手伝をしてきています。先月も二人で山梨へ行ってきたばかりです。
翻訳の仕事
高砂 Gregoryの翻訳だけではなく、先生、結果的にですけれども、古典の翻訳に割と関わっておられますよね。例えば、Berkeleyなど、あれは、翻訳そのものではないと思いますけれども、下條さんのあとがきには、「先生に勧められて」というような文章がありましたが。
鳥居 Berkeleyの『視覚新論』は、なぜか翻訳されていなかったのです。『新視覚新論』を書いておられる大森荘蔵先生にお目にかかって、その理由をお尋ねしてみたこともあります。その後、話が現実味を帯びてきましたので、哲学研究室の杖下隆英氏〔『認識と価値』(1989, 東大出版会)の著者〕と相談の上、植村恒一郎氏と一ノ瀬正樹氏とにお願いすることにしました。お二方は訳注も担当しておられることをあとで知りました。「心理学者も誰か入った方がいいんじゃないですか」とすすめられたので、「下條がいるから、彼がいいかな」という鹿取さんの提案もあり、承諾してもらいました。私自身は「先天盲における開眼手術後の視覚とバークリ」という解説で一応の役目を果たしたつもりです。
高砂 そのときには、当然のことながら、Sendenの方は英訳はありましたけれども。
鳥居 確かに英訳(1960)はありましたが、日本語の翻訳はなかった筈ですね。
高砂 ないですね。
鳥居 原著の出版は1932年ですから、英訳でさえそれが出るまでに30年近く経っていることになります。
高砂 そして、先生が、割と最近、出されていますね。
鳥居 『視覚発生論』(望月と共訳)というタイトルで2009年に協同出版(小貫輝雄社長)から翻訳を出してもらいました。英訳出版の年から数えても50年近く経ったあと、ということになりますね。ただ原著の「奥行視」(1部B-Ⅱ)以下については、その訳出を見送っていますから、実は全訳ではないのです。
高砂 そうなのですね。
鳥居 私はドイツ語版と英語版を併用したのですが、Peter Heath氏の英訳に大いに助けられましたね。それでも、とにかく時間がかかりましたね。翻訳をやっていると、他の仕事ができなくなってしまうんですよ。
高砂 そうですね、そう思います。
鳥居 なお、2008年の国際学会の折に、キール大学を訪ねて、Sendenのファーストネーム(長いこと不明のままだった)がMariusであることを知ったような次第です。
高砂 そして、それとほとんど前後して、Hebbの『行動の機構』を訳されていますが…。
鳥居 鹿取さんが推進役の改訳(2011年)の一部を手伝ったのです。白井さんの邦訳が1957年には岩波から出ていたのですが、すでに絶版になっていました。
高砂 そうですね、白井常先生はHebbを訳されていますね、はい。
鳥居 改訳の計画はかなり以前からあったようですが、鹿取さんが岩波書店と交渉し、先方のすすめもあって、文庫版(上下2冊)が実現したとのこと、私はその上巻に含まれる4章と5章を分担したのです。
質問
インA Perceptual and Motor Skillsから、最初、声がかかったという話でしたけれども、それは、何か理由はあるのですか。
鳥居 当時も以後も、それが不明のままなのです。日本の何人かの心理学研究者に声をかけたのではないか、と想像しているのですが。
高砂 すみません、もう1件だけ。先ほどの3人の先生、Alpern先生とRushton先生と先生の、A.R.T.と言っていましたよね。
鳥居 はい。Alpern、Rushton、Toriiの頭文字を取って、『J.Physiol.』に提出した自分たちの論文の中で先行論文を引用する際に、(A.R.T.)とか(A.R.T.a,b)などと表記しているのです。「これはartになるよ」というRushton先生の言葉が今でも耳に残っています。
イン わかりました。長時間にわたり、ありがとうございました。
鳥居 では、旧制の高等学校の理科乙類に入った頃から始めます。3年間を高校で過したのは私どもの学年が最後です。新制に切り替わったものですから、私どもの次の年からはもう3年間在学する人たちはいなくなってしまいました。
理科乙類というところは、医学部、そして農学部などの方面に進みたい人が入るコースなのですが、医学部志望の人が多く、ドイツ語が第一外国語だったのです。そのせいで、時間割を見ると、ドイツ語の時間の方が多く、英語には思ったほどの時間が組まれていなかったという記憶があります。
ただ、私はもともと医学部に行くつもりはありませんでした。なぜ理科乙類に進んだかというと、最初に父親に相談したら、「他の学科に行っても就職口はないぞ」と言われ、次に中学の先生に相談したら、「君は理科が不得意だというから、不得意な方をやった方がいい」と言われました。そこで、「では試しに」と思って受けたような次第です。
その頃、読んだ本の中で、心理学に関係しそうなものを挙げるなら、高良武久著『性格学』という本があります。もう一冊はOtto Weiningerの『性と性格』という本で、書棚を探してもどこへ行ったか出てこないのですが、面白く読んだ記憶があります。
理科ですから、授業では、数学、物理学、動物、植物、化学という工合いに、理科系のものが目白押しでしたが、そのようなものの中で文科系と思ったのは、串田孫一先生が講師で来ておられた哲学の授業です。普通、哲学というと、だいたい哲学史でしょうが、串田先生の授業は、例えば「虚栄について」というテーマで1時間、考察を加えるという方式でした。これはあとから考えてみますと、かなり心理学に近いという気がするのですが、受講しているのは大半が医学や農学志望の連中ですから、だんだん受講者が減ってしまい、最後は2人だけになりました。
それから、個人的に少し関係するかなと思うのは、英語の講読テキストで、H. G. Wellsの『タイム・マシン』を楽しく読んだことです。先生が少し訳されては、学生にも、「この先を訳しなさい」という授業でした。細かな内容は覚えていないのですけれども、強く記憶に残ったのは、「threshold」というterm(ターム)でした。そのテキストの後ろに注が出てくるのですが、そこを見ると、「心理学上の術語」と書いてあり、ドイツ語では、「die Schwelle」、それを「識閾」と和訳してありましたね。それから、もう一つ面白かったのは、Darwinの『ビーグル号航海記』です。このようなところが、今思えば心理学に関係した読書の遍歴だったのかも知れません。
さて、いよいよ卒業が近づきましたので受験しなければ、ということになり、医学部を受けるかどうか決めなければなりませんでした。しかし、医学部というところは、人体のいろいろな部位の名称、術語を覚えなくてはならず、あまり暗記が得意ではないので、それは厄介だと思い、また、解剖をやるのが億劫になる出来事があって敬遠したくなりました。その出来事というのは、六高を出て人類学科に入った友人(江原昭善氏)に「脳の解剖をやるから来い」と誘われたのです。彼はどこからか脳を取り出してきて目の前にポンと置き、「ここからここまでは、云々」と領野区分を大まかに説明してくれたのです。彼はその脳を素手で持ち、さらには、「昼になった」と言って、洗いもしないその手でコッペパンをかじり出したのです。そのことを指摘すると、「いや、自分だって、最初はこんなことできなかった。3日ぐらい飯、食えなかったよ」と言っていましたね。そのようなこともあって、医学部はとにかく敬遠し、結局1年待って、文学部を受験しようかと思ったのです。
なぜ文学部かというと、本当は美学科へ行きたかったのです。ところがこれまた、「美学出たって、就職口は何にもない」などと反対されました。「では心理学ではどうかな」と思い付き、志望先を書くよう指示されていましたので、第1志望を心理学、第2志望を美学美術史と書きました。そうしたら、受験後何日かして合格通知が家に来たとき、「心理学」と書いてあったものですから、またおやじに「医学をやっていれば、心理学でも美学でもできないわけじゃないだろう」と反対されたのです。しかし、いまさら医学部受験も面倒だし、受かるどうかも分からないということで心理学に決めてしまいました。
出身大学と出会った先生
かくして、昭和26年、1951年に文学部心理学科に入学したのですが、そのときの主任教授は千輪浩先生で、担当しておられた講義の一つは「心理学概論」でした。先生のもう一つの講義が、「社会心理学の基本問題」でこれも受講することにしました。
さらに、教授のポストに高木貞二先生がおられ、担当されたのは「学習の問題」という講義ではなかったかと思います。当時の私の手帳には、「学習の問題」としか書いてないので不確かですが。2年目に「実験心理学」を受講しているのですが、これは間違いなく高木先生のご担当でした。高木・城戸両先生の『実験心理学提要』という必読の本がありますが、その第1巻のI.を高木先生が書いておられます。先生から、心理学における実験法として精神物理学的測定法を体系的に教えていただいたのです。
その頃海外に出張しておられた助教授の相良守次先生が帰国されて翌年には、「記憶心理学の諸問題」という講義を担当されました。
このほか、学内の講師として増山元三郎先生の「推計学」の授業がありました。これが難しい内容で、次々書かれていく数式を、何しろ文学部の連中ですから、ぽかんとして見ているだけなのです。「これで試験になったらどうしよう」と、みな恐れていたのですが、ノートさえ出せば単位を頂くことができました。しかし、まるで分かっていませんので、推計学に関しては、あとでも言及しますが、いろいろな本で勉強した覚えがあります。
もうお一方、のちに文学部に移られる梅津八三先生ですが、当時はまだ教養学部のご担当で、文学部へは非常勤として来ておられました。1年生のときに、受講したのが「知覚空間の問題」でした。次の1952年(昭和27年)には、「知覚心理学の諸問題」を受講しました。前者の講義の中では、あとでお話しするSendenや、そして梅津先生ご自身が執筆された先天性白内障手術後の視覚に関する論文にも言及されているのですが、これは受講ノートを見るまでもなく覚えていました。
この他に、1年のときには、「実験心理学演習」いわゆる一般実験ないし普通実験という演習があり、むろん必修でした。これは、当時心理学研究室の助手をしておられた瀬谷正敏、東洋、詫摩武俊の諸先生による指導のもとに実施されていました。また、能率研究室という部門が心理学研究室以外にありまして、そこに助手として臼居利朋先生がおられました。さらに特別研究生として水原泰介、大山正、大川信明といった方々が研究室で机を構えておられ、心理学の実験方法に関する具体的な指導をしていただきました。終了後レポートを出し、採点のうえ返してもらいましたので、今でもそのレポートは全部自分の机の中に残してあります。
非常勤の先生として千葉大学の盛永四郎先生が、それは学部のときか大学院のときか、ちょっと不確かなのですが、「ドイツ心理学の発展」というテーマで講義をしてくださいました。これも受講ノートが保存してあります。盛永先生は、5年間ドイツに留学され、Metzgerや、反転図形のRubinのところで研究された方ですから、ドイツ心理学史については通暁しておられたのだと思います。ご専門の視知覚の問題についても、ずいぶん詳しく教えていただきました。
大学院に入ってからも、盛永先生が講師として来ておられて、MetzgerのPsychologie : die Entwicklung ihrer Grundannahmen seit der Einführung des Experimentsという厚い本をテキストとして使いましょうということになったのですが、ドイツ語ですから、だんだん受講生が少なくなってしまい、最後は私1人が残りました。
それから、慶応義塾大学の横山松三郎先生が大学院の非常勤として来ておられました。私の記憶が確かならば、「機能主義と構成主義」というタイトルの講義をしていただいて、心理学の歴史についてずいぶん勉強になりました。
横山先生は、講義を終えられると、5、6人、あるいは7、8人いる聴講生全部を一緒に喫茶店へ連れていってくださって、そこでもいろいろなお話をしてくださったことを覚えています。さあ、帰るという段になると、先生が全部払ってくださるのです。それで皆で「講師料がなくなるのでは…」などと余計な心配をし合った覚えがあります。
さらに、当時東京工大におられた宮城音弥先生が精神疾患に関する講義をされたと思うのですが、受講ノートも見当らずその内容がもはや分からないのです。
1年生のときには、何しろ割とゆとりがありました。それで、文学部の他学科の講義も聴いてみようと思って、美学科の竹内敏雄先生の「文芸のジャンル」と、元教育大の家永三郎先生の「日本近世思想史」、それから、吉田精一先生の「自然主義研究」も聴講しました。その他に、「西洋哲学史概説」、「独文学史概説」などがあったのですがだんだん負担になってきて、全部聴講しおおせたのは、上に挙げた三つの講義、「文芸のジャンル」と「近世思想史」と「自然主義研究」だけです。
先程助手の先生方をご紹介しましたが、その後、吉田正昭先生、確か2年先輩の方ですが上記のどなたかの後任として助手に就いておられます。その次でしたか、教養学部梅津先生の研究室で助手をされていた中島昭美先生が文学部助手として転任してこられました。また金城辰夫さんがこの時期に助手をしておられる筈ですが、どの辺りで活躍されたのか私には分からなくなっています。
吉田先生は山と写真が十八番の方で、私は山歩きにずいぶん同行させてもらいました。後立山連峰のときは吉田さんと私の2人だけでしたが、確か同級の笹本至心君も参加した3人による槍ヶ岳から宇奈月の方までの縦走もありました。南アルプスへも行っています。北アルプスの稜線は、割合高低差が少なく、少し下りてもまたすぐ上がって、またちょっと下りてまたすぐ上がるという工合ですが、南アルプスは、急激に上がって、また急激に下りるという状態の山々が連なり、また山小屋が相互に非常に離れていますから、われわれのような貧弱な体力の者では、とても一日で、たどり着けないこともあるのです。南アルプスのときは私は比較的足が速かったものですから、一番後ろに吉田先生がいて、その前に、初めて山歩きをしたという深田芳郎君がいるのを尻目に先頭切って歩いていったのです。そうしたら途中で、屈強な山歩きの男性が数人下りてきたのに出会って「1人か?」と言うのです。「いや、友達が2人後ろに」、「え? 後ろに? だめだよ、分かれちゃ」と、「1人でばらばらに歩いちゃだめだ」、「このへんでビバークした方がいいんじゃないか」とも言われました。まだ山小屋まではかなりあったのですけれど、吉田さんの決断でその辺りでビバークすることになりました。あとで気がついたのですが、その屈強な人たちは、多分もっと先まで行く予定だったのでしょうが、近くで、やはりテントを張っているのですね。どうやら、われわれが危なっかしいのでチェックしてくれていたのではないかと思います。この辺りで吉田さんが撮影された写真がたくさんわが家にも残っています。以上が公私のさまざまな面にわたって当時研究室でお世話になった方々です。
研究室以外でお世話になった方についても忘れることはできません。それは学部1年の夏休みのことだったと思うのですが、学生が集まる研究室の壁に、統計的な資料の処理に関するアルバイトを国立教育研究所で募集しているという貼り紙が出ていたのです。それで、私は「統計的な処理を勉強するよいチャンス」と思って、先輩の税所篤郎さんと2人で応募し採用されました。
仕事の内容は、あとで知ったのですが、肥田野直先生が担当された、いわゆる進学適性検査に相当する旧制高校受験の際の試験結果の分析でした。私自身もそれを受けているのですが、それらの資料は、全部教育研究所に集められて、保管されてあったらしいのです。それに対してランダム・サンプリングを企画されたのだと思うのですが、肥田野先生のご指示で、何枚かおきに1枚取って、集めたサンプルを処理する下仕事をしました。タイガー計算機を来る日も来る日も回していました。ところがある日そのサンプリングの対象になんと自分の答案が当たってしまったのですね。これは確かではないのですけれども、あとで伺った話では、全国の旧制高校で、何人受けたのかは知りませんが、満点を取った人が二十数名いたということでした。残念ながら、私は、1題、暗号を解かなくてはならない問題を時間切れで解くに至らず、満点ではなかったのを覚えています。
ただ計算機を回すだけでは勉強にならないので、推計学や数理統計学の本を読むことにしました。東京女子大の数学科と津田の数学科のそれぞれ出身という研究所の職員の方たち(榎本富美子さんと二星イセさん)には、ずいぶん助けていただきました。
もう一つは、学部の2年以降のことなのですが、最初八重洲口の国鉄本社内にあり、あとで駒込駅の構内に移った国鉄の労働科学研究室に、アルバイターとして、ずいぶん長く通わせていただきました。このときの研究員として、相馬紀公、清宮栄一、小瀬 輝の諸先生がいらっしゃいました。戦争当時、中目黒に海軍技術研究所という施設があり、私は中学2年のときには勤労動員でそこへ通っていたのですが、正門を入るとすぐ、白い横長の看板がありました。「実験心理学研究室」と書いてあり、左の方へ行くように矢印がしてあったのが今でもありありと目に浮かびます。先程の先生方はまさしくここにおられたらしいのです。要するに海軍が解体されましたから、海軍技術研究所所属の方たちが、その国鉄の労働科学研究室へ移られたのではないかというような気がいたします。
この労働科学研究室でも統計的な処理法に関して、多くのことを教えていただきました。あとで知ったのですが、どなたも東大心理学科出身の先輩だったのです。
インA 大学の心理の学科の授業だけではなくて、あちらこちらに行かれたのですね。
鳥居 そうですね。あの頃は、今と違って、大体、年に3回か4回ぐらいは休講があります。始まるのも4月後半ぐらいで7月に入ると、もう殆ど講義はないという状態ですから、実験でもしていれば別ですけれども、まだ学部では自分の実験というわけにはいかないものですから、とにかく統計法の勉強を、と考えて探しました。
特に、あの頃は、統計がやかましく叫ばれるようになってきた時代なのです。論文を出したくても、統計処理や何%で有意などというような話が載っていなければ通らないという有様の風潮が始まりかけていました。増山先生の推計学は難しいので、臼居先生のご紹介もあって、『医学・生物学のための推計学』(鳥居敏雄・高橋晄正・土肥一郎, 1954, 東大出版会)をまず入手し、少しずつ勉強し始めました。
インA ありがとうございます。そして、「図‐地反転を規定する諸要因の分析」という卒論を書かれたと思うのですが、このテーマを選ばれたきっかけなどはあるのでしょうか。
鳥居 きっかけですか?新制で入学した場合と違って、私は旧制の扱いだったので、2年生のときに、特殊問題研究(卒論の予備実験のようなもの)をしなければいけなかったのです。テーマを考えているとき、梅津先生が書かれた触空間の問題に関わる論文を思い出したのです。臼居先生のお世話で、円盤あるいは、針金をいろいろな大きさ、長さで木の板に貼りつけた実験材料を作ってもらい、それを使って触覚的な大きさや長さの判断を求める一連の実験を試みました。ところが、卒論はこれとは違うテーマでした。このテーマの決定にはある出来事が関係していると思っています。いつのことだったか覚えていないのですが、図-地反転の問題に関連した大山先生の手書きの論文を、「清書」したことがありました。また『Dynamics in Psychology』(1940)というKöhlerの本が、あの頃出ていて、それを読んで以来、図-地とその反転の問題に関心をもっていました。これを卒論のテーマにしようということで、「図-地反転を規定する諸要因の分析」というタイトルで書きました。その際、大山先生が、『千輪浩先生還暦紀念論文集』(1952)に書かれていた「図形残効と反転図形」という論文や、同じ本に掲載されている、当時北大におられて、その後聖心女子大に移ってこられることになる野澤晨先生が書かれた、「図形残効に関する一実験」も、たいへん参考になりました。
インA:それを発表されたのが、心理学研究に大山先生と共著で書かれた『図-地反転の実験的研究』ですね。
鳥居 はい。1955年のことでした。ところがその頃、1949年に出たHebbの『The Organization of Behavior』が視知覚の研究分野に画期的ともいえる影響を及ぼし始めていました。梅津先生のゼミで1年先輩の院生たちが、これを読んでいると知り、同級生と語らって、「読もう」ということになり読み始めました。最初の数章では、Köhlerへの批判やSendenの仕事に関係した問題が扱われていますから、何とか鳩首勉強した覚えがあります。
さて、実は大学院に入って2年目にあたりますが、私にとって新たな経験となることが起こりました。中山書店から『芸術心理学講座』というシリーズが出始めたのです。 5冊ある講座の分冊のうちの一冊が、相良先生編の『芸術と心理』という巻で、この中の「実験心理学」という項目について、書くように、と言われました。もう一つは、宮城音弥先生編集の『芸術と人間』という巻なのですが、ここでは「絵画と生活」について書くようにと指示されました。これらを完成させるまでに、国谷誠朗氏(美術史学科と心理学科卒業)にずい分輔けてもらい、深く感謝しています。すると、梅津先生にあるとき呼ばれて、「芸術心理学に興味があるようだから、これを研究テーマにしたらどうか」と勧められたのです。でも、芸術について実験心理学的に研究するのは容易ではないと考え、もっと先の課題にしようと、ひとまず諦めました。
それから、もう一つは、1957年に平凡社から『心理学事典』が出たことと関連しています。これは、もう大々的なもので、本郷に平凡社の分室(のようなもの)があったのですが、確かそこに藤永保先生が泊まり込んで、項目選定や執筆者の選出などをしておられたようです。われわれ院生もお手伝いに行った覚えがあります。その折、一つは「図-地」、そして、もう一つは「色のあらわれ方」について書くようにと言われました。それらは、もともと盛永先生にお願いしたものだったらしいのですが、先生が、私に回すようにと言われたとのことでした。Rubinの原著と、色のあらわれ方はKatzの原著を、ノートを取りつつ読み返して項目を書いた覚えがあります。この経験もあって、図と地とその反転という問題はこのあとも私の研究テーマの一つになっていきました。
サブリミナル広告の委託研究
これ以外に私が関わったものに、相良先生のところに寄せられた委託研究がありました。実は、当時、サブリミナル広告というものが米国で問題となっていたのです。映画を上映しているときに、ごく短い提示時間で「Eat pop・corn」あるいは「Drink Coca Cola」というメッセージを出したというのです。それを出したことには、観客は気づかなかったというのですが(つまり、閾下だったというわけですが)、それを提示しなかった場合と比べると、売り上げに差が出たというのです。これがちょっとした騒ぎになりました。それで輿論協会が、「サブリミナル広告というようなことが言われているけれども、本当に効果があるのかどうか、実験的に吟味してもらえませんか」という委託研究を相良先生にお願いしてきたのです。相良先生からそのことを伺ったのですが、1人ではできませんので、同級生だった鹿取廣人さんに話しました。それから、当時東京工大の助手をしておられた多湖輝先生が、ミュラー・リヤーの錯視図形の矢羽を閾下で出しても錯視が出るかどうかという実験をしておられたことを思い出して、鹿取さんと2人で多湖さんのところに行き、「相良先生から、こういうお話があるのですが、一緒にやっていただけませんか」ということで、共同実験を開始しました。
いきなり広告効果があるかどうかというのでは飛躍しすぎなので、もう少し地道にやろうと、これは、確か文献があったと思うのですが、顔の表情判断を実験テーマの一つに選びました。
もう一つは、図形の直後再生に及ぼす閾下の命名効果という実験でした。この二種類の実験に関わる結果は、世論協会発行の市場調査に発表したのですが、この冊子が、もう1か月近く探しているのに出てきません。
その後、相良先生のもとに、今度は電通から閾下刺激の効果に関する実験の依頼が来ました。そのため上記のメンバーで電通ではずいぶん実験を重ねました。ある程度成果が出ましたので、「識閾下刺激の効果に関する実験的研究」というタイトルで、1954年の日心23回大会で、相良先生を筆頭にして、多湖さん、渋谷さん(東京女子大卒)、鹿取さん、そして私と、5人の連名で発表しています。
ここで発表した実験の1つは、分割線錯視を使ったものです。これは、二本の線分の間隔が小さいいくつかの線で分割されると、コントロールよりも長く見えるという錯視です。分割する線を閾下で出したらどうなるかという実験でした。この実験の結果は、1962年に相良、鹿取、鳥居の連名で『Japanese Psychological Research』に発表してあります。その他にもいくつか実験があったのですが、いずれもさらに吟味を加える必要があるという結論になっていたと思います。
しかし、やがて、だんだんサブリミナル広告など怪しいのではないかという議論が、アメリカでも行われるようになり、もっと実験を重ねるという意欲は消えてしまったのです。ずっとあとになって、サブリミナルへの関心が復活したようですが…。
ここまでが、大学院在学中の研究にあたるでしょう。
博士論文の提出
私がドクター論文「視野における図-地の形成とその存続に関する研究」を提出したのは1964年、昭和39年のことですが、これは学部を卒業してから、ちょうど10年目にあたります。なぜ、このように時間がかかったか振り返ってみると、その当時の大学院生の間では、ドクターコースが終わってもすぐにドクター論文にはつながらないというような考えがあったのではないか、と思います。ところがあるとき、大学院生や院を卒業した30人ほどが本郷にある学士会館の分館に呼び集められまして、相良先生から「ドクター論文を書くように」とのご指示がありました。そこで、ドクターコースの1期生であるわれわれが走り出さなくてはいけないのではないかと麦島文夫、鹿取廣人の両氏とも話し合って出す決心を固めました。
私が博士論文の第1章で扱ったのは、図と地の形成がどのようなファクターで決まるのかという問題です。これは盛永先生の『類同の法則と視野体制』という、先程の『千輪先生還暦紀念論文集』(1952)に掲載された論考を私なりに発展させようとしたものです。この中でRubinの「横顔と酒杯の図形」について「2つの横顔をそれぞれ異なった色で描く」と「2つの横顔は見えやすくなる」と書いておられる一文をヒントに、その上下の一部をカットした変形図形を作りました。ちなみに「これは酒杯というよりも高坏の方がよい」と、苧阪良二先生から伺った覚えがあります。この左右の横顔を同じ色にした場合、あるいは、同じ明度にした場合、これらを変えた場合などと条件を変えると、一定の条件下では横顔が地になりにくくなるのです。つまり、横顔が、図としてあらわれやすくなるのですね。これは、学会発表もしましたし、『Perceptual and Motor Skills』の編集部から、あるとき手紙が来まして、「無料で載せるから、1ページの論文を書くように」と言ってきたのです。そこで、このときの一部を『Effect of unequality in color upon figure-ground dominance』(1963)というタイトルで書き送った記憶があります。
何日かして北大におられた結城先生が、たまたま研究室にいた私に電話をかけてこられて、「君の書いた論文は、不十分だ。あれだけで論文を書いてはだめだ」とお叱りを受けました。それがご縁になったのかも知れませんが、以後結城先生からは多くのことを教えていただきましたし、先生が北大から中京大学に移られたあとならびに退官されたあとに、先生を囲む研究会を有志と続けました。例えば、八王子セミナーハウスのようなところで、結城先生を囲む、泊まり込みの研究会を実施しております。
博論に戻りますと、第2章では図と地の反転速度が何によって規定されるのかという問題を扱っています。この一部は、『Japanese Psychological Research』(1960)の中に含まれています。
このあと、第3章では、反転と眼球運動の関係を研究課題にしています。このテーマは結城先生が1952年に北大の紀要に書かれた「形と動き」というタイトルの論考および苧阪先生が1970年に大山先生編集の『知覚』(講座心理学)の中で書かれた「眼球運動と形態知覚」という論考の影響を強く受けたものです。その当時、同じような考えを、Luriaが出していて、1975年に、「複雑な対象の視知覚の過程は、複雑な能動的受容活動である」と言っています。視知覚の場合も対象が複雑になるにつれて運動成分の参加が必須となり、それにより触知覚にますます近くなる、というのです。
眼球運動の研究
その頃、アイカメラが研究室に入ってきたのです。最初に入ってきたアイカメラは輸入品のBrandt-Eye-Cameraでした。いわゆる角膜反射法という方式の、調整が厄介なアイカメラです。次に購入されたのが竹井機器による竹井式アイカメラでした。上記の「酒杯-横顔」の変形図形を活用して、例えば「真ん中の視標だけをじっと(30秒間)見ていて、目を動かさないようにしてください」という教示の際の目の動きを撮りました。晴眼成人による凝視時の角膜反射光の軌跡が、微動を伴いつつもほぼ一直線に伸びているのに対して、開眼者の場合には不規則な眼球の動揺を伴うものになることなどを見出しています。
一方、1950年頃から静止網膜像stabilized retinal imageを観察するための装置が登場してきました。その一つは、アメリカの、Riggsたちのもの(Riggs, L. A., Ratliff, F., Cornsweet, J. C., & Cornsweet, T. N. The disappearance of steadily fixated visual test objects. Journal of the Optical Society of America, 1953,43, 495–501.)、もう一つは、PritchardやHebbが考案したもの(Pritchard, R. M., Heron, W., & Hebb, D. O. Visual perception approached by the method of stabilized images. Canadian Journal of Psychology, 1960,14, 67–77.)です。Pritchardの1961年の論文を、私は見逃していたのですが、京大で、苧阪先生がそれを見せてくださったのです。『Scientific American』(204, 72-78.)という雑誌に載った『Stabilized images on the retina』(1961)でした。「では、静止網膜像の装置で、反転図形を見たらどうなるのか」と思い、何とかして、その装置を作ることを計画しました。最初に、Riggsの方式で行こうと思って、本郷3丁目の駅のすぐ近くにあった「コンタクトレンズ東京研究所」を訪ねました。「こういう実験をやりたいのですが」と言いましたら、「それならコンタクトレンズをはめる練習からやらなければだめですよ」と言われて、練習した覚えがあります。当時はずっと長い間はめていてはよくないということでした。装置も、すぐ近くのナルミ商会という光学機械を作る会社に頼んで作ってもらいました。
アメリカ留学による眼球運動研究の中断
静止網膜像研究がうまく行かないうちに、その頃は東大を出て、東京農工大に移ったあとだったのですけれども、アメリカに行く話が飛び出しました。ミシガン大学医学部眼科学の視覚研究室におられた相場覚氏が帰国されるためAlpern教授から、「後釜を」と言われ、鹿取さんに打診があったのです。
少し話が前後してしまうのですが、その頃まだ東大にいた私は先程のナルミ商会で別の光学系の実験装置というのを作ってもらって、いわゆる精神物理学的な研究を当時修士課程の院生だった上村保子さんと共同で始めていたのです。その結果をもとに共著の論文も出しました(『Effects of inducing luminance and area upon the apparent brightness of test field』Japanese Psychological Research,1965)。そのようなバックグラウンドがあったことと、鹿取さんが「自分はいま動けない」ということで、私が行くことになったのです。結局、静止網膜像の研究は、そこでストップしてしまいました。ただアメリカへ行ってから再開可能かとも思ったのです。アメリカに着いてしばらくしてからAlpern先生に、そのことを相談しました。すると「Stabilizedは、とにかく、すごくタフな実験だが、それに耐えられるか」と暗に反対されてしまいました。 Riggsの研究室まで装置を見せてもらいには行きましたものの、静止網膜像については中断したままになりました。
東京工業大学にて
話がとび過ぎましたので、ここで巻き戻すことにします。博論が終わって、最初に就職したのは東京工大の工学部で、1959年の10月からです。
ただ、東京工大には心理学専門の学科はありませんから、一般教育で宮城音弥先生がヘッドの研究室での助手のひとりとしてです。多湖さんが、助手を辞めて千葉大へ移られたので、その後任としてでした。もう1人の助手候補は、私より1歳上の穐山貞登さんで、一高を1年で終えて当時の教育大に進まれた方です。とにかく東京工大では二つの助手のポストの一方は東大から、他方は教育大からそれぞれ採るという方針だったようです。ところが、その時穐山さんは病気のためすぐには応じられず、馬場道夫氏が来られました。その後、病気がよくなった穐山さんが着任されたというわけです。東工大の時代には、穐山さんにずいぶん親密にしていただいて、助手の仕事も研究も一緒に楽しく続けた覚えがあります。何しろ秀才で、あとあとまでも、その交流が色褪せることはありませんでした。
東大での助手と先天盲開眼者との出会い
東工大に移って1年半ほど経った頃、思いがけず東大への移籍という事態が起こりました。1961年5月から文学部の助手として勤務することになったのです。その翌年奇縁とも思えるような大きな研究テーマに出会うことになりました。1961年から、読売新聞社が、開眼手術とその後の治療の資金を援助するという「光のプレゼント運動」を始めたのを知ったのです。そして、間もなく白内障にかかった人が手術を受けて、「あ、見えるようになった」というような新聞記事が出てきました。学部の頃から私は、Sendenの本も、梅津先生の論文も知っていましたから、すぐに新聞社に電話をかけたのです。 そのときの社会部所属の記者で、その後ずっとお付き合いすることになる今村新之助氏がまもなく研究室に来られたので、「少なくとも先天性の白内障の方の場合、手術のあと眼帯が取れるやいなや母の笑っている顔が見えたというようなことはあり得ないでしょう」という状況を紹介したと思います。すると、今村さんは「なるほど。われわれは光のプレゼントはしたけれども視覚のプレゼントはしていないんですね」とすぐさま了解されました。そこで、「視覚のプレゼントとまでいくかどうか分かりませんが、どなたか手術を受けた方を紹介していただけないでしょうか」と依頼してみました。それでは、と紹介された方が、TMさんだったのです。お母さんは、元看護婦さんで、私どもの要請にこたえてTMさんを大学に連れてきてくださることになりました。TMさんと私が実験室で課題などを試みている間に、研究室で、梅津先生は、お母さんと、いろいろ話し合っておられました。帰りぎわ、「お母さん、今日はとても楽しかった」とTMさんに告げておられました。TMさんの方はどうかというと、「帰りにお菓子を買ってくれるので」と言って、それが楽しみでやってきたとのことでした。あのときは、まだ11歳ですからね。
TMさんは、生後1年2ヵ月でハシカにかかって、両眼とも失明し(角膜白斑)、その後の保有(残存)視力は「右眼ゼロ、左眼光覚弁」と記載されています。色は、少し分かったようです。形はどうかというと、白い台紙に、黒い紙から切り抜いた三角、丸、四角をそれぞれ貼りつけたものを用意し、見てもらったのですが、目の前に提示しただけではどんな「形」か分かりませんでした。台紙を手に取って眼前に近づけ、さらに動かしてみたものの、「何カガアル」とは分かったようですが、「名前(形の)ハ分カラナイ」という状態でした[手術後3ヵ月目の最初(1962年7月)の観察記録による]。
この状況がどう伝わったのか分かりませんが、当時の週刊サンケイという雑誌の取材を受けて、その1966年9月5日号に、「全盲の少女、開眼の意外な体験」というタイトルの記事が出たのです。なぜ「意外な体験」かというと、多くの人は、手術後眼帯を取ればすぐ色や形が分かると思うかもしれないが、そうではなかったからというわけでしょう。そこで私は手術を担当された日本医大の樋渡正五先生にお話を伺うことにしました。
医局にお邪魔して樋渡先生から「まず3月16日に虹彩前癒着をはがし、3月24日に全層の角膜移植手術を実施しました」というお話を伺い、さらに手術後に起こり得る問題についても教えていただきました。この場をかりて、先生と眼科学教室のスタッフの方(当時)に厚く御礼を申し上げたいと存じます。
TMさんに会った日から5か月ぐらい経って、MMさんという方を紹介していただきました。生後約10ヵ月で両眼とも失明(角膜軟化症)し12歳(1962年当時)のときに、都立駒込病院眼科部長の山本由記夫先生の執刀で、光覚が残っていた右眼だけの手術を受けました(1962.12.5)。紹介を受けたときMMさんはまだ入院中でしたので、病室で初めてお目にかかったのですが、「手術の前、明るい、暗いは分かった、でも色は分からなかった」と話してくれました。手術の日から6日後に訪ねた際、MMさんが自分の手で眼帯を短かい時間だけはずす場面に立ち会ったのですが、その途端、「まぶしい」と声を上げました。そして「明るさは分かるけど、色は分からない」と言っています。色の名前も全然知らないという状態でした。したがって、MMさんは「先天盲の開眼者は一体どんな色名を、どのような順序で習得していくのか」という疑問に答え得る希有のひとだったのです。
第2に、「開眼手術のあと、その視覚活動は一体どのような順序で進行するのか」という根本問題の一端に初めて答えてくれた(形の弁別活動にまでは到達しなかったものの)開眼者もMMさんだったのです。
視覚活動形成のためのMMさんとの共同実践活動が1966年夏にさしかかったところで、私の関与をしばらく中断せざるを得ない事態となりました。先程言いましたように、滞米研究生活がここにはいり込んできたためです。
アメリカ留学時の経験
この辺りで、アメリカ留学時の出来事について2、3お話ししておきたいと思います。1966年8月末、ミシガン大学の所在地アナーバーに着き、正式にリサーチ・アソシエイトの資格で視覚研究室の一員となった9月初め、研究テーマについてAlpern先生と話し合うことになりました。『心理学ワールド』の62号に、「アナーバー滞在日記からの抜書き」というタイトルですでに書いてありますので、ここでは端折りますが、「ヒトの色覚の型と錐体細胞内の感光色素(ピグメント)との関係に関する研究」というのがそのとき決まったテーマでした。二色型第一(protanopia)と第二(deuteranopia)のピグメントについてはYoung以来の「欠損説」を支持するデータがRushton教授らによりすでに提出されていたのですが、異常三色型の錐体構成とピグメントに関しては当時まだ確証が得られていなかったのです。そのためミステリー・ピグメントなどと呼ばれていたのですが、それらを探り当てる実験を重ねてみようという計画でした。さまざまな色覚型の多くの人たち(主に大学生)が研究室に来てくれたお陰で、開始後1年弱である程度の成果がありました。しかし、「やっと結果が出始めたな」と、Alpern先生が言われますので、大学に在外期間延期を願い出る手紙を送りました。「では、1年だけは待ちましょう」という許可を拝受しました。
2年目の研究がひと段落して、「さて、もう帰らなくては」と思っていた矢先、次の話が舞い込んできたのです。ケンブリッジ大学の生理学の教授だったRushton先生が定年になって、フロリダ州立大学の分子生物物理学研究所に赴任されることになり、Alpern先生のところに、「一緒に仕事をしないか」という誘いがあったようです。フロリダ行きを決心した先生が一緒に行かないかと私に声をかけて下さったというわけです。
私は困惑して農工大に「もう1年、在外期間を延長していただきたいのですが」と手紙で打診してみました。すると、(そのとき私は助教授だったのですが、)「教授会で、君を教授にするという話が出ている。すぐ帰ってくるように」とのこと。しかし、このようなチャンスはもう二度とないだろうと思いましたので、「この際、申し訳ないので辞職します」という辞職願を提出し、そのことを、Alpern先生に報告したのですが、「それは、ちょっと冒険ではないか」と一旦は止められました。しかし結論としては、「止むを得ないな」ということになり、間もなく農工大からは「休職扱いにする」という許可をいただきました。あわただしく引っ越しの準備をして、フロリダの研究所に着任したのは9月8日(1968)のことでした。
『心理学ワールド』の53号の巻頭言に「実証に150年かかる理論」というタイトルで当時のことを若干紹介しましたが、着くとすぐに実験の準備にとりかかりました。散瞳眼による光覚閾の測定がその具体的な仕事です。視角2度の閃光が見えたか否かを報告しなくてはならないため、最初のうちはデータが安定せず、とりわけ桿体視条件下ではその状態が顕著だったようです。装置と閃光判別法とに若干の改良を加えた結果、どうやら順調に進行し始めて、最初の結果をRushton先生の部屋へ持参したのは11月中旬頃だったかと思います。「Good harvest!」と言われたことをよく覚えています。速報をすぐさま、アメリカの科学雑誌『Science』に送ったのだそうです。しかし、 Rushton先生がしばらくしてやって来られて、「却下されたよ。どうもこの国は、われわれ外国人に対して冷たいようだね」と私にだけ言われました。すぐに『Nature』に送り、受理されたというわけです。これは3人の名で提出されていますが、次の『Nature』の論文には眼科医で視覚研究者のMs Anne Fultonも参加しています。
東大へ
1年弱のフロリダでの研究生活を終えて、9月に農工大に戻りました。ところが翌年東大から声がかかり、帰任後日が浅いので、親しくしていただいていた農工大の先生方に事情についてご相談申し上げました。どなたも了解してくださったことを深く感謝申し上げております。
再び開眼後の視覚研究へ
帰国後、何よりもまず中断していた開眼者の方との協同実験を再開することを思い立ちました。先程のMMさん、TMさんを含めて、1971年以降約20年にわたって10人の方にお目にかかることができました。むろん、少しずつ時期がずれているのですが、殆どが日本女子大児童学科助手(当時)だった望月登志子氏との共同プロジェクトとなりました。
1975年には、名古屋大学眼科の市川宏先生とそのとき医局におられた安間哲史先生からHHさんを紹介していただき、共同で観察を続けませんかと誘ってくださったのです。多いときは1週間に1回くらいの頻度で名古屋大学病院に通いました。HHさんについての観察結果は、市川、安間両先生と私どもの共著論文〔『臨床眼科』(1977, 31, 389-399.)など〕になりました。
このあと1980年には、ToMさんとその弟KMさんという先天性白内障の少女、少年に出会いました。お父さんも先天性白内障とのことでした。その当時、たしか東北大の院生で、のちに弘前学院大学教授に就任される佐々木正晴氏が、この機会をつくってくださったのです。一緒に、研究をしませんかということで、私どもは仙台に数え切れないくらい通うことになりました。それ以来、佐々木さんとは、今日までずっと緊密に共同で仕事をしてきています。
なお、10人の中のMMさんだけは、角膜移植ができるような目ではなかったようです。角膜の真ん中が濁っていましたので、本当は、そこを取らなくてはいけないのですが、手術を敢行すると目が壊れてしまうという状態と伺いました。それで虹彩切除という処置を受けたとのことでした。私がアメリカから帰ってきたあと、MMさんの目はまもなく濁ってしまって、視覚に関する課題はそれ以上続けられなくなりました。とはいえ、MMさんとの長期にわたる協同実験で蓄積された資料は、1972年以降に知り合った開眼者の方々(SH、NH、KT、YS、HH、MOの諸兄、諸姉)のための弁別・識別課題とその設定順序を決めるうえで、貴重な指針となりました。
細かい所まで言及している時間はもうありませんので、1974年10月に初めて出会ったYSさんとの2年間にわたる実践研究の成果について要約しておきます。それは、図領域の検出・定位課題から始まって2次元図形の弁別課題に至るまでの中継段階を余すところなく浮かび上がらせてくれました(『サイエンス』1983年7月号, 28-39.)。
詳細は東大出版会の『開眼手術後の視覚世界』(鳥居・望月,2000)に書かせていただきましたが、その際、編集部の伊藤一枝さんに多大なご尽力をいただきました。
立体の弁別と識別
先天盲開眼者が「2次元図形」の次に対面しなくてはならないのは「立体」です。手術を受けた人に、初めて立方体と球を見せたとき、触ることなくそれらを区別できるかどうかという疑問を、Molyneux,W.が、当時(17c)の哲学者John Lockeに宛てた書簡の中で初めて提起したといわれています。以来、これがモリヌー(ときにモリヌークスと表記)問題と呼ばれるようになりました。
さて立体となると、どのように提示するかという問題にぶつかります。台紙の上に立体を落ちないように貼りつけて、それを持ってもらうなどの工夫もしましたが、結局はテーブルの上に並置して身体を少々傾けつつ見てもらうという並の方式をとってきました。この場合それらを上から見たらどうなるか、真横からあるいは斜めからだとどうなるか、つまり視点によって同一対象の見え方が異なるという事態が起こります。これは、開眼者の方にとってまことに厄介ですね。もう一つの難題は、陰影の存在です。ここでのような普通のライトの下で立体をテーブルに置きますと、光の反対側に影ができます。「この黒いもの、これは何ですか」とある開眼者の方にきかれましたので、「では、触ってみたら」と勧めてみました。眼では見えたものが、触ると「ない」ことを体験してもらった、というわけです。それでも、私どもが出会ったどの開眼者も実物と影を「ひとつながり」のものと見てしまって、「実物」を誤認することがよく起こりました。TMさんがあるとき、ふとつぶやいた「どんな小さい物にも影があるんですね。不思議ですね」という言葉は、まことに印象的でした。
物の識別
立体の弁別・識別が錬成試行を経て少しずつ可能になってきた頃を見計って、物(事物、物体、物品)を「類」として、さらに「個物」として特定する課題に移行し始めました。18cのフランスの眼科医Daviel,J.は「白内障の手術を実施した先天盲の患者22人に物を見せたが、それらが何であるかすぐに分かったひとは皆無だった」と述べています。私どもの開眼者の場合にも状況は全く同様でした。
そこで、物の識別とその錬成に関わる試みを上記の何人かの開眼者の方と始めることにしました。
ところが開始早々、どんな類いのものか告げずに身辺の物品を一つだけテーブルの上などに提示するという課題場面の設定方式には重大な難点があることに気づきました。あるとき、運動靴を片方だけ机の上に置いたときのことですが、上記のNHさんがそれに触って分かったあと「こんなところに運動靴なんかあるわけがない。こんなところに運動靴が置かれたって分かるはずがないよ」と言ったのです。このように不用意に採用する「物の識別課題」の方式には問題がある、という趣旨のPalmer(1999)の卓抜な批判もあります。
ここで脳損傷後に物の識別が困難になった方についてご紹介してみましょう。
国立障害者リハビリテーションセンターの山田麗子さん(東京女子大卒業後、聴力言語センターを経て、国立障害者リハビリテーションセンターの心理部門に移った方)と一緒に、同時失認(脳損傷により)と診断されたSさんにある期間お目にかかったことがあります。
同時失認というのは、いろいろ定義があって厄介なのですが、Sさんの場合Luriaの言う同時失認の症状に一番近く、一つの物を見たとき、それしか見えないとのことでした。例えば「刺身が目の前に出されると、その一切れが取れない」と言われるのです。靴などの履物を左右揃えて描いた絵に対しても「二つ出されると分からない、一つだけ出してくれませんか」とのこと。Luriaが実施している方法ですが、紙の上にたくさん黒のドットを打っておき、「ドットの上に、赤鉛筆で印をつけてください」という課題を実施してみました。赤の印が黒から外れてしまうのです。黒を見ると赤が見えない、赤を見ると黒が見えないというわけで、適当な所にポンと打ちますから、多くの赤が黒から外れてしまうのですね。
物体失認の症状を呈した(交通事故による脳挫傷により)Kさんの場合、お目にかかってから半年ぐらいの間は、具体物やその写真、あるいは黒線の描画、動物の模型、プラスチック製の果物などが、ごくごく少数のもの以外、視覚的にも触覚的にも識別できない状態でした。その自覚もなかったようです。上記のものなどを見分ける試行を続けるうちに、半年程も経った頃でしたか、あるとき、「物が分からない。どうも、私は物が分からないようだね」と言われるようになりました。いわゆる「病識」ができたのでしょうか。とにかく、初めのうち「何で、こんなつまんないことやるんだ」と怒っておられました。「こんな子ども相手みたいなこと、なぜやるんだ。この物は何だなんて、そんなこと聞くとは無礼だ」と言われたりしたのですが、山田さんは、よく対応しておられましたね。
あるとき山田さんがたまたま席をはずしてKさんと私の2人だけのときに、ふと思い付いて、手元にあった黒いくしを目の前に置いて、「分かりますか」と尋ねてみたのです。すると「いや、分からない」、「触ってもよいか」とおっしゃるのですが「いや、触るのは少し待ってください」と言って、私がくしを取り、「髪をとかす動作」をしてみたのですね。そうしたら、すぐ「あ、くしだ」というわけです。しばらく間を置き、それを再び机に置いて、「これ、分かりますか」と尋ねたところ、「分からない」とのことでした。物によっては、それが、どのようなときにどのような動作で使われるか、その所作が大事だということを私としては初めて教えられました。
もう一つ例を挙げます。毎日使っているはずなのに、テーブルに置かれた歯ブラシに「分からない」と言われたときの出来事です。山田先生が、それを使って目の前で髪をとくように動かしたところ、「違う」、次に耳掃除の動作をしてみたのですが、これにも「違う」というお答えです。このあと先生が歯磨きの動作をしてみたとたんに、「あ、歯ブラシだ」と見事正解に至りました。
またあるとき、目では分からなかった歯ブラシに触ってすぐ分かったあと「なんだ、歯ブラシじゃないか。こんなところにあるもんじゃない」とKさんに怒られました。「こんなところにあるから、分からないんだ」とその理由について開眼者のNHさんと同じことを言っておられました。物には、用途に応じた、あるべき場所があって、そこにあれば分かるということではないでしょうか。
顔・表情
物と並んで、いやそれ以上に厄介なのは顔ですね。物は近づいて見ることもできますけれど、他人の顔を接近して見るわけにはいかないという社会的な制約があります。それでKTさん(15歳の頃水晶体摘出手術を左眼だけに受けた方)は幼児の顔を観察することを、自分で試み始めたと述べておられます。「笑っている」ときの顔を見て「頬の筋肉が盛り上がるのが分かるようになった」とのこと。来訪時(1974.10)から1年半経った頃には「笑顔は想像がつくようになった」ものの、まだ「悲しそうな顔や怒った顔は想像がつかない」(1976.3)という状況が続いています。当初から「顔を見てそれが誰なのか、どうして分かるのですか」という疑問はずっと抱いておられるようです。このところ、よく似た2人の女性の顔写真を10枚用意し、それらを振り分けるという弁別課題を試みているのですが、今一歩というところでしょうか。
鏡映像とグレゴリー
ここで鏡映像に対して開眼少女MOさんが示した反応とその変遷について、ごくあらましを〔詳細は『先天盲開眼者の視覚世界』(2000, 東大出版会)〕ご紹介しておきます。
MOさんは、左、右眼の角膜移植を何回かにわたって受けているとのことで、「読売光と愛の事業団」(1971年発足)の担当の方から紹介されました(当時14歳)。出会って2ヵ月半経った頃(1989.12)、初めて姿見の前に立ってもらったとき、「何が見えますか」と尋ねてみたのですが「見えない、分からない」としか答えませんでした。しかし、1ヵ月(2回目)以降は、鏡の表面を触ったり、裏側に手を回して探ったり、裏側へ回るというようなことを試みています。だんだん、鏡というものが、自分を映す、自分の顔を映してくれる、外が映っているということも分かってきて、後ろにある物体は前に映っているのだとか、外の中に私がいるとか、そのような報告が、約2年後には現われています。
その経過を、ブリュッセルで国際学会があったとき(1992年:東大定年後、聖心女子大学に在職中)に、ポスター形式で発表したのです。そうしたら、そこにGregory教授(視知覚の研究、開眼後の視覚状況に関する論文でも著名な)が見にきてくれたらしいのです。そのとき、私はポスターの前から離れていて、望月ひとりが立っていたのですが、「何か偉そうな人が来ていろいろ質問された」とあとで言うのです。そして、もちろんポスターだけでは詳細は分かりませんので、英文で細かく書いた報告ノートを持参していましたから、それをお渡ししておいたというわけです。するとそれがGregory著の『Mirrors in Mind』という本の中で引用されていたのです。そこに載せてくれたことを私どもは知らなかったのですが、新曜社の社長堀江洪さんがあるとき電話をかけてくださって、「今度Gregoryの本が出て、先生達の研究が載っているの知ってますか」、「載ってるんですよ。訳しませんか」ということになってしまい、訳すはめになりました。
Gregory教授は、とても博識らしく、扱っている分野も多方面にわたっていますので、鹿取さんと鈴木さんにもお願いして、4人の共訳で『鏡という謎』(2001)を出版してもらいました。編集部の塩浦暲、吉田昌代の両氏のご尽力にも深く感謝しています。
変換視
先程の佐々木さんは、20数年前から、当時宮城教育大に在職中の八木文雄氏と共同で変換視メガネの短期・長期着用実験を続けてきています。さらに視野全体をかくすアイマスクや小視角の穴だけ開けたピンホールメガネの着用実験も実施し始めています。私も視角が3度前後のピンホールメガネで外界(見知らぬ場所)を観察することを、何回か試みてきました。
2010年からは日本大学の佐藤佑介氏がこの共同研究に参加してくれることになりました。お陰で体操競技における視覚の役割について具体的な研究を実施する道が拓けつつあります。「倒立における視野制限の影響」といったテーマの実験はその一例です。
ピンホールの実験には思い出が一つあります。大学院の頃、梅津先生のゼミで、視野の広さは物の見え方に、どのような影響を及ぼすのかという問題で論じ合ったことがあるのです。「視野を、できるだけ縮めて、小さな穴を通して外を見てみるようにしたら、どんなことになりますかね」と先生がふと言われたことを、よく覚えています。「実験してみよう」と思ったのですが、今までそのままになっていました。
脳損傷と視神経低形成
先程は、脳損傷による物体失認あるいは同時失認症状についてご紹介しましたが、そのほか大脳性色覚喪失、半側無視、両眼立体視の欠如、実体鏡視における左右像のズレ、眼球運動の不調、複視、画像などにおけるGestaltの解体、といった諸症状の方々にお目にかかりました。そして、鹿取さん、河内さんおよび助手、院生(当時)の諸兄(木村英司、山本豊、今水寛、山上精次、高橋晃、渡辺武郎、中沢仁の諸氏、順不同)と共同で、それらの症状の軽減・改善に関わる試みを続けてきました。東大教育学部の能智正博さんのご尽力もあって、その一端をまとめることができました。
インA 一昨年本を出された、『認知世界の崩壊と再形成』ですね。
鳥居 そうです、あの本には、以上のほかに先天性の視神経低形成と診断されたKさん(多分光覚盲)に関する1歳4ヵ月から2歳4ヵ月までの1年間の行動記録も含まれています。主に国リハの研究室内での非視覚系による空間行動の観察が含まれています。
なお、このKさんに関しては、事物と形態に対する呼称ならびに操作の活動状況を記録した全体で5年半に及ぶデータが未公刊のままになっています。とにかく多岐にわたる資料のため、今度の本には収めることができませんでした。これらを収録した新しい本の完成を見ずに山田さんが逝去(2007年5月)されたことは、まことに心残りと言うほかありません。
学会での仕事
インA 学会の仕事はいかがでしょうか?
鳥居 日心に関係する仕事ですと、編集委員をたしか2年、そのあと、編集委員長を3年務めています。編集委員長をしているときに、Blackwellという、イギリスの出版社から、「日心で出しているリサーチの出版、印刷を引受けたい」と言ってきたのです。 7月に「ブリュッセルで会いたい」とのことで、心理学会事務局の朝倉和子さん、久野洋子さんと一緒に3人で、EditorのMs Claire Andrewsと会いました。 いろいろ話し合い、出版の条件も聞くなどして、「今度は日本で会いましょう」ということになりました。11月になって、アンドリュースさんとManaging DirectorのRene Olivieri氏が来日し、当時の学士会館分館で会ったのです。細かいことは、もう覚えていないのですが、ともかくこうして最終的にBlackwellからの出版が決定しました。
感覚代行研究会
学会とまでは言えないのですが、感覚代行という名称の研究会設立に関与しています。これは、名大の市川先生、早稲田大学理工学部の大頭仁先生、そのときはまだ研究所に在職中の和気典二さん、それに私の4人で立案したもので、いずれは学会にしようという目標を立てていました。しかし、研究会のまま今日に至っているのですが、毎年1回はシンポジウムを開いてきています。去年の12月で41回目ですから、設立以来ほぼ40年ということになります。これまでに『視覚障害とその代行技術』(1984,名大出版会)という本を出していますから、今度は、40回を記念して第10回以降の論文をまとめた本を出したかったのです。しかし、まだペンディングのままになっています。
視覚に極度の制約がある人たちにとって大きな問題の一つは、自在に出歩くことが厄介な点にあります。感覚代行シンポジウムのお陰で歩行補助用ロボットの研究をしておられる森英雄先生(山梨大学)と知り合いになりました。いわゆる盲導犬ロボットの研究を長年積み重ねてこられたのですが、大学を定年で退職された今も、新しい方式の開発に営々と取り組んでおられます。佐々木さんと私とはアイマスクを着用したり、ピンホールメガネをかけたりした状態で、新式の補助車を押して歩く実験のお手伝をしてきています。先月も二人で山梨へ行ってきたばかりです。
翻訳の仕事
高砂 Gregoryの翻訳だけではなく、先生、結果的にですけれども、古典の翻訳に割と関わっておられますよね。例えば、Berkeleyなど、あれは、翻訳そのものではないと思いますけれども、下條さんのあとがきには、「先生に勧められて」というような文章がありましたが。
鳥居 Berkeleyの『視覚新論』は、なぜか翻訳されていなかったのです。『新視覚新論』を書いておられる大森荘蔵先生にお目にかかって、その理由をお尋ねしてみたこともあります。その後、話が現実味を帯びてきましたので、哲学研究室の杖下隆英氏〔『認識と価値』(1989, 東大出版会)の著者〕と相談の上、植村恒一郎氏と一ノ瀬正樹氏とにお願いすることにしました。お二方は訳注も担当しておられることをあとで知りました。「心理学者も誰か入った方がいいんじゃないですか」とすすめられたので、「下條がいるから、彼がいいかな」という鹿取さんの提案もあり、承諾してもらいました。私自身は「先天盲における開眼手術後の視覚とバークリ」という解説で一応の役目を果たしたつもりです。
高砂 そのときには、当然のことながら、Sendenの方は英訳はありましたけれども。
鳥居 確かに英訳(1960)はありましたが、日本語の翻訳はなかった筈ですね。
高砂 ないですね。
鳥居 原著の出版は1932年ですから、英訳でさえそれが出るまでに30年近く経っていることになります。
高砂 そして、先生が、割と最近、出されていますね。
鳥居 『視覚発生論』(望月と共訳)というタイトルで2009年に協同出版(小貫輝雄社長)から翻訳を出してもらいました。英訳出版の年から数えても50年近く経ったあと、ということになりますね。ただ原著の「奥行視」(1部B-Ⅱ)以下については、その訳出を見送っていますから、実は全訳ではないのです。
高砂 そうなのですね。
鳥居 私はドイツ語版と英語版を併用したのですが、Peter Heath氏の英訳に大いに助けられましたね。それでも、とにかく時間がかかりましたね。翻訳をやっていると、他の仕事ができなくなってしまうんですよ。
高砂 そうですね、そう思います。
鳥居 なお、2008年の国際学会の折に、キール大学を訪ねて、Sendenのファーストネーム(長いこと不明のままだった)がMariusであることを知ったような次第です。
高砂 そして、それとほとんど前後して、Hebbの『行動の機構』を訳されていますが…。
鳥居 鹿取さんが推進役の改訳(2011年)の一部を手伝ったのです。白井さんの邦訳が1957年には岩波から出ていたのですが、すでに絶版になっていました。
高砂 そうですね、白井常先生はHebbを訳されていますね、はい。
鳥居 改訳の計画はかなり以前からあったようですが、鹿取さんが岩波書店と交渉し、先方のすすめもあって、文庫版(上下2冊)が実現したとのこと、私はその上巻に含まれる4章と5章を分担したのです。
質問
インA Perceptual and Motor Skillsから、最初、声がかかったという話でしたけれども、それは、何か理由はあるのですか。
鳥居 当時も以後も、それが不明のままなのです。日本の何人かの心理学研究者に声をかけたのではないか、と想像しているのですが。
高砂 すみません、もう1件だけ。先ほどの3人の先生、Alpern先生とRushton先生と先生の、A.R.T.と言っていましたよね。
鳥居 はい。Alpern、Rushton、Toriiの頭文字を取って、『J.Physiol.』に提出した自分たちの論文の中で先行論文を引用する際に、(A.R.T.)とか(A.R.T.a,b)などと表記しているのです。「これはartになるよ」というRushton先生の言葉が今でも耳に残っています。
イン わかりました。長時間にわたり、ありがとうございました。