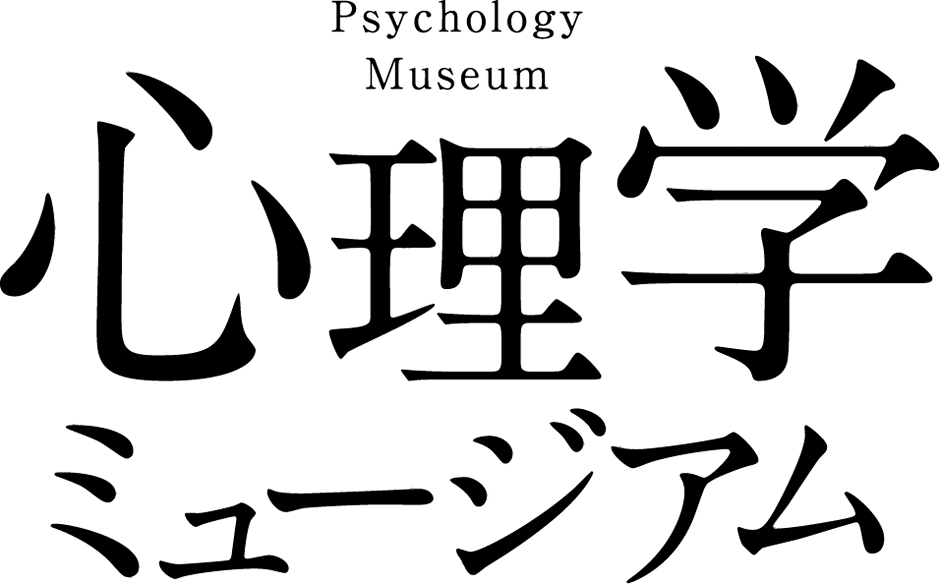杉溪 一言先生
動画は抜粋です。インタビュー全文は下記からご覧ください。
杉溪 一言先生の略歴
・東京帝国大学、学生相談、家族カウンセリング、産業カウンセリング、グループダイナミクス
・1943年に東京帝国大学に入学。同年12月に学徒出陣で海軍に入営。適性検査の業務を担当。終戦後は横浜国立大学助教授、日本女子大学家政学部教授、川村学園女子大学教授、日本産業カウンセリング学会名誉会長、日本家族カウンセリング協会会長などを歴任。
・東京帝国大学の先生方や海軍航空要員研究所、戦後のSPS研修会などの話を聞かせていただきました。カウンセリングの分野でも活躍をされて、日本学生相談学会、日本家族心理学会、日本人間性心理学会、産業組織心理学会などの設立にも関わりました。
日時:2016年2月9日
場所:
インタビュアー:小泉晋一(共栄大学)、鈴木朋子(横浜国立大学)、高砂美樹(東京国際大学)
場所:
1.なぜ心理学を学ぼうと思ったか
心理学との出会い
私は大正11年の生まれで、戦前の教育制度の中で思春期・青年期を過しました。当時は中学が5年で、高校の3年間は17才〜19才の多感な年頃でした。
旧制の高等学校には、中学校にはない第2外国語(ドイツ語、フランス語)や、哲学、倫理、心理といった教養課目があり、何か少しエラくなったような気分でしたが、私はその中でも心理学に興味を持ちました。担当の先生は豊川昇という人で哲学が専門でしたが、当時ドイツから入ってきたゲシュタルト心理学のテキスト(小保内虎夫『心理学概要』)を使っていました。私はこの先生と親しくなりお宅にも伺ったりしましたが、後年、私が心理学の道を選んだのは、直接的には高校時代の心理学との出会いが端緒になったように思います。
人格主義、理想主義への傾倒
旧制高校にもそれぞれの気風の違いはありましたが、おしなべて若者の自由を謳歌する空気が学園を包んでいました。当時の日本は満州事変、支那事変と外地での戦乱が続き、次第に国際的な緊張も高まり、軍国主義的な風潮が広がってきていましたが、大正デモクラシーの余韻の中で成長してきた私たちは、自分らしく生きようという人生観、よく生きるとは何かを問いつづける価値観をめぐって、友人たちと口角泡を飛ばしてディスカッションをしていました。
思い返してみると、そうした時代背景の中で、迫り来るミリタリズムのプレッシャーが逆に若者の悩みを育んだと言う側面もありますが、私にとっては、青年期の人間形成過程に、仲間たちと「人間研究」に打ち込んだ経験はとても貴重なものだったと思います。そしてそのことが、後年の心理学者としてのアイデンティティの確立の一助になったと思っています。
ディスカッションの中で私たちの考え方にインパクトを与えたのは、東大経済学部教授・河合栄治郎の『学生に与う』と言う一冊の本でした(1940年出版)。彼は理想主義、自由主義の思想に基く社会評論活動を、敵対勢力からの圧迫に耐えながら怯まずに展開し、信念を貫き通した気骨の人として名を残しています。
河合の説くところを簡単に述べることは出来ませんが、彼は同書の中で「教師は何よりも教育者でなければならない。彼は自らが苦しみ悩んで人生を生きたものでなければならない」。「“教養”とは、有閑人の安易な閑事業ではなく、雄々しいがしかし惨(いた)ましい人生の戦いである」。「教育の本来の目的は人間各自に本来具わっている真・善・美の三つの価値をすべて引き出すことであり、人間を彼自身たらしむることである」などと述べています。また理想的な学生像とは、「自己の感情や欲望に流されることなく、どこまでも他者の立場を考慮しながら思慮深く行動し、その行動に十分責任を持つことのできる自律した人間である」といっています。
私は改めて振り返ってみると、心理学を志す一歩手前のところで、高校時代の自分探しにもがく姿が垣間見られ、何か懐かしくもあり、ほゝ笑ましいような気がします。
生き方のモデルになった祖父、杉溪六橋
私が大学で心理学を専攻しようとした動機づけには、祖父の存在が大きかったと思います。といっても、祖父は心理学とは全く無縁の人なのですが私はいわば祖父の生き方をモデルとして心理学の道に進み、その後の人生を歩んできたように思います。そこで少し私の祖父のことをお話しましょう。
私の家のルーツは京都の公家(くげ)で、祖父は公家の家の三男として慶応元年(1865)に生まれました。一時は奈良の寺に遣られましたが、まもなく明治維新となり、動乱の中、青年期を京都で過ごしました。その後時勢を見て東京に出てくるのですが、帝国議会(国会)の開設とともに最年少の貴族院議員になったそうです。また、国政に参与する傍ら少年期から学んできた漢詩や書画に親しみ、政界を退いて隠居してからは専ら「文人」として芸術的な活動をしていました。文人と言うのは武人に対する言葉で、詩文や書画など風雅を嗜む風流人を意味しています。
祖父・杉溪言長(ときなが)は六橋(りっきょう)と号し、世に「三絶」(漢詩・書道・南画に秀でた人)と称され、独自の世界を拓いた人として一定の評価を受けましたが、私自身は若輩でそのような脱俗の世界など全く解りませんでした。
そんな私が祖父をロール・モデルにしたのは、激しい変革の時代にあって、自らの資質を生かし努力を重ね、独自の世界を構築した志の強さに学びたいと思ったからです。私は幼い頃から生活の中で祖父の謦咳(けいがい)に接し、その人格と生き方に触れたことが、心理学を志す上で潜在的な力になったように感じています。
高校時代の先輩の影響
私の学んだ旧制の高等学校は学習院高等科ですが、学習院から東大の心理学科に進んだ先輩が3人いました。その中の一人は私が入学したときに研究室の副手をやっていた松村康平氏(1941年3月卒)です。松村さんは外林大作氏と並んで我国に心理劇を導入した人ですが、私の大学入学に際して頂いた助言は今でもよく覚えています。松村さんの天才的な言説には、とてもついて行けないところもありましたが、後年ワークショップなどでご一緒になり、個人的にも親しくして頂きいろいろとお世話になりました。
もう一人の先輩は松平定康氏(1941年12月卒)です。松平さんとのご縁はとても深いのですが、私が心理学科を志望した頃、彼は海軍予備学生から任官して少尉になり、海軍で航空心理の研究をしていました。私は学習院在学中から部活動などでご一緒でしたので、身近な先輩の軍服姿を見て、心理学の研究が国家目的につながることに心を動かされました。その当時はまだハッキリした道筋は見えていなかったのですが、先輩が私の進む道の前を歩いているように思えて、心強く感じたことを覚えています。
2. 東京帝国大学(現東京大学)で心理学を学ぶ
心理学科に入学して
私が入学したのは1943年9月ですが、同期生は20名余りいたと思います。しかし学徒動員などがあって卒業はばらばらになりました。大学に入ってみてまず感じたのは、心理学科の仲間たちが総じて真面目そうなおとなしい感じで、高校時代にいた暴れん坊や異色の人物は見当たりませんでした。私自身もハメを外す方ではなかったので、何となく同質の集団という印象でした。(その後のつきあいの中で、互いの個性がわかってきましたが)。
その頃のカリキュラムには「教練」という軍事科目があり、週一回グランドで銃劍術などの訓練がありました。また、富士山麓にあった陸軍の厰舎で、一週間程の野外教練が行われました。これは文学部の各学科でまとまって合宿するのですが、心理学科の隣に社会学科の学生が来て、それぞれの空気が大変違うので、改めて心理学の連中のキメ細かな肌合いのようなものを感じました。
短い期間でしたが応召までの一年間に私は大切な仲間と出会いました。水原泰介、先崎正次郎、亀井一綱、森岡寿夫、高月東一、森重敏などの諸兄です。これらの友人とは卒業後も研究や社会活動のみならず個人的な面でも交流を重ねてきましたが、それも心理学の扉を叩いたからこそ得られた絆だといえましょう。
大学の授業を思い起こしてみると、やはり一番印象深いのは心理学の一般実験です。これは現在でも行われていると思いますが、心理学の基礎的な教養として大きな意味があったと思います。
師事した教授、研究室のスタッフ
私が入学した当時の心理学科主任教授は桑田芳蔵先生でした。私の記憶にある桑田教授は白髪白髥、ヴントの心理学を講じ、老教授の風格を具えておられました。後に文学部長に就かれたと聞いています。
千輪浩、高木貞二の両先生は、助教授から教授に昇格されて心理学科の二本柱でした。千輪先生はゲシュタルト心理学、高木先生は心理学的測定の講義を担当されていましたが、私の記憶では高木先生が私たちのクラスの指導教官であったように思います。先生は見るからに英国風のジェントルマンで、胸ポケットにハンカチーフをのぞかせていました。それで有名なエピソードをご紹介しますと、先生が以前に教鞭をとられた京都の第三高等学校(三高)で、或る日教室に行ってみたら生徒全員が制服の胸ポケットに新聞紙をさしていたという話です。今では胸ハンカチも珍しくはないでしょうが、高木先生のキチッとした風姿を彷彿とさせる話ですね。私は先生の従容としたご人格を尊敬していましたので、出征に当って先生のお宅に伺い、日の丸(日章旗)に「武運長久」と書いて頂いたことを覚えています。
当時の心理学科の講義の中で私の記憶に残っているのは、宮城音彌先生の臨床心理学、山下俊郎先生の児童心理学、牛島義友先生の青年心理学、岡部彌太郎先生の幼児教育、桐原葆見先生の産業心理学などです。
研究室の助手は学生にとって怖い存在でしたが、当初は黒木総一郎氏、その後間もなく小川隆氏が代られました。小川先生とは後年海外出張でお会いし久闊を叙しました。
当時つけていた日記から学生生活の断片を拾うと、日常の物資も次第に乏しくなってきた頃で、必要な大学ノートを買うのに行列で、漸く5冊買えたなどと記しています。また通学も交通の便が悪くなり、私は御茶ノ水駅から大学まで歩くのが常でした。バスは木炭車で坂を昇るのが大変でした。このように何かと不自由な生活でしたが、戦時中のゆとりのない現実の中にあって、学問研究の一端に触れ得たことは、私の精神生活を培うこよなき土壌となり、我が人生の貴重な1ページとなったと思っています。
3.学徒出陣で海軍へ
私が海軍に入ったわけ
私は青春の日々を日記に綴っていましたが、大学1年生(昭和18年)の9月23日の日記にこんな記述があります。
「昨晩 東条首相の重大演説に依って学生生徒の徴集猶予延期停止が発表された。朝刊は情報局発表の国家総力体制確立に関する記事で埋まってゐる。豫想されてゐた大学閉鎖は断行されたのだ。理、工、農、医は入営延期の形で残り、法、文、経は延期停止だ。だが一部の病弱者、適齢未満者等の為に講義はあるらしい… (原文のまま)」。
日記は続けて「心理学」が理工系と見做されて続けられるかどうか、多分難しいであろうなどと当時の不安な心情を綴っています。
とにかく私たち若者は、学徒出陣の大号令によって、陸軍は12月1日、海軍は12月10日に入営、入団することになりました。私は徴兵検査を受け「第1乙」と認定され、検査に合格しました。徴兵検査には甲乙丙丁の判定があり、丁以外は合格です(乙は更に第1乙、第2乙、第3乙と分かれる)。私は幼少時から風邪を引き易く弱い体質だと思っていましたので、検査で第1乙とは意外でした。しかし、そう判定されてみると、それなりの自信も湧き、よし、やるゾ!と言う気概が生まれました。
さて、検査に合格すれば陸軍か海軍に入らねばなりません。どちらを選んだらいいか、いろいろ迷いました。私の家は前にも述べたように公家の出ですから、先祖にも周囲にも軍人は一人もいません。学習院の友人には明治以来の軍人の子弟が何人もいましたが、私には先例とかモデルが無いわけです。どちらかに決める拠りどころが無い中で迷う日々が続きました。
私自身の経験では、学校で馬術部に入り乗馬は好きでしたから、陸軍将校の乗馬姿がイメージし易かったと思います。また、私の生まれ育った家が、当時東洋一と称された陸軍の連隊の近くで、夜の消灯ラッパを聞きながら成長したので身近に感じていました。
一方、海軍の方も学習院の制服が海軍士官の蛇腹のついた軍服を模したものだったり、少年時代に戦艦長門の見学をしたことの印象も深く、なんとなく親近感を持っていました。
こうした青少年期の心象風景を背景にしながら、私たちは応召を前にして、不確かな情報に一時翻弄されていました。「心理の専攻生は将来海軍の適性部に入れる…」、「陸軍でも一定の訓練を経て適性検査業務に就く道がある…」、「海軍では特別技術将校として心理学出身者をうけ入れるのではないか…」などなど。
丁度その頃、大学の先輩の望月衛氏が陸軍で航空適性検査を担当されていて、私たち心理の学生を検査業務のアルバイトとして臨時に雇用してくれました。それは数日の経験でしたが、兵隊の食事を食べたりして、いわば体験入営のようなものでした。
海軍の方は前に述べた先輩の松平さんの話から想像するくらいで体験的には何もなかったのですが、漠とした印象では、海軍の方が合理主義的で、心理学を齧り始めた私の価値観にも合っているように思えました。(しかし入ってみると必ずしもそうでなかったのですが…)。
私は、日記にも当時の心境を記していますが、陸軍にしても海軍にしても、心理学者としての活動が国家目的に適い、専攻の勉強が役に立つのであれば、それは大変やり甲斐のある話である。しかし戦況から見ても将来のことは解らないのだから、今の段階でジタバタするのは見苦しいのではないか…と思っていました。そして若し思い通りの進路に進めなくても、自分はそれを与えられた天命として受け容れようと心に決めていました。
折しも 昭和18年5月21日、聯合艦隊司令長官山本五十六元帥(当時大将)の戦死が報ぜられました。国民が戦局の重大さをひしひしと感じていた頃のことです。私自身も心の奥で、軍服を着ることの意味を、一つの「覚悟」として心に刻み、応召の日を迎えました。
海軍二等水兵から豫備学生へ
いよいよ12月10日がやってきました。私は出征軍人の誰もがやっているように、大学から貰った日の丸(国旗)を襷(たすき)に掛け、横須賀海兵団に入団しました。そしてその日から学生たちはジョンベラ(水兵服)を着せられ、海軍二等水兵としての生活が始まったのです。
入団してまず吃驚したのは、東大の心理の仲間たちと同じグループになったことです。私は第31分隊・第8教班に配属されました。因みに「分隊」は二百数十名、「班」は十数名の単位です。分隊の編成は出身大学・学部別に配置され、第31分隊は東大の文学部が主体でした。第8教班は心理、哲学、独文(ドイツ文学)、西洋史などの人たちの集りでしたが、その中で心理が最も多かったと思います。一緒だったのは池内一、石毛長雄、糸川民生、樋口伸吾の諸兄です。他に学習院初等科時代の同窓生穂積重行君も同じメンバーで奇遇を喜びあいました。(これらの諸兄は後年大学教授として活躍されました。)
私たちは全くの異次元の世界に身を置きながらも、娑婆(しゃば)(世間)の仲間と共にいる安心感に支えられて、2ヶ月弱の水兵生活を過しました。今から考えると、この時の体験は期間は僅かでしたが、組織の最下層の実体験として貴重な人生経験になったと思います。
私は若い頃から胃腸が弱く、何かというと休み勝ちで軍隊生活に耐えられるかどうか心配でしたが、矢張り予想した通り腹をこわし、「軽食」といって粥食に変えてもらったことも再三ありました。通常の食事も山盛りのメシを喰べきれず、周りの人に分けて喜ばれたこともありました。そんなひ弱な私でしたが、飛行適性検査に合格したので「飛適」の烙印が押されて、大勢の仲間と共に横須賀から土浦まで輸送され、いよいよ海軍豫備学生として「海鷲」になる道を進むことになりました。歌にもなった「豫科練」(豫科練習生)で有名な土浦海軍練習航空隊に入隊したのは2月1日のことでした。
さて水兵服から海軍士官の軍服に着替え、短剣を腰に吊すとすっかり気分も改まりました。しかし東大生から海軍士官への変身は、服装が変わったからといってそう簡単にはいきません。土浦特有の「筑波おろし」の寒風が吹き付ける中、「軍人精神」を叩き込む猛訓練が豫備学生の先輩の士官たち(少尉、中尉)によって行われ、日夜緊張に満ちた生活が始まりました。
私は前にも述べたように、胃腸に自信が無く、とりわけ厳しい土空(土浦海軍航空隊の略称)でのトレーニングに耐えられるか全く不安でしたが、人間、覚悟を決めると体質まで変わるのかと思える程に元気が湧き出てきて、雪中のハダカ体操などにも積極的に参加しました。今から考えると私の症状は多分に心身症的であったのかもしれません。
土浦から鹿児島へ
土浦での日夜の猛訓練に馴れ出した頃、再び身体検査があり、その結果私は「要務学生」としての教育を鹿児島航空隊で受けることになりました。この検査はパイロットとしての適格性を見るためのものでしたが、私は当時風邪気味で鼻の調子が良くなかったので、検査で撥ねられたのです。青年期に蓄膿症(副鼻腔炎)を患っていた私は、その結果に納得はしましたが、航空要務の任務も定かではなく、折角「海鷲」への道を歩み始めた時でしたから、胸中には複雑なものがありました。しかし後から考えると、この時点で私の運命は大きく変ったのだと思います。
当時の日誌によると、2月12日の夜半に特別軍用列車で土浦を出発し、鹿児島まで殆どノンストップで走り続け、3日後の朝漸く到着。その間車内から出ることは厳禁。途中、家族と面会したくて電報を打った者のいることがわかり、懲らしめのために全員の夕食が半分に減らされたと書いてあります。“犯人”たちが軍服を裏返しに着せられ、車内を歩かされた姿は、私情を否定することによって秩序を保とうとする軍隊組織の非情な一面を見る思いがして、今も瞼に焼き付いています。
とにかく私たちは巨大なベルトに乗せられ、思考停止のまま身を委せる他はありませんでした。しかし、寒風の吹き晒す土浦から南国の鹿児島へ来たことは、矢張りほっとする部分もあり、毎日桜島の美しい姿を見ながら、豫備学生としての生活に馴染んで行った数ヶ月でした。
いよいよ鹿児島での訓練も終わり、要務の学生たちはそれぞれの志望に従って配属先へと分れて行きました。その行き先は様々で、軍艦に乗って暗号解読に従事する者、偵察のための航空写真を任務とする者、若い豫科練たちの教育に携わる者、司令部付の用務を担当する者などなどあり、海軍という組織の大きさと多様さを改めて知る思いでした。
私はその中で適性検査業務を志望し、再び土浦航空隊の門をくぐることになりました。土空の適性部勤務を命じられたわけです。東大の心理学科に入学以来、出来ることなら専攻する分野で国家に役立ちたいと言う念願が実り、私は新たな希望を胸に土浦へと旅立ちました。
4.適性検査に従事
適性部勤務
土浦に来てみると、すぐには適性部に配属にならず、それから夏の炎暑を挟んで約4カ月間、術課教程と称するアドバンスコースの訓練が待っていました。これも中々にしんどい体験でしたが、この頃になると海軍士官の軍服も身につき、「第14期海軍豫備学生」としての自覚が芽生えてきたように思います。そしてその年の10月に、いよいよ「適性部員」として勤務することになりました。
適性部には、東大の心理の先輩の日上泰輔氏、松平定康氏(豫備学生1期、海軍大尉 両氏とも東大1941卒)が居られ、特に松平さんは学習院の先輩でもあるので心強くアットホームな感じも味わいました。
適性部の部員は武官と文官に分かれ、武官では上記の2先輩の他、重松毅(東大1943卒)、日高英行(東大1943卒)、石毛長雄(東大1944卒)、旭享(東大1944卒)などの心理の諸先輩が一緒でした。
文官と言うのは、専門職として勤務する「軍属」の人たちですが、それぞれのキャリアで「士官相当官」として胸に階級章をつけていました。適性部の中核を担っていたのは文官の人たちで、トップが高木貫一(東大1925卒)、続いて鶴田正一(東大1933卒)、山根清道(東大1935卒)、相馬紀公(東大1938卒)、遠藤辰雄(東大1939卒)、西堀道雄(東大1941卒)、田中良久(東大1941卒)の諸氏です。
このような陣容からもわかるように、海軍の航空心理に対する気の入れようは決して半端なものではなかったといえましょう。先任部員の高木さんは海軍中佐待遇で、飄々としたお人柄の中に、航空心理学の拠点を預かる重責感を持っておられたと思います。
当時の適性検査は、航空戦の人的資源を確保するという国家目的に照らして、豫科練を中心とする若いパイロットの選抜、養成という重点課題があり、私たちは連日のように心理テストの実施に努めました。
検査の種目はいろいろありましたが、主なものとして知能検査、精神作業検査、技能検査が行われていました。70年以上前のことですから記憶も定かではありませんが、知能検査は民間で行われていた田中B式団体知能検査が用いられていました。また事故防止の目的から、内田・クレペリン精神作業検査が、「海軍航空精神作業検査」と銘打って活用されました。その他「処置判断テスト」などの状況判断の適否をみる検査や、暗夜の計器飛行のシミュレーター、目標に向かって安定操縦をする技能を調べる「地上演習機」などの機器もありました。IT時代の今日から見ればオモチャのようなものでしたが…。
検査データの処理は、地元から微用された「技工士」と呼ばれる人たちが担当していました。また、やはり地元土浦の女学校(女子高校)の生徒が「女子挺身隊」として採用され、集計業務に携わっていました。
海軍兵学校に出張
私が当時のことを想い起こすときに忘れ得ないのは、海軍兵学校のある江田島に出張したことです。江田島は瀬戸内海の呉市の近くにある島で、海軍のエリート教育の牙城でした。海軍兵学校は陸軍士官学校と並んで海軍大学、陸軍大学へ進学するエリート育成の場であり、多くの名将、勇将を生み出してきました。独特の教育システムを持ち、小説や映画の舞台にもなっていました。
私は江田島出張を命じられたとき、とても嬉しく思いました。それは、今まで缶詰のように航空隊の中に閉じ込められていた身が、久し振りに娑婆の中に出て行けるからです。それに数ある適性部員の中から私が選ばれたことも私のプライドを擽(くすぐ)りました。さらにいえば、豫備士官の私が「本職」の軍人相手に検査をすることに、専門職としての責任とやり甲斐を感じたことも与(あずか)っていることと思います。
昭和19年10月、私は日上泰輔大尉の引率の下に同僚の大角欣治部員(関西学院大出身)とともに江田島に赴き海軍兵学校第76期生の適性検査を実施しました。後年、私が大手企業の管理者研修に関わる中で、76期の生徒だった人と邂逅したことも一再ならずありました。
江田島出張にからむ思い出は、プライベートな側面では、私がかねてから親炙(しんしゃ)していた祖父の訃報に接したことや、心理学科の親友の水原泰介君のお世話で、当時既に希少価値になっていたスキヤキのご馳走にあずかったことなどありましたが、今でも記憶に残っているのは私たちの提出した適性の合否判定が海軍当局によって覆されたことです。詳しいことは省きますが、兵学校の検査では我々の心理測定と並行して、手相・骨相による適性判断がさる“名人”によって行われており、彼の判断が優先して採用されたということがありました。海軍という所は合理主義が通用するものと思っていましたが、これも戦争の末期的現象の一つだったのかも知れません。
とにもかくにも江田島出張は、私の胸に広島みかんのように甘酸っぱい印象となって今に残っています。
5.103分隊に配属、土空空襲
分隊士の体験
昭和18年12月に海兵団に入団以来、1年余りの年月を経て、翌年の12月25日、私は漸く海軍少尉になりました。これは学徒動員で海軍に入った人たちの一斉の任官でした。正直、ヤレヤレと思いました。少尉になってみると、やはり行動の自由は広がります。週末は外出できるし生活にゆとりが出てきました。土浦の市内に寛ぐ場所も見つけました。
士官になってからも適性部の部員としての職務は変らなかったのですが、翌年の2月に入ってから第103分隊という特別編成の部隊の「分隊士」(分隊長の下の管理職)として勤めることになりました。この部隊は、簡単に言えば防空壕掘りの作業員の部隊で各地から集められた中高年の人たちです。中には大工さんや洋服職人、工場長をやっていたという人もいました。
その頃は戦況も既に傾き、本土空襲の可能性も現実的になっていましたから、航空隊としても避難対策に迫られていたのでしょう。103分隊の任務は適性部用の防空壕を作ることでした。
そこで適性部員から松平定康大尉が分隊長になり、その下の分隊士に私がなったわけです。同僚には吉田禎吾氏(東大1947卒)、小佐治朝生氏(東大1948卒)等がいました。この103分隊は分隊長の温かい人柄もあってまとまりも良く、軍隊の中のオアシスのような場所でした。適性部とは違って純然たる軍隊組織ですから若い私の部下に社会経験の豊富な年上の人がつくことになるわけですが、人と人との心のつながりは年齢や階級を越えたところに成り立つことを知ったのは、私にとって新鮮な体験で、後年の産業カウンセリングの研究の土台になったような気がします。
103分隊で培われた人脈は終戦後も枯れずに、松平さんや吉田さん、小佐治さんとは仕事の面だけでなく、同じ釜の飯を食った間柄として長く親しい交流が続きました。
土浦航空隊空襲
103分隊のおかげで防空壕も出来ましたが、それから間もなく東京の下町がB29の大編隊による空襲で大きな被害を受けました。昭和20年3月10日夜のことです。その日は土浦から100キロも離れた東京の空が赤く染まって見えました。暗然たる気持ちでそれを眺めていたことを覚えています。続いて4月、5月と東京大空襲が続き、皇居の焼けた5月25日には私の生家も直撃を喰らって灰燼に帰しました。
さらに6月10日、敵の編隊は容赦なく土空を襲い、豫科練の若い生命が多数失われました。私はその時、103分隊の兵士たちと適性部前の防空壕に身を潜めていましたが、大編隊のB29から降ってくる爆弾のザァーッという音や、至近弾が50m先のプールに落ちたときに壕の中が激しく揺れたことをまざまざと覚えています。
空襲の後もグラマンという敵の戦闘機が絶え間なくやってきて、機銃掃射を喰らいましたが、そうした光景もまだ瞼に焼き付いています。
空襲によって航空隊は相当な打撃を受け、私が個人的に懇意にしていた下士官の人が戦死しました。幸い適性部は全員無事だったのですが、戦争の生々しい恐怖を肌で味わい、一段と身の引き締まる思いでした。
6.海軍航空要員研究所に転任。そして終戦
海軍航空要員研究所
空襲の後間もなく、私は適性部から研究所に配置替えになりました。103分隊も使命を終えて解散になり、分隊長も分隊士も皆研究所に集められました。
研究所は土空本隊の近くの丘の上にある見晴らしの良い所にあって、航空心理学研究棟と航空医学研究棟の二棟がありました。
海軍の心理学関係の研究所は通称“技研”といわれていたところと土浦の航空要員研究所の二ヶ所があり、技研(技術研究所)には兼子宙氏(東大1931卒)をトップに、肥田野直氏(東大1943卒)や末永俊郎氏(東大1943卒)、池内一氏(東大1944卒)等がいました。
私が所属した航空要員研究所のスタッフは先任所員(所長)高木貫一(以下敬称略)、研究員(所員)に鶴田正一、山根清道、相馬紀公、遠藤辰雄、田中良久、日上泰輔、松平定康、小瀬輝、小林達三、重松毅、日高英行、平野直人、小林亮太、石川英夫、平井隆太郎、吉田禎吾、瀬谷正敏、宮川知彰、糸川民生、その他数名の諸氏です。
こうして研究員の名前を挙げてみると、わが国の心理学者の錚々たるメンバーが名を連ねており、国家総力戦が背景にあったとはいえ、日本の心理学史上に特筆すべき組織だったのではないかと思われます。
さて私自身は、研究班が6つある中の「教育研究班」に入りました。ここは予科練など若い人たちの教育を心理学的に研究するという主旨のグループで、私は宿願の研究課題に打ち込めるという希望に胸を膨らませましたが、その頃は空襲の打撃が消えず、士気も上がらずに徒らな時が経過したように記憶しています。そしてとうとう8月15日がやってきました。
玉音放送
その日はジリジリするような真夏の太陽が照りつけていました。私たち研究所の所員一同は前庭に整列して「重要放送」を聞きました。陛下のお声は雑音が交じって聞きづらいところもありましたが内容は大体理解できました。「敗戦!?」うすうす感じていたとはいえ、ショックがじわじわと広がって行きました。高木先任の、拳で眼を拭っている姿が目に焼きつきました。
その時の名状し難い胸の内は、70年経った今日でもリアルに浮かんできます。魂の抜けたような虚脱感が全員を掩い、暫くは時間が止まったような感覚でした。放送のあと、一時は不穏な情報も耳にしましたが、土空全体は粛然と行動し、私たちは旬日のうちに除隊・復員となりました。私は青春の一時期を燃焼した思い出の航空隊をあとに、家族が疎開している千葉県に帰省しました。そしてその年の10月に、再び大学に戻りました。
7.復学から卒業まで
終戦直後の学生生活
復学してみると、母校の東京大学のキャンパスは無事に残っていましたが、そこに集まってきた人たちの姿は、戦争の影を背負っていました。帰ってきた学徒兵たちは軍服を脱いだ筈ですが、着るべき金ボタンの学生服も無く、階級章を剥ぎ取った陸海軍の哀れな軍服がキャンパスのあちこちで見られました。教授の先生方もご苦労は同じで、哲学のさる有名な教授が、ツンツルテンのズボンをはき、冷飯草履で教室に入ってこられたことなど、懐かしい思い出です。
私の記憶では学生食堂も開いていましたが、まともな食事とてなく、海藻のようなものを主食にしたり、ご飯の上に怪しげなソースをふりかけただけの“ソーライス”と称するものを食べていた時代でした。また弁当にはよくふかし芋を持っていきましたが、三四郎の池の辺りで友人と食べたことも再三ありました。
しかし、そうした貧しい生活の中にも、戦後の新しい時代を生きていこうとする気概のようなものが、復学してきた学生たちに共通してあったように思います。
私は海軍の103分隊で一緒だった吉田禎吾君と気が合い、起居を共にしながら文学部の講義を聞いて廻りました。精神的な飢餓を癒すべく、辰野隆先生(仏文)や、和辻哲郎先生(倫理)の教室に通い、熱心にノートを取りました。その時のノートは今も大切に保存しています。
今にして思えばほゝ笑ましい思い出ですが、同世代の仲間たちが集まり、ドブロクを汲み交わしながら盛んに放談していたのは終戦後2〜3年の頃でしょうか。特攻隊にいて出陣の寸前に終戦になり、九死に一生を得た土空以来の友人や、空襲時高射砲隊の隊長をしていた高校時代からの友人などと一緒によく集っていました。その席に仏文学で高名な渡辺一夫先生も時折みえていて、何を話したかはすっかり忘れましたが、非常に楽しかった記憶が残っています。これも軍隊の抑圧から解放された青春謳歌の一コマだったのでしょう。
卒業論文の作成
大学に戻ってから一年が経ち、卒業論文に取り組む時期になりました。その頃はまだ戦後の復興も始まったばかりで、生活基盤も定まらず、何か一つの課題に集中するゆとりは、生活的にも心理的にもありませんでしたが、私は卒論作成に私なりの努力をしました。指導教官は千輪浩先生でしたが、私は少々ヘソ曲りだったのでしょう、当時の研究室の主流だった知覚研究のテーマを選ばずに、敢えて教育心理学的な課題を選びました。タイトルは「怠惰児の実験的研究」です。今から考えると、まことにお粗末でお恥ずかしい内容ですが、私の中には学習困難児への関心があって、近年注目されている発達障害児の問題につながる意味もあり、もっと本腰を入れて研究すればよかったと反省しています。
卒論を提出して、私は吉田禎吾、先崎正次郎、中村陽吉等の諸兄とともに昭和22年9月に卒業しました。入学以来、戦争をはさんで5年経つわけですが、心理学科の学生生活は多くの友人・知己を得て、それからの社会活動の土台になったと思っています。
私は卒業後旧制の大学院に籍を置く一方で、生活上の必要から教職につき、海軍の豫科練習生に相当する年齢の人たちに向き合っていました。20代前半という多感な時期にめぐりあった水兵、海軍士官、教師という社会経験は、私の人間形成に深く刻み込まれたように思います。
8.カウンセリングとの出会い
SPS研修会
私は大学に勤めるようになって、児童心理学や青年心理学を講じながら、戦前とは異なる新しい教育制度の下での学生指導に関心を向けていました。
丁度その頃、文部省(現文部科学省)のバックアップでアメリカから数名の講師団が来日し、「学徒厚生補導研修会」(Student Personnel Services S・P・S)という名のもとに、約1年間に及ぶワークショップが開かれました。九州大学を皮切りに、京都大学、東京大学で3ヶ月ずつ行われたのです。私は真夏のさ中に冷房の無い(当時は専ら扇風機でした)東大の図書館に毎日のように通いました。昭和27年のことです。
セミナーの内容は学生指導に関するいろいろなアプローチの紹介で、アメリカで行われている方式を伝授するというものでした。セミナーの途中でアンケートが行われましたが、参加者の関心が最も高かったテーマが「カウンセリング」でした。回想すれば、私とカウンセリングとの出会いは、このセミナーに始まるといえましょう。
その後。SPS研修会のフォローアップの意味もあって、昭和30年に「SPS特別研修会」が矢張り東大で開催されました。これはまさにカウンセリング研修会でした。講師はF.P.Robinson、E.Bordinの2人で、両先生とも一流の学者です。私は当時の勤務校の横浜国立大学から同僚の伊東博氏とともに大きな期待をもって参加しました。
この特別研修会に参加した心理学者には東洋氏(東京大学)、三隅二不二氏(九州大学)など後年心理学界をリードされた方や、私の先輩の松村康平氏(お茶の水女子大学)がおられ、レベルの高いものでした。私はこの研修会のあと数名の人たちと語らって、「相談心理学」という本を編集しました。(沢田慶輔編 朝倉書店刊 1957)。また、同志を糾合して「学生相談研究会」を立ち上げ、毎月集まって研究討議を行いました。
私の中では、SPSへの参加を契機としてカウンセリングへの思いが強くなり、自らの研究と実践の方向性をそこに定めたのです。
学生相談室を開く
SPS研修会に横浜国大から参加した伊東氏と私は、学生相談の実践の場としてキャンパス内に学生相談室をつくる計画を立てました。しかし大学の教授会の理解が得られず、その実現には苦労しました。昭和30年の当時は、カウンセリングという言葉も殆んどの人が知らず、「学生は一人前で大学がお節介を焼く必要はない」という考え方が教授たちの頭を支配していましたから、どこの大学でも相談室の設置には少なからず抵抗があったと思います。
しかし、昭和28年には東京大学に学生相談所が設けられ、続いて大手の国公私立大学にも相談室が出来てきて、私たちもその流れの中でカウンセリングを行うようになりました。
相談室といっても、当初は宿直室の古自転車が置いてある土間に、粗末な机と椅子を置いただけの素朴なものでしたが、漸次設備もよくなり、相談活動も軌道に乗ってきました。
私は試行錯誤の中でカウンセラーとしてのスキルを磨きつつ、この活動がわが国の青少年の成長発達にとって不可欠のものであることを確信していました。
産業カウンセリングとグループダイナミックス
我が国で学生相談活動がまだ緒についた頃、産業界にもアメリカのホーソン実験やNTL(National Training Laboratory)の成果が伝えられ、人間関係やリーダーシップの重要性について関心が高まってきていました。
私は学生相談で学んだカウンセリングの理論と方法を、企業組織の中でも活せないかと考えていたので、職業指導の分野で活躍されていた藤本喜八氏(立教大学)や、海軍時代からご縁のあった相馬紀公氏(国鉄・現JR)や、NTTの前身である電々公社のカウンセラーをしていた福山政一氏らと共に、産業組織の中にカウンセリングを根付かせるべく昭和36年に日本産業カウンセラー協会を立ち上げました。それまでは産業人事相談として企業の片隅で生活福祉的な活動に留まっていたのですが、1960年代の高度経済成長の波に乗って我が国の産業カウンセリングが開花して行きました。
学生相談や産業カウンセリングが社会の一隅で産声をあげる頃、K.レヴィンによって開発されたグループダイナミックスがわが国にも波及してきました。私はレヴィンの理論は大学で学び、その考え方に共鳴していましたので、グループの研究に大いに刺激されました。丁度畏友の水原泰介君が社会心理学をやっていて、NTLで行われたレヴィンの研究を日本でも試みようというので、数名の仲間と一緒に、区の教育委員会や企業の人事部の協力を得て実験グループをつくり、集団発達とリーダーシップの研究を3年ほどやりました。協力してくれた会社の人事部長から、日本のホーソン研究にしようなどと持ち上げられたりしましたが、長続きしなかったのは残念でした。
グループダイナミックスの研究は、SPSで一緒に学んだ九州大学の三隅二不二さんが中心になり、研究会や学会をつくったことはよく知られていますが、私たちの研究はパワー不足でした。
しかしその後しばらくして、海軍時代の仲間だった池内一氏(東大新聞研究所教授)の研究プロジェクト「社会的葛藤解決の研究」に水原泰介君らと共に参加し、私が中心となって大規模なロールプレイングを行い、集団間葛藤のシミュレーションをやったことは今でも記憶に残っています。
グループダイナミックスの日本への導入には、別の大きな流れとしてJICE(立教大学キリスト教教育研究所)の活動があります。この流れは現在も南山大学を中心に続いていますが、私がこの「ラボラトリー・トレーニング」と称する合宿セミナーに参加した頃(1969)から産業界でも注目しだして、「Tグループ」、「ST(Sensitivity Training)」として全国的に広がって行きました。また殆ど時を同じくしてロジャーズのエンカウンターグループ(EG)も伝えられ、小グループの体験学習方式は人間関係トレーニングの方法として次第に日本の社会に定着し、今に至っています。
私はカウンセリングもグループダイナミックスも、それが日本に入ってくる時期に居合わせていたわけですが、その理論と方法の中に自らの居場所を求めていろいろと動き廻っていたのだと、今になってみると判るような気がします。
9.私の研究活動
研究活動の軌跡
私は心理学を学び、心理学の分野で仕事をしてきましたが、心理学者としての研究実績を問われると、あれこれ手を出していて、まとまった業績としてお話しするものがないのですが、高齢になって来し方を振り返ってみると、自分なりの足取りが見えてくるように思います。そしてその軌跡を辿ると、自分が心理学を志した原点が浮かんできます。私は前にも述べたように、思春期の頃心身が不安定な中で、自分自身の存在を確かめるために、心理学に拠り所を求めました。自分は誰か、人間とは何かという根源的な問いは、成長期にある者の普遍的なテーマであると思いますが、私はそれを観念の世界にではなく、日常の営みの中に答えを求めて、心理学者としての研究と実践を重ねてきました。
これらの活動を心理学の分野別に見ると、①教育心理学・発達心理学の領域、②産業組織心理学の領域、③社会教育・生涯学習の領域、④家族心理学の領域の4つの分野に亘っています。そしてそれぞれの領域における研究と実践をつなぐ横糸がカウンセリングであり、グループダイナミックスであるといえるでしょう。別のいい方をすれば、私は心理臨床の土台に立って、学校、産業、社会、家族の心理学的な課題に、実践的な切り口で取り組んできたというわけです。
教育心理、学生相談の研究
私の研究活動の流れを時系列的に見て行くと、昭和20年代の研究は教育心理、乃至発達心理の問題を取り上げました。これは勤めていた横浜国立大学で児童心理の講義を担当していたことも背景にあるでしょう。学会や研究誌で親子関係、きょうだい関係の実験的な研究を発表しました。しかし当時は整った施設もなかったので、共同研究者の石井哲夫さん(1950東大卒)のいた社会事業大学に仮設の観察室をつくってやっていました。
何かと乏しい時代でしたが研究意欲は旺んで、研究の楽しさ、醍醐味というものを自分なりに味わったような気がしていました。敗戦後の焼野原の東京に復興の槌音が響き、私も千葉の疎開先から東京に移ってきました。個人的なことですが、結婚し新居も構えて、落着いた中に研究環境も次第に整ってきたのが昭和30年以降のことです。
その頃大学に学生相談室を開いて学生相談に乗り出したことは前に述べましたが、数年経って各大学で相談室を持つところが増えてきたので、私は肥田野直氏(1943東大卒)らと一緒に学生相談活動の実態調査を行いました。また同じ頃、創刊間もない「心理学評論」に「学校カウンセリングの問題点」という論文を載せましたが、私はカウンセリングの実践を通して相談室の運営面にも関心が強かったのだと思います。
昭和30年代は、31年にE.G.Williamsonが、36年にC.R.Rogersが来日し、それぞれ大きな足跡を残していきましたが、学生相談の研究でも、その方法論をめぐって指示的か、非指示的か、折衷的かという論争が盛んに行われた時代でした。
産業カウンセラー養成、職場の人間関係の研究
丁度その頃に、前にも述べたように産業界で職場のリーダーシップや人間関係のあり方が注目されだしてきて、私の研究と実践は次第に教育の分野から産業組織の方にシフトして行きました。
昭和39年度から労働省(現厚生労働省)婦人少年局が産業カウンセリング普及導入事業を始め、それに協力する形で産業カウンセリングの実施状況の全国調査を行いました。そして盟友の伊東博氏らと共著で「カウンセリングを職場に生かそう―産業カウンセリング手引き―」を執筆しました。
私は企業内にカウンセリング制度を定着させるためにはカウンセラーの質的向上が大切だと考え、既に活動している社団法人日本産業カウンセラー協会で、産業カウンセラーの資格認定の仕事に関わり、試験委員会の委員長として8年間勤めました。
社会にカウンセリングを根づかせるために、カウンセラーの専門性を高めることに腐心する一方において、私は「職場のカウンセリング」という本を書いて組織内の人間関係にカウンセリングの考え方や技術を役立たせるように努めました。私のこうした問題意識の中で行った実践的研究として「ロールプレイング」があります。ここでその詳細を語ることはできませんが、私の行ったロールプレイは、サイコドラマの理論と方法を取り入れながら、職場の人間関係の改善につながる体験学習としてプログラムしたものです。
私は、私の考えに理解を示したF社で、第一線監督者の研修にこれを用いて相応の手応えを得ましたので、わが国の基幹産業のS社、K社をはじめ各種メーカー、金融機関、官公庁、大学・研究所等々で、カウンセリングとロールプレイの普及と活用につとめました。それに私の生き甲斐を注ぎ込んだといっても過言ではないと思っています。
カウンセリングの諸理論と技法は、専門の心理臨床家だけでなく、社会生活の中で、一般の人たちにも使えるものですが、それを「生兵法は大怪我のもと」にならないように、日常的な活用法、具体的な応用力を身につけることが求められると思います。
私の研究は、K.レヴィンがいうように、研究と実践を車の両輪として、研究も実践もより洗練されたものに進化することを目指しました。しかし、今ふり返ってみると、当時の社会状況に流されて、研究よりも実践にエネルギーをより多く費やしたように思います。その頃の実践的研究は方法論も不確かでしたが、もっと腰を据えて「研究」に取り組むべきだったと反省しています。
家族カウンセリングの研究
私が家族の心理支援に踏み出したいきさつについてお話ししますと、1981年に行われた日本心理学会の第45回大会がその発端になりました。その頃、家族をめぐる事件が相次いでマスコミを賑わし、テレビドラマでも家族の問題が屢々取り上げられていました。家族療法はアメリカでも既に大きな流れになっており、わが国でも精神医学や社会学の人たちの間で関心が持たれていました。心理学者の中でも、岡堂哲雄氏、国谷誠朗氏、平木典子氏と私の4人が集まって、「家族心理学」の開発を話しあいました。
そうした雰囲気の中で日本心理学会の大会が日本女子大学の主催で開かれ、私がその準備委員長を務めることになりました。 数ある企画のひとつに「家族臨床心理の現状と展望」というタイトルのシンポジウムが行われ、多数の参加者があってこの分野の研究開発に弾みがついたというわけです。
その後1984年に「日本家族心理学会」、ついで1985年に「日本家族カウンセリング協会」が設立され、私は学会の運営に関わる一方で協会の責任者として「家族相談士」(家族心理臨床の専門職)の養成と資格認定に当たってきました。私が家族の心理支援に意欲を持った背景には、グループダイナミックスの研究と実践に関わってきた経験から、人と人との関係性のダイナミズムに、心理学者としてのつきせぬ興味を感じたことと、それと相俟って、社会生活の基盤であり人間成長の基地でもある家庭・家族に巣くう病理を探り、その予防への手掛かりを得たいと言う意志が働いていたと思っています。
その意味から私の研究的な関心は「家族ロールプレイ」の開発に向けられました。試行錯誤を重ねながら現在も開発途上にありますが、職場の人間関係の研修に用いたロールプレイングのキャリアを活かして家族支援の実をあげたいと願っています。
10.私の社会活動
学会・協会の設立
繰り返し申しますように、私は戦後の復興期に社会人として歩み始めた年回りなので、わが国の心理学の発展とともに年を重ねてきたわけです。そういう廻り合わせから、心理学諸学会の設立準備や創立に立ち会ったり、関わったりする機会が少なからずありました。翻って考えてみると、そういう機会を捉えたり、そこに身を置くということは、私自身の中に何か新しいものを形づくって行くことに興味関心を抱く「ものづくり」的な志向性が潜んでいたのかもしれません。
時系列的に見ると、最初に研究団体をつくる事に関わったのは「学生相談研究会」の結成で、これは1955年頃のことです。前述のSPSワークショップのあと間もなくのことでした。この研究会は後年「日本学生相談学会」として発展して行きます。
次いで1961年に、日本応用心理学会の中の組織として「相談部会」をつくることを先輩の松村康平さんが提唱され、私もその設立を手伝いました。当時はカウンセリングを「相談」と言い換えていましたが、日本にも相談という仕事を心理学的に研究する場ができることに、小さな希望の灯をともしたつもりでした。
それから数年経ち、1967年にようやく「日本相談学会」が一本立ちします。私も仕掛け人の一人として創立総会に立ち合いましたが、その時の写真が「カウンセリング研究vol.26 No.1 1993」に載っています。この学会は、1987年に名称を「日本カウンセリング学会」と変えていきます。その頃になってカウンセリングの語が日本の社会に定着してきたと言うことでしょう。
20世紀の後半になると、心理療法に関する諸学説が、やや大仰な言い方をすると、雨後の筍の如くわが国に伝えられ始めました。その中の一つの「交流分析」は、池見酉次郎氏(九州大学教授)によって導入されたもので、その体系化された理論が関心を集め、1976年に「日本交流分析学会」が設立されました。この学会は池見先生を中心にして心療内科の専門医の人たちが主な構成員でしたが、私は心理畑から国谷誠朗さん、深沢道子さん等と共に学会設立に参加しました。
1980年代になると、心理学系の専門学会が相次いで産声を上げています。その中で私が発起人として関係したのは、「日本人間性心理学会」(1982年)、「日本家族心理学会」(1984年)、「産業組織心理学会」(1985年)、「日本健康心理学会」(1986年)です。こうした流れは、わが国の心理学の幅広い発展を示す道標であると同時に、当時の心理学者たちの盛んな意欲の表れであるともいえましょう。
20世紀末の学会ラッシュの中で、医療系の学会と心理系の学会のコラボレーションを企画した「日本心理医療諸学会連合(UPM)」の結成(1988年)は、心理学の歴史の1ページを飾るモニュメントではないかと思います。この組織(略称心医連)は、医学と心理学の連繫を強調された池見酉次郎先生のリーダーシップの下に成立を見たのですが、私も心理学の諸学会に関与していた立場からその趣旨に賛同し、有力な心理学者と共にその立ち上げに協力しました。
時代はさらに移って昭和から平成に変わり、バブル崩壊後の不安定な時代に入って行きますが、1996年、私は松原達哉氏、楡木満生氏、木村周氏らの同志と共に、「日本産業カウンセリング学会」の創立を実現し、初代会長に就任しました。それぞれの学会が生まれるまでにはいろいろな経緯があり、安産も難産もあるでしょうが、そこに人と人とをつなぐ横糸としての"志"が大切であることを改めて感じています。
心理学の専門学会の設立に与ると共に、私はカウンセリング関係の「協会」をつくることにも積極的に関わりました。学会は学術研究団体としての性格を軸に成り立っていますが、協会はより緩やかな集まりで、職能団体的な意味もあり、社会活動を行う上で学会とは異なった機能を持っていると思います。私はわが国にカウンセリングを普及発展させていくために、協会という組織の役割もあるのではないかと考えて、その創設と運営にエネルギーをつかいました。
その一つは「日本産業カウンセラー協会」です。この協会のことは前にも触れましたが1961年の設立以来紆余曲折を経て、1990年に元労働事務次官の藤縄正勝氏を会長に迎えてから産業カウンセラーの資格が労働大臣認定の公的資格となり、活性化してきました。私は同氏の依頼で協会の試験委員長を引き受け8年間勤めました。その頃かかわりのあった人たちは殆どが故人となりましたが、創成期の苦労を分かちあったことなど思い出はつきません。
もう一つは「日本交流分析協会」で、これは1976年にできた日本交流分析学会と同時にスタートし、私が初代会長を引き受けて約10年余り勤めました。さらに、1985年には前年に創立された日本家族心理学会の活動の一翼を担う形で、「日本家族カウンセリング協会」を立ち上げました。そして初代会長を勤めていましたが途中でNPO法人となったので、引きつづき理事長職に就いて今日に至っています。
学会の年次大会を主催する
上述の学会は毎年年次大会を開いていますが、私は創立に関わった立場から、大会の運営に主催責任者として連なることが度々ありました。そのリストを揚げると次の通りです。
・日本相談学会第10回大会(1977)
・日本心理学会第45回大会(1981)
・日本家族心理学会第1回大会(1984)
・日本交流分析学会第10回大会(1985)
・日本人間性心理学会第4回大会(1985)
・第27回全国学生相談研修会(1988)
この中でも忘れられないのは日本心理学会の大会です。当時私は日本女子大学の教授をしていましたが、学会から主催校の打診があったとき、これは大役なので準備委のチームワークがとても大切だと思い、心理学関係の先生方と話しあいました。同じ学内でも所属の学部学科が異なると、普段顔を合わせる機会もなく、コミュニケーションは円滑ではなかったのですが、大会開催を機に結束が高まり、大会を引受けた副次的な効果となりました。
プログラムの中でも特に印象が深いのは、大会最終日に会場の国立教育会館の虎ノ門ホールで、「心理学を問い直す――現代の状況と人間研究――」と題するパネルディスカッションを催し(メンバーは林知己夫、河合隼雄、南博、山本七平、司会・本明寛の諸氏)、大ホールに千数百名の参加者があったことです。当日、心理学の大先輩の結城錦一先生からお賞めに与ったことも忘れ得ぬ思い出です。
生涯学習への寄与
心理学に関する私の仕事は以上のような流れですが、かかわった社会活動の中でかなり多くの時間を社会教育・生涯学習に費やしたので、このことに言及しておきたいと思います。
1974年、朝日新聞社が文化事業の一環として、当時はまだ珍しかった超高層ビル(新宿住友ビル)の48階で、生涯学習の研修センター(朝日カルチャーセンター)を開くことになり、教養講座の一つに「カウンセリング講座」を入れたいということで私に依頼がありました。
私はカウンセリングの普及啓蒙に社会的な意義を認めていたので、ふたつ返事で引き受け、以来40年間に亘って講座の主任講師を勤めてきました。前半の十数年は平木典子氏
(日本女子大)、その後は村瀬旻氏(慶応義塾大)、小山田治子氏(CHR研究所)と共同で担当しました。受講生は延べ数千人になると思いますが、その中から臨床心理士や専門の学者、研究者も相当数育っています。また、受講生が集まってNPOを立ち上げているケースもいくつかあり、一つの時代の中で、社会教育の一端を担っていたとすれば大変うれしいことです。
それから、今一つは時代が大分逆るのですが、NHKの教育テレビの「大学講座」で足かけ3年間「心理学」を担当しました(1970,1971,1973)。タイトルは「人間関係の心理」でしたが、内容は対人認知やグループダイナミックスに関するものでした。この講座は比較的地味なものでしたが、視聴者が全国で7万人もあり、毎回の準備にかなり努力したことを覚えています。
おわりに
以上が心理学者としての私の半生のダイジェストです。果たして「オーラルヒストリー」の趣旨に適った話になったかどうか疑問ですが、私にとっては、人生を振り返る良い機会を与えていただいたと思っております。話しのおわりに、インタビューの中から補足的な話を2、3拾って、質疑応答形式で述べておきます。
――― 先生のお名前は珍しい読み方ですが、その由来をお聞かせください。
私の名前は「一言」と書いて「きよとき」と読みます。これは辞書にもない発音ですからよく人に尋ねられます。
名付け親は私の祖父ですが、「言」を「とき」と読むのは、遠く平安時代からの命名の習わしで、私の先祖は代々男子に言の字がつけられていました。私は祖父にとっては初孫で、長男だったので一郎とか一夫とか名付けるところですが、しきたりで「一言」ということになったわけです。
「一」を「きよ」と読ませるのは、私が祖父から直接聞いたところでは、中国古典の「老子」第39章に「天、一を得て以って清し。地、一を得て以って寧(やす)し。…」という言葉があり、そこから取って命名したということです。
老子の思想の解釈はいろいろあるようですが、私は単純に「一」はものごとのはじめだから汚れてなく清いのだ、その意味をとって「きよ」と読むのだと解しています。
「きよとき」と言う読み方はともかくとして、私は「一言」という名前にこだわって生きてきました。世間では、何事にもひとこと意見を言わないと気がすまない人のことを「一言居士」といいますが、私はむしろひとこと足りない方で、大切な一言を疎かにしないよう常々心がけています。
その一言によって人生が大きく左右されたと言う話もよく聞きますが、私もカウンセラーのひとりとして、自分の名前に恥じないよう言葉を大切にしたいと願っています。
――― 先生は93歳と伺っていますが、まだお元気ですね。何か健康法のようなものがあるのでしょうか。
いや、特別なことをやっているわけではありませんが…、私はお話ししたように若い頃は健康に自信がなく、とても長生きできないと思っていました。しかし友人たちが次々と亡くなっていく中で自分が今だに健康を保っているのは、一つには健康管理に気を使っているからでしょう。矢張りモノでも人間でも長持ちさせるにはメンテナンスが大切ですね。
具体的には、極く当たり前のことですが、食事、運動、睡眠に留意して、できるだけ規則的な生活習慣を維持するように心掛けています。ハラ8分目の食事、ウォーキング、安眠が毎日の課題です。それと年齢に見合ったバランスの良い生活設計が必要でしょう。
しかし健康法は人によっていろいろで、それぞれの流儀があっていい。自分の体の声を聴いて自己流の健康法を実践することが長寿の秘訣ではないでしょうか。
もう一つ大事なことは、自分の健康は自分ひとりで保っているわけではないということです。人間は誰でも人と人とのかかわり、つながりの中で生き、生かされています。
日常の人間関係の中にこそ、いきいきと生きるカギがあると考えると、これは心理学の大きなテーマになってきますね。
―――先生は心理学者として、戦前・戦中・戦後の激動の時代を生きぬいて来られたわけですが、93歳というご高齢のいま、ふり返ってどんな感想をお持ちでしょうか。
そうですね。いろんなことがありましたね。でも今から思うと、私が心理学を学んできたのは、私にとって大正解だったと思っています。私は前に話した通り、体も心もタフではなかったのですが、心理学の世界に身を置いてきて、私なりに自分を生かすことが出来たのではないかと思っています。戦争中も心理学のおかげで命をつなげられたし、戦後も心理学者としての仕事に生き甲斐を見出してきましたから。
しかし、改めてふり返ってみると、まだ自分の中の可能性は燻(くすぶ)っている部分もあり、生きる限り心理学の道を歩んで行きたいと願っています。
――― まだ十分ヤル気をお持ちのようですね。心理学者の先輩として、若い人たちに何かアドバイスを頂けませんか。
そうですね。エラそうなことを言うつもりはありませんが、半生を振り返ってみて感じたことを率直に申し上げると、第一に基本のキが大切ということでしょうか。世の中がますます多様化複雑化し、情報も氾濫しているので、つい目移りしがちですが、基礎とか土台とかが大切なことはいつの世でも同じでしょう。私は心理学科に入って一般実験をやりましたが、そこで学んだことは方法論としてよりも、心理学的な目を養う上で大変勉強になりました。 専攻の分野の中で何が基本かということはいろいろ論議があると思いますが、まずは基本をしっかり学び、身につけることですね。
自分の中に研究の土台を築くことと相俟って大切なもう一つの視点は、人とのつながり、連携ということです。改めて自分の歩んできた道を振り返ってみると、私の人生は関係性の中で紡いできたように思えます。人と人との支えあいの中に、限りない可能性が潜んでいると私は信じています。これは社会や文化の交流についてもいえることでしょう。
心理学の人たちは――私も含めてですが――おしなべてキメの細かいセンスを持っているといえるのではないでしょうか。これは長所ではあるけれども、他方でスケールを狭めてしまう恐れがないでしょうか。異質の関わりの中から新しいものを見出し、作り出していく前向きのエネルギーを、若さの中に求めたいですね。
現代は歴史の過度期であるとか、転換期であるとかいわれています。先の見えない不安は誰しもが抱えています。だからこそ混迷の時代を生き抜く知恵と行動力を、これからの心理学者に期待したいと思っています。
『わたしの半生 ―戦前・戦中・戦後を生きた心理学者の回想録―』は、財団法人日本心理学会の教育研究委員会資料保存小委員会によるインタビューの記録に基づいて、杉溪一言先生が執筆されたものです。インタビューは2015年8月23日(日)に吉祥寺の杉溪先生のご自宅で行われました。インタビューを行ったのは、鈴木朋子(横浜国立大学)、高砂美樹(東京国際大学)、小泉晋一(共栄大学)の3人です。インタビューを承諾していただき、また本稿を執筆していただいた杉溪先生に心から感謝を申し上げます。
2016年2月9日
インタビュー主担当 小泉晋一
心理学との出会い
私は大正11年の生まれで、戦前の教育制度の中で思春期・青年期を過しました。当時は中学が5年で、高校の3年間は17才〜19才の多感な年頃でした。
旧制の高等学校には、中学校にはない第2外国語(ドイツ語、フランス語)や、哲学、倫理、心理といった教養課目があり、何か少しエラくなったような気分でしたが、私はその中でも心理学に興味を持ちました。担当の先生は豊川昇という人で哲学が専門でしたが、当時ドイツから入ってきたゲシュタルト心理学のテキスト(小保内虎夫『心理学概要』)を使っていました。私はこの先生と親しくなりお宅にも伺ったりしましたが、後年、私が心理学の道を選んだのは、直接的には高校時代の心理学との出会いが端緒になったように思います。
人格主義、理想主義への傾倒
旧制高校にもそれぞれの気風の違いはありましたが、おしなべて若者の自由を謳歌する空気が学園を包んでいました。当時の日本は満州事変、支那事変と外地での戦乱が続き、次第に国際的な緊張も高まり、軍国主義的な風潮が広がってきていましたが、大正デモクラシーの余韻の中で成長してきた私たちは、自分らしく生きようという人生観、よく生きるとは何かを問いつづける価値観をめぐって、友人たちと口角泡を飛ばしてディスカッションをしていました。
思い返してみると、そうした時代背景の中で、迫り来るミリタリズムのプレッシャーが逆に若者の悩みを育んだと言う側面もありますが、私にとっては、青年期の人間形成過程に、仲間たちと「人間研究」に打ち込んだ経験はとても貴重なものだったと思います。そしてそのことが、後年の心理学者としてのアイデンティティの確立の一助になったと思っています。
ディスカッションの中で私たちの考え方にインパクトを与えたのは、東大経済学部教授・河合栄治郎の『学生に与う』と言う一冊の本でした(1940年出版)。彼は理想主義、自由主義の思想に基く社会評論活動を、敵対勢力からの圧迫に耐えながら怯まずに展開し、信念を貫き通した気骨の人として名を残しています。
河合の説くところを簡単に述べることは出来ませんが、彼は同書の中で「教師は何よりも教育者でなければならない。彼は自らが苦しみ悩んで人生を生きたものでなければならない」。「“教養”とは、有閑人の安易な閑事業ではなく、雄々しいがしかし惨(いた)ましい人生の戦いである」。「教育の本来の目的は人間各自に本来具わっている真・善・美の三つの価値をすべて引き出すことであり、人間を彼自身たらしむることである」などと述べています。また理想的な学生像とは、「自己の感情や欲望に流されることなく、どこまでも他者の立場を考慮しながら思慮深く行動し、その行動に十分責任を持つことのできる自律した人間である」といっています。
私は改めて振り返ってみると、心理学を志す一歩手前のところで、高校時代の自分探しにもがく姿が垣間見られ、何か懐かしくもあり、ほゝ笑ましいような気がします。
生き方のモデルになった祖父、杉溪六橋
私が大学で心理学を専攻しようとした動機づけには、祖父の存在が大きかったと思います。といっても、祖父は心理学とは全く無縁の人なのですが私はいわば祖父の生き方をモデルとして心理学の道に進み、その後の人生を歩んできたように思います。そこで少し私の祖父のことをお話しましょう。
私の家のルーツは京都の公家(くげ)で、祖父は公家の家の三男として慶応元年(1865)に生まれました。一時は奈良の寺に遣られましたが、まもなく明治維新となり、動乱の中、青年期を京都で過ごしました。その後時勢を見て東京に出てくるのですが、帝国議会(国会)の開設とともに最年少の貴族院議員になったそうです。また、国政に参与する傍ら少年期から学んできた漢詩や書画に親しみ、政界を退いて隠居してからは専ら「文人」として芸術的な活動をしていました。文人と言うのは武人に対する言葉で、詩文や書画など風雅を嗜む風流人を意味しています。
祖父・杉溪言長(ときなが)は六橋(りっきょう)と号し、世に「三絶」(漢詩・書道・南画に秀でた人)と称され、独自の世界を拓いた人として一定の評価を受けましたが、私自身は若輩でそのような脱俗の世界など全く解りませんでした。
そんな私が祖父をロール・モデルにしたのは、激しい変革の時代にあって、自らの資質を生かし努力を重ね、独自の世界を構築した志の強さに学びたいと思ったからです。私は幼い頃から生活の中で祖父の謦咳(けいがい)に接し、その人格と生き方に触れたことが、心理学を志す上で潜在的な力になったように感じています。
高校時代の先輩の影響
私の学んだ旧制の高等学校は学習院高等科ですが、学習院から東大の心理学科に進んだ先輩が3人いました。その中の一人は私が入学したときに研究室の副手をやっていた松村康平氏(1941年3月卒)です。松村さんは外林大作氏と並んで我国に心理劇を導入した人ですが、私の大学入学に際して頂いた助言は今でもよく覚えています。松村さんの天才的な言説には、とてもついて行けないところもありましたが、後年ワークショップなどでご一緒になり、個人的にも親しくして頂きいろいろとお世話になりました。
もう一人の先輩は松平定康氏(1941年12月卒)です。松平さんとのご縁はとても深いのですが、私が心理学科を志望した頃、彼は海軍予備学生から任官して少尉になり、海軍で航空心理の研究をしていました。私は学習院在学中から部活動などでご一緒でしたので、身近な先輩の軍服姿を見て、心理学の研究が国家目的につながることに心を動かされました。その当時はまだハッキリした道筋は見えていなかったのですが、先輩が私の進む道の前を歩いているように思えて、心強く感じたことを覚えています。
2. 東京帝国大学(現東京大学)で心理学を学ぶ
心理学科に入学して
私が入学したのは1943年9月ですが、同期生は20名余りいたと思います。しかし学徒動員などがあって卒業はばらばらになりました。大学に入ってみてまず感じたのは、心理学科の仲間たちが総じて真面目そうなおとなしい感じで、高校時代にいた暴れん坊や異色の人物は見当たりませんでした。私自身もハメを外す方ではなかったので、何となく同質の集団という印象でした。(その後のつきあいの中で、互いの個性がわかってきましたが)。
その頃のカリキュラムには「教練」という軍事科目があり、週一回グランドで銃劍術などの訓練がありました。また、富士山麓にあった陸軍の厰舎で、一週間程の野外教練が行われました。これは文学部の各学科でまとまって合宿するのですが、心理学科の隣に社会学科の学生が来て、それぞれの空気が大変違うので、改めて心理学の連中のキメ細かな肌合いのようなものを感じました。
短い期間でしたが応召までの一年間に私は大切な仲間と出会いました。水原泰介、先崎正次郎、亀井一綱、森岡寿夫、高月東一、森重敏などの諸兄です。これらの友人とは卒業後も研究や社会活動のみならず個人的な面でも交流を重ねてきましたが、それも心理学の扉を叩いたからこそ得られた絆だといえましょう。
大学の授業を思い起こしてみると、やはり一番印象深いのは心理学の一般実験です。これは現在でも行われていると思いますが、心理学の基礎的な教養として大きな意味があったと思います。
師事した教授、研究室のスタッフ
私が入学した当時の心理学科主任教授は桑田芳蔵先生でした。私の記憶にある桑田教授は白髪白髥、ヴントの心理学を講じ、老教授の風格を具えておられました。後に文学部長に就かれたと聞いています。
千輪浩、高木貞二の両先生は、助教授から教授に昇格されて心理学科の二本柱でした。千輪先生はゲシュタルト心理学、高木先生は心理学的測定の講義を担当されていましたが、私の記憶では高木先生が私たちのクラスの指導教官であったように思います。先生は見るからに英国風のジェントルマンで、胸ポケットにハンカチーフをのぞかせていました。それで有名なエピソードをご紹介しますと、先生が以前に教鞭をとられた京都の第三高等学校(三高)で、或る日教室に行ってみたら生徒全員が制服の胸ポケットに新聞紙をさしていたという話です。今では胸ハンカチも珍しくはないでしょうが、高木先生のキチッとした風姿を彷彿とさせる話ですね。私は先生の従容としたご人格を尊敬していましたので、出征に当って先生のお宅に伺い、日の丸(日章旗)に「武運長久」と書いて頂いたことを覚えています。
当時の心理学科の講義の中で私の記憶に残っているのは、宮城音彌先生の臨床心理学、山下俊郎先生の児童心理学、牛島義友先生の青年心理学、岡部彌太郎先生の幼児教育、桐原葆見先生の産業心理学などです。
研究室の助手は学生にとって怖い存在でしたが、当初は黒木総一郎氏、その後間もなく小川隆氏が代られました。小川先生とは後年海外出張でお会いし久闊を叙しました。
当時つけていた日記から学生生活の断片を拾うと、日常の物資も次第に乏しくなってきた頃で、必要な大学ノートを買うのに行列で、漸く5冊買えたなどと記しています。また通学も交通の便が悪くなり、私は御茶ノ水駅から大学まで歩くのが常でした。バスは木炭車で坂を昇るのが大変でした。このように何かと不自由な生活でしたが、戦時中のゆとりのない現実の中にあって、学問研究の一端に触れ得たことは、私の精神生活を培うこよなき土壌となり、我が人生の貴重な1ページとなったと思っています。
3.学徒出陣で海軍へ
私が海軍に入ったわけ
私は青春の日々を日記に綴っていましたが、大学1年生(昭和18年)の9月23日の日記にこんな記述があります。
「昨晩 東条首相の重大演説に依って学生生徒の徴集猶予延期停止が発表された。朝刊は情報局発表の国家総力体制確立に関する記事で埋まってゐる。豫想されてゐた大学閉鎖は断行されたのだ。理、工、農、医は入営延期の形で残り、法、文、経は延期停止だ。だが一部の病弱者、適齢未満者等の為に講義はあるらしい… (原文のまま)」。
日記は続けて「心理学」が理工系と見做されて続けられるかどうか、多分難しいであろうなどと当時の不安な心情を綴っています。
とにかく私たち若者は、学徒出陣の大号令によって、陸軍は12月1日、海軍は12月10日に入営、入団することになりました。私は徴兵検査を受け「第1乙」と認定され、検査に合格しました。徴兵検査には甲乙丙丁の判定があり、丁以外は合格です(乙は更に第1乙、第2乙、第3乙と分かれる)。私は幼少時から風邪を引き易く弱い体質だと思っていましたので、検査で第1乙とは意外でした。しかし、そう判定されてみると、それなりの自信も湧き、よし、やるゾ!と言う気概が生まれました。
さて、検査に合格すれば陸軍か海軍に入らねばなりません。どちらを選んだらいいか、いろいろ迷いました。私の家は前にも述べたように公家の出ですから、先祖にも周囲にも軍人は一人もいません。学習院の友人には明治以来の軍人の子弟が何人もいましたが、私には先例とかモデルが無いわけです。どちらかに決める拠りどころが無い中で迷う日々が続きました。
私自身の経験では、学校で馬術部に入り乗馬は好きでしたから、陸軍将校の乗馬姿がイメージし易かったと思います。また、私の生まれ育った家が、当時東洋一と称された陸軍の連隊の近くで、夜の消灯ラッパを聞きながら成長したので身近に感じていました。
一方、海軍の方も学習院の制服が海軍士官の蛇腹のついた軍服を模したものだったり、少年時代に戦艦長門の見学をしたことの印象も深く、なんとなく親近感を持っていました。
こうした青少年期の心象風景を背景にしながら、私たちは応召を前にして、不確かな情報に一時翻弄されていました。「心理の専攻生は将来海軍の適性部に入れる…」、「陸軍でも一定の訓練を経て適性検査業務に就く道がある…」、「海軍では特別技術将校として心理学出身者をうけ入れるのではないか…」などなど。
丁度その頃、大学の先輩の望月衛氏が陸軍で航空適性検査を担当されていて、私たち心理の学生を検査業務のアルバイトとして臨時に雇用してくれました。それは数日の経験でしたが、兵隊の食事を食べたりして、いわば体験入営のようなものでした。
海軍の方は前に述べた先輩の松平さんの話から想像するくらいで体験的には何もなかったのですが、漠とした印象では、海軍の方が合理主義的で、心理学を齧り始めた私の価値観にも合っているように思えました。(しかし入ってみると必ずしもそうでなかったのですが…)。
私は、日記にも当時の心境を記していますが、陸軍にしても海軍にしても、心理学者としての活動が国家目的に適い、専攻の勉強が役に立つのであれば、それは大変やり甲斐のある話である。しかし戦況から見ても将来のことは解らないのだから、今の段階でジタバタするのは見苦しいのではないか…と思っていました。そして若し思い通りの進路に進めなくても、自分はそれを与えられた天命として受け容れようと心に決めていました。
折しも 昭和18年5月21日、聯合艦隊司令長官山本五十六元帥(当時大将)の戦死が報ぜられました。国民が戦局の重大さをひしひしと感じていた頃のことです。私自身も心の奥で、軍服を着ることの意味を、一つの「覚悟」として心に刻み、応召の日を迎えました。
海軍二等水兵から豫備学生へ
いよいよ12月10日がやってきました。私は出征軍人の誰もがやっているように、大学から貰った日の丸(国旗)を襷(たすき)に掛け、横須賀海兵団に入団しました。そしてその日から学生たちはジョンベラ(水兵服)を着せられ、海軍二等水兵としての生活が始まったのです。
入団してまず吃驚したのは、東大の心理の仲間たちと同じグループになったことです。私は第31分隊・第8教班に配属されました。因みに「分隊」は二百数十名、「班」は十数名の単位です。分隊の編成は出身大学・学部別に配置され、第31分隊は東大の文学部が主体でした。第8教班は心理、哲学、独文(ドイツ文学)、西洋史などの人たちの集りでしたが、その中で心理が最も多かったと思います。一緒だったのは池内一、石毛長雄、糸川民生、樋口伸吾の諸兄です。他に学習院初等科時代の同窓生穂積重行君も同じメンバーで奇遇を喜びあいました。(これらの諸兄は後年大学教授として活躍されました。)
私たちは全くの異次元の世界に身を置きながらも、娑婆(しゃば)(世間)の仲間と共にいる安心感に支えられて、2ヶ月弱の水兵生活を過しました。今から考えると、この時の体験は期間は僅かでしたが、組織の最下層の実体験として貴重な人生経験になったと思います。
私は若い頃から胃腸が弱く、何かというと休み勝ちで軍隊生活に耐えられるかどうか心配でしたが、矢張り予想した通り腹をこわし、「軽食」といって粥食に変えてもらったことも再三ありました。通常の食事も山盛りのメシを喰べきれず、周りの人に分けて喜ばれたこともありました。そんなひ弱な私でしたが、飛行適性検査に合格したので「飛適」の烙印が押されて、大勢の仲間と共に横須賀から土浦まで輸送され、いよいよ海軍豫備学生として「海鷲」になる道を進むことになりました。歌にもなった「豫科練」(豫科練習生)で有名な土浦海軍練習航空隊に入隊したのは2月1日のことでした。
さて水兵服から海軍士官の軍服に着替え、短剣を腰に吊すとすっかり気分も改まりました。しかし東大生から海軍士官への変身は、服装が変わったからといってそう簡単にはいきません。土浦特有の「筑波おろし」の寒風が吹き付ける中、「軍人精神」を叩き込む猛訓練が豫備学生の先輩の士官たち(少尉、中尉)によって行われ、日夜緊張に満ちた生活が始まりました。
私は前にも述べたように、胃腸に自信が無く、とりわけ厳しい土空(土浦海軍航空隊の略称)でのトレーニングに耐えられるか全く不安でしたが、人間、覚悟を決めると体質まで変わるのかと思える程に元気が湧き出てきて、雪中のハダカ体操などにも積極的に参加しました。今から考えると私の症状は多分に心身症的であったのかもしれません。
土浦から鹿児島へ
土浦での日夜の猛訓練に馴れ出した頃、再び身体検査があり、その結果私は「要務学生」としての教育を鹿児島航空隊で受けることになりました。この検査はパイロットとしての適格性を見るためのものでしたが、私は当時風邪気味で鼻の調子が良くなかったので、検査で撥ねられたのです。青年期に蓄膿症(副鼻腔炎)を患っていた私は、その結果に納得はしましたが、航空要務の任務も定かではなく、折角「海鷲」への道を歩み始めた時でしたから、胸中には複雑なものがありました。しかし後から考えると、この時点で私の運命は大きく変ったのだと思います。
当時の日誌によると、2月12日の夜半に特別軍用列車で土浦を出発し、鹿児島まで殆どノンストップで走り続け、3日後の朝漸く到着。その間車内から出ることは厳禁。途中、家族と面会したくて電報を打った者のいることがわかり、懲らしめのために全員の夕食が半分に減らされたと書いてあります。“犯人”たちが軍服を裏返しに着せられ、車内を歩かされた姿は、私情を否定することによって秩序を保とうとする軍隊組織の非情な一面を見る思いがして、今も瞼に焼き付いています。
とにかく私たちは巨大なベルトに乗せられ、思考停止のまま身を委せる他はありませんでした。しかし、寒風の吹き晒す土浦から南国の鹿児島へ来たことは、矢張りほっとする部分もあり、毎日桜島の美しい姿を見ながら、豫備学生としての生活に馴染んで行った数ヶ月でした。
いよいよ鹿児島での訓練も終わり、要務の学生たちはそれぞれの志望に従って配属先へと分れて行きました。その行き先は様々で、軍艦に乗って暗号解読に従事する者、偵察のための航空写真を任務とする者、若い豫科練たちの教育に携わる者、司令部付の用務を担当する者などなどあり、海軍という組織の大きさと多様さを改めて知る思いでした。
私はその中で適性検査業務を志望し、再び土浦航空隊の門をくぐることになりました。土空の適性部勤務を命じられたわけです。東大の心理学科に入学以来、出来ることなら専攻する分野で国家に役立ちたいと言う念願が実り、私は新たな希望を胸に土浦へと旅立ちました。
4.適性検査に従事
適性部勤務
土浦に来てみると、すぐには適性部に配属にならず、それから夏の炎暑を挟んで約4カ月間、術課教程と称するアドバンスコースの訓練が待っていました。これも中々にしんどい体験でしたが、この頃になると海軍士官の軍服も身につき、「第14期海軍豫備学生」としての自覚が芽生えてきたように思います。そしてその年の10月に、いよいよ「適性部員」として勤務することになりました。
適性部には、東大の心理の先輩の日上泰輔氏、松平定康氏(豫備学生1期、海軍大尉 両氏とも東大1941卒)が居られ、特に松平さんは学習院の先輩でもあるので心強くアットホームな感じも味わいました。
適性部の部員は武官と文官に分かれ、武官では上記の2先輩の他、重松毅(東大1943卒)、日高英行(東大1943卒)、石毛長雄(東大1944卒)、旭享(東大1944卒)などの心理の諸先輩が一緒でした。
文官と言うのは、専門職として勤務する「軍属」の人たちですが、それぞれのキャリアで「士官相当官」として胸に階級章をつけていました。適性部の中核を担っていたのは文官の人たちで、トップが高木貫一(東大1925卒)、続いて鶴田正一(東大1933卒)、山根清道(東大1935卒)、相馬紀公(東大1938卒)、遠藤辰雄(東大1939卒)、西堀道雄(東大1941卒)、田中良久(東大1941卒)の諸氏です。
このような陣容からもわかるように、海軍の航空心理に対する気の入れようは決して半端なものではなかったといえましょう。先任部員の高木さんは海軍中佐待遇で、飄々としたお人柄の中に、航空心理学の拠点を預かる重責感を持っておられたと思います。
当時の適性検査は、航空戦の人的資源を確保するという国家目的に照らして、豫科練を中心とする若いパイロットの選抜、養成という重点課題があり、私たちは連日のように心理テストの実施に努めました。
検査の種目はいろいろありましたが、主なものとして知能検査、精神作業検査、技能検査が行われていました。70年以上前のことですから記憶も定かではありませんが、知能検査は民間で行われていた田中B式団体知能検査が用いられていました。また事故防止の目的から、内田・クレペリン精神作業検査が、「海軍航空精神作業検査」と銘打って活用されました。その他「処置判断テスト」などの状況判断の適否をみる検査や、暗夜の計器飛行のシミュレーター、目標に向かって安定操縦をする技能を調べる「地上演習機」などの機器もありました。IT時代の今日から見ればオモチャのようなものでしたが…。
検査データの処理は、地元から微用された「技工士」と呼ばれる人たちが担当していました。また、やはり地元土浦の女学校(女子高校)の生徒が「女子挺身隊」として採用され、集計業務に携わっていました。
海軍兵学校に出張
私が当時のことを想い起こすときに忘れ得ないのは、海軍兵学校のある江田島に出張したことです。江田島は瀬戸内海の呉市の近くにある島で、海軍のエリート教育の牙城でした。海軍兵学校は陸軍士官学校と並んで海軍大学、陸軍大学へ進学するエリート育成の場であり、多くの名将、勇将を生み出してきました。独特の教育システムを持ち、小説や映画の舞台にもなっていました。
私は江田島出張を命じられたとき、とても嬉しく思いました。それは、今まで缶詰のように航空隊の中に閉じ込められていた身が、久し振りに娑婆の中に出て行けるからです。それに数ある適性部員の中から私が選ばれたことも私のプライドを擽(くすぐ)りました。さらにいえば、豫備士官の私が「本職」の軍人相手に検査をすることに、専門職としての責任とやり甲斐を感じたことも与(あずか)っていることと思います。
昭和19年10月、私は日上泰輔大尉の引率の下に同僚の大角欣治部員(関西学院大出身)とともに江田島に赴き海軍兵学校第76期生の適性検査を実施しました。後年、私が大手企業の管理者研修に関わる中で、76期の生徒だった人と邂逅したことも一再ならずありました。
江田島出張にからむ思い出は、プライベートな側面では、私がかねてから親炙(しんしゃ)していた祖父の訃報に接したことや、心理学科の親友の水原泰介君のお世話で、当時既に希少価値になっていたスキヤキのご馳走にあずかったことなどありましたが、今でも記憶に残っているのは私たちの提出した適性の合否判定が海軍当局によって覆されたことです。詳しいことは省きますが、兵学校の検査では我々の心理測定と並行して、手相・骨相による適性判断がさる“名人”によって行われており、彼の判断が優先して採用されたということがありました。海軍という所は合理主義が通用するものと思っていましたが、これも戦争の末期的現象の一つだったのかも知れません。
とにもかくにも江田島出張は、私の胸に広島みかんのように甘酸っぱい印象となって今に残っています。
5.103分隊に配属、土空空襲
分隊士の体験
昭和18年12月に海兵団に入団以来、1年余りの年月を経て、翌年の12月25日、私は漸く海軍少尉になりました。これは学徒動員で海軍に入った人たちの一斉の任官でした。正直、ヤレヤレと思いました。少尉になってみると、やはり行動の自由は広がります。週末は外出できるし生活にゆとりが出てきました。土浦の市内に寛ぐ場所も見つけました。
士官になってからも適性部の部員としての職務は変らなかったのですが、翌年の2月に入ってから第103分隊という特別編成の部隊の「分隊士」(分隊長の下の管理職)として勤めることになりました。この部隊は、簡単に言えば防空壕掘りの作業員の部隊で各地から集められた中高年の人たちです。中には大工さんや洋服職人、工場長をやっていたという人もいました。
その頃は戦況も既に傾き、本土空襲の可能性も現実的になっていましたから、航空隊としても避難対策に迫られていたのでしょう。103分隊の任務は適性部用の防空壕を作ることでした。
そこで適性部員から松平定康大尉が分隊長になり、その下の分隊士に私がなったわけです。同僚には吉田禎吾氏(東大1947卒)、小佐治朝生氏(東大1948卒)等がいました。この103分隊は分隊長の温かい人柄もあってまとまりも良く、軍隊の中のオアシスのような場所でした。適性部とは違って純然たる軍隊組織ですから若い私の部下に社会経験の豊富な年上の人がつくことになるわけですが、人と人との心のつながりは年齢や階級を越えたところに成り立つことを知ったのは、私にとって新鮮な体験で、後年の産業カウンセリングの研究の土台になったような気がします。
103分隊で培われた人脈は終戦後も枯れずに、松平さんや吉田さん、小佐治さんとは仕事の面だけでなく、同じ釜の飯を食った間柄として長く親しい交流が続きました。
土浦航空隊空襲
103分隊のおかげで防空壕も出来ましたが、それから間もなく東京の下町がB29の大編隊による空襲で大きな被害を受けました。昭和20年3月10日夜のことです。その日は土浦から100キロも離れた東京の空が赤く染まって見えました。暗然たる気持ちでそれを眺めていたことを覚えています。続いて4月、5月と東京大空襲が続き、皇居の焼けた5月25日には私の生家も直撃を喰らって灰燼に帰しました。
さらに6月10日、敵の編隊は容赦なく土空を襲い、豫科練の若い生命が多数失われました。私はその時、103分隊の兵士たちと適性部前の防空壕に身を潜めていましたが、大編隊のB29から降ってくる爆弾のザァーッという音や、至近弾が50m先のプールに落ちたときに壕の中が激しく揺れたことをまざまざと覚えています。
空襲の後もグラマンという敵の戦闘機が絶え間なくやってきて、機銃掃射を喰らいましたが、そうした光景もまだ瞼に焼き付いています。
空襲によって航空隊は相当な打撃を受け、私が個人的に懇意にしていた下士官の人が戦死しました。幸い適性部は全員無事だったのですが、戦争の生々しい恐怖を肌で味わい、一段と身の引き締まる思いでした。
6.海軍航空要員研究所に転任。そして終戦
海軍航空要員研究所
空襲の後間もなく、私は適性部から研究所に配置替えになりました。103分隊も使命を終えて解散になり、分隊長も分隊士も皆研究所に集められました。
研究所は土空本隊の近くの丘の上にある見晴らしの良い所にあって、航空心理学研究棟と航空医学研究棟の二棟がありました。
海軍の心理学関係の研究所は通称“技研”といわれていたところと土浦の航空要員研究所の二ヶ所があり、技研(技術研究所)には兼子宙氏(東大1931卒)をトップに、肥田野直氏(東大1943卒)や末永俊郎氏(東大1943卒)、池内一氏(東大1944卒)等がいました。
私が所属した航空要員研究所のスタッフは先任所員(所長)高木貫一(以下敬称略)、研究員(所員)に鶴田正一、山根清道、相馬紀公、遠藤辰雄、田中良久、日上泰輔、松平定康、小瀬輝、小林達三、重松毅、日高英行、平野直人、小林亮太、石川英夫、平井隆太郎、吉田禎吾、瀬谷正敏、宮川知彰、糸川民生、その他数名の諸氏です。
こうして研究員の名前を挙げてみると、わが国の心理学者の錚々たるメンバーが名を連ねており、国家総力戦が背景にあったとはいえ、日本の心理学史上に特筆すべき組織だったのではないかと思われます。
さて私自身は、研究班が6つある中の「教育研究班」に入りました。ここは予科練など若い人たちの教育を心理学的に研究するという主旨のグループで、私は宿願の研究課題に打ち込めるという希望に胸を膨らませましたが、その頃は空襲の打撃が消えず、士気も上がらずに徒らな時が経過したように記憶しています。そしてとうとう8月15日がやってきました。
玉音放送
その日はジリジリするような真夏の太陽が照りつけていました。私たち研究所の所員一同は前庭に整列して「重要放送」を聞きました。陛下のお声は雑音が交じって聞きづらいところもありましたが内容は大体理解できました。「敗戦!?」うすうす感じていたとはいえ、ショックがじわじわと広がって行きました。高木先任の、拳で眼を拭っている姿が目に焼きつきました。
その時の名状し難い胸の内は、70年経った今日でもリアルに浮かんできます。魂の抜けたような虚脱感が全員を掩い、暫くは時間が止まったような感覚でした。放送のあと、一時は不穏な情報も耳にしましたが、土空全体は粛然と行動し、私たちは旬日のうちに除隊・復員となりました。私は青春の一時期を燃焼した思い出の航空隊をあとに、家族が疎開している千葉県に帰省しました。そしてその年の10月に、再び大学に戻りました。
7.復学から卒業まで
終戦直後の学生生活
復学してみると、母校の東京大学のキャンパスは無事に残っていましたが、そこに集まってきた人たちの姿は、戦争の影を背負っていました。帰ってきた学徒兵たちは軍服を脱いだ筈ですが、着るべき金ボタンの学生服も無く、階級章を剥ぎ取った陸海軍の哀れな軍服がキャンパスのあちこちで見られました。教授の先生方もご苦労は同じで、哲学のさる有名な教授が、ツンツルテンのズボンをはき、冷飯草履で教室に入ってこられたことなど、懐かしい思い出です。
私の記憶では学生食堂も開いていましたが、まともな食事とてなく、海藻のようなものを主食にしたり、ご飯の上に怪しげなソースをふりかけただけの“ソーライス”と称するものを食べていた時代でした。また弁当にはよくふかし芋を持っていきましたが、三四郎の池の辺りで友人と食べたことも再三ありました。
しかし、そうした貧しい生活の中にも、戦後の新しい時代を生きていこうとする気概のようなものが、復学してきた学生たちに共通してあったように思います。
私は海軍の103分隊で一緒だった吉田禎吾君と気が合い、起居を共にしながら文学部の講義を聞いて廻りました。精神的な飢餓を癒すべく、辰野隆先生(仏文)や、和辻哲郎先生(倫理)の教室に通い、熱心にノートを取りました。その時のノートは今も大切に保存しています。
今にして思えばほゝ笑ましい思い出ですが、同世代の仲間たちが集まり、ドブロクを汲み交わしながら盛んに放談していたのは終戦後2〜3年の頃でしょうか。特攻隊にいて出陣の寸前に終戦になり、九死に一生を得た土空以来の友人や、空襲時高射砲隊の隊長をしていた高校時代からの友人などと一緒によく集っていました。その席に仏文学で高名な渡辺一夫先生も時折みえていて、何を話したかはすっかり忘れましたが、非常に楽しかった記憶が残っています。これも軍隊の抑圧から解放された青春謳歌の一コマだったのでしょう。
卒業論文の作成
大学に戻ってから一年が経ち、卒業論文に取り組む時期になりました。その頃はまだ戦後の復興も始まったばかりで、生活基盤も定まらず、何か一つの課題に集中するゆとりは、生活的にも心理的にもありませんでしたが、私は卒論作成に私なりの努力をしました。指導教官は千輪浩先生でしたが、私は少々ヘソ曲りだったのでしょう、当時の研究室の主流だった知覚研究のテーマを選ばずに、敢えて教育心理学的な課題を選びました。タイトルは「怠惰児の実験的研究」です。今から考えると、まことにお粗末でお恥ずかしい内容ですが、私の中には学習困難児への関心があって、近年注目されている発達障害児の問題につながる意味もあり、もっと本腰を入れて研究すればよかったと反省しています。
卒論を提出して、私は吉田禎吾、先崎正次郎、中村陽吉等の諸兄とともに昭和22年9月に卒業しました。入学以来、戦争をはさんで5年経つわけですが、心理学科の学生生活は多くの友人・知己を得て、それからの社会活動の土台になったと思っています。
私は卒業後旧制の大学院に籍を置く一方で、生活上の必要から教職につき、海軍の豫科練習生に相当する年齢の人たちに向き合っていました。20代前半という多感な時期にめぐりあった水兵、海軍士官、教師という社会経験は、私の人間形成に深く刻み込まれたように思います。
8.カウンセリングとの出会い
SPS研修会
私は大学に勤めるようになって、児童心理学や青年心理学を講じながら、戦前とは異なる新しい教育制度の下での学生指導に関心を向けていました。
丁度その頃、文部省(現文部科学省)のバックアップでアメリカから数名の講師団が来日し、「学徒厚生補導研修会」(Student Personnel Services S・P・S)という名のもとに、約1年間に及ぶワークショップが開かれました。九州大学を皮切りに、京都大学、東京大学で3ヶ月ずつ行われたのです。私は真夏のさ中に冷房の無い(当時は専ら扇風機でした)東大の図書館に毎日のように通いました。昭和27年のことです。
セミナーの内容は学生指導に関するいろいろなアプローチの紹介で、アメリカで行われている方式を伝授するというものでした。セミナーの途中でアンケートが行われましたが、参加者の関心が最も高かったテーマが「カウンセリング」でした。回想すれば、私とカウンセリングとの出会いは、このセミナーに始まるといえましょう。
その後。SPS研修会のフォローアップの意味もあって、昭和30年に「SPS特別研修会」が矢張り東大で開催されました。これはまさにカウンセリング研修会でした。講師はF.P.Robinson、E.Bordinの2人で、両先生とも一流の学者です。私は当時の勤務校の横浜国立大学から同僚の伊東博氏とともに大きな期待をもって参加しました。
この特別研修会に参加した心理学者には東洋氏(東京大学)、三隅二不二氏(九州大学)など後年心理学界をリードされた方や、私の先輩の松村康平氏(お茶の水女子大学)がおられ、レベルの高いものでした。私はこの研修会のあと数名の人たちと語らって、「相談心理学」という本を編集しました。(沢田慶輔編 朝倉書店刊 1957)。また、同志を糾合して「学生相談研究会」を立ち上げ、毎月集まって研究討議を行いました。
私の中では、SPSへの参加を契機としてカウンセリングへの思いが強くなり、自らの研究と実践の方向性をそこに定めたのです。
学生相談室を開く
SPS研修会に横浜国大から参加した伊東氏と私は、学生相談の実践の場としてキャンパス内に学生相談室をつくる計画を立てました。しかし大学の教授会の理解が得られず、その実現には苦労しました。昭和30年の当時は、カウンセリングという言葉も殆んどの人が知らず、「学生は一人前で大学がお節介を焼く必要はない」という考え方が教授たちの頭を支配していましたから、どこの大学でも相談室の設置には少なからず抵抗があったと思います。
しかし、昭和28年には東京大学に学生相談所が設けられ、続いて大手の国公私立大学にも相談室が出来てきて、私たちもその流れの中でカウンセリングを行うようになりました。
相談室といっても、当初は宿直室の古自転車が置いてある土間に、粗末な机と椅子を置いただけの素朴なものでしたが、漸次設備もよくなり、相談活動も軌道に乗ってきました。
私は試行錯誤の中でカウンセラーとしてのスキルを磨きつつ、この活動がわが国の青少年の成長発達にとって不可欠のものであることを確信していました。
産業カウンセリングとグループダイナミックス
我が国で学生相談活動がまだ緒についた頃、産業界にもアメリカのホーソン実験やNTL(National Training Laboratory)の成果が伝えられ、人間関係やリーダーシップの重要性について関心が高まってきていました。
私は学生相談で学んだカウンセリングの理論と方法を、企業組織の中でも活せないかと考えていたので、職業指導の分野で活躍されていた藤本喜八氏(立教大学)や、海軍時代からご縁のあった相馬紀公氏(国鉄・現JR)や、NTTの前身である電々公社のカウンセラーをしていた福山政一氏らと共に、産業組織の中にカウンセリングを根付かせるべく昭和36年に日本産業カウンセラー協会を立ち上げました。それまでは産業人事相談として企業の片隅で生活福祉的な活動に留まっていたのですが、1960年代の高度経済成長の波に乗って我が国の産業カウンセリングが開花して行きました。
学生相談や産業カウンセリングが社会の一隅で産声をあげる頃、K.レヴィンによって開発されたグループダイナミックスがわが国にも波及してきました。私はレヴィンの理論は大学で学び、その考え方に共鳴していましたので、グループの研究に大いに刺激されました。丁度畏友の水原泰介君が社会心理学をやっていて、NTLで行われたレヴィンの研究を日本でも試みようというので、数名の仲間と一緒に、区の教育委員会や企業の人事部の協力を得て実験グループをつくり、集団発達とリーダーシップの研究を3年ほどやりました。協力してくれた会社の人事部長から、日本のホーソン研究にしようなどと持ち上げられたりしましたが、長続きしなかったのは残念でした。
グループダイナミックスの研究は、SPSで一緒に学んだ九州大学の三隅二不二さんが中心になり、研究会や学会をつくったことはよく知られていますが、私たちの研究はパワー不足でした。
しかしその後しばらくして、海軍時代の仲間だった池内一氏(東大新聞研究所教授)の研究プロジェクト「社会的葛藤解決の研究」に水原泰介君らと共に参加し、私が中心となって大規模なロールプレイングを行い、集団間葛藤のシミュレーションをやったことは今でも記憶に残っています。
グループダイナミックスの日本への導入には、別の大きな流れとしてJICE(立教大学キリスト教教育研究所)の活動があります。この流れは現在も南山大学を中心に続いていますが、私がこの「ラボラトリー・トレーニング」と称する合宿セミナーに参加した頃(1969)から産業界でも注目しだして、「Tグループ」、「ST(Sensitivity Training)」として全国的に広がって行きました。また殆ど時を同じくしてロジャーズのエンカウンターグループ(EG)も伝えられ、小グループの体験学習方式は人間関係トレーニングの方法として次第に日本の社会に定着し、今に至っています。
私はカウンセリングもグループダイナミックスも、それが日本に入ってくる時期に居合わせていたわけですが、その理論と方法の中に自らの居場所を求めていろいろと動き廻っていたのだと、今になってみると判るような気がします。
9.私の研究活動
研究活動の軌跡
私は心理学を学び、心理学の分野で仕事をしてきましたが、心理学者としての研究実績を問われると、あれこれ手を出していて、まとまった業績としてお話しするものがないのですが、高齢になって来し方を振り返ってみると、自分なりの足取りが見えてくるように思います。そしてその軌跡を辿ると、自分が心理学を志した原点が浮かんできます。私は前にも述べたように、思春期の頃心身が不安定な中で、自分自身の存在を確かめるために、心理学に拠り所を求めました。自分は誰か、人間とは何かという根源的な問いは、成長期にある者の普遍的なテーマであると思いますが、私はそれを観念の世界にではなく、日常の営みの中に答えを求めて、心理学者としての研究と実践を重ねてきました。
これらの活動を心理学の分野別に見ると、①教育心理学・発達心理学の領域、②産業組織心理学の領域、③社会教育・生涯学習の領域、④家族心理学の領域の4つの分野に亘っています。そしてそれぞれの領域における研究と実践をつなぐ横糸がカウンセリングであり、グループダイナミックスであるといえるでしょう。別のいい方をすれば、私は心理臨床の土台に立って、学校、産業、社会、家族の心理学的な課題に、実践的な切り口で取り組んできたというわけです。
教育心理、学生相談の研究
私の研究活動の流れを時系列的に見て行くと、昭和20年代の研究は教育心理、乃至発達心理の問題を取り上げました。これは勤めていた横浜国立大学で児童心理の講義を担当していたことも背景にあるでしょう。学会や研究誌で親子関係、きょうだい関係の実験的な研究を発表しました。しかし当時は整った施設もなかったので、共同研究者の石井哲夫さん(1950東大卒)のいた社会事業大学に仮設の観察室をつくってやっていました。
何かと乏しい時代でしたが研究意欲は旺んで、研究の楽しさ、醍醐味というものを自分なりに味わったような気がしていました。敗戦後の焼野原の東京に復興の槌音が響き、私も千葉の疎開先から東京に移ってきました。個人的なことですが、結婚し新居も構えて、落着いた中に研究環境も次第に整ってきたのが昭和30年以降のことです。
その頃大学に学生相談室を開いて学生相談に乗り出したことは前に述べましたが、数年経って各大学で相談室を持つところが増えてきたので、私は肥田野直氏(1943東大卒)らと一緒に学生相談活動の実態調査を行いました。また同じ頃、創刊間もない「心理学評論」に「学校カウンセリングの問題点」という論文を載せましたが、私はカウンセリングの実践を通して相談室の運営面にも関心が強かったのだと思います。
昭和30年代は、31年にE.G.Williamsonが、36年にC.R.Rogersが来日し、それぞれ大きな足跡を残していきましたが、学生相談の研究でも、その方法論をめぐって指示的か、非指示的か、折衷的かという論争が盛んに行われた時代でした。
産業カウンセラー養成、職場の人間関係の研究
丁度その頃に、前にも述べたように産業界で職場のリーダーシップや人間関係のあり方が注目されだしてきて、私の研究と実践は次第に教育の分野から産業組織の方にシフトして行きました。
昭和39年度から労働省(現厚生労働省)婦人少年局が産業カウンセリング普及導入事業を始め、それに協力する形で産業カウンセリングの実施状況の全国調査を行いました。そして盟友の伊東博氏らと共著で「カウンセリングを職場に生かそう―産業カウンセリング手引き―」を執筆しました。
私は企業内にカウンセリング制度を定着させるためにはカウンセラーの質的向上が大切だと考え、既に活動している社団法人日本産業カウンセラー協会で、産業カウンセラーの資格認定の仕事に関わり、試験委員会の委員長として8年間勤めました。
社会にカウンセリングを根づかせるために、カウンセラーの専門性を高めることに腐心する一方において、私は「職場のカウンセリング」という本を書いて組織内の人間関係にカウンセリングの考え方や技術を役立たせるように努めました。私のこうした問題意識の中で行った実践的研究として「ロールプレイング」があります。ここでその詳細を語ることはできませんが、私の行ったロールプレイは、サイコドラマの理論と方法を取り入れながら、職場の人間関係の改善につながる体験学習としてプログラムしたものです。
私は、私の考えに理解を示したF社で、第一線監督者の研修にこれを用いて相応の手応えを得ましたので、わが国の基幹産業のS社、K社をはじめ各種メーカー、金融機関、官公庁、大学・研究所等々で、カウンセリングとロールプレイの普及と活用につとめました。それに私の生き甲斐を注ぎ込んだといっても過言ではないと思っています。
カウンセリングの諸理論と技法は、専門の心理臨床家だけでなく、社会生活の中で、一般の人たちにも使えるものですが、それを「生兵法は大怪我のもと」にならないように、日常的な活用法、具体的な応用力を身につけることが求められると思います。
私の研究は、K.レヴィンがいうように、研究と実践を車の両輪として、研究も実践もより洗練されたものに進化することを目指しました。しかし、今ふり返ってみると、当時の社会状況に流されて、研究よりも実践にエネルギーをより多く費やしたように思います。その頃の実践的研究は方法論も不確かでしたが、もっと腰を据えて「研究」に取り組むべきだったと反省しています。
家族カウンセリングの研究
私が家族の心理支援に踏み出したいきさつについてお話ししますと、1981年に行われた日本心理学会の第45回大会がその発端になりました。その頃、家族をめぐる事件が相次いでマスコミを賑わし、テレビドラマでも家族の問題が屢々取り上げられていました。家族療法はアメリカでも既に大きな流れになっており、わが国でも精神医学や社会学の人たちの間で関心が持たれていました。心理学者の中でも、岡堂哲雄氏、国谷誠朗氏、平木典子氏と私の4人が集まって、「家族心理学」の開発を話しあいました。
そうした雰囲気の中で日本心理学会の大会が日本女子大学の主催で開かれ、私がその準備委員長を務めることになりました。 数ある企画のひとつに「家族臨床心理の現状と展望」というタイトルのシンポジウムが行われ、多数の参加者があってこの分野の研究開発に弾みがついたというわけです。
その後1984年に「日本家族心理学会」、ついで1985年に「日本家族カウンセリング協会」が設立され、私は学会の運営に関わる一方で協会の責任者として「家族相談士」(家族心理臨床の専門職)の養成と資格認定に当たってきました。私が家族の心理支援に意欲を持った背景には、グループダイナミックスの研究と実践に関わってきた経験から、人と人との関係性のダイナミズムに、心理学者としてのつきせぬ興味を感じたことと、それと相俟って、社会生活の基盤であり人間成長の基地でもある家庭・家族に巣くう病理を探り、その予防への手掛かりを得たいと言う意志が働いていたと思っています。
その意味から私の研究的な関心は「家族ロールプレイ」の開発に向けられました。試行錯誤を重ねながら現在も開発途上にありますが、職場の人間関係の研修に用いたロールプレイングのキャリアを活かして家族支援の実をあげたいと願っています。
10.私の社会活動
学会・協会の設立
繰り返し申しますように、私は戦後の復興期に社会人として歩み始めた年回りなので、わが国の心理学の発展とともに年を重ねてきたわけです。そういう廻り合わせから、心理学諸学会の設立準備や創立に立ち会ったり、関わったりする機会が少なからずありました。翻って考えてみると、そういう機会を捉えたり、そこに身を置くということは、私自身の中に何か新しいものを形づくって行くことに興味関心を抱く「ものづくり」的な志向性が潜んでいたのかもしれません。
時系列的に見ると、最初に研究団体をつくる事に関わったのは「学生相談研究会」の結成で、これは1955年頃のことです。前述のSPSワークショップのあと間もなくのことでした。この研究会は後年「日本学生相談学会」として発展して行きます。
次いで1961年に、日本応用心理学会の中の組織として「相談部会」をつくることを先輩の松村康平さんが提唱され、私もその設立を手伝いました。当時はカウンセリングを「相談」と言い換えていましたが、日本にも相談という仕事を心理学的に研究する場ができることに、小さな希望の灯をともしたつもりでした。
それから数年経ち、1967年にようやく「日本相談学会」が一本立ちします。私も仕掛け人の一人として創立総会に立ち合いましたが、その時の写真が「カウンセリング研究vol.26 No.1 1993」に載っています。この学会は、1987年に名称を「日本カウンセリング学会」と変えていきます。その頃になってカウンセリングの語が日本の社会に定着してきたと言うことでしょう。
20世紀の後半になると、心理療法に関する諸学説が、やや大仰な言い方をすると、雨後の筍の如くわが国に伝えられ始めました。その中の一つの「交流分析」は、池見酉次郎氏(九州大学教授)によって導入されたもので、その体系化された理論が関心を集め、1976年に「日本交流分析学会」が設立されました。この学会は池見先生を中心にして心療内科の専門医の人たちが主な構成員でしたが、私は心理畑から国谷誠朗さん、深沢道子さん等と共に学会設立に参加しました。
1980年代になると、心理学系の専門学会が相次いで産声を上げています。その中で私が発起人として関係したのは、「日本人間性心理学会」(1982年)、「日本家族心理学会」(1984年)、「産業組織心理学会」(1985年)、「日本健康心理学会」(1986年)です。こうした流れは、わが国の心理学の幅広い発展を示す道標であると同時に、当時の心理学者たちの盛んな意欲の表れであるともいえましょう。
20世紀末の学会ラッシュの中で、医療系の学会と心理系の学会のコラボレーションを企画した「日本心理医療諸学会連合(UPM)」の結成(1988年)は、心理学の歴史の1ページを飾るモニュメントではないかと思います。この組織(略称心医連)は、医学と心理学の連繫を強調された池見酉次郎先生のリーダーシップの下に成立を見たのですが、私も心理学の諸学会に関与していた立場からその趣旨に賛同し、有力な心理学者と共にその立ち上げに協力しました。
時代はさらに移って昭和から平成に変わり、バブル崩壊後の不安定な時代に入って行きますが、1996年、私は松原達哉氏、楡木満生氏、木村周氏らの同志と共に、「日本産業カウンセリング学会」の創立を実現し、初代会長に就任しました。それぞれの学会が生まれるまでにはいろいろな経緯があり、安産も難産もあるでしょうが、そこに人と人とをつなぐ横糸としての"志"が大切であることを改めて感じています。
心理学の専門学会の設立に与ると共に、私はカウンセリング関係の「協会」をつくることにも積極的に関わりました。学会は学術研究団体としての性格を軸に成り立っていますが、協会はより緩やかな集まりで、職能団体的な意味もあり、社会活動を行う上で学会とは異なった機能を持っていると思います。私はわが国にカウンセリングを普及発展させていくために、協会という組織の役割もあるのではないかと考えて、その創設と運営にエネルギーをつかいました。
その一つは「日本産業カウンセラー協会」です。この協会のことは前にも触れましたが1961年の設立以来紆余曲折を経て、1990年に元労働事務次官の藤縄正勝氏を会長に迎えてから産業カウンセラーの資格が労働大臣認定の公的資格となり、活性化してきました。私は同氏の依頼で協会の試験委員長を引き受け8年間勤めました。その頃かかわりのあった人たちは殆どが故人となりましたが、創成期の苦労を分かちあったことなど思い出はつきません。
もう一つは「日本交流分析協会」で、これは1976年にできた日本交流分析学会と同時にスタートし、私が初代会長を引き受けて約10年余り勤めました。さらに、1985年には前年に創立された日本家族心理学会の活動の一翼を担う形で、「日本家族カウンセリング協会」を立ち上げました。そして初代会長を勤めていましたが途中でNPO法人となったので、引きつづき理事長職に就いて今日に至っています。
学会の年次大会を主催する
上述の学会は毎年年次大会を開いていますが、私は創立に関わった立場から、大会の運営に主催責任者として連なることが度々ありました。そのリストを揚げると次の通りです。
・日本相談学会第10回大会(1977)
・日本心理学会第45回大会(1981)
・日本家族心理学会第1回大会(1984)
・日本交流分析学会第10回大会(1985)
・日本人間性心理学会第4回大会(1985)
・第27回全国学生相談研修会(1988)
この中でも忘れられないのは日本心理学会の大会です。当時私は日本女子大学の教授をしていましたが、学会から主催校の打診があったとき、これは大役なので準備委のチームワークがとても大切だと思い、心理学関係の先生方と話しあいました。同じ学内でも所属の学部学科が異なると、普段顔を合わせる機会もなく、コミュニケーションは円滑ではなかったのですが、大会開催を機に結束が高まり、大会を引受けた副次的な効果となりました。
プログラムの中でも特に印象が深いのは、大会最終日に会場の国立教育会館の虎ノ門ホールで、「心理学を問い直す――現代の状況と人間研究――」と題するパネルディスカッションを催し(メンバーは林知己夫、河合隼雄、南博、山本七平、司会・本明寛の諸氏)、大ホールに千数百名の参加者があったことです。当日、心理学の大先輩の結城錦一先生からお賞めに与ったことも忘れ得ぬ思い出です。
生涯学習への寄与
心理学に関する私の仕事は以上のような流れですが、かかわった社会活動の中でかなり多くの時間を社会教育・生涯学習に費やしたので、このことに言及しておきたいと思います。
1974年、朝日新聞社が文化事業の一環として、当時はまだ珍しかった超高層ビル(新宿住友ビル)の48階で、生涯学習の研修センター(朝日カルチャーセンター)を開くことになり、教養講座の一つに「カウンセリング講座」を入れたいということで私に依頼がありました。
私はカウンセリングの普及啓蒙に社会的な意義を認めていたので、ふたつ返事で引き受け、以来40年間に亘って講座の主任講師を勤めてきました。前半の十数年は平木典子氏
(日本女子大)、その後は村瀬旻氏(慶応義塾大)、小山田治子氏(CHR研究所)と共同で担当しました。受講生は延べ数千人になると思いますが、その中から臨床心理士や専門の学者、研究者も相当数育っています。また、受講生が集まってNPOを立ち上げているケースもいくつかあり、一つの時代の中で、社会教育の一端を担っていたとすれば大変うれしいことです。
それから、今一つは時代が大分逆るのですが、NHKの教育テレビの「大学講座」で足かけ3年間「心理学」を担当しました(1970,1971,1973)。タイトルは「人間関係の心理」でしたが、内容は対人認知やグループダイナミックスに関するものでした。この講座は比較的地味なものでしたが、視聴者が全国で7万人もあり、毎回の準備にかなり努力したことを覚えています。
おわりに
以上が心理学者としての私の半生のダイジェストです。果たして「オーラルヒストリー」の趣旨に適った話になったかどうか疑問ですが、私にとっては、人生を振り返る良い機会を与えていただいたと思っております。話しのおわりに、インタビューの中から補足的な話を2、3拾って、質疑応答形式で述べておきます。
――― 先生のお名前は珍しい読み方ですが、その由来をお聞かせください。
私の名前は「一言」と書いて「きよとき」と読みます。これは辞書にもない発音ですからよく人に尋ねられます。
名付け親は私の祖父ですが、「言」を「とき」と読むのは、遠く平安時代からの命名の習わしで、私の先祖は代々男子に言の字がつけられていました。私は祖父にとっては初孫で、長男だったので一郎とか一夫とか名付けるところですが、しきたりで「一言」ということになったわけです。
「一」を「きよ」と読ませるのは、私が祖父から直接聞いたところでは、中国古典の「老子」第39章に「天、一を得て以って清し。地、一を得て以って寧(やす)し。…」という言葉があり、そこから取って命名したということです。
老子の思想の解釈はいろいろあるようですが、私は単純に「一」はものごとのはじめだから汚れてなく清いのだ、その意味をとって「きよ」と読むのだと解しています。
「きよとき」と言う読み方はともかくとして、私は「一言」という名前にこだわって生きてきました。世間では、何事にもひとこと意見を言わないと気がすまない人のことを「一言居士」といいますが、私はむしろひとこと足りない方で、大切な一言を疎かにしないよう常々心がけています。
その一言によって人生が大きく左右されたと言う話もよく聞きますが、私もカウンセラーのひとりとして、自分の名前に恥じないよう言葉を大切にしたいと願っています。
――― 先生は93歳と伺っていますが、まだお元気ですね。何か健康法のようなものがあるのでしょうか。
いや、特別なことをやっているわけではありませんが…、私はお話ししたように若い頃は健康に自信がなく、とても長生きできないと思っていました。しかし友人たちが次々と亡くなっていく中で自分が今だに健康を保っているのは、一つには健康管理に気を使っているからでしょう。矢張りモノでも人間でも長持ちさせるにはメンテナンスが大切ですね。
具体的には、極く当たり前のことですが、食事、運動、睡眠に留意して、できるだけ規則的な生活習慣を維持するように心掛けています。ハラ8分目の食事、ウォーキング、安眠が毎日の課題です。それと年齢に見合ったバランスの良い生活設計が必要でしょう。
しかし健康法は人によっていろいろで、それぞれの流儀があっていい。自分の体の声を聴いて自己流の健康法を実践することが長寿の秘訣ではないでしょうか。
もう一つ大事なことは、自分の健康は自分ひとりで保っているわけではないということです。人間は誰でも人と人とのかかわり、つながりの中で生き、生かされています。
日常の人間関係の中にこそ、いきいきと生きるカギがあると考えると、これは心理学の大きなテーマになってきますね。
―――先生は心理学者として、戦前・戦中・戦後の激動の時代を生きぬいて来られたわけですが、93歳というご高齢のいま、ふり返ってどんな感想をお持ちでしょうか。
そうですね。いろんなことがありましたね。でも今から思うと、私が心理学を学んできたのは、私にとって大正解だったと思っています。私は前に話した通り、体も心もタフではなかったのですが、心理学の世界に身を置いてきて、私なりに自分を生かすことが出来たのではないかと思っています。戦争中も心理学のおかげで命をつなげられたし、戦後も心理学者としての仕事に生き甲斐を見出してきましたから。
しかし、改めてふり返ってみると、まだ自分の中の可能性は燻(くすぶ)っている部分もあり、生きる限り心理学の道を歩んで行きたいと願っています。
――― まだ十分ヤル気をお持ちのようですね。心理学者の先輩として、若い人たちに何かアドバイスを頂けませんか。
そうですね。エラそうなことを言うつもりはありませんが、半生を振り返ってみて感じたことを率直に申し上げると、第一に基本のキが大切ということでしょうか。世の中がますます多様化複雑化し、情報も氾濫しているので、つい目移りしがちですが、基礎とか土台とかが大切なことはいつの世でも同じでしょう。私は心理学科に入って一般実験をやりましたが、そこで学んだことは方法論としてよりも、心理学的な目を養う上で大変勉強になりました。 専攻の分野の中で何が基本かということはいろいろ論議があると思いますが、まずは基本をしっかり学び、身につけることですね。
自分の中に研究の土台を築くことと相俟って大切なもう一つの視点は、人とのつながり、連携ということです。改めて自分の歩んできた道を振り返ってみると、私の人生は関係性の中で紡いできたように思えます。人と人との支えあいの中に、限りない可能性が潜んでいると私は信じています。これは社会や文化の交流についてもいえることでしょう。
心理学の人たちは――私も含めてですが――おしなべてキメの細かいセンスを持っているといえるのではないでしょうか。これは長所ではあるけれども、他方でスケールを狭めてしまう恐れがないでしょうか。異質の関わりの中から新しいものを見出し、作り出していく前向きのエネルギーを、若さの中に求めたいですね。
現代は歴史の過度期であるとか、転換期であるとかいわれています。先の見えない不安は誰しもが抱えています。だからこそ混迷の時代を生き抜く知恵と行動力を、これからの心理学者に期待したいと思っています。
『わたしの半生 ―戦前・戦中・戦後を生きた心理学者の回想録―』は、財団法人日本心理学会の教育研究委員会資料保存小委員会によるインタビューの記録に基づいて、杉溪一言先生が執筆されたものです。インタビューは2015年8月23日(日)に吉祥寺の杉溪先生のご自宅で行われました。インタビューを行ったのは、鈴木朋子(横浜国立大学)、高砂美樹(東京国際大学)、小泉晋一(共栄大学)の3人です。インタビューを承諾していただき、また本稿を執筆していただいた杉溪先生に心から感謝を申し上げます。
2016年2月9日
インタビュー主担当 小泉晋一