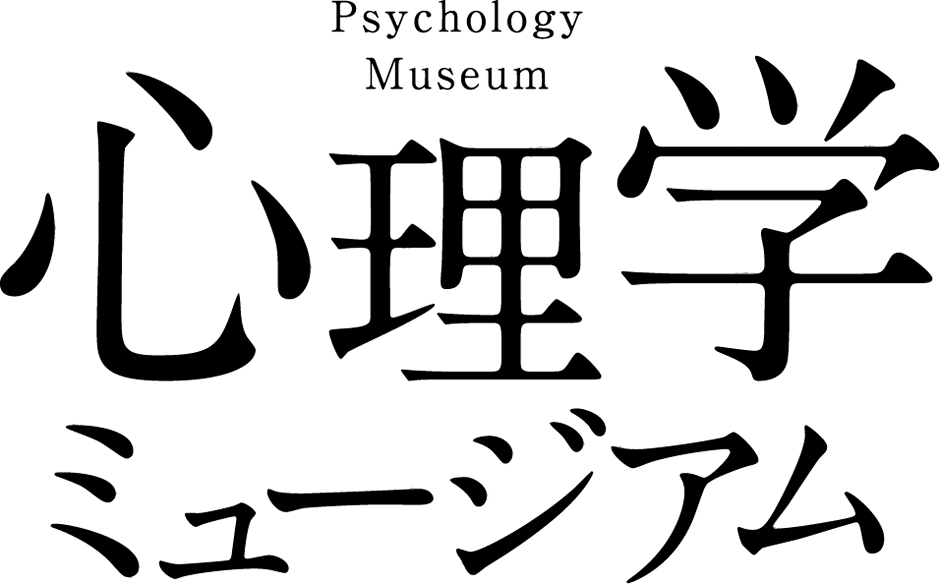今田 寛先生
動画は抜粋です。インタビュー全文は下記からご覧ください。
今田 寛先生の略歴
・関西学院大学・学部での態度教育の重要さ・アイオワ大学留学・水なめ装置開発・アイゼンクの所での在外研修・国際学会
・関西学院大学博士課程修了。1963年アイオワ大学でPhD取得。2003年関西学院大学定年退職。広島女学院大学学長。博士論文『恐怖と不安』
・心理学者の家庭で育ち、学部生の頃に心理学者としての態度教育を受けたお話、ゼミ発表でうまくいかなかった体験から、人の適応を阻む事柄に興味をもち、あがりや不安を研究テーマに選んだお話、アメリカ留学で感じた予算の格差から、独自の装置を開発して研究を進めるお話などから、研究者として試行を深めること、工夫をすることの重要さが見えてきました。
日時:2016年7月28日(木)
場所:パシフィコ横浜(ICP2016会場)
インタビュアー:鈴木朋子(横浜国立大学)、高砂美樹(東京国際大学)
場所:パシフィコ横浜(ICP2016会場)
インタビュアー(以下、「イン」と略) 本日はお忙しい中、ありがとうございます。今日は日本心理学会教育研究部会の歴史小委員会のインタビューと言うことで順にお話しを伺っていきます。最初は、心理学を学ぶに至る経緯についてです。では、まずは、心理学を始めるに至った経緯についてお話しいただければと思います。
心理学に進んだきっかけ
今田 御存じかもしれませんが、私の父・恵は関西学院大学の心理学研究室の創始者でしたので、私を含む兄弟姉妹6人は世間知らずの学者の家庭で育ちました。その結果、姉2人の配偶者を含めて誰ひとり一般のサラリーマンの道を選んだ者はなく、皆研究者あるいはそれに近い道に進みました。結果論ですが、配偶者も入れると博士号が、父の2つ、私の2つを入れると合計9つあるという変わった家庭でした。私自身も、大学を出て会社勤めをして、毎日会社に出社してという自分のイメージは全く浮かびませんでした。
私は昭和9年の生まれなので、現在に続く戦後の6・3・3・4の学制が出来た最初の新制中学1期生として、昭和22年に関西学院新制中学部に入学しました。そしてエスカレーター式に上に上がって、高等部を卒業するにあたって、大学の学部選択ということになります。当時の関西学院大学には、経済学部、商学部、法学部、文学部、神学部の5学部しかありませんでしたので選択肢は限られていました。サラリーマンが嫌なら、あれもダメこれもダメで、結局文学部しか残りません。ですから動機は恥ずかしいほどあいまいなものでした。そして文学部の中では、科学が心とドッキングしている心理学科に興味を覚えました。もし、その当時、関学に理学部があったなら、ひょっとして私は理学部へ行っていたかもしれません。けれども、今思い出してみると、私は理学部向きではなかったと思います。ちょうど心理学は、理科系と文科系とがミックスしている世界で、つまり「まあまあ」「なあなあ」の世界と、論理的で非常にきちんとした組み立てをする世界とがドッキングしているところですから、私にとっては非常によかったと思います。
実は父親の教授をしている心理学教室に入るということの大変さに気づいたのは、私が晩熟だったのか、30近くになってからなのです。大学に進む時には気づいていませんでした。別の言い方をしますと、私の父親が偉かったと思います。といいますのは、青年期独特の親への反抗が、不甲斐ないことほど起こらない人格者でした。息子の私が言うのもおかしいですが。元々父親は牧師になるつもりで関西学院の神学部に進み、卒業して牧師の資格まで取っておきながら、牧師の道を選ばないで、結果的に東大の心理学に行った人ですから、非常に円満な人格者でした。今思っても、あれほど人柄が円満な人間はざらにはいないのではないかと思うぐらい、温厚な人でした。ですから、息子でありながら父親をすごく尊敬していました。
このような事情に加えて、家庭での普段の会話にも、割に心理学的といいますか、それほど専門的ではないですけれども、人間の心や生命についてのことが、家の中に漂っていたのかもしれません。だから、子供たちは、一番上の姉が嫁いだ先は生物学者でしょう。その次の兄貴は命に関わる医者でしょう。それから3番目は牧師ですから、やはり命に関わります。そして私でしょう。また下の2人は生物科学に行きましたからね。ですから、皆、何か、生物、命・生命に関係がある道に進んだのは、家庭での父親の影響が非常にあったと思います。
それと、母親はものすごく好奇心が旺盛で、とにかく物事を納得のいくまで突き詰めなければ気が済まないたちだったのです。そういうことで、客観的でサイエンティフィックなものの考え方というもののルーツは、むしろ母親から来ていたのかもしれません。そして心理学の対象である心や生命というものに対する漠然としたあこがれのようなものは父親から来ています。ということで、私の中では、関西学院大学の高等部を卒業して大学の学部を選ぶ時に、何の抵抗もなく、すっと父親のところへ行ってしまいました。
それを後悔し始めたのは、学会活動を始めてから、いつまでたっても「今田先生の坊ちゃん」と言われることで、何か、もうどうしようもなく父親が疎ましく思える時期がありました。いつまでも「今田先生の坊ちゃん」で、父親から離れられないのです。父親は割によく知られていたので、30を過ぎてからもそう言われている有様で、「大変な道を選んだな」と思った時には遅すぎました。もっとも、それが後の私の頑張りの源になったところもありますが。親の七光りといわれるのは嫌ですから。
イン 高等学校の時などには、何か心理学の本などは読まれましたか?
今田 何も。あまり読まなかったです。エスカレーター式で受験の心配がないものですから、自治会の仕事をしたり、卒業アルバムをつくったり、そういうことに没頭していたように思います。ちょっと情けない話です。
学部生時代で受けた態度教育
イン なるほど。では、大学で初めて本格的に実験心理学に出会われて、思っていた印象と違ったりしましたか。
今田 それほど違っていたとは思いません。また抵抗もありませんでした。私の父親は、私が入った時にはすでに学院全体の行政に関わるようになっていましたから、研究室は、うちの父親の第一弟子であった古武弥正(こたけやしょう)先生が中心でした。
古武先生は非常にはっきりした先生で、いつも自分の考えを鮮明に打ち出す人でした。ご存じのように、古武先生はPavlovの条件反射を日本に定着させる基を築いた人です。その古武先生は、実験心理学、しかも条件づけを教室の運営の柱にしていました。よく古武先生がおっしゃったことは、「私学は国立大学には対抗できない。国立大学は百貨店かもしれない。私学は専門店だ。だから、うちは条件づけ・学習・条件反射でいくのだ」ということで、教育方針がはっきりしていました。
ですから、関西学院大学の教育は、条件づけを柱とした実験心理学に特化されていたように思います。これに対しては、狭すぎるという考え方があるかもしれませんが、私は心理学の学部教育というものはコンテンツ教育ではなくて、態度教育、すなわち物事の客観的な考え方、論理的な考え方を身につけることだと思うのです。不注意に結論に飛びつかない態度を身に着けることです。小さなことから大風呂敷を広げるような、何を証拠でそんな大きなことが言えるのか疑いたくなるようなことを平気で言う人もいるではないですか。そういうのと全く対極にありました。
古武先生の学部教育はそのような非常に狭い教育でした。今から思えば提供されていた学科目の幅もそれほど広くはなかったのですが、徹底した実験・実習、それから卒業論文でも必ず実験など、実験の繰り返しによって客観的な物の考え方が自然に身につくような教育方針だったと思います。いわば、宣言的知識ではなくて手続き的知識。頭の知識ではなくて体の知識として、客観的な物の考え方や、論理的な物の考え方が自然に身についたことに、私は非常に感謝しています。
コンテンツ教育、つまり中身の教育は、後から勉強できますが、態度教育というものは、最初が粗くなってしまえば、後できめを細かくしようと思っても身につかないものだと思います。やはり熱いうちに鉄は打たなければならないという、そのような思いがしました。
後に私がアメリカに留学した時に受けた教育も、その延長上にありました。アメリカには心理学の専門教育のモデルとしてボールダー・モデルというのがありますが、私の学んだアイオワ大学はまさにこのモデルにしたがった教育を行っていました。その教育方針は古武先生の方針と全く一緒で、「心理学者というものは、後に臨床心理学に進む人も、実験心理学に進む人も、まずサイエンティストでなければならない。そして、一人できっちりと実験計画ができて、きっちりと論文が書けて、パブリッシュできるような基礎教育を受けた後に、それぞれの道に進んでいくべきだ」という考え方に立ったのが、ボールダー・モデル、あるいはサイエンティスト・プラクティショナー・モデル(科学者実践家モデル)というものなのです。この精神を古武先生は先んじて教育に反映されていました。
心理学の対象は複雑ですが、このような考えと一致する教育を関西学院大学で受けたことで、複雑なことを複雑なまま放っておかないで、整理整頓して、何かしかるべきゲシュタルトといいますか、骨組みを見つけ出すという訓練が、若い時からできていたと思います。ですから、留学先で、複雑なことについてレポートを書く課題が出ると、まず情報を集め、表を作って複雑な情報を整理整頓し、そこから図柄をつかみ出す形でレポートを書いたものです。そしてその姿勢を私の留学先の教授であるK. W. Spenceは非常に高く評価してくれました。授業中でも、「この複雑なことを簡単にするには、今田に表を書いてもらおう」という冗談が出るぐらい、彼は目にかけてくれていたように思います。それには、元々持っているもの、育った家庭の影響もあるかもしれませんが、学部時代の教育というものは、大きな意味を持っていたように思います。
イン もし、覚えていらっしゃれば、学部の頃受けた一般実験なり、特殊実験なりで、何か覚えていらっしゃるエピソードなどはありますか。
今田 私は、ミュラー=リヤーの実験というものは、今でも非常に印象に残っています。ミュラー=リヤーの実験一つでも、正しい事実を導き出すためにはどうすればいいかという心理学の態度教育ができます。エラーを除外しなければいけませんので、標準刺激を左に持ってくるのが半分、右に持ってくるのが半分、比較刺激が標準刺激より短い所から始める上昇系列が半分、逆の下降系列が半分というように、カウンター・バランスをしなければいけません。これには感銘を受けました。このような空間の異方性に伴う誤差や運動誤差の他、習熟の誤差というようなことをキャンセルアウトするためのデザインを組まなければならないなど、ものすごく面白かったです。
その背景には、私の子どもの頃の体験もあります。私の家は6人きょうだいで、戦時中、物のない時代に育っただけに、例えば、カステラ1本が家に到来したとすると、6人が、皆ギラギラした目で眺めていて、大きな一切れを取ろうとしているわけです。ところが、私の母はカステラを切る時に、いつでも左が大きくなるのです。だから、母の左側に座っていた方が得だということを子どもはよく知っていて、そのつもりで待っているわけですね。そういうことが背景にあるものだから、ミュラー=リヤーの実験を学んで、「なるほど。人間を対象に実験をすると、正しさをゆがめるエラーがいろいろあるので、正しい結論に持っていくためには、いろいろ手続き上の工夫をしなければならないのだな」とすんなり理解できました。あの実験を徹底してやるだけでも、心理学の教育にとってすごく意味があると、今でも思います。
イン 今は実験演習の話でしたけれども、講義などで特に印象に残っているものは、他にございませんか。
今田 実験・実習の影響が大きかったのですが、講義は、古武先生の「心理学概論」は非常に筋が通っていて面白かったです。視力の非常に悪い先生なのですが、大きな声ですごく明快な話をなさる先生で、あの「心理学概論」は面白かったです。それと私の父・恵の「心理学史」も印象に残っています。口述筆記とそれの補足の講義を交えたものでしたが、その講義が土台になって、1962年に岩波書店から『心理学史』が出版されたことになります。私が講義を受けたのは1956年度ですから。
それと今一つ忘れられないテキストがあります。それはUnderwood のExperimental Psychology (1949)で、心理学購読演習のテキストでした。非常に説得力のある整然とした書物で、これは実験実習でやっていることを裏打ちする名著でした。もう一つの心理学購読演習では、Hilgard & Marquis(1940)のConditioning and Learningがテキストでした。3年生の時だったと思いますが、当然教室ではほんの一部しか読めません。そこで残った部分を自力で読み切りました。英語の単行本を一冊読みあげたのはその時が初めてで、非常に満足感がありました。
研究テーマを選んだきっかけ
イン はい。ありがとうございます。その後、卒業論文のテーマを選ばれたきっかけはどのようなものだったのでしょうか?
今田 先ほども言ったように、関西学院大学は、条件づけや学習の専門店でいこうという方針だったものですから、動物実験も一つの柱だったのです。
少し話はずれますが、私は父親の息子として心理学科に入ったわけですから、どうしても自意識過剰になっていたのでしょうね。ですから常に人に見られているといいますか、評価されていると意識がありました。そんなこともあってか、人相手の実験など全く想像もできませんでした。「被験者をお願いします」と言って断られるのは、どうもプライドも許さないですし。そんな中、実験実習(3年次の特殊実験)の中で一番私にとって気が楽だったのは、暗室の中で独りで白ねずみを相手に実験をしている時でした。一番心の安らぎがありました。
これは、実は、John B. Watsonも伝記の中に書いているのです。学生時代を振り返って「自分は、白ねずみと暗室の中にいる時が一番心が安らいだ」と書いています。それと同じ経験を私はしたわけです。動物実験にほれ込んだ理由の一つがここにあります。
それと、私が後に不安や恐怖などということをテーマにしたわけですが、そのきっかけの1つは、ゼミでの体験にありました。古武先生のゼミに入って3年生になるとゼミ発表があるのですが、そのゼミ発表の時に、一つの英語の論文を、これ以上読み込めないというぐらい徹底して読みました。その当時ゼロックスはないので、全部タイプライターで打つわけですね。苦労してタイプして、これ以上準備のしようがないほど準備をして発表に臨んだのですが、もう全くあがってしまいました。この頃の言葉で言えば、頭が真っ白になってしまって、もう本当に、あのときの経験は今思い出しても涙が出ます。あれほど準備していて、あれほどみじめな思いをしたのです。そして、泣きの涙でうちに帰って、ふとんをかぶって寝てしまいました。
その時に私をやっつけたのは何だったろうかと考えて、それは不安やストレスなどというものだと思いました。そして、一生かかって敵討ちをしてやろうということが、後の不安、ストレスの研究につながるわけですね。だから半ば臨床的興味があったように思います。それと、研究を「やるからには何かに役に立ちたい」という思いはありました。「あがり」は、能力がありながら能力が発揮できない状態でしょう。そのように、不安など人を生きづらくさせるもの、人の適応を阻む事柄に、私は非常に関心を持ちました。
それに、先ほど言った動物実験というものへのほれ込みがあったものですから、不安に対する興味と動物実験に対する興味とがドッキングして、不安・恐怖・ストレスに関する基礎実験をすることになったのです。けれども、うちの研究室は、学習や条件づけということで一本の柱が通っていましたから、それを、学習心理学や条件づけとドッキングさせながらやるという方向を探りました。その結果、私が一番ほれ込んだのが、アメリカの心理学者のO. H. Mowrerと、イエール大学にいたN. E.Millerなどです。私はMowrerやイエール学派といわれる人たちの、基礎と臨床を結びつける考え方に非常に興味を持ちました。学習理論のHullを中心としたイエール学派の人々は、動物で基礎実験をしているけれども、そこから出てきた不安の条件づけ研究を、将来的には精神分析学における不安、そしてその症状形成、治療に結びつけようとしました。つまり、実験だけで終わるのではなく、その実験の成果を臨床につなげようとしたのです。
私がMowrerの考え方に関心を持ったもう一つの理由は、彼の整然とした学習2過程理論です。電気ショックの到来を予想してショックの回避を行う回避学習は、恐怖の古典的条件づけと、その恐怖を動機として起こる回避行動によって恐怖が低減されることでそれが強化されると、回避学習を2過程で考えます。まず恐れることの学習・古典的条件づけ、そして恐れに基づく学習・道具的条件づけ、それが見事にドッキングした考え方で、その考えを応用することによって、人間の強迫神経症の症状などが見事に説明できように思えたので、私はMowrerの考え方に非常に魅せられました。また自分の体験からも共感できました。
従って、私は古武先生の下で条件づけ・学習の研究はしたけれども、常にその応用といいますか、臨床とのつながりのようなものを意識しながらやっていました。それの元になったのが「あがり」で、そのためにとんでもない悔しい目に遭った経験です。このような生存にとって不都合な問題を何とかして自分自身で解決したいという思いが、ずっと長い研究生活をリードしてきたように思います。
言い忘れましたが、卒論のテーマは「マイヤーのフラストレーション理論に関する実験的研究」でした。
イン ちなみに、先生が学部のときには、もうすでにラットが飼われていたわけですね。
今田 はい。関学の研究室では、昭和17年ぐらいに、すでにラットを飼っていました。
イン どこから入手されていましたか?
今田 『関西学院大学心理学研究室80年史』に書いたかもしれませんが、ラットの研究が始められたのは私の代より大分前のことなのです。私たちの代には、もうすでに、大阪大学の医学部とつながりのあるラットの業者がいました。ラットの販売業者がいて、そこでたいてい買っていました。その当時のラットの飼育状態は臭かったですね。今は自動洗浄で臭気も全部抜けますし、うそのようです。当時は、戦後まだ間もない頃だったので、臭い動物室の横で昼食を食べていました。そのような時代でした。
回避行動の消去困難さの研究へ
イン 修士でも動物実験を続けられて、修士論文も、「回避行動の罰の効果」ですね。
今田 はい。修士論文も、正常・異常や、適応などというものに関係のある研究でした。回避反応の消去過程に関する実験でした。回避反応の一つの特徴は、一旦形成されるとなかなか消えない、消去されないということです。したがってこのなかなか消えない回避反応の消去を促す条件を探れば、これは不安神経症や強迫神経症の症状の治療にもつながるのではないかという思いがありました。そこで修士論文では、シャトル・ボックス(同じつくりの2部屋の間を移動することでショックから逃避・回避できるボックス)を用いて、隣室への移動回避行動をまず形成しました。具体的には光が点灯し10秒後に床からショックが与えられますが、隣室に移動すればショックから逃避できますし、点灯から10秒以内に移動すればショックを回避できるという手続きです。そのような手続きで形成された回避反応の消去過程では、移動しなくてもショックが来ないようにするわけですが、それでもいつまでも移動し続けて消去しないのです。そこで消去を促進するために、隣室に移動すれば、そこで一瞬の罰を与えました。そうするときっと隣室への移動はやめるだろうと考えて。そして隣室で与える罰の強度をいろいろ変化させてみました。
結果的に分かったことは、隣の部屋で与える罰が強ければ強いほど、かえって回避反応は長続きして、しかもその罰せられる部屋に対して激しく、しかも速く飛び込むということが分かりました。つまり、回避反応に対する罰の逆説的効果というような現象が見られたのです。今でも、強い罰に向かって激しく飛び込むあのマゾヒズム的というか自虐的な激しい行動が目に浮かびます。それを私はMowrerの学習2過程説で説明を試みました。
ちょっと余談になりますが、実は隣の部屋へ飛び込む行動の激しさを何とか測定したいと思って、部屋の床の蹴りの強さを測りました。まず部屋の床の四隅に、フィルムの空き缶の上にゴム膜を張って、それで床を支え、移動時のねずみの床の蹴りの強さを4つのフィルム缶膜面の沈みでとらえました。4か所から押し出された空気は、ゴムホースで集められ、それを別の缶のゴムの膜面の膨れでとらえ、膜面に取り付けられたペンの振れで記録用紙に行動の激しさとして記録したのです。そういう装置を全部自分で作っていたわけですから、実験には非常に愛着がありました。強い罰に向かってネズミが大きく床を蹴れば、自分が作った装置の大きな針の振れとして目の前ですぐにフィードバックされるわけですから感激でした。その論文が、私の処女作となりました(Imada, H. (1959). The effects of punishment on avoidance behavior. Japanese Psychological Research, 8, 23-38.)。
イン 先生が学生の頃の研究と今の研究で違うところは何でしょうか?
今田 昔の研究は手間とエネルギーが要ったということではないでしょうか。論文一つ読むにも、ゼロックスなどないわけですから、いちいち自分でタイプしなければなりません。実験もそうです。装置などは全部手作りでした。そして手間をかけた分だけ、汗をかいた分だけ研究に愛着がわいたように思います。この頃はゼロックスもありますし、機器も大抵は業者から購入できます。やっかみかもしれませんが、こんなことで研究への愛着がわくのかなと思う時があります。
アイオワ大学への留学
イン その後、先生はアメリカへ留学されるのですが、留学にまつわるお話しをうかがえませんか?
今田 私が留学したのは1961年、ドクターの3年生の時でした。実は私自身はその時に留学は全く考えていなかったのですが、ある時、古武先生が私の部屋(私は当時専任助手でした)に来られて、バイオリニストのお嬢さんのためにフルブライトの留学試験の願書を取り寄せたけれども、結婚が決まったので願書が要らなくなった。「君、受けてみんか」と言われるのです。言われるままに、もらった願書で受験したところ、うまくいって留学ということになったのです。古武先生のお膳立てによる偶然で、全く他動的でした。
イン すごく不思議なエピソードですね。
今田 ええ、不思議ですね。後でお話ししますが、私の意思でなく人の言われるままに動いてそれが私の人生に大きな影響を与えたこれに似た例が他にもあります。
さて留学先ですが、試験にパスした後、父親は私にこう言いました。「寛、もしアメリカへ留学するんだったら、田舎の小さな大学町を選んだ方がいいよ」と。そして大学よりも人を選べとも。そこで私が選んだのは中西部のアイオワ大学でした。そこにはJudson Brownという人がいて、O. H. Mowrerなどと同じように異常行動と不安とを結びつけた研究をしていました。私はその人の下で勉強したかったのですが、アイオワに行くと、Brownは西海岸に移ってしまっていました。私にすれば空振りです。しかし、そこには学習理論のC.L.Hullの高弟、K.W. Spenceがいました。実は古武先生は私をSpenceの所で学ばせたかったようです。第一目標にしていたBrownはいませんでしたが、結果的にSpenceの下で、徹底した厳しい大学院のコース・ワークを受けたことは、私にとって非常によかったと思います。空振りという偶然が生んだ幸運でした。
実はアイオワで学位を取るようになったのも、Spenceの「おまえは自分のところで学位を取って帰るべきだ」という鶴の一声の結果でした。ある時提出した論文が非常に高い評価を受けたのがきっかけで、半ば強制でした。私はすでにその時関学の専任助手でしたもので、「そんな長くは滞在できない」と言いますと、「これまで関学の大学院でとった単位を送ってもらえ」と言われ、言われるままに取り寄せた結果、かなりの単位が認定され、語学試験、総合試験、博士論文にパスすれば短期でも学位をとれる目途が立ちました。その後は死にもの狂いでしたが、幸い難関を乗り越え、結果的にPh.D.を取って帰ることになりました。
古武、Spenceという、今ではお目にかかることの出来ない2人のビッグ・ボスによって私の人生は大きく変わったわけです。
イン 先生がアイオワにいらっしゃっている頃のお写真を、原一雄先生がお持ちでした。
今田 それは、大学の視察で原先生が視察団全体の世話役で、他の役職者に同伴してアメリカの諸大学を回っておられた時のことです。その視察団の中に私の父もおりました。原先生にお会いしたのはアイオワではなく、スタンフォードだったと思います。私をアイオワに訪ねてきてくださったのは同じICUでも星野命先生でした。先生は、アイオワ大学に留学されていたので、私がいる時にたまたま来てくださって、そして私のおんぼろ車でシカゴへ一緒に行ったことを覚えています。だから、ICUの先生方とは、そのようなつながりがありました。
実は、私は高等学校の3年生の時、私の父親と縁が深かったようなので、「寛、ICUを受験してみんか」と言われたことがあります。もし、私が行っていればICUの1期生になっていたはずです。父には「1期生というのはいいよ、行かないか」と言われたのですが、受験勉強も全くしていませんでしたし、結局私は行きませんでしたが、もし行っていれば、また別の人生になっていただろうと思います。
しかし、面白いことに、フルブライトでアメリカに行く時に、ハワイでの1ヶ月にわたるオリエンテーションがあったのですが、その間、何か気心が通じ合い、一番親しくなったのはICUの卒業生でした。心理学関係の人はいませんでしたが、1期生が何人かいたもので面白い偶然を感じました。
イン アイオワでは、日本から留学に来ている人のコミュニティのようなものがあって、お互いにどこにいるかということは、少しは連絡などがあったのですか。
今田 アイオワというところはド田舎でしたから、日本人はそれほど多くはなかったのですが、東海岸の大学には日本人はある程度おられてコミュニティもあったのかも知れません。しかし私は外に目を向けるほどゆとりもありませんでしたし、今のようにメールのある時代ではなかったので、他大学の方々と交流があったわけではありません。当時コロンビアにおれらた秋田宗平さんから、留学生のネットワークを作ろうという呼びかけの通信をもらったことがあるのですが、私はそれどころではありませんでした。
イン アイオワ大学の心理学の学習の研究室以外のところはご存じでしたか。
今田 アイオワには日本人は何人かおられました。理学部にもいましたし、ジャーナリズムにもいましたね。記憶ははっきりしませんが、アイオワはcreative writingが有名だったように思います。また吃音の研究で非常に有名なWendell Johnsonという先生がおられ、日本からも何人か行っていたようです。私のフルブライトの同期でも内須川さんがおられました。
イン アイオワといえば、Lewinが行っていたところですね。
今田 Lewinがいたのは、アイオワでも心理学プロパーではなく、Child Welfareという児童福祉系の心理学の部門でした。Child Welfareの方には、小橋川慧さんという沖縄から来ておられた発達心理の方がおられました。その後カナダにずっととどまって、今でもカナダにおられます。当時は、心理学はEast Hallという建物の中にあったのですが、小橋川さんは同じ建物の別のウィングにおられたので、よく行き来がありました。ご家族とも随分親しくさせていただき今でも交流が続いています。
イン Spenceのところは、結果的に、先生だけしか日本人は行かなかったのでしょうか。
今田 私はコンディショニングだから、Spenceの直系なのですが、アイオワ大学の心理学全体で言うと星野先生が私の前に行っておられましたし、沖縄の東江先生ご兄弟もおられたようです。私の後のことはよく知りません。Child Welfareの方まで入れるとどうなのかはよく分かりません。
イン ありがとうございました。それで、日本に帰っていらっしゃってから、当時のアメリカの状況と日本の状況を比べて、感じられたことなどはありますか。
日米の研究予算の格差から水なめ装置を考案
今田 とにかく今から半世紀以上も前の1961~1963年ですから、日本は貧しく、アメリカは大きくて豊かな国で、その差は歴然としていました。研究の面でも、アメリカは、リサーチ・アシスタントなどを使って、また、実験機器の使用も進んでいましたから、実験をやるにしてもデータの生産性という意味ではアメリカと日本では比べものになりません。そこで私は、アメリカ人と勝負するのに、独りで暗室にこもって、シコシコと少しずつデータを積み上げていくようなやり方をしていては、なかなか追いつけないと思い、何かデータを量産できる方法はないだろうかということを考えました。
つまり、リサーチ・アシスタントのように自由に自分の研究をやってもらえるような人もいないわけですから、何とかしてもう少し効率のいい研究の仕方がないだろうかと考えたのです。その結果、貧者の知恵で「水なめ装置」というものを考案しました。
私のこの装置は、のどが渇いたねずみを箱の中に入れて、箱の端っこにある穴からチューブの先端をペロペロなめるという行動をさせるものです。1日1時間ぐらいしか水を与えないのどが渇いたねずみの場合は、よく馴れさせると、大体5分間ぐらい立て続けに1秒に5~7回ぐらいのペースでペロペロと水をなめるのです。
私は実は、Spenceの学習理論との関係で水なめ装置を考案したのですが、その水をなめる行動というものをベースにして、私の本来の不安の研究、恐怖の条件づけの研究ができるのではないかと思いました。何かといいますと、要するに、水をなめる行動は平和な営みです。恐ろしい時には、人でも動物でも、食べたり飲んだりする行動は抑えられます。だから安定した水なめの行動をまずつけておいて、その後、ピーッと5秒間音を呈示して、最後にショックを与える恐怖の古典的条件づけの手続きをそれに重ねます。すると危険信号の5秒の間の水なめがぴたりと抑制されます。そして、それが終わると、また、パパパッと飲み始めます。そういうことで、恐怖の条件づけの研究を、水なめ行動をベースラインとしてできることを、私はすでにアメリカの学位論文実験の時にも確かめていました。
けれども、1回に1匹ということでは能率が悪いので、最終的に6匹を同時に実験できる工夫をしたのです。のどの乾いたネズミ6匹を入れて一斉に飲ませると、隣室の操作室の電磁石のカウンターが一斉に動き出します。昔は、コンピューターがなかったのですごい音でした。ところが危険信号の音が鳴るとそれがピシャッと止まり、デッド・サイレンスが訪れます。そしてそれが済むと、またガチャガチャガチャ。このフィードバックが実験者にはすごい強化でした。だから、その後に、リレーがサイレント・リレーになり、コンピューター化されてもすごく物足りなさを感じました。昔の機械はフィードバックがすごかったので実験者には張り合いがありました。あの感激は忘れられません。
その装置を使って、1回に6匹できるということは、アメリカの生産性に近いわけでしょう。それで5分間やれば、5分で一丁上がりです。それを5回繰り返すと、30匹で、10匹・10匹・10匹で3群実験ができるのです。そういうことで、ものすごく仕事の能率化ができました。
そのきっかけは、やはりアメリカで刺激を受けたことにあります。彼らと対等の勝負をするための方法を編み出したわけです。
そういうことで水なめの装置というものを作り出して、その装置を使ってずっと一生やってきました。今はもう使われていないかもしれませんが、私の研究室の一つの目玉でした。また水なめの装置を使ったことの副産物で、私の研究は次の転機を迎えます。
ITI中の行動の研究へ―発想の図地反転―
今田 ラットの水なめ行動をベースラインにした恐怖の条件づけの研究は、このような経緯で始めたのですが、この実験は本来スキナーボックスを使って行われているモノでした。VIスケジュール等に設定しておくと、比較的安定してコンスタントにレバーを押し続ける行動が形成されます。その上に恐怖の条件づけの手続きを重ねると、水なめの場合と同様に、その恐怖によって進行中のレバー押し行動が抑制されるようになります。本来は、こちらの方が一般的な方法だったのですが、当時は、幸か不幸か、スキナーボックスなど買うお金がありませんでした。スキナーボックスの場合には、エサのペレットも結構高価でした。そこで私は、アメリカで使っていた水なめ装置を使うことに思いつきました。水なめ装置は手作りのボックスにチューブをつなげば、ものすごく安価に自作できます。消耗品も水道水だけです。ですから、これに行き着いたのは、貧乏であったことによる幸いがありました。
しかもスキナーボックスのレバー押しにくらべると、水なめ行動は1秒間に5回から7回ぐらいペロペロとなめるものですから、いわば測定の目盛が細かいと言えます。ある時に学会でスキナーボックスを使っている人に、なぜ水なめの装置を使っているかと聞かれて、「ミリメートル単位の物差しを使っているのだ」と答えたことがあります。短時間に細かくデータが取れるのですね。
しかし水なめ行動をベースラインにすると泣き所もありました。水なめ行動はスキナーボックスのレバー押しに比べると、ショックの導入によって乱されやすい特徴があります。つまりパブロフの言葉をつかうと外制止をうけやすい敏感なところがあります。これが、また私に幸いしました。といいますのは、例えば、水なめ行動を安定させると、大体5分間に1,500回から、場合によっては、1,800回ぐらい、ペロペロとなめるのですが、条件づけの初期に、信号を与えてショックを与えると、しばらく水なめ行動が全体的にバタッと止まってしまいます。それが回復するのは、信号のない時は安全で、信号のある時は危険だという弁別ができるようになってからで、ラットは信号のない時は安定して水を飲み、信号が来た時にだけピタッと抑制されるとようになります。それでもって恐怖の条件づけの研究ができるのです。
つまり水なめ行動を用いて恐怖の条件づけの研究を行うためには、恐怖によって押さえられるべきベースラインがまずなければ行えません。したがってベースラインがなくなってしまうということは恐怖の条件づけの研究にとっては致命傷です。しかしこの事実を見て、まったく別の観点からの研究を思いつきました。
恐怖の条件づけの結果、恐れるべきものを的確に恐れることは、ごくごく自然なことです。ですから、ショックの到来を告げる光が来ると水なめ行動をやめるということは、ごく当たり前のことです。しかし私のもともとの関心は、あがりのように生存にとって不都合な出来事の研究にあったもので、恐怖・不安の研究でもこのような当たり前の現象よりも、もっと当たり前でない、例えば恐れる必要のない時にもビクビクし続けるような状態に関心があったもので、このベースライン全体が乱されてしまう事実そのものを非常に興味深く思い、これを手掛りに新しい、私の本来の関心の研究への道が開けないかと思いました。
条件づけの言葉で言えば、CS(音)- US(ショック)を対呈示した結果、音を怖がるようになるのは正常ですが、それ以外の試行間隔(ITI)中にも恐れ続けるのは不都合で正常ではありません。そこで私は、条件づけの研究の本道から離れて、CS中のことは十分研究されてきたからもういい。むしろITI中の行動に注目して、それを従属変数にした研究をすれば、「恐れる必要のない時にもビクビクし続ける行動の研究」、つまり慢性的不安の研究ができるのではないかと考えました。これまでの条件づけ研究ではCS中の行動が「図」で、ITI中のことは「地」ですから誰も注目しませんでした。私はこれまで「地」として、いわばゴミ箱行きの事実をむしろ「図」とする、図地反転の発想で研究を展開しようと思ったわけです。
そのようなヒントが得られたのは、貧乏だったためにスキナーボックスが買えず、外部刺激に非常に敏感な水なめ行動をベースラインにしたことからです。何が幸いするか分かりません。
もう少し幅を広げて、1960年代から70年代にかけての私のスタンスを申しますと、私は学習心理学や条件づけの研究に従事しながら、何となく満たされないものを感じていました。それは簡単にいうとブツ切り主義とでも言うべきものに対する不満でした。私は学習心理学を、広く生活体の環境への適応過程の研究として関心をもっていたもので、条件づけの実験で、CSに対して起こる反応だけを切り取って問題にするブツ切り主義がどうも気に入りませんでした。生活体はCS中もCSのない時もずっと生存・存在し続けているにもかかわらず、まるでCS中以外には生活体は存在していないかのような研究姿勢にどうも満足できませんでした。私はむしろ環境全体に対するトータルとしての生活体の適応に関心があったもので、‘行動の流れ’というか、‘情動の流れ’というものを問題にしたかったのです。学習心理学へのこのような当時の不満が、上のような研究姿勢の転換の背後にありました。
これはいわば実験における従属変数側への私の不満でしたが、実は私は学習心理学研究における独立変数側にも不満がありました。条件づけ研究ではCSやUSや、それらの時間的関係のような物理的変数(強さ、長さ、時間)を操作して、それらの効果についてのパラメトリックな研究を行うことが主流でした。不満というのは、心理学者であればどうして物理的変数でなく、心理的変数を独立従属変数側にもってこないのかということでした。物理的変数を恒常に保ちながら心理的変数を操作してその効果を見ることこそ、心理学者が関心をもつべきことではないかという不満でした。
日常経験からの発想
そこで実験室を離れて、人や動物を慢性的・持続的に(つまりITI中も)ストレスフルにさせる心理的変数はないかといろいろ考えました。また私自身の経験の中にこれに関係のありそうな経験はないものかと、記憶の糸を探りました。そして2つのことに思い当たりました。
一つは戦時中の経験です。私の小学校(当時は国民学校)時代は太平洋戦争と重なります。私は大阪と神戸という大きな町の中間の西宮に住んでいたので、また近くの現在の阪神競馬場のところに川西航空機という軍需工場があったもので、戦争も末期になるとよくB29の爆撃を受けました。そしてB29の襲来は必ず警戒警報と空襲警報という2段階の警報によって予告されました。思い出してみますと、あの時もし警報がなければどうだったろうか。敵機の飛来を気にして四六時中空を眺めていたのではないか。警報はあろうがなかろうが爆弾が落ちる時には落ちるのです。つまり物理的経験は変わらないのですが、警報のあるなしは人の慢性的不安を大きく左右します。これがまさに私が物理的変数を恒常にして心理的変数を操作することにあたります。つまり心理的変数とは、危険(爆弾・ショック)の予測可能性・不可能性という変数です。これが私のねずみの水なめ行動を用いた実験的研究の大きなテーマの一つになります。
今一つ、思い当たったストレスがらみの心理的変数がありました。それは対処可能性・不可能性という心理的変数です。実は私は大の注射ぎらいでした。ですから注射をせざるを得ないときには、二の腕の内側をあざが残るほど思いっきりつねるのです。痛いので顔をしかめながら。これは、どうすることもできない(対処不可能)な注射の痛み刺激よりも、自分でコントロールできる(対処可能な)はるかに痛いつねりの痛みの方がましだということなのです。つまりストレスは痛み刺激の物理量によって決まるのではなく、対処可能性・不可能性という心理的変数によって大きく左右されるのです。
蛇足かもしれませんが、中学校の時の英語のクラスを思い出してみてください。ある先生は、生徒に当てる時に出席簿順とか席順で当てますが、別の先生はまったくランダムに当てるとします。当たる時には当たるので、いわば物理的条件は同じですが、両先生のクラスの緊張度はかなり違うでしょう。また授業に予習をして臨んだ場合と、予習しないで臨んだ場合の緊張度も想像してみてください。予習しないで当たると対処不可能なので、できるだけ当てられないようにビクビクして頭を低くしているのではないでしょうか。
私は長年動物実験に携わってきましたので、まるで、象牙の塔にこもった現実知らずの研究者のように思われるかもしれませんが、いまお話ししたように、私の研究の発想のきっかけは必ず日常経験にあったと思います。きっかけからして「あがり」ですし、そして予測可能性・不可能性や対処可能性・不可能性という心理変数も日常経験から来たもので、そのような問題を動物実験で再現しようとして研究が展開されてきたのです。
異常行動研究会の創設
イン 先生は、動物の実験の研究をジャーナルや学会で報告されると同時に、ご著書では実験神経症の話や、フラストレーション、人間の嫌悪刺激による行動療法など人間の臨床に密接に関わることについてもまとめられていますね。
今田 そうですね。この話をすればまた長くなりますが、私は1961年にアメリカに行ったのですが、1959年に北大で日本心理学会があった時に、上智の平井さんや、早稲田の春木さんや、同志社の松山先生、それから、慶応でいいますと梅津耕作さんなど、当時、回避学習をしている人たちが多くいて、回避についての一つのセッションで集まっていたことがあります。その回避学習に関心を持っている人の中には、MowrerやMillerなどの考えと似たように、臨床と実験とを結びつけて異常行動を研究することに関心を持っている人たちが多くいて、そのセッションが終わった後に、北海道大学の芝生の上で集まって、会を作ろうではないかということで作ったのが、その当時の「異常行動研究会」(現在の行動科学学会)です。
偶然のことですけれども、参加者は私学ばかりでした。そしてその4大学を中心にした異常行動研究会というものができました。あがりのこともあって、私はそのような研究に人一倍関心を強く持っていて、私より少し上の先輩としてが、松山義則先生がおられて、同じく関西であるということもあってか、松山先生はことあるごとに私を引っ張り出してくださいました。東大出版会の『異常心理学』でも、神経症の話やフラストレーションの話を松山先生に依頼されて書きました。だから、私の駆け出し時代に松山先生に負うところがものすごく多いです。私を引き立てて下さったといいますか。
その異常行動研究会が行動科学学会に名前を変えたのは、異常行動研究会という名前のビラを張って、ホテルなどで会合をしていると、側を通る人は皆笑うのだそうです。そこで、この名前を何とかしてくれないかと言われて変わった経緯があります。
イン そのような内容も含めて、恐怖と不安ということで博士論文を、二つめの博士号ですけれども、関学で取られたということですね。
今田 その通りです。私は既にPh.D.をもっていたので、日本の学位はいらないと思っていたのですが、父に、「日本では、日本の学位もとっておいた方がいいよ」と言われたもので、『恐怖と不安』(1975、誠信書房)でとりました。残念ながら父が1970年に亡くなっていたので間に合いませんでしたが。
イン 水なめの話は、元々動物が持っている種に特異的な行動の話の後から来たのですか。
今田 いや、水なめ行動は、実は、フラストレーション研究で有名なA.Amselが初期の研究でアイオワで使っていたのです。ただAmselは条件づけがらみの実験です。しかしそういう背景があったので、私は学位論文を書くに当たって水なめ行動に着目しましたし、またそれを帰国後も使ったのです。したがって後に学習心理学で話題になる、種に特異的な行動(species-specific behavior)の問題とは全く関係ありません。
ロンドンへの留学
イン ありがとうございます。少し話が変わりますが、2度目の留学で、ロンドンに行かれていますけれども、そのことに関して、印象に残っていることなどありますか?
今田 2回目の留学は、ロンドン大学の精神医学研究所に行きました。ブリティッシュ・カウンシルの留学制度によるポスドク留学で1968年のことです。ご存じのように、ロンドン大学の精神医学研究所には、Hans Jurgen Eysenckがいたのですが、ここに行った理由は二つあります。
一つは行動療法です。先ほど言った、異常行動研究会の目玉の一つは、条件づけ・学習心理学の原理を臨床的に応用する行動療法でした。そしてその行動療法のメッカがEysenckのところでした。特に、Eysenckは行動療法についての本を書いていて、それを異常行動研究会の連中が手分けして1965年に翻訳したといういきさつもありました。したがって実験的な研究、基礎研究の臨床的応用としての行動療法というものを、目の当たりにしたいということが一つありました。
もう一つは、Eysenckのところに、特別なねずみがいたのです。私は、「あがり」というものの研究に関心を持った当初から、その不安やストレスに対する個人差というものにとても関心をもっていました。それはなぜかというと、3年生の時に、初めてゼミ発表をした時に、私以外にもう一人、ラグビー部の男が発表したのですが、私は彼のために全部英語を訳してあげました。彼はラグビーが忙しくてほとんど勉強していなかったのですが、私があがってメロメロになってしまったのと対照的に、彼は、私の訳を基にして、堂々たる発表をしました。その時に、ストレスに対する弱さ・強さというものには、個人差があることを強く思い、関心をもったのです。加えて、動物実験をしていると、実験では条件単位で平均値を算出しますが、特に回避学習など嫌悪刺激を使う実験では、ものすごく標準偏差が大きい高いのです。1個の値で代表させるということに無理があると思うことが多々ありました。そこで、そのようなばらつきの原因の個人差にすごく関心をもちました。
私が関心をもったラットの個体差は、情動性(emotionality)と呼ばれるもので、人間で言えば、不安度の個人差と呼ばれるものです。私は、常々、何とかして、ラットの情動性における個体差というものを測定し、人間でいうならば不安尺度のようなものを作りたい、そうすると、それによって前もって選別すれば、標準偏差が小さいグラフが描けるだろうと考えていたのです。私は、情動性の研究を筑波(当時は東京教育大)の藤田統さんたちと連絡を取りながら、いろいろやっていたのですが、むなしい努力が続いていました。ラットの情動性は、新規な場面での移動の少なさや排せつの頻度がインデックスなので、それを使って情動性の区別をしようとしていたのですけれども、その手の研究はすべて実りませんでした。
そういうことを考えていたところに、Eysenckのところに、情動性の高い系統のラット、情動性の低い系統のラットを、インブリーディング(選択交配)で、つまり、ある物差しで測った情動性の高い、あるいは低い個体同士どうしの雄と雌をかけ合わせて(選択交配させて)、遺伝的に高情動性系、低情動系のラットを作っていることを知りました。Eysenckはパーソナリティの研究者ですから、パーソナリティの研究の一助として、その基礎研究をやっていたわけです。そしてそのラットを使った研究をすれば、情動性というものの研究に糸口がつかめるかもしれないということで、半分の目的は、そのラットを使った動物実験をするために行ったのです。そこでやった動物実験は論文になっています(Imada,H.(1972).Emotional reactivity and conditionability in four strains of rats.
Journal of Comparative and Physiological Psychology, 79.474-480.)。当時は外国の雑誌に投稿する人はあまりいませんでしたので、このように外国の雑誌に投稿することに先鞭をつけた一人は、私だったように思います。
ただ、最初にその二つの系統のラットを見た時に私はがっかりしました。なぜかといいますと、高情動のラットと低情動のラットは、体のサイズが全然違うのです。高情動のものは大きいのです。低情動のものは小さくてちょこちょこと動くのです。選択交配をしているので、体重の違いが出てしまっていたのです。行動実験をする人間にしてみると、これはものすごく不都合です。例えば、隣室に移動するような回避行動の場合、大きさが違うと移動時間の違いを測っても意味がないわけです。
その点、水なめ行動というものは、舌の先だけ動かせばいいわけです。箱の中でじっとしていて舌の先だけ動かすわけですから体重の違いは問題になりませんので、それは非常にうまくいきました。
イギリスでは、関学でやっていたように何箱も使えませんでしたが、それでも四つぐらいは作ってくれました。イギリスには専用の職人がいて、何か装置が要るといえば、自分で作るのは許されませんでした。専門の人にあれこれと図面を書いてやってもらうのですが、作る人とやる人とは別々なので、小回りが全然効きませんでした。
私はイギリスではあまり生産的ではありませんでした。まず、第一に、イギリスは動物愛護の国ですから、動物実験するのに、特にショックなどを与えるといいますと、これにはライセンスがいるのです。許可証は簡単に発行してもらえず、医学部の医者に面接まで受けに行きました。実験内容を説明してやっと実験ができるようになるのに3か月待ちました。それから、装置を注文しました。だから、結果的には、1年弱で1個しか実験ができませんでした。
ただ、結果は、彼らを満足させるような結果になりました。高情動のものは非常に情動的で、低情動のものは非常に非情動的であるという結果がきちんと出ました。水なめの行動の抑制が、同じ条件であるにもかかわらず、高情動のものはピタッとやめるし、低情動のものはたくさんなめるしという結果でしたし、また標準偏差も、コントロールに使った他の二つの系統のラットに比べて小さいものでした。
Eysenckはイギリスに来る前、ドイツのジュニアでテニス選手でして、チャンピオンまでは行かなかったけれども、かなりいいところまで行ったというテニス好きでした。それで、私がイギリスに滞在中彼とはテニスをしました。またEysenckが行動療法学会の講演で日本に来た時には、関学でもテニスをしました。Eysenckとテニスをした心理学者は、私だけではないでしょうか。『関西学院大学心理学研究室80年史』に写真が出ています。
イン どのような感じの人なのですか。要するに、書いている物を読んでいると、割と当時は、いろいろと論争的な印象ですが、実際の人物としては、どのような感じのかたですか。
今田 印象は正反対です。非常に表現は穏やかで、大きな声で話さないし、英国紳士という感じです。けれども、もう自信の塊ですね。自分は偉いのだということは確信していました。そのような人です。けれども、それは、鼻につくような威張り方ではないです。彼はものすごくたくさん物を書いているでしょう。いつでもオフィスで、時には立ち上がって歩きながら話し、それを秘書が書き取る、いわゆる口述筆記による執筆です。
イン ありがとうございます。すこし話が変わりますが、先生は多くの学会でも役員をされています。差し支えない範囲で、印象に残っていることを教えていただけますか?
今田 学会は、異常行動研究会という会を作って、それは今でも行動科学学会として存続しています。他にも日本心理学会、日本動物心理学会、日本基礎心理学会の理事をしたり、編集委員もしましたけれども、学会活動で忘れられないのは国際学会との関わりです。私は基礎研究者なので、あまり実質的でない国際学会は嫌いで避けていました。
ところが1990年に、阪大の三隅二不二先生が中心になって、国際応用心理学会を京都で開催することになって、近くの大学だからということで動員されました。そして、1990年の大会時は開会式の司会までやらされることになりました。私は割に英語は不自由しない方ですから、あまり苦にはならなかったのですが、その司会でにわかに脚光を浴びてしまいました。国際心理科学連合IUPsySという組織で日本からの理事をされていた東洋(あずま ひろし)先生が、ちょうどその年で退任で、後任を探しておられたところへ、私がステージに現れたものですから、「おまえは俺の後をやれ」ということになって、初めて92年のブラッセルの国際心理学会に行き、選挙で理事に選出されました。
私はほどほどに社交的ですし、言葉も割に不自由しないほうだから、12年間の理事の間には随分いろいろな人と知り合って、よい経験になりました。だから、私の国際との関わりも、三隅先生というボスの一声で決まってしまったようなところがあります。これも他動です。古武、Spenceに続く三つ目です。
実は、今思い出しますと四つ目がありました。そのボスは私の家内です。1970年代のことですが、関西外国語大学というところから、留学生を相手に「日本人の心理」の講義を担当してほしいと依頼がありました。しかし実験心理の私がそんな講義が出来るわけがありません。こんなテーマは本来社会心理学者の領域のものですが、英語での講義ということで誰にでもできるというわけにはいかず、私に目をつけたようなのです。依頼主の元関学の先生は、それでも何度も頼んで来たのですが、その都度断っていました。ところが私が留守中に家内が勝手に引き受けてしまったのです。かねがね、ねずみ相手の実験心理学者の私の狭い視野を何とか広げたいと思っていたようで、これで私は抜き差しならぬ状態になりました。結局、引き受けざるを得なくなったのですが、随分勉強をしたこともあってか、幸いJapanese Psychologyと題したその講義は大変好評で、後に関学でも国際プログラムが始まったときにも担当したので、15年近く続けたと思います。これは私の大きな財産になり、後に大学行政に関わって挨拶や講演の機会が増えたときに、大変役に立ちました。家内が引き受けてしまったときにはパニックでしたが、これも大ボスの圧力がよい結果につながった四つ目の例です。
しかし、私は、今思うのですけれども、あまり目的論になってもいけませんが、すべて、世の中に意味がないことはないと思っています。逆に言えば、すべての事を意味あらしめるように行動してきたといえるかもしれません。「そのことがその時に起こったのは、絶対、何か私の人生において意味があるに違いない、それならば、それを生かそうではないか」という思いが私の中にあり、いやいやすることはありませんでした。
また、何かを始めれば、手抜きのできない性質ですから、一生懸命にやります。そうすると、深みにはまるということになってしまうのです。もっとも国際心理学会関係の仕事が、現役バリバリの時であれば仕事を犠牲にしなくてはならなかったと思います。しかし、1990年頃には、もう私は文学部長もしていましたし、随分、大学の行政との関わりがあり、95年からは学長にも選ばれ、心理学とは疎遠になっていた時代でしたので、ある意味ではよかったと思います。視野も広がったし、学校の行政をするについても、それらの経験はプラスでこそあれ、マイナスではなかったと思います。だから、私の人生を振り返ると、すべて神様はよきに計らってくださったなという感じがします。
イン ありがとうございました。
心理学に進んだきっかけ
今田 御存じかもしれませんが、私の父・恵は関西学院大学の心理学研究室の創始者でしたので、私を含む兄弟姉妹6人は世間知らずの学者の家庭で育ちました。その結果、姉2人の配偶者を含めて誰ひとり一般のサラリーマンの道を選んだ者はなく、皆研究者あるいはそれに近い道に進みました。結果論ですが、配偶者も入れると博士号が、父の2つ、私の2つを入れると合計9つあるという変わった家庭でした。私自身も、大学を出て会社勤めをして、毎日会社に出社してという自分のイメージは全く浮かびませんでした。
私は昭和9年の生まれなので、現在に続く戦後の6・3・3・4の学制が出来た最初の新制中学1期生として、昭和22年に関西学院新制中学部に入学しました。そしてエスカレーター式に上に上がって、高等部を卒業するにあたって、大学の学部選択ということになります。当時の関西学院大学には、経済学部、商学部、法学部、文学部、神学部の5学部しかありませんでしたので選択肢は限られていました。サラリーマンが嫌なら、あれもダメこれもダメで、結局文学部しか残りません。ですから動機は恥ずかしいほどあいまいなものでした。そして文学部の中では、科学が心とドッキングしている心理学科に興味を覚えました。もし、その当時、関学に理学部があったなら、ひょっとして私は理学部へ行っていたかもしれません。けれども、今思い出してみると、私は理学部向きではなかったと思います。ちょうど心理学は、理科系と文科系とがミックスしている世界で、つまり「まあまあ」「なあなあ」の世界と、論理的で非常にきちんとした組み立てをする世界とがドッキングしているところですから、私にとっては非常によかったと思います。
実は父親の教授をしている心理学教室に入るということの大変さに気づいたのは、私が晩熟だったのか、30近くになってからなのです。大学に進む時には気づいていませんでした。別の言い方をしますと、私の父親が偉かったと思います。といいますのは、青年期独特の親への反抗が、不甲斐ないことほど起こらない人格者でした。息子の私が言うのもおかしいですが。元々父親は牧師になるつもりで関西学院の神学部に進み、卒業して牧師の資格まで取っておきながら、牧師の道を選ばないで、結果的に東大の心理学に行った人ですから、非常に円満な人格者でした。今思っても、あれほど人柄が円満な人間はざらにはいないのではないかと思うぐらい、温厚な人でした。ですから、息子でありながら父親をすごく尊敬していました。
このような事情に加えて、家庭での普段の会話にも、割に心理学的といいますか、それほど専門的ではないですけれども、人間の心や生命についてのことが、家の中に漂っていたのかもしれません。だから、子供たちは、一番上の姉が嫁いだ先は生物学者でしょう。その次の兄貴は命に関わる医者でしょう。それから3番目は牧師ですから、やはり命に関わります。そして私でしょう。また下の2人は生物科学に行きましたからね。ですから、皆、何か、生物、命・生命に関係がある道に進んだのは、家庭での父親の影響が非常にあったと思います。
それと、母親はものすごく好奇心が旺盛で、とにかく物事を納得のいくまで突き詰めなければ気が済まないたちだったのです。そういうことで、客観的でサイエンティフィックなものの考え方というもののルーツは、むしろ母親から来ていたのかもしれません。そして心理学の対象である心や生命というものに対する漠然としたあこがれのようなものは父親から来ています。ということで、私の中では、関西学院大学の高等部を卒業して大学の学部を選ぶ時に、何の抵抗もなく、すっと父親のところへ行ってしまいました。
それを後悔し始めたのは、学会活動を始めてから、いつまでたっても「今田先生の坊ちゃん」と言われることで、何か、もうどうしようもなく父親が疎ましく思える時期がありました。いつまでも「今田先生の坊ちゃん」で、父親から離れられないのです。父親は割によく知られていたので、30を過ぎてからもそう言われている有様で、「大変な道を選んだな」と思った時には遅すぎました。もっとも、それが後の私の頑張りの源になったところもありますが。親の七光りといわれるのは嫌ですから。
イン 高等学校の時などには、何か心理学の本などは読まれましたか?
今田 何も。あまり読まなかったです。エスカレーター式で受験の心配がないものですから、自治会の仕事をしたり、卒業アルバムをつくったり、そういうことに没頭していたように思います。ちょっと情けない話です。
学部生時代で受けた態度教育
イン なるほど。では、大学で初めて本格的に実験心理学に出会われて、思っていた印象と違ったりしましたか。
今田 それほど違っていたとは思いません。また抵抗もありませんでした。私の父親は、私が入った時にはすでに学院全体の行政に関わるようになっていましたから、研究室は、うちの父親の第一弟子であった古武弥正(こたけやしょう)先生が中心でした。
古武先生は非常にはっきりした先生で、いつも自分の考えを鮮明に打ち出す人でした。ご存じのように、古武先生はPavlovの条件反射を日本に定着させる基を築いた人です。その古武先生は、実験心理学、しかも条件づけを教室の運営の柱にしていました。よく古武先生がおっしゃったことは、「私学は国立大学には対抗できない。国立大学は百貨店かもしれない。私学は専門店だ。だから、うちは条件づけ・学習・条件反射でいくのだ」ということで、教育方針がはっきりしていました。
ですから、関西学院大学の教育は、条件づけを柱とした実験心理学に特化されていたように思います。これに対しては、狭すぎるという考え方があるかもしれませんが、私は心理学の学部教育というものはコンテンツ教育ではなくて、態度教育、すなわち物事の客観的な考え方、論理的な考え方を身につけることだと思うのです。不注意に結論に飛びつかない態度を身に着けることです。小さなことから大風呂敷を広げるような、何を証拠でそんな大きなことが言えるのか疑いたくなるようなことを平気で言う人もいるではないですか。そういうのと全く対極にありました。
古武先生の学部教育はそのような非常に狭い教育でした。今から思えば提供されていた学科目の幅もそれほど広くはなかったのですが、徹底した実験・実習、それから卒業論文でも必ず実験など、実験の繰り返しによって客観的な物の考え方が自然に身につくような教育方針だったと思います。いわば、宣言的知識ではなくて手続き的知識。頭の知識ではなくて体の知識として、客観的な物の考え方や、論理的な物の考え方が自然に身についたことに、私は非常に感謝しています。
コンテンツ教育、つまり中身の教育は、後から勉強できますが、態度教育というものは、最初が粗くなってしまえば、後できめを細かくしようと思っても身につかないものだと思います。やはり熱いうちに鉄は打たなければならないという、そのような思いがしました。
後に私がアメリカに留学した時に受けた教育も、その延長上にありました。アメリカには心理学の専門教育のモデルとしてボールダー・モデルというのがありますが、私の学んだアイオワ大学はまさにこのモデルにしたがった教育を行っていました。その教育方針は古武先生の方針と全く一緒で、「心理学者というものは、後に臨床心理学に進む人も、実験心理学に進む人も、まずサイエンティストでなければならない。そして、一人できっちりと実験計画ができて、きっちりと論文が書けて、パブリッシュできるような基礎教育を受けた後に、それぞれの道に進んでいくべきだ」という考え方に立ったのが、ボールダー・モデル、あるいはサイエンティスト・プラクティショナー・モデル(科学者実践家モデル)というものなのです。この精神を古武先生は先んじて教育に反映されていました。
心理学の対象は複雑ですが、このような考えと一致する教育を関西学院大学で受けたことで、複雑なことを複雑なまま放っておかないで、整理整頓して、何かしかるべきゲシュタルトといいますか、骨組みを見つけ出すという訓練が、若い時からできていたと思います。ですから、留学先で、複雑なことについてレポートを書く課題が出ると、まず情報を集め、表を作って複雑な情報を整理整頓し、そこから図柄をつかみ出す形でレポートを書いたものです。そしてその姿勢を私の留学先の教授であるK. W. Spenceは非常に高く評価してくれました。授業中でも、「この複雑なことを簡単にするには、今田に表を書いてもらおう」という冗談が出るぐらい、彼は目にかけてくれていたように思います。それには、元々持っているもの、育った家庭の影響もあるかもしれませんが、学部時代の教育というものは、大きな意味を持っていたように思います。
イン もし、覚えていらっしゃれば、学部の頃受けた一般実験なり、特殊実験なりで、何か覚えていらっしゃるエピソードなどはありますか。
今田 私は、ミュラー=リヤーの実験というものは、今でも非常に印象に残っています。ミュラー=リヤーの実験一つでも、正しい事実を導き出すためにはどうすればいいかという心理学の態度教育ができます。エラーを除外しなければいけませんので、標準刺激を左に持ってくるのが半分、右に持ってくるのが半分、比較刺激が標準刺激より短い所から始める上昇系列が半分、逆の下降系列が半分というように、カウンター・バランスをしなければいけません。これには感銘を受けました。このような空間の異方性に伴う誤差や運動誤差の他、習熟の誤差というようなことをキャンセルアウトするためのデザインを組まなければならないなど、ものすごく面白かったです。
その背景には、私の子どもの頃の体験もあります。私の家は6人きょうだいで、戦時中、物のない時代に育っただけに、例えば、カステラ1本が家に到来したとすると、6人が、皆ギラギラした目で眺めていて、大きな一切れを取ろうとしているわけです。ところが、私の母はカステラを切る時に、いつでも左が大きくなるのです。だから、母の左側に座っていた方が得だということを子どもはよく知っていて、そのつもりで待っているわけですね。そういうことが背景にあるものだから、ミュラー=リヤーの実験を学んで、「なるほど。人間を対象に実験をすると、正しさをゆがめるエラーがいろいろあるので、正しい結論に持っていくためには、いろいろ手続き上の工夫をしなければならないのだな」とすんなり理解できました。あの実験を徹底してやるだけでも、心理学の教育にとってすごく意味があると、今でも思います。
イン 今は実験演習の話でしたけれども、講義などで特に印象に残っているものは、他にございませんか。
今田 実験・実習の影響が大きかったのですが、講義は、古武先生の「心理学概論」は非常に筋が通っていて面白かったです。視力の非常に悪い先生なのですが、大きな声ですごく明快な話をなさる先生で、あの「心理学概論」は面白かったです。それと私の父・恵の「心理学史」も印象に残っています。口述筆記とそれの補足の講義を交えたものでしたが、その講義が土台になって、1962年に岩波書店から『心理学史』が出版されたことになります。私が講義を受けたのは1956年度ですから。
それと今一つ忘れられないテキストがあります。それはUnderwood のExperimental Psychology (1949)で、心理学購読演習のテキストでした。非常に説得力のある整然とした書物で、これは実験実習でやっていることを裏打ちする名著でした。もう一つの心理学購読演習では、Hilgard & Marquis(1940)のConditioning and Learningがテキストでした。3年生の時だったと思いますが、当然教室ではほんの一部しか読めません。そこで残った部分を自力で読み切りました。英語の単行本を一冊読みあげたのはその時が初めてで、非常に満足感がありました。
研究テーマを選んだきっかけ
イン はい。ありがとうございます。その後、卒業論文のテーマを選ばれたきっかけはどのようなものだったのでしょうか?
今田 先ほども言ったように、関西学院大学は、条件づけや学習の専門店でいこうという方針だったものですから、動物実験も一つの柱だったのです。
少し話はずれますが、私は父親の息子として心理学科に入ったわけですから、どうしても自意識過剰になっていたのでしょうね。ですから常に人に見られているといいますか、評価されていると意識がありました。そんなこともあってか、人相手の実験など全く想像もできませんでした。「被験者をお願いします」と言って断られるのは、どうもプライドも許さないですし。そんな中、実験実習(3年次の特殊実験)の中で一番私にとって気が楽だったのは、暗室の中で独りで白ねずみを相手に実験をしている時でした。一番心の安らぎがありました。
これは、実は、John B. Watsonも伝記の中に書いているのです。学生時代を振り返って「自分は、白ねずみと暗室の中にいる時が一番心が安らいだ」と書いています。それと同じ経験を私はしたわけです。動物実験にほれ込んだ理由の一つがここにあります。
それと、私が後に不安や恐怖などということをテーマにしたわけですが、そのきっかけの1つは、ゼミでの体験にありました。古武先生のゼミに入って3年生になるとゼミ発表があるのですが、そのゼミ発表の時に、一つの英語の論文を、これ以上読み込めないというぐらい徹底して読みました。その当時ゼロックスはないので、全部タイプライターで打つわけですね。苦労してタイプして、これ以上準備のしようがないほど準備をして発表に臨んだのですが、もう全くあがってしまいました。この頃の言葉で言えば、頭が真っ白になってしまって、もう本当に、あのときの経験は今思い出しても涙が出ます。あれほど準備していて、あれほどみじめな思いをしたのです。そして、泣きの涙でうちに帰って、ふとんをかぶって寝てしまいました。
その時に私をやっつけたのは何だったろうかと考えて、それは不安やストレスなどというものだと思いました。そして、一生かかって敵討ちをしてやろうということが、後の不安、ストレスの研究につながるわけですね。だから半ば臨床的興味があったように思います。それと、研究を「やるからには何かに役に立ちたい」という思いはありました。「あがり」は、能力がありながら能力が発揮できない状態でしょう。そのように、不安など人を生きづらくさせるもの、人の適応を阻む事柄に、私は非常に関心を持ちました。
それに、先ほど言った動物実験というものへのほれ込みがあったものですから、不安に対する興味と動物実験に対する興味とがドッキングして、不安・恐怖・ストレスに関する基礎実験をすることになったのです。けれども、うちの研究室は、学習や条件づけということで一本の柱が通っていましたから、それを、学習心理学や条件づけとドッキングさせながらやるという方向を探りました。その結果、私が一番ほれ込んだのが、アメリカの心理学者のO. H. Mowrerと、イエール大学にいたN. E.Millerなどです。私はMowrerやイエール学派といわれる人たちの、基礎と臨床を結びつける考え方に非常に興味を持ちました。学習理論のHullを中心としたイエール学派の人々は、動物で基礎実験をしているけれども、そこから出てきた不安の条件づけ研究を、将来的には精神分析学における不安、そしてその症状形成、治療に結びつけようとしました。つまり、実験だけで終わるのではなく、その実験の成果を臨床につなげようとしたのです。
私がMowrerの考え方に関心を持ったもう一つの理由は、彼の整然とした学習2過程理論です。電気ショックの到来を予想してショックの回避を行う回避学習は、恐怖の古典的条件づけと、その恐怖を動機として起こる回避行動によって恐怖が低減されることでそれが強化されると、回避学習を2過程で考えます。まず恐れることの学習・古典的条件づけ、そして恐れに基づく学習・道具的条件づけ、それが見事にドッキングした考え方で、その考えを応用することによって、人間の強迫神経症の症状などが見事に説明できように思えたので、私はMowrerの考え方に非常に魅せられました。また自分の体験からも共感できました。
従って、私は古武先生の下で条件づけ・学習の研究はしたけれども、常にその応用といいますか、臨床とのつながりのようなものを意識しながらやっていました。それの元になったのが「あがり」で、そのためにとんでもない悔しい目に遭った経験です。このような生存にとって不都合な問題を何とかして自分自身で解決したいという思いが、ずっと長い研究生活をリードしてきたように思います。
言い忘れましたが、卒論のテーマは「マイヤーのフラストレーション理論に関する実験的研究」でした。
イン ちなみに、先生が学部のときには、もうすでにラットが飼われていたわけですね。
今田 はい。関学の研究室では、昭和17年ぐらいに、すでにラットを飼っていました。
イン どこから入手されていましたか?
今田 『関西学院大学心理学研究室80年史』に書いたかもしれませんが、ラットの研究が始められたのは私の代より大分前のことなのです。私たちの代には、もうすでに、大阪大学の医学部とつながりのあるラットの業者がいました。ラットの販売業者がいて、そこでたいてい買っていました。その当時のラットの飼育状態は臭かったですね。今は自動洗浄で臭気も全部抜けますし、うそのようです。当時は、戦後まだ間もない頃だったので、臭い動物室の横で昼食を食べていました。そのような時代でした。
回避行動の消去困難さの研究へ
イン 修士でも動物実験を続けられて、修士論文も、「回避行動の罰の効果」ですね。
今田 はい。修士論文も、正常・異常や、適応などというものに関係のある研究でした。回避反応の消去過程に関する実験でした。回避反応の一つの特徴は、一旦形成されるとなかなか消えない、消去されないということです。したがってこのなかなか消えない回避反応の消去を促す条件を探れば、これは不安神経症や強迫神経症の症状の治療にもつながるのではないかという思いがありました。そこで修士論文では、シャトル・ボックス(同じつくりの2部屋の間を移動することでショックから逃避・回避できるボックス)を用いて、隣室への移動回避行動をまず形成しました。具体的には光が点灯し10秒後に床からショックが与えられますが、隣室に移動すればショックから逃避できますし、点灯から10秒以内に移動すればショックを回避できるという手続きです。そのような手続きで形成された回避反応の消去過程では、移動しなくてもショックが来ないようにするわけですが、それでもいつまでも移動し続けて消去しないのです。そこで消去を促進するために、隣室に移動すれば、そこで一瞬の罰を与えました。そうするときっと隣室への移動はやめるだろうと考えて。そして隣室で与える罰の強度をいろいろ変化させてみました。
結果的に分かったことは、隣の部屋で与える罰が強ければ強いほど、かえって回避反応は長続きして、しかもその罰せられる部屋に対して激しく、しかも速く飛び込むということが分かりました。つまり、回避反応に対する罰の逆説的効果というような現象が見られたのです。今でも、強い罰に向かって激しく飛び込むあのマゾヒズム的というか自虐的な激しい行動が目に浮かびます。それを私はMowrerの学習2過程説で説明を試みました。
ちょっと余談になりますが、実は隣の部屋へ飛び込む行動の激しさを何とか測定したいと思って、部屋の床の蹴りの強さを測りました。まず部屋の床の四隅に、フィルムの空き缶の上にゴム膜を張って、それで床を支え、移動時のねずみの床の蹴りの強さを4つのフィルム缶膜面の沈みでとらえました。4か所から押し出された空気は、ゴムホースで集められ、それを別の缶のゴムの膜面の膨れでとらえ、膜面に取り付けられたペンの振れで記録用紙に行動の激しさとして記録したのです。そういう装置を全部自分で作っていたわけですから、実験には非常に愛着がありました。強い罰に向かってネズミが大きく床を蹴れば、自分が作った装置の大きな針の振れとして目の前ですぐにフィードバックされるわけですから感激でした。その論文が、私の処女作となりました(Imada, H. (1959). The effects of punishment on avoidance behavior. Japanese Psychological Research, 8, 23-38.)。
イン 先生が学生の頃の研究と今の研究で違うところは何でしょうか?
今田 昔の研究は手間とエネルギーが要ったということではないでしょうか。論文一つ読むにも、ゼロックスなどないわけですから、いちいち自分でタイプしなければなりません。実験もそうです。装置などは全部手作りでした。そして手間をかけた分だけ、汗をかいた分だけ研究に愛着がわいたように思います。この頃はゼロックスもありますし、機器も大抵は業者から購入できます。やっかみかもしれませんが、こんなことで研究への愛着がわくのかなと思う時があります。
アイオワ大学への留学
イン その後、先生はアメリカへ留学されるのですが、留学にまつわるお話しをうかがえませんか?
今田 私が留学したのは1961年、ドクターの3年生の時でした。実は私自身はその時に留学は全く考えていなかったのですが、ある時、古武先生が私の部屋(私は当時専任助手でした)に来られて、バイオリニストのお嬢さんのためにフルブライトの留学試験の願書を取り寄せたけれども、結婚が決まったので願書が要らなくなった。「君、受けてみんか」と言われるのです。言われるままに、もらった願書で受験したところ、うまくいって留学ということになったのです。古武先生のお膳立てによる偶然で、全く他動的でした。
イン すごく不思議なエピソードですね。
今田 ええ、不思議ですね。後でお話ししますが、私の意思でなく人の言われるままに動いてそれが私の人生に大きな影響を与えたこれに似た例が他にもあります。
さて留学先ですが、試験にパスした後、父親は私にこう言いました。「寛、もしアメリカへ留学するんだったら、田舎の小さな大学町を選んだ方がいいよ」と。そして大学よりも人を選べとも。そこで私が選んだのは中西部のアイオワ大学でした。そこにはJudson Brownという人がいて、O. H. Mowrerなどと同じように異常行動と不安とを結びつけた研究をしていました。私はその人の下で勉強したかったのですが、アイオワに行くと、Brownは西海岸に移ってしまっていました。私にすれば空振りです。しかし、そこには学習理論のC.L.Hullの高弟、K.W. Spenceがいました。実は古武先生は私をSpenceの所で学ばせたかったようです。第一目標にしていたBrownはいませんでしたが、結果的にSpenceの下で、徹底した厳しい大学院のコース・ワークを受けたことは、私にとって非常によかったと思います。空振りという偶然が生んだ幸運でした。
実はアイオワで学位を取るようになったのも、Spenceの「おまえは自分のところで学位を取って帰るべきだ」という鶴の一声の結果でした。ある時提出した論文が非常に高い評価を受けたのがきっかけで、半ば強制でした。私はすでにその時関学の専任助手でしたもので、「そんな長くは滞在できない」と言いますと、「これまで関学の大学院でとった単位を送ってもらえ」と言われ、言われるままに取り寄せた結果、かなりの単位が認定され、語学試験、総合試験、博士論文にパスすれば短期でも学位をとれる目途が立ちました。その後は死にもの狂いでしたが、幸い難関を乗り越え、結果的にPh.D.を取って帰ることになりました。
古武、Spenceという、今ではお目にかかることの出来ない2人のビッグ・ボスによって私の人生は大きく変わったわけです。
イン 先生がアイオワにいらっしゃっている頃のお写真を、原一雄先生がお持ちでした。
今田 それは、大学の視察で原先生が視察団全体の世話役で、他の役職者に同伴してアメリカの諸大学を回っておられた時のことです。その視察団の中に私の父もおりました。原先生にお会いしたのはアイオワではなく、スタンフォードだったと思います。私をアイオワに訪ねてきてくださったのは同じICUでも星野命先生でした。先生は、アイオワ大学に留学されていたので、私がいる時にたまたま来てくださって、そして私のおんぼろ車でシカゴへ一緒に行ったことを覚えています。だから、ICUの先生方とは、そのようなつながりがありました。
実は、私は高等学校の3年生の時、私の父親と縁が深かったようなので、「寛、ICUを受験してみんか」と言われたことがあります。もし、私が行っていればICUの1期生になっていたはずです。父には「1期生というのはいいよ、行かないか」と言われたのですが、受験勉強も全くしていませんでしたし、結局私は行きませんでしたが、もし行っていれば、また別の人生になっていただろうと思います。
しかし、面白いことに、フルブライトでアメリカに行く時に、ハワイでの1ヶ月にわたるオリエンテーションがあったのですが、その間、何か気心が通じ合い、一番親しくなったのはICUの卒業生でした。心理学関係の人はいませんでしたが、1期生が何人かいたもので面白い偶然を感じました。
イン アイオワでは、日本から留学に来ている人のコミュニティのようなものがあって、お互いにどこにいるかということは、少しは連絡などがあったのですか。
今田 アイオワというところはド田舎でしたから、日本人はそれほど多くはなかったのですが、東海岸の大学には日本人はある程度おられてコミュニティもあったのかも知れません。しかし私は外に目を向けるほどゆとりもありませんでしたし、今のようにメールのある時代ではなかったので、他大学の方々と交流があったわけではありません。当時コロンビアにおれらた秋田宗平さんから、留学生のネットワークを作ろうという呼びかけの通信をもらったことがあるのですが、私はそれどころではありませんでした。
イン アイオワ大学の心理学の学習の研究室以外のところはご存じでしたか。
今田 アイオワには日本人は何人かおられました。理学部にもいましたし、ジャーナリズムにもいましたね。記憶ははっきりしませんが、アイオワはcreative writingが有名だったように思います。また吃音の研究で非常に有名なWendell Johnsonという先生がおられ、日本からも何人か行っていたようです。私のフルブライトの同期でも内須川さんがおられました。
イン アイオワといえば、Lewinが行っていたところですね。
今田 Lewinがいたのは、アイオワでも心理学プロパーではなく、Child Welfareという児童福祉系の心理学の部門でした。Child Welfareの方には、小橋川慧さんという沖縄から来ておられた発達心理の方がおられました。その後カナダにずっととどまって、今でもカナダにおられます。当時は、心理学はEast Hallという建物の中にあったのですが、小橋川さんは同じ建物の別のウィングにおられたので、よく行き来がありました。ご家族とも随分親しくさせていただき今でも交流が続いています。
イン Spenceのところは、結果的に、先生だけしか日本人は行かなかったのでしょうか。
今田 私はコンディショニングだから、Spenceの直系なのですが、アイオワ大学の心理学全体で言うと星野先生が私の前に行っておられましたし、沖縄の東江先生ご兄弟もおられたようです。私の後のことはよく知りません。Child Welfareの方まで入れるとどうなのかはよく分かりません。
イン ありがとうございました。それで、日本に帰っていらっしゃってから、当時のアメリカの状況と日本の状況を比べて、感じられたことなどはありますか。
日米の研究予算の格差から水なめ装置を考案
今田 とにかく今から半世紀以上も前の1961~1963年ですから、日本は貧しく、アメリカは大きくて豊かな国で、その差は歴然としていました。研究の面でも、アメリカは、リサーチ・アシスタントなどを使って、また、実験機器の使用も進んでいましたから、実験をやるにしてもデータの生産性という意味ではアメリカと日本では比べものになりません。そこで私は、アメリカ人と勝負するのに、独りで暗室にこもって、シコシコと少しずつデータを積み上げていくようなやり方をしていては、なかなか追いつけないと思い、何かデータを量産できる方法はないだろうかということを考えました。
つまり、リサーチ・アシスタントのように自由に自分の研究をやってもらえるような人もいないわけですから、何とかしてもう少し効率のいい研究の仕方がないだろうかと考えたのです。その結果、貧者の知恵で「水なめ装置」というものを考案しました。
私のこの装置は、のどが渇いたねずみを箱の中に入れて、箱の端っこにある穴からチューブの先端をペロペロなめるという行動をさせるものです。1日1時間ぐらいしか水を与えないのどが渇いたねずみの場合は、よく馴れさせると、大体5分間ぐらい立て続けに1秒に5~7回ぐらいのペースでペロペロと水をなめるのです。
私は実は、Spenceの学習理論との関係で水なめ装置を考案したのですが、その水をなめる行動というものをベースにして、私の本来の不安の研究、恐怖の条件づけの研究ができるのではないかと思いました。何かといいますと、要するに、水をなめる行動は平和な営みです。恐ろしい時には、人でも動物でも、食べたり飲んだりする行動は抑えられます。だから安定した水なめの行動をまずつけておいて、その後、ピーッと5秒間音を呈示して、最後にショックを与える恐怖の古典的条件づけの手続きをそれに重ねます。すると危険信号の5秒の間の水なめがぴたりと抑制されます。そして、それが終わると、また、パパパッと飲み始めます。そういうことで、恐怖の条件づけの研究を、水なめ行動をベースラインとしてできることを、私はすでにアメリカの学位論文実験の時にも確かめていました。
けれども、1回に1匹ということでは能率が悪いので、最終的に6匹を同時に実験できる工夫をしたのです。のどの乾いたネズミ6匹を入れて一斉に飲ませると、隣室の操作室の電磁石のカウンターが一斉に動き出します。昔は、コンピューターがなかったのですごい音でした。ところが危険信号の音が鳴るとそれがピシャッと止まり、デッド・サイレンスが訪れます。そしてそれが済むと、またガチャガチャガチャ。このフィードバックが実験者にはすごい強化でした。だから、その後に、リレーがサイレント・リレーになり、コンピューター化されてもすごく物足りなさを感じました。昔の機械はフィードバックがすごかったので実験者には張り合いがありました。あの感激は忘れられません。
その装置を使って、1回に6匹できるということは、アメリカの生産性に近いわけでしょう。それで5分間やれば、5分で一丁上がりです。それを5回繰り返すと、30匹で、10匹・10匹・10匹で3群実験ができるのです。そういうことで、ものすごく仕事の能率化ができました。
そのきっかけは、やはりアメリカで刺激を受けたことにあります。彼らと対等の勝負をするための方法を編み出したわけです。
そういうことで水なめの装置というものを作り出して、その装置を使ってずっと一生やってきました。今はもう使われていないかもしれませんが、私の研究室の一つの目玉でした。また水なめの装置を使ったことの副産物で、私の研究は次の転機を迎えます。
ITI中の行動の研究へ―発想の図地反転―
今田 ラットの水なめ行動をベースラインにした恐怖の条件づけの研究は、このような経緯で始めたのですが、この実験は本来スキナーボックスを使って行われているモノでした。VIスケジュール等に設定しておくと、比較的安定してコンスタントにレバーを押し続ける行動が形成されます。その上に恐怖の条件づけの手続きを重ねると、水なめの場合と同様に、その恐怖によって進行中のレバー押し行動が抑制されるようになります。本来は、こちらの方が一般的な方法だったのですが、当時は、幸か不幸か、スキナーボックスなど買うお金がありませんでした。スキナーボックスの場合には、エサのペレットも結構高価でした。そこで私は、アメリカで使っていた水なめ装置を使うことに思いつきました。水なめ装置は手作りのボックスにチューブをつなげば、ものすごく安価に自作できます。消耗品も水道水だけです。ですから、これに行き着いたのは、貧乏であったことによる幸いがありました。
しかもスキナーボックスのレバー押しにくらべると、水なめ行動は1秒間に5回から7回ぐらいペロペロとなめるものですから、いわば測定の目盛が細かいと言えます。ある時に学会でスキナーボックスを使っている人に、なぜ水なめの装置を使っているかと聞かれて、「ミリメートル単位の物差しを使っているのだ」と答えたことがあります。短時間に細かくデータが取れるのですね。
しかし水なめ行動をベースラインにすると泣き所もありました。水なめ行動はスキナーボックスのレバー押しに比べると、ショックの導入によって乱されやすい特徴があります。つまりパブロフの言葉をつかうと外制止をうけやすい敏感なところがあります。これが、また私に幸いしました。といいますのは、例えば、水なめ行動を安定させると、大体5分間に1,500回から、場合によっては、1,800回ぐらい、ペロペロとなめるのですが、条件づけの初期に、信号を与えてショックを与えると、しばらく水なめ行動が全体的にバタッと止まってしまいます。それが回復するのは、信号のない時は安全で、信号のある時は危険だという弁別ができるようになってからで、ラットは信号のない時は安定して水を飲み、信号が来た時にだけピタッと抑制されるとようになります。それでもって恐怖の条件づけの研究ができるのです。
つまり水なめ行動を用いて恐怖の条件づけの研究を行うためには、恐怖によって押さえられるべきベースラインがまずなければ行えません。したがってベースラインがなくなってしまうということは恐怖の条件づけの研究にとっては致命傷です。しかしこの事実を見て、まったく別の観点からの研究を思いつきました。
恐怖の条件づけの結果、恐れるべきものを的確に恐れることは、ごくごく自然なことです。ですから、ショックの到来を告げる光が来ると水なめ行動をやめるということは、ごく当たり前のことです。しかし私のもともとの関心は、あがりのように生存にとって不都合な出来事の研究にあったもので、恐怖・不安の研究でもこのような当たり前の現象よりも、もっと当たり前でない、例えば恐れる必要のない時にもビクビクし続けるような状態に関心があったもので、このベースライン全体が乱されてしまう事実そのものを非常に興味深く思い、これを手掛りに新しい、私の本来の関心の研究への道が開けないかと思いました。
条件づけの言葉で言えば、CS(音)- US(ショック)を対呈示した結果、音を怖がるようになるのは正常ですが、それ以外の試行間隔(ITI)中にも恐れ続けるのは不都合で正常ではありません。そこで私は、条件づけの研究の本道から離れて、CS中のことは十分研究されてきたからもういい。むしろITI中の行動に注目して、それを従属変数にした研究をすれば、「恐れる必要のない時にもビクビクし続ける行動の研究」、つまり慢性的不安の研究ができるのではないかと考えました。これまでの条件づけ研究ではCS中の行動が「図」で、ITI中のことは「地」ですから誰も注目しませんでした。私はこれまで「地」として、いわばゴミ箱行きの事実をむしろ「図」とする、図地反転の発想で研究を展開しようと思ったわけです。
そのようなヒントが得られたのは、貧乏だったためにスキナーボックスが買えず、外部刺激に非常に敏感な水なめ行動をベースラインにしたことからです。何が幸いするか分かりません。
もう少し幅を広げて、1960年代から70年代にかけての私のスタンスを申しますと、私は学習心理学や条件づけの研究に従事しながら、何となく満たされないものを感じていました。それは簡単にいうとブツ切り主義とでも言うべきものに対する不満でした。私は学習心理学を、広く生活体の環境への適応過程の研究として関心をもっていたもので、条件づけの実験で、CSに対して起こる反応だけを切り取って問題にするブツ切り主義がどうも気に入りませんでした。生活体はCS中もCSのない時もずっと生存・存在し続けているにもかかわらず、まるでCS中以外には生活体は存在していないかのような研究姿勢にどうも満足できませんでした。私はむしろ環境全体に対するトータルとしての生活体の適応に関心があったもので、‘行動の流れ’というか、‘情動の流れ’というものを問題にしたかったのです。学習心理学へのこのような当時の不満が、上のような研究姿勢の転換の背後にありました。
これはいわば実験における従属変数側への私の不満でしたが、実は私は学習心理学研究における独立変数側にも不満がありました。条件づけ研究ではCSやUSや、それらの時間的関係のような物理的変数(強さ、長さ、時間)を操作して、それらの効果についてのパラメトリックな研究を行うことが主流でした。不満というのは、心理学者であればどうして物理的変数でなく、心理的変数を独立従属変数側にもってこないのかということでした。物理的変数を恒常に保ちながら心理的変数を操作してその効果を見ることこそ、心理学者が関心をもつべきことではないかという不満でした。
日常経験からの発想
そこで実験室を離れて、人や動物を慢性的・持続的に(つまりITI中も)ストレスフルにさせる心理的変数はないかといろいろ考えました。また私自身の経験の中にこれに関係のありそうな経験はないものかと、記憶の糸を探りました。そして2つのことに思い当たりました。
一つは戦時中の経験です。私の小学校(当時は国民学校)時代は太平洋戦争と重なります。私は大阪と神戸という大きな町の中間の西宮に住んでいたので、また近くの現在の阪神競馬場のところに川西航空機という軍需工場があったもので、戦争も末期になるとよくB29の爆撃を受けました。そしてB29の襲来は必ず警戒警報と空襲警報という2段階の警報によって予告されました。思い出してみますと、あの時もし警報がなければどうだったろうか。敵機の飛来を気にして四六時中空を眺めていたのではないか。警報はあろうがなかろうが爆弾が落ちる時には落ちるのです。つまり物理的経験は変わらないのですが、警報のあるなしは人の慢性的不安を大きく左右します。これがまさに私が物理的変数を恒常にして心理的変数を操作することにあたります。つまり心理的変数とは、危険(爆弾・ショック)の予測可能性・不可能性という変数です。これが私のねずみの水なめ行動を用いた実験的研究の大きなテーマの一つになります。
今一つ、思い当たったストレスがらみの心理的変数がありました。それは対処可能性・不可能性という心理的変数です。実は私は大の注射ぎらいでした。ですから注射をせざるを得ないときには、二の腕の内側をあざが残るほど思いっきりつねるのです。痛いので顔をしかめながら。これは、どうすることもできない(対処不可能)な注射の痛み刺激よりも、自分でコントロールできる(対処可能な)はるかに痛いつねりの痛みの方がましだということなのです。つまりストレスは痛み刺激の物理量によって決まるのではなく、対処可能性・不可能性という心理的変数によって大きく左右されるのです。
蛇足かもしれませんが、中学校の時の英語のクラスを思い出してみてください。ある先生は、生徒に当てる時に出席簿順とか席順で当てますが、別の先生はまったくランダムに当てるとします。当たる時には当たるので、いわば物理的条件は同じですが、両先生のクラスの緊張度はかなり違うでしょう。また授業に予習をして臨んだ場合と、予習しないで臨んだ場合の緊張度も想像してみてください。予習しないで当たると対処不可能なので、できるだけ当てられないようにビクビクして頭を低くしているのではないでしょうか。
私は長年動物実験に携わってきましたので、まるで、象牙の塔にこもった現実知らずの研究者のように思われるかもしれませんが、いまお話ししたように、私の研究の発想のきっかけは必ず日常経験にあったと思います。きっかけからして「あがり」ですし、そして予測可能性・不可能性や対処可能性・不可能性という心理変数も日常経験から来たもので、そのような問題を動物実験で再現しようとして研究が展開されてきたのです。
異常行動研究会の創設
イン 先生は、動物の実験の研究をジャーナルや学会で報告されると同時に、ご著書では実験神経症の話や、フラストレーション、人間の嫌悪刺激による行動療法など人間の臨床に密接に関わることについてもまとめられていますね。
今田 そうですね。この話をすればまた長くなりますが、私は1961年にアメリカに行ったのですが、1959年に北大で日本心理学会があった時に、上智の平井さんや、早稲田の春木さんや、同志社の松山先生、それから、慶応でいいますと梅津耕作さんなど、当時、回避学習をしている人たちが多くいて、回避についての一つのセッションで集まっていたことがあります。その回避学習に関心を持っている人の中には、MowrerやMillerなどの考えと似たように、臨床と実験とを結びつけて異常行動を研究することに関心を持っている人たちが多くいて、そのセッションが終わった後に、北海道大学の芝生の上で集まって、会を作ろうではないかということで作ったのが、その当時の「異常行動研究会」(現在の行動科学学会)です。
偶然のことですけれども、参加者は私学ばかりでした。そしてその4大学を中心にした異常行動研究会というものができました。あがりのこともあって、私はそのような研究に人一倍関心を強く持っていて、私より少し上の先輩としてが、松山義則先生がおられて、同じく関西であるということもあってか、松山先生はことあるごとに私を引っ張り出してくださいました。東大出版会の『異常心理学』でも、神経症の話やフラストレーションの話を松山先生に依頼されて書きました。だから、私の駆け出し時代に松山先生に負うところがものすごく多いです。私を引き立てて下さったといいますか。
その異常行動研究会が行動科学学会に名前を変えたのは、異常行動研究会という名前のビラを張って、ホテルなどで会合をしていると、側を通る人は皆笑うのだそうです。そこで、この名前を何とかしてくれないかと言われて変わった経緯があります。
イン そのような内容も含めて、恐怖と不安ということで博士論文を、二つめの博士号ですけれども、関学で取られたということですね。
今田 その通りです。私は既にPh.D.をもっていたので、日本の学位はいらないと思っていたのですが、父に、「日本では、日本の学位もとっておいた方がいいよ」と言われたもので、『恐怖と不安』(1975、誠信書房)でとりました。残念ながら父が1970年に亡くなっていたので間に合いませんでしたが。
イン 水なめの話は、元々動物が持っている種に特異的な行動の話の後から来たのですか。
今田 いや、水なめ行動は、実は、フラストレーション研究で有名なA.Amselが初期の研究でアイオワで使っていたのです。ただAmselは条件づけがらみの実験です。しかしそういう背景があったので、私は学位論文を書くに当たって水なめ行動に着目しましたし、またそれを帰国後も使ったのです。したがって後に学習心理学で話題になる、種に特異的な行動(species-specific behavior)の問題とは全く関係ありません。
ロンドンへの留学
イン ありがとうございます。少し話が変わりますが、2度目の留学で、ロンドンに行かれていますけれども、そのことに関して、印象に残っていることなどありますか?
今田 2回目の留学は、ロンドン大学の精神医学研究所に行きました。ブリティッシュ・カウンシルの留学制度によるポスドク留学で1968年のことです。ご存じのように、ロンドン大学の精神医学研究所には、Hans Jurgen Eysenckがいたのですが、ここに行った理由は二つあります。
一つは行動療法です。先ほど言った、異常行動研究会の目玉の一つは、条件づけ・学習心理学の原理を臨床的に応用する行動療法でした。そしてその行動療法のメッカがEysenckのところでした。特に、Eysenckは行動療法についての本を書いていて、それを異常行動研究会の連中が手分けして1965年に翻訳したといういきさつもありました。したがって実験的な研究、基礎研究の臨床的応用としての行動療法というものを、目の当たりにしたいということが一つありました。
もう一つは、Eysenckのところに、特別なねずみがいたのです。私は、「あがり」というものの研究に関心を持った当初から、その不安やストレスに対する個人差というものにとても関心をもっていました。それはなぜかというと、3年生の時に、初めてゼミ発表をした時に、私以外にもう一人、ラグビー部の男が発表したのですが、私は彼のために全部英語を訳してあげました。彼はラグビーが忙しくてほとんど勉強していなかったのですが、私があがってメロメロになってしまったのと対照的に、彼は、私の訳を基にして、堂々たる発表をしました。その時に、ストレスに対する弱さ・強さというものには、個人差があることを強く思い、関心をもったのです。加えて、動物実験をしていると、実験では条件単位で平均値を算出しますが、特に回避学習など嫌悪刺激を使う実験では、ものすごく標準偏差が大きい高いのです。1個の値で代表させるということに無理があると思うことが多々ありました。そこで、そのようなばらつきの原因の個人差にすごく関心をもちました。
私が関心をもったラットの個体差は、情動性(emotionality)と呼ばれるもので、人間で言えば、不安度の個人差と呼ばれるものです。私は、常々、何とかして、ラットの情動性における個体差というものを測定し、人間でいうならば不安尺度のようなものを作りたい、そうすると、それによって前もって選別すれば、標準偏差が小さいグラフが描けるだろうと考えていたのです。私は、情動性の研究を筑波(当時は東京教育大)の藤田統さんたちと連絡を取りながら、いろいろやっていたのですが、むなしい努力が続いていました。ラットの情動性は、新規な場面での移動の少なさや排せつの頻度がインデックスなので、それを使って情動性の区別をしようとしていたのですけれども、その手の研究はすべて実りませんでした。
そういうことを考えていたところに、Eysenckのところに、情動性の高い系統のラット、情動性の低い系統のラットを、インブリーディング(選択交配)で、つまり、ある物差しで測った情動性の高い、あるいは低い個体同士どうしの雄と雌をかけ合わせて(選択交配させて)、遺伝的に高情動性系、低情動系のラットを作っていることを知りました。Eysenckはパーソナリティの研究者ですから、パーソナリティの研究の一助として、その基礎研究をやっていたわけです。そしてそのラットを使った研究をすれば、情動性というものの研究に糸口がつかめるかもしれないということで、半分の目的は、そのラットを使った動物実験をするために行ったのです。そこでやった動物実験は論文になっています(Imada,H.(1972).Emotional reactivity and conditionability in four strains of rats.
Journal of Comparative and Physiological Psychology, 79.474-480.)。当時は外国の雑誌に投稿する人はあまりいませんでしたので、このように外国の雑誌に投稿することに先鞭をつけた一人は、私だったように思います。
ただ、最初にその二つの系統のラットを見た時に私はがっかりしました。なぜかといいますと、高情動のラットと低情動のラットは、体のサイズが全然違うのです。高情動のものは大きいのです。低情動のものは小さくてちょこちょこと動くのです。選択交配をしているので、体重の違いが出てしまっていたのです。行動実験をする人間にしてみると、これはものすごく不都合です。例えば、隣室に移動するような回避行動の場合、大きさが違うと移動時間の違いを測っても意味がないわけです。
その点、水なめ行動というものは、舌の先だけ動かせばいいわけです。箱の中でじっとしていて舌の先だけ動かすわけですから体重の違いは問題になりませんので、それは非常にうまくいきました。
イギリスでは、関学でやっていたように何箱も使えませんでしたが、それでも四つぐらいは作ってくれました。イギリスには専用の職人がいて、何か装置が要るといえば、自分で作るのは許されませんでした。専門の人にあれこれと図面を書いてやってもらうのですが、作る人とやる人とは別々なので、小回りが全然効きませんでした。
私はイギリスではあまり生産的ではありませんでした。まず、第一に、イギリスは動物愛護の国ですから、動物実験するのに、特にショックなどを与えるといいますと、これにはライセンスがいるのです。許可証は簡単に発行してもらえず、医学部の医者に面接まで受けに行きました。実験内容を説明してやっと実験ができるようになるのに3か月待ちました。それから、装置を注文しました。だから、結果的には、1年弱で1個しか実験ができませんでした。
ただ、結果は、彼らを満足させるような結果になりました。高情動のものは非常に情動的で、低情動のものは非常に非情動的であるという結果がきちんと出ました。水なめの行動の抑制が、同じ条件であるにもかかわらず、高情動のものはピタッとやめるし、低情動のものはたくさんなめるしという結果でしたし、また標準偏差も、コントロールに使った他の二つの系統のラットに比べて小さいものでした。
Eysenckはイギリスに来る前、ドイツのジュニアでテニス選手でして、チャンピオンまでは行かなかったけれども、かなりいいところまで行ったというテニス好きでした。それで、私がイギリスに滞在中彼とはテニスをしました。またEysenckが行動療法学会の講演で日本に来た時には、関学でもテニスをしました。Eysenckとテニスをした心理学者は、私だけではないでしょうか。『関西学院大学心理学研究室80年史』に写真が出ています。
イン どのような感じの人なのですか。要するに、書いている物を読んでいると、割と当時は、いろいろと論争的な印象ですが、実際の人物としては、どのような感じのかたですか。
今田 印象は正反対です。非常に表現は穏やかで、大きな声で話さないし、英国紳士という感じです。けれども、もう自信の塊ですね。自分は偉いのだということは確信していました。そのような人です。けれども、それは、鼻につくような威張り方ではないです。彼はものすごくたくさん物を書いているでしょう。いつでもオフィスで、時には立ち上がって歩きながら話し、それを秘書が書き取る、いわゆる口述筆記による執筆です。
イン ありがとうございます。すこし話が変わりますが、先生は多くの学会でも役員をされています。差し支えない範囲で、印象に残っていることを教えていただけますか?
今田 学会は、異常行動研究会という会を作って、それは今でも行動科学学会として存続しています。他にも日本心理学会、日本動物心理学会、日本基礎心理学会の理事をしたり、編集委員もしましたけれども、学会活動で忘れられないのは国際学会との関わりです。私は基礎研究者なので、あまり実質的でない国際学会は嫌いで避けていました。
ところが1990年に、阪大の三隅二不二先生が中心になって、国際応用心理学会を京都で開催することになって、近くの大学だからということで動員されました。そして、1990年の大会時は開会式の司会までやらされることになりました。私は割に英語は不自由しない方ですから、あまり苦にはならなかったのですが、その司会でにわかに脚光を浴びてしまいました。国際心理科学連合IUPsySという組織で日本からの理事をされていた東洋(あずま ひろし)先生が、ちょうどその年で退任で、後任を探しておられたところへ、私がステージに現れたものですから、「おまえは俺の後をやれ」ということになって、初めて92年のブラッセルの国際心理学会に行き、選挙で理事に選出されました。
私はほどほどに社交的ですし、言葉も割に不自由しないほうだから、12年間の理事の間には随分いろいろな人と知り合って、よい経験になりました。だから、私の国際との関わりも、三隅先生というボスの一声で決まってしまったようなところがあります。これも他動です。古武、Spenceに続く三つ目です。
実は、今思い出しますと四つ目がありました。そのボスは私の家内です。1970年代のことですが、関西外国語大学というところから、留学生を相手に「日本人の心理」の講義を担当してほしいと依頼がありました。しかし実験心理の私がそんな講義が出来るわけがありません。こんなテーマは本来社会心理学者の領域のものですが、英語での講義ということで誰にでもできるというわけにはいかず、私に目をつけたようなのです。依頼主の元関学の先生は、それでも何度も頼んで来たのですが、その都度断っていました。ところが私が留守中に家内が勝手に引き受けてしまったのです。かねがね、ねずみ相手の実験心理学者の私の狭い視野を何とか広げたいと思っていたようで、これで私は抜き差しならぬ状態になりました。結局、引き受けざるを得なくなったのですが、随分勉強をしたこともあってか、幸いJapanese Psychologyと題したその講義は大変好評で、後に関学でも国際プログラムが始まったときにも担当したので、15年近く続けたと思います。これは私の大きな財産になり、後に大学行政に関わって挨拶や講演の機会が増えたときに、大変役に立ちました。家内が引き受けてしまったときにはパニックでしたが、これも大ボスの圧力がよい結果につながった四つ目の例です。
しかし、私は、今思うのですけれども、あまり目的論になってもいけませんが、すべて、世の中に意味がないことはないと思っています。逆に言えば、すべての事を意味あらしめるように行動してきたといえるかもしれません。「そのことがその時に起こったのは、絶対、何か私の人生において意味があるに違いない、それならば、それを生かそうではないか」という思いが私の中にあり、いやいやすることはありませんでした。
また、何かを始めれば、手抜きのできない性質ですから、一生懸命にやります。そうすると、深みにはまるということになってしまうのです。もっとも国際心理学会関係の仕事が、現役バリバリの時であれば仕事を犠牲にしなくてはならなかったと思います。しかし、1990年頃には、もう私は文学部長もしていましたし、随分、大学の行政との関わりがあり、95年からは学長にも選ばれ、心理学とは疎遠になっていた時代でしたので、ある意味ではよかったと思います。視野も広がったし、学校の行政をするについても、それらの経験はプラスでこそあれ、マイナスではなかったと思います。だから、私の人生を振り返ると、すべて神様はよきに計らってくださったなという感じがします。
イン ありがとうございました。