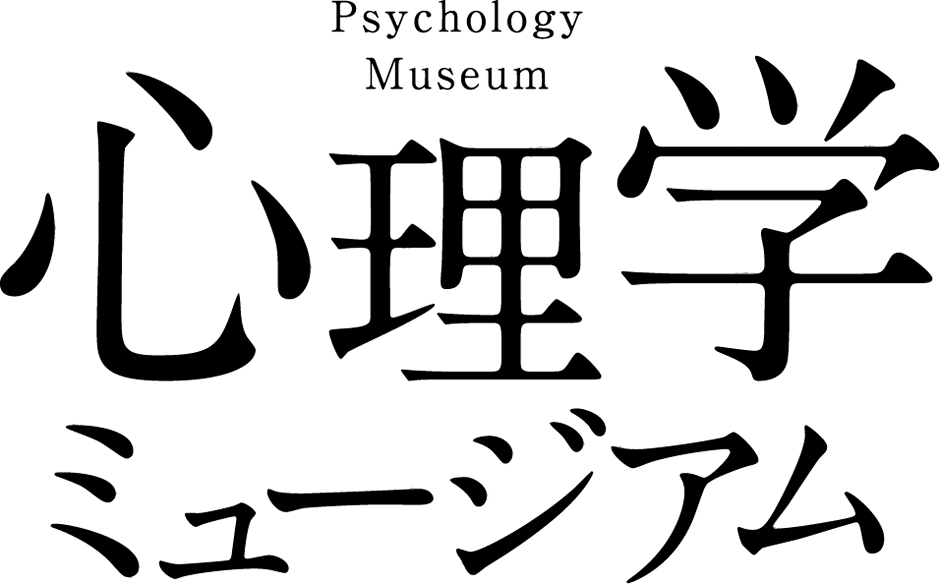原 一雄先生
動画は抜粋です。インタビュー全文は下記からご覧ください。
原 一雄先生の略歴
・天王寺師範学校での原谷達夫先生と「鈴木ビネー式知能検査」の出会い、小学校での障害のある子どもの教育経験、アメリカで出会った日本の心理学者、Joseph Cooper先生のもとでの民族的偏見研究、ターマン教授クラスへの選抜とターマン教授の死、ヒルガードゼミ、フェスティンガー教授との碁、視床の中継核の組織学的研究、国立衛生研究所での在外研修
・天王寺師範学校、小学校教員を経て、1954年カリフォルニア州立サンノゼ大学MA修了、スタンフォード大学助手を経て、1960年スタンフォード大学博士課程修了Ph.D「Behavioral effect of posterior association cortical lesionsin cats」。1995年国際基督教大学定年退職、1999年亜細亜大学定年退職
・小学校の先生として障害児を教えた経験のお話しから、数多くの内外の歴史的な研究者との交流など、原先生のお話しは幅広く、心理学の領域の幅広さを改めて感じました。
日時:2015年3月5日(木)
場所:武蔵野美術大学吉祥寺キャンパス
インタビュアー:荒川歩(武蔵野美術大学)、高砂美樹(東京国際大学)、小泉晋一(共栄大学)
場所:武蔵野美術大学吉祥寺キャンパス
インタビュアー(以下、「イン」と略)A 本日はお忙しい中、日本心理学会のオーラルヒストリーの企画にご賛同いただき、ありがとうございます。事前に簡単に大枠のお話しいただくテーマを提示させていただきましたので、順にそれにそってお話をうかがえればと思います。最初のテーマは、心理学を学ぶに至る経緯です。当時はまだ心理学は、少なくとも日本では、それほど有名な分野ではなかったと思いますけれども、なぜ心理学に関心を持つに至ったのかということについてお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
原 はい。そもそも、私は最初、数学と物理の教員になろうと考えていた人間です。終戦の時は海軍兵学校の舞鶴分校(旧海軍機関学校)というところにおり、8月6日に広島へ「ピカ・ドン」が落された翌日、京大出身の教官からウラニューム92の原子核構造について学び、どうやらこれが今度の爆弾に使われたらしいということを聞かされました。
間もなく終戦の日を迎えましたが、あの玉音放送も雑音に紛れて何のことやら全く分からず、その日の午後は「もっと頑張れ」と言われたものと思って一層訓練に励んでおりました。ところが、夕方になって「どうやら日本が負けたらしい」と判り、「それじゃあ、私の命も助かった!」と、悲喜こもごもの複雑な思いで復員しました。
家庭の事情もあり、他の友人たちのように横滑りに旧制高校へ入ることができず、1年半ばかりゴム工場で職工をしておりましたが、どうしても勉強したい気持ちを抑えることが出来ず、授業料が要らなくて、逆に毎月給費がもらえた天王寺師範(後に大阪第一師範学校と改称)に入り、数学と物理の中等教員免許状を取るつもりで勉強しておりました。最初の年に何方からどのような授業を受けたか、ほとんど記憶にありません。ところが、2年目に男女共学となり、理系の学生は平野にある元の女子師範へ転校することとなり、そこで原谷達夫先生という東大出の若い心理学の先生に初めてお目にかかりました。
この原谷先生は非常に進歩的なお考えの方で、教職員代表をなされており、学生委員長の私とは何度か議論を交わしました。ところが、ある日突然、「大阪城の隣にある追手門学院より知能検査を依頼されたから、原君、やってみないか」とお声を掛けて下さいましたので、早速友達を誘い、全校の生徒に対して「鈴木ビネー式知能検査」をやらせてもらいました。他にもう一つ「大伴式」がありましたが、田中寛一先生のものは未だない時でした。
実はこのテストを引き受けるまで、心理学と数学がこれほどまでに縁の深いものとは一度も考えたことがなく、大変驚きました。ちょうど数学の演習で、正規分布の公式は(2分の1+2分の1)のN乗を無限大に積分すれば出てくると知り、「公式なんかを覚えるのは馬鹿のすることで、必要なときに自分で作ればよい」などと生意気にうそぶいていた頃でした。このときから、原谷先生とは急に親しくなり、先生のご推薦によって付属中学で教育実習をし、また、就職の内定までもいただいておりました。
ちょうどその頃に、30年前に日本を飛び出して行方不明になっていた母方の祖父が、戦時中はワイオミング州の強制キャンプに収容され、戦後はコロラド州に住んでいるということが、進駐軍を通してやっと分かりました。その途端に、是非ともアメリカでもっと勉強をしたいと思うようになりましたが、市民権を持っていなかった祖父には、孫の私を呼び寄せる資格がありません。そこで、アメリカ人の「保証人」を探してもらうことになりました。
ところが、どうやら私の留学の意志が大阪府の教育委員会へ伝わったらしく、卒業後は付属中学へ就職できる筈だったのに、実際に手にした辞令には「中河内郡縄手町立小学校教諭」と書かれていたのです。そして、受け持った児童50余人の中に、二人の障害児がおりました。一人は知恵遅れで鼻の欠けた女の子、母親が梅毒だと聞かされました。もう一人の男の子は、両親がアル中で、片時もじっとしておられない、今で言う多動症の子でした。私の前の担任は、児童たちへ「二人は『お客さん』だから一切構わないように」と躾ていたらしいのです。
当時は養護学級などありませんから、障害のある子も、ない子も、同じ教室で教えねばなりません。そこで、いずれこの子の親たちが死んだとき、いったい二人はどうやって生きてゆけるだろうか。もしも今の内に、少しでも自分に出来ることを探してやれないものだろうかと、他の児童たちと一緒の小さなグループに入れ、そこの班長に「今日はあの子に何ができたか、教えてほしい」と毎日尋ねておりました。そうこうしている内に、ようやく私の渡航に必要な保証人が見つかり、領事館からビザも降りましたので、「皆には申し訳ないけれど、先生にもっと勉強をさせてくれないか」と子供たちに詫び、アメリカへ向かいました。
それは1950年の11月、ちょうど朝鮮戦争の最中で、北側の軍隊がいつ何時九州へ上陸するか分からない時で、プレジデント・クリーブランド号という大きな客船でしたが、潜水艦の攻撃を避けて灯火管制を敷き、真っ暗闇の中を神戸港から出航しました。次の日に横浜港へ立ち寄り、ドラの音と共に初めて大声で「さようなら」を叫び、五色のテープを投げることができました。16日間の船旅の後でやっとサンフランシスコに到着し、そして、上陸した直ぐ次の日から保証人の親戚の家に引き取られることになりました。そこはサンフランシスコの南、サンノゼという町の高校の先生の家でしたが、皿洗いと庭掃除をしながら昼間は学校に行かせてもらえる「ハウス・ボーイ」、すなわち、住み込みの書生として働きました。
通学したサンノゼ州立大学は、実は西海岸で最初に建てられた師範学校(normal school)が州立大学(state college)へ昇格した学校で、先生たちがとても授業に熱心、私にとっては非常にラッキーでした。そこで初めて「アメリカの心理学」に接し、心理学と数学をダブル・メイジャーに選んで、1953年6月に卒業しました。卒業式の翌日には、戦後日本から来た最初の卒業生ということで、地方の新聞にも写真が載りました。
この頃、私は目に留まった本を何冊か、師範時代にお世話になった原谷先生にお贈りしました。そうしたら、先生が訳されたゴードン・オルポート(Gordon W. Allport)著、 The individual and his religion.(1950) の翻訳書『個人と宗教』(岩波現代叢書 1953)がアメリカに届いたのです。そして、「あとがき」の最後には、「原著と参考文献とを送ることにより機縁を与えられた在米中の原一雄氏・・・」と、私の名前が初めて活字にされていたのです。それを見た途端、これではますます本気で心理学を勉強せねばならないと改めて思いました。ところが、更にこの本の序文に、今田恵先生が著者のオルポート博士について詳しく解説をされておられたのです。そのような訳で、日本には今田先生という私の恩師の原谷先生が最も尊敬している方がいらっしゃることを知りました。そして、1961年に帰国し、日心の会員となった翌年1962年度の学会大会が、何と幸運にも、今田先生の関西学院大学で催されましたので、そこで初めて先生に直々にご挨拶をする機会が得られたのです。
しかし、その前のアメリカ滞在中、佐藤幸治先生にお会いいたしました。それは1955年にサンフランシスコで催されたAPAの全国大会の折でした。私はスタンフォード大学の院生たちと大会の事務局で受付係をしておりましたら、一人の日本人がお見えになり、「京大の佐藤幸治だ」とおっしゃられ、会期中は私のオンボロ車で送り迎えをして差し上げました。また、学会の後でバークレーのカリフォルニヤ大学やミルス・カレッジにお出掛けのときには、私が運転手を勤めました。佐藤先生はお話を始める前に、カバンの中から木魚を取り出して「ポクポク・ポクポク」と叩かれるので、関係者の間では大変評判になりました。この時はまだ、佐藤先生がどのようなお方か全く存じ上げておりませんでしたが、後になり、ご著書の『人格心理学』(創元社 1951)の最終章で、最も理想的な人格像、すなわち、ゴードン・オルポートのいう「成熟した」パーソナリティとして、「菩薩」を挙げておられた方だということが分かり、お知り合いになれたことを今でも深く感謝しております。
それから、私が在米中に親しくしていただいた方の中には、音楽心理学で著名な、同じく京大の梅本堯夫先生がおられます。先生はピアノが大層お上手でした。恩師の矢田部達郎先生の奥様が宝塚のご出身だそうで、その伴奏を引き受けておられたとのこと。ですから、スタンフォード大学の構内に住む教授たちやそのご夫人方から「是非一曲聴かせて欲しい」と引っ張り凧でした。それでもお寂しかったのか、時々私の家でお茶漬けやおにぎりを所望されておられました。
少し脱線しましたが、私自身の心理学の勉強についてお話ししましょう。先にも申したように、私は元々心理学を専攻する心算はなく、途中から障害児の発達や心理統計に興味を持つようになりながらも、世の中の人間関係には極めて関心の薄い人間でした。ところが、アメリカ人の家庭に住み込むと、主人は高校の教師でも息子たちは、「日本人は卑怯者でずるがしこい」と私を詰るのです。「宣戦布告なしに真珠湾を攻撃した。だからジャップは・・・」と、ステレオタイプでもってしか私を見てくれませんでした。そして、同年輩の二世や三世の人たちは、自分たちを「バナナ」と称しておりました。「肌は黄色だが、中身は白い」という意味です。このように日系アメリカ人たちが己のアイデンティティを保たんがために大変悩んでいる姿を見て、私は修士論文の課題として、マイノリティ・グループの抱く民族的偏見を採り上げました。あのような社会では、誰しもが偏見を持たざるを得ません。マジョリティがマイノリティに対するのと同じように、マイノリティもまたマジョリティや他のマイノリティに対して偏見を抱くメカニズムが、私の眼には非常におもしろく映りました。そこで、解決の鍵が社会心理学にあるのではと思い、ジョセフ・クーパー (Joseph Cooper) 先生の下で、「少数民族の社会的態度」につき調査研究を行った訳です。
後で判りましたが、この先生はクルト・レヴィン(Kurt Lewin)教授の門下生で、したがって、行動の全てをライフ・スペース内におけるgoal seeking behaviorと考えます。そこで、少数民族集団がどのように心理的バランスを保とうとしているのか調べるため、私は三つのスケールを用いました。一つはドイツのナチズムに染まり易かった人たちの性格特性を測るため、レヴィンが考案したEF(ethnocentrism‐fascism)スケール。二つ目はマズローの不安(anxiety)スケール。三つ目には、かつてゴードン・オルポートが性格特性の表記に選んだ数多くのタームの中から、アメリカ人の特性と、日本人ないし日系人の特性に合いそうなもの、それぞれ20個を選択項目に選び出しました。そして、これら相互の関係から、民族集団間の偏見(prejudice)、すなわち、判断以前に働かす色眼鏡(pre - judgment)の特質を検討しようと試みました。そこで、『北米毎日』という新聞社を通して、シアトルからロサンゼルスまでの西海岸に住む日系二世たちへ、質問紙への回答を依頼したのです。
調査の結果は、EFスケールの値が高い、すなわち、エスノセントリックな人たちほど、それから、不安度が増せば増すほど、アメリカ人と日系二世に与えられるステレオタイプが、だんだんと似通ってくるのです。ところが、最も不安度が高く、直ぐにでも治療を要するような人々だけが、その類似度を逆にすとんと落し、自分たちはこれだけアメリカ人とは異なるのだと、世間で言われている民族的性格特性を容認しようとするのです。もしこれを解釈すれば、フロイトの云う抑圧(repression)、投射(projection)、反動形成(reaction formation)、転移(displacement)などなど、心理的なバランスを保つための、いわゆる自我防衛機構(ego defense mechanism)の表れではないか。このようなことを修士論文に纏めましたら、ファイ・デルタ・カパー(ΦΔΚ)からもこの年度の新メンバーに選んでもらえました。
その後で幾つかの大学院へ願書を出したところ、ミネソタ大学とスタンフォード大学の両方から入学許可の通知が届きました。しかし、ミネソタ大学の方は奨学金付きながらも西海岸からは大層遠いので、働きながらでも何とかやっていけそうな、多少とも様子の分かっている近くのスタンフォード大学を選び、追手門学院での知能検査や縄手小学校で接した子供たちのことを再び頭に蘇らせて、何とかして彼の有名なルイス・ターマン(Lewis M. Terman)教授のご指導を仰ぎたいと思ったのです。
この年に入った院生20名の内、ターマン先生から指導を受ける予定の4名の中に加えてもらえて大喜びしておりましたら、9月の入学式の日に先生が既にご入院中と聞かされ、その年の暮れには大学こぞっての盛大なご葬儀が大学教会で営まれ、私も参列することとなりました。ですから、先生にはとうとう一度もお目にかかることができませんでした。そして、私たち院生の指導はクイーン・マッケンマー(Quinn McNemar)先生、日本ではマクニーマーと訳されており、スタンフォード・ビネー知能検査(1937年度版)の改訂を担当した統計学者に引き継がれ、学内でアルバイトを探していた私に、「今度、ウィスコンシン大学のハリ―・ハウロー(Harry F. Harlow)教授のところから来たマイク・ウォーレン(J. M. Warren)准教授が動物飼育室で人を探している」と教えて下さいました。多変量解析のゼミに出ていたので、お声を掛けていただけたのでしょう。
このマッケンマー先生は、ターマン教授が最初の1916年版スケールを作成したときの「ジーニアス・グループ」の一人で、同僚のアーネスト・ヒルガード(Earnest R. Hilgard)先生も、また、ロバート・シアース(Robert R. Sears)先生も、そのメンバーだと聞きました。実はハウロー先生もスタンフォード大学の先輩で、在学中の名前は「何とかヴィスキー」と云って違っており、大学の図書館で先生の修士論文を探し出すのに一苦労した覚えがあります。先生の指導教授が、「もしこの名前だと直ぐにユダヤ人と判ってしまうから、将来学会で活躍するためには今の内に変えろ」と改名させたそうです。そのハウロー先生が、愛弟子のウォーレン先生を母校に送り込み、有り難いことにその実験室で私がアルバイトをさせてもらえることとなり、この時に初めて生理心理学の世界へ本気で首を突っ込むこととなりました。
この頃、ヒルガード先生にも大層お世話になりました。かねてよりご本の Theories of Learning(1948)でお名前だけは存じ上げておりましたので、当然「学習」についてご指導をいただけるものと思い、先生のゼミに入りました。
その前に、少し余談になりますが、当時のスタンフォード大学の心理学研究科について述べますと、そこは「統計」「実験」「学習と発達」「人格と社会」「比較と生理」「臨床」の六つの部門に分かれており、そして、doctorial candidate(博士候補)になる前にはqualifying exam(資格認定試験)があり、主専攻と二つの副専攻、および心理学以外の副専攻と外国語の五つの筆記試験を後期課程1年目の終わりまでに通らせないと、続けて在籍することが出来なかったのです。
そこで、これまで余り勉強してこなかった「学習理論」を学ぼうと、ヒルガード先生のゼミに入りましたら、何と討議や演習の課題は専らhypnosis(催眠)についてなのです。何故かと思ったら、アメリカ航空宇宙局(NASA)からの要請で、委託研究を引き受けておられたのです。宇宙飛行士を月に送り出すには、長い時間をカプセルの中で過ごさせねばならず、大きなストレスがかかるので、その間は催眠状態にしておき、月に到着する直前にそれを解けば、心理的負担が少なくて済むだろう。そのためのマニュアル作りだ、ということでした。
そこで、私たち受講生は、先ずあの5本の指を組む手法でもって、どれだけ催眠にかかり易いかの検査を受けました。私の名は「一雄」ですが、「キャーズ」と呼ばれていたので、先生が申されるには、「キャーズ、おまえはなかなか催眠にかかり難いようだ。しかし、そのブロークン・イングリッシュは催眠をかける方に向いているから、そっちの役へ回れ。」すなわち、「呪文のように聞こえてよく効くだろう。」そんな冗談を言って下さる、大変思いやりのある先生でした。
もうお一人、この頃にお世話になった先生には、認知的不協和理論で人気の高かったレオン・フェスティンガー(Leon Festinger)先生がいます。しかし、教室での指導はなかなか厳しくて、時々意地悪をなさる先生でした。ところが、ゼミの後で、「キャーズ、おまえは後に残れ」と言われるのです。それで、「何のご用でしょうか」と訊ねたら、「日本から来たのだから、俺に碁を教えろ」とのこと。そこでやむなく碁の手ほどきをして差し上げたところ、一月も経たぬ内に私を負かしてしまうのです。後で判ったことですが、先生は高校生のときにヨーロッパでチェスのチャンピオンになったそうです。後にフルブライト交換教授として東大に来られた際、日本囲碁連盟から初段を授与されて、得意なお顔で帰国なさいました。このような先生方のお陰で、学位論文の最終審査、すなわち、私の最も苦手とした口述試験も何とか切り抜けることが出来ました。
そして、これらの恩師の中にもうお一人、コムラド・アカート(Komrad Akert)教授を是非とも加えねばなりますまい。この方はスイスのチューリッヒ大学にある脳研究所の所長で、私が初めてお目にかかったのは、ウイスコンスン大学でハウロー教授との共同研究をなさっていた時でした。夏休みにはスタンフォード大学へもお出でになり、医学部の手術室で、ウォーレン先生と一緒に、ネコとアカゲザルの脳皮質損傷および切除手術の手ほどきを授けていただいた方なのです。
前後してしまいましたが、この当時に私がやっていた研究の概略を述べますと、先ず被検動物の正常時の行動、例えば、どれだけの精度で弁別学習ができるのかなどを個体毎に検査しておき、次に脳のある特定部位を破壊して、術後に機能がどれだけ脱落したのか、また、再訓練でどこまで回復させることが可能かを気長に観察し、最後には動物たちに甚だ申し訳ないけれども、いわゆる安楽死をさせて脳を取り出し、皮質に施した損傷が他の部位、中でも特に視床(thalamus)の中継核に、どのような変性が起きていたかを組織学(histology)的に調べるものでした。
ご存知の通り、神経線維が一旦切断されますと、終末ボタン(terminal button)が接続していた次の細胞体の周辺に「グリオーシス」(gliosis)と呼ばれる症候、すなわち、そこを取り囲むグリア細胞が増殖し、徐々に細胞体を食い潰していくような病変が起こります。この二次的変性を詳細に検出することにより、初めて脳内のある部位と他の部位、例えば新皮質と視床核や、古皮質と脳幹部との関係などが追跡できるのです。もちろん、神経細胞と神経線維の分布密度や配置の状態は、既にいろいろな染色剤を用いて解剖学的に調べられておりましたが、機能的な関係を明らかにするためには、裏付けとなる組織学的データが是非とも必要で、それが論文に付いていないと、この領域の学会誌へは載せてもらえませんでした。ですから、後に私はヨーロッパへの視察旅行の帰り道、スライド標本を片手にチューリッヒへ立ち寄り、顕微鏡による二次的変性の判定に間違いがなかったかどうかをアカート先生に確認していただきました。
何度も脱線して申し訳ないですが、ハウロー先生の研究室を訪れた時、先生のお顔が大きく腫れ上がっていたので、「何故か」とお訊ねしたら、「コバルト60にやられた」とのお返事でした。サルを使って放射能の影響を調べる実験をされている最中だったようです。当時のアメリカでは、国策に従って、また、研究費獲得のために、「学習理論」の大家であるヒルガード先生が催眠に、「学習セット」や「スキンシップ」で高名なハウロー先生がコバルト60を用いた研究に関わっていたような時代でした。
次に、また元に戻って日本での恩師について話を続けますと、1963年の秋に文部省と民主教育協会(Institute for Democratic Education:IDE)の主催で、国・公・私立大学の学長先生方総勢14名がアメリカ・イギリス・ヨーロッパ諸国の大学を視察旅行することになり、私にカバン持ち(書記)の役が命ぜられました。ところが、その一行の中に、あの今田恵先生も入っておられました。お陰で二ヶ月ばかりの旅行中、先生とはいろいろなところへご一緒させていただき、親しくお話を伺うことが出来ました。その中でも一番強く記憶に残っていることは、ちょうど大西洋を渡る飛行機の機内でのことでしたが、「原君、世の中にはICUのことを何かと批判する人が大勢いるけれども、一つ徹底的にアメリカ流の教養教育を試みて欲しい。その成功例も、また失敗例も、共に日本の大学教育にとって貴重な事例となるのだから、しっかり頑張るように」と励まして下さったことでした。
この視察旅行中に今田先生とご一緒に撮影した写真では、羽田空港の出発時とデューク大学を訪ねた折のものがあります。デューク大学には、嘗て創立当初にイギリスから迎え入れたウイリヤム・マックドーガル(William McDougall)教授が、彼の有名な Social Psychology (1916)を書いたときの机がそのままに残されており、今田先生が大層感慨深く手のひらで何度も撫でておられました。また、スタンフォード大学のキャンパスで、ヒルガード先生と今田先生と息子さんご夫妻の並んだ写真も残っています。これは寛先生がアイオワ大学で学位を取られて帰国の途中、ヒルガード先生の研究室で恵先生と何年振りかに親子の対面をなされたときのものです。
このように、今田恵先生と原谷達夫先生とのお二人こそが、数こそ少なく、しかもいずれの方からも教室で直接ご指導を仰ぐ機会はなかったものの、私にとっては掛け替えなき「恩師」とお呼び申し上げたい日本人の心理学者なのです。
インB 貴重なお話をありがとうございました。ところで先生をICUに呼んでくださった方は。
原 それは、形の上では岡部弥太郎先生です。しかし、帰国して初めて新任のご挨拶に伺いましたら、いきなり「その内に古畑和孝君がイリノイ大学から帰ってくるから、講師の契約が切れるまでに次の就職先を探しておくように」と告げられ、寝耳に水と大変びっくりいたしました。幸い次の年には助教授へ昇格することができ、いわゆる「終身雇用」(tenure)の権利が得られたのですが、しかし、既にかつてお世話になったウォーレン先生へ仕事口を頼んでおいたものですから、3年後の1964年にはペンシルベニア州立大学の動物行動研究所へ客員研究員として異動しております。
インB客員というものは、イメージとしては、何か月間か行けるという感じ、今のサバティカルのような感じなのですか。
原 はい。ただし、この時は休職扱いでした。ICUには既にサバティカルの制度があり、6年教えると7年目にはまるまる1年間の有給休暇がもらえましたので、後にはアメリカの国立衛生研究所やプエルト・リコ大学の医学部、あるいはコロラド大学へも2度ばかり、7年毎に出掛けることができました。
ここで少しICUの心理学研究室の創設について経緯をお話ししますと、この大学はもともと大学院大学を目指しておりましたが、当時の「大学設置基準」によれば、学部なしには大学院を置くことができないと言うことで、「それならば、卒業生がどのような分野の大学院へも進められるように、学部4年間を教養学部(リベラルアーツ・カレッジ)にしよう」と、元同志社大学の総長だった湯浅八郎先生を学長に、そして、アメリカのシラキュース大学で教育研究所所長をしていたモーリス・トロイヤー(Maurice E. Troyer)先生を副学長にお招きしました。
甚だ乱暴な言い方かも知れませんが、そもそも日本が戦争に負けた原因は、軍人たちが判断を誤ったばかりでなく、良識を持つべき教師も役人も共にだらしがなかった。そして、金持ちは優遇されても、貧乏人が無視されたからではなかったか。よって新しく生まれ変わるべき日本の人材育成のためには、大学院に「教育」「行政」「社会福祉」という今までになかった三つの専攻科を設けよう。ところが、当時は「教育学」を英語で「ペダゴジィ―」(pedagogy)と呼び、「教育」(education)という専門分野はまだ一人前の学問として認められていなかったので、大学院で教育に関する理論と実践の両方をしっかり研究するために、戦後に進駐軍のGHQと難しい折衝を重ねながら新しい「学校教育法」を制定したときの文部次官であった日高第四郎先生を大学院部長に、そして、カリキュラムの最も要となる教育心理学の主任教授として岡部弥太郎先生をお迎えしたのです。
ところで、私自身はと云えば、トロイヤー先生がロックフェラー財団からの助成金で「大学生の価値観研究」を始めるに当り、統計的処理を受け持つようにと言われて日本へ帰ってきた者です。この研究の目的を簡潔に述べますと、学生たちに自分自身の価値観と在学中における変容とを顧みさせ、卒業後の進路選択の参考に供するという趣旨のものでした。そこで、入学した直後の春学期と2年生最後の冬学期、そして、4年生の冬学期は就職活動で忙しいからその前の秋学期にと、在学中の3回に亘って1+1+1単位の必修科目を取らせ、授業中に質問紙を用いて「人生観」「政治経済観」「宗教道徳観」「芸術観」などを調べ、その結果を討議の時間に本人たちへフィードバックして、自分の価値観の全貌を明らかにさせようというものでした。
インBスタンフォードで学位を取得されて、先生はすぐにお戻りになったのですか。
原 いいえ、最初はカナダのブリティッシュ・コロンビア大学へ行く予定でした。既にそこの心理学研究室へ就任が内定しており、それまでの間をスタンフォード大学の医学部の生理学教室で副手(Research Associate)として勤務していたのですが、突然ICUからお呼びの声が舞い込んできた訳です。
実は、このICUとは、その創立以前から妙にご縁がありました。渡米した翌年の1951年にサンフランシスコ市のオペラ・ハウスで連合国との間で講和条約の会議が開かれたとき、私は夏休みのアルバイトを辞めて毎日傍聴人として通い続け、9月4日の最終日には吉田茂首相が条約にサインするのを2階のバルコニー席から見ておりました。そして、高揚した気分のまま帰り道にパイン・ストリートの日本人教会へ立ち寄りましたら、「今夜の献金は、近々日本に新しく建てられる大学へ贈られるものだ」と聞かされ、そのときは未だ大学の名前すら知りませんでしたが、「アメリカとカナダのキリスト教徒による共同プロジェクトなら、大変結構なことではないか」と、サンノゼへ帰るためのバス代1ドル50セントを残し、僅かでしたが財布の底をはたいて献金袋へ入れたことを覚えております。
それに加えて、スタンフォード大学から学位の取れることが分かった頃、かつての保証人が私に内緒でこの新しい大学に寄付をし、併せて「キャーズを雇ってみてはどうか」と湯浅学長宛に手紙を書いてくれたらしく、「それならば、丁度トロイヤー先生が統計の出来る人間を探しているから来い」ということで、教育心理学研究室の岡部先生の下で働くことになった訳であります。当時、この研究室には先任者の星野命先生とガイダンス専門の都留春夫先生がおられ、そして、肥田野直先生と池田央先生が、毎週非常勤講師として東大からお出でになっておられました。
ですから、私は4年目に一旦ペンシルヴァニヤ州立大学へ出て行きましたが、休職中であったにもかかわらず、「この度行政部の中に新しく入学志願者の選考を担当する専門部局を設けたから、その責任者になれ」と、1966年の夏休みに急ぎ帰国するよう命じられました。些か自慢げに聞こえますが、日本の大学で「入学事務部長」(Director of Admissions Office)という公式の肩書きを与えられたのは、多分私が最初の人間と言えるでしょう。
ここで是非、入学志願者の選考方法にかかわる岡部弥太郎先生のご功績についてお話しさせて下さい。恐らく皆さん方もよくご存知のことと思いますが、戦後間もなく、確か1946年から、大学の入学試験には文部省が作成する「進学適性検査」が使用されました。ところが、6年間は続けられたものの、7年目に中止となりました。多くの学会や日教組、そして、特に国立大学の人々が、「入試問題は学生を受け入れるそれぞれの大学が作るべきものであり、文部省が作るようなテストは・・・」とこぞって強く反対し、遂に廃止へと追い込んでしまったのです。そのとき、「受験生の能力を測る道具として如何ほど有効なものかがまだ十分解っていないのだから、追跡研究をするためにも中断してはならない」と、テストの継続を主張したのは、岡部先生が会長をなさっておられた応用心理学会のみであったのです。
しかし、岡部先生はICUへ来られた後も、この「適性検査」の必要性を唱えられ、「高校で身に付けた『学力(achievement)』を測ることはもちろん大切だが、将来大学に入学してから今までに学んだことのない新しい学問に挑戦することができそうかどうか、是非とも志願者たちの『適性(aptitude)』をも同時に測るべきだ」というお考えでした。しかし、アメリカのカレッジ・ボード(CEEB)が施行するSATには版権が付いており、日本でそのまま翻訳して利用することはできません。幸いにもSATの原型を作成したミラー博士という心理学者がトロイヤー先生のお友達でしたので、ご了解を得てその方が作成した「ミラー・アナロジー・テスト」を日本語に訳し、「一般能力検査」と称して判定資料の一つに加えました。部外へは極秘でしたが、心理学研究室の教員たちが、毎年このテストの改訂作業、すなわち、古い問題の項目分析と新しい質問項目の開発に関与しておりました。因みに付け加えれば、その手法は、将にマッケンマー先生からの受け売りです。
他方の「学力」評価については、高校間に格差があるのは致し方ないけれど、それでも志願者の能力は内申書で一応の見当をつけることが可能であろう。さほど教育環境に恵まれない学校にいても、クラスのリーダーをしていたような生徒には、やはりどこかに見所がある筈だ。したがって、一先ず内申書の記述を信頼し、積極的に審査の参考資料に利用すべきであろう。そして、大学側で作る適性検査、すなわち、「一般能力検査」と、更に、高校生がこれまでに眼にしたことのない教材を基に、どれだけ正確に内容を把握し、記憶し、そして新しい場面へ応用できるかを測るところの、自然科学・人文科学・社会科学それぞれの「学習能力検査」三つを加え、個人毎のプロフィールを眺めて総合的に判断する、というのがこの大学の入試方法でありました。私も少しは教育心理学の勉強をしたことのある人間でしたから、ただ単に教室で教えるだけでなく、学内での実践的奉仕活動として何が出来るかと問われれば、やはり、入試問題の作成や志願者選考のお手伝いが最も身近なものと言えましょう。そこで、この仕事にすっかりのめり込んでしまった訳です。
この時はちょうど池田内閣の時代で、東京女子大学の学長だった高木貞二先生が、新しく創設された能力開発研究所の所長に就かれました。そこでは、かつての「進学適性検査」やアメリカのカレッジ・ボード・テストのように、全国の高校生が何処にいても受けられるテストを作り、採点の結果は大学側が自由に入試へ利用できるもの、という案でした。その中の一つ、「適性検査」の開発に、私にも参加するようにと肥田野直先生からお声を掛けていただいたのです。
ところが、世間からは、「池田内閣の所得倍増計画のお先棒を担いでいる」と、さんざん悪口を言われました。「18歳人口を輪切りにして、進学組と就職組とに仕分けするためのテストだ」というのが彼らの解釈です。そのような雰囲気の中でICUが真っ先にこの「能研テスト」を採用すると公表したところ、直ちに学園紛争の火種となり、よその大学の学生たちまでが「わっしょい、わっしょい」と私の研究室へ押しかけてきて、遂には建物までも封鎖し、運悪く机の上に出しておいたフォルマリン漬けの脳切片やスライド標本を全部駄目にしてしまいました。そして、このスト騒ぎの責任を取らされて入学事務部長の職を首になり、更には2度目の学園紛争、すなわち、1969年に東大紛争の余波で学内が又もや荒れたとき、新しい学長の行政部から「キャンパスの中におられては困る」と、謂わば停職命令で出かけた先がアメリカ国立衛生研究所だったのです。
インB 少し戻りますけれども、先生が帰ってこられてから動物実験を続けることに当たっては、ICUには施設はなかったのですか。
原 はい。この大学には、そのような施設が全くありませんでした。ですから、同僚からは「もしも動物実験をやりたければ、外から研究費を稼いで来い」と言われ、そこでせっせと科研費を申請したり、アメリカの知人に寄付を頼んだり、足りないところは自分のポケットマネーでネコやサルなどを飼育しておりました。自動式のウィスコンシン学習実験装置(WGTA)も作りましたが、いよいよ資金が乏しくなり、サルの飼育と機械の維持管理が困難になったときには、甚だ残念ながら、当時東京女子大学から阪大に移られようとしていた南徹弘先生(現在甲子園大学副学長)に、動物と器具共々引き取っていただいたこともありました。なお、東京女子大学といえば、白井常先生がラットの実験をなされておられましたので、私も度々見学にお邪魔をし、また、先生にICUへお越し願って、学生たちに報酬用チーズの切り方を教えていただいたこともありました。
インB そうなのですか。ICUの中にも自然科学をやっておられる先生方が、当然いらっしゃったわけですけれども。
原 生物学研究室の先生たちとは領域が大分違いました。開学以来、遺伝学の泰斗でメンデル賞授賞者の篠遠喜人先生が東大から移られて自然科学科科長(後に学長)をなされておられましたし、モグラの生態学者もいましたが、生理学や神経学の研究者はいなく、私がこれらに関心を持つ学生たち、特に他大学の医学部へ進学を考える学生たちの相談相手を務めたこともありました。
インB では、もっぱら昔ながら心理の中に、心理と言いませんか、普通の文科系の大学の中に、その研究室があったのですか。
原 いいえ、赴任してきたときには、心理学研究室の中に生理学関係の設備は何もなく、全て一から始めねばなりませんでした。幸いキャンパスの中に、今は「富士重工」と名を替えた元「中島飛行機製作所」の社長さんの別荘があり、競馬用の馬を飼っていた小屋が残っていましたので、それを日曜大工でネコ小屋に、後にはプレハブのサル小屋へと改造しました。
インB当時のサルはどこから、買っていらっしゃったのですか、それとも。
原 輸入業者を通してインドからです。その前に、なぜ最初にネコを使ったかと申しますと、ネコは一種の国際的な規格品なのです。進化の途中で食肉類が分かれた後、イヌやオオカミなどはそれぞれがなおも進化を続けましたが、ネコはそこでストップしてしまいました。ですから、シャムネコと三毛猫とでは外見が大違いですが、世界中どこへ行ってもネコの頭は大きさも形も同じなので、手術に必要な脳の解剖図鑑は一つで済むのです。
ところがサルは、同じアカゲザル系統のニホンザルとインドのアカゲザル(Rhesus monkey)とでは、脳の形が少し異なります。ですから、犬山の京大霊長類研究所で分離脳(split brain)の手術をするときには、いつも苦労しました。ニホンザルの場合には、少し角度を変えてアプローチしないと、脳幹部の深い場所へメスが入らないのです。よく脳梁(corpus callosum)を切ると言いますが、実は脳梁だけでは不十分で、それが進化する基になった前交連(anterior commissure)も一緒に切らないと、本当の分離脳にはなりません。そこで、ニホンザルにこの手術を施すときは、通常のアカゲザルの脳図鑑に頼ることができません。このように、脳の組織解剖学的な知見を加えた研究をする場合には、インド産のアカゲザルを使用することが、医学や生理学では当時の慣習とされておりました。
さて、このアカゲザルは、もともとインド半島に生息している動物ですが、戦時中にあるアメリカ人の心理学者がカリブ海のプエルト・リコにある離れ島を買い取り、このサルを放して群れ同士の縄張り争いや、食糧不足の際のサバイバル方策などを観察していました。後に人が餌を与えるようになると、サルの数が増え過ぎてしまったので、国立衛生研究所(National Institute of Health : NIH)がその一部門の周産期生理学研究所(Laboratory of Perinatal Physiology)を移転させて、実験用の動物に利用することとしたのです。
ところで、なぜ私がNIHへ行くことになったかと申しますと、そこにドナルド・マイヤ―ズ(Donald Myers)先生が周産期生理学研究所の所長をしておられたからです。話はまた前に戻りますが、私がまだ院生の頃、ウォ―レン先生の紹介でロサンゼルス郊外のカリフォルニヤ工科大学(Cal. Tech.)にロジャース・スペリー(Roger Wolcott Sperry)教授をお訪ねしたことがありました。私が用いた実験装置も、実は「スペリー・ボックス」に手を加えたものだったからです。さて、心理学者のスペリー先生は手術があまりお得意でなく、後にノーベル賞を受賞された大脳半球の機能的左右差の研究も、分離脳手術は全てシカゴ大学の医学部でインターンをしていた若手医師のマイヤ―ズ先生に任されたそうです。そのマイヤーズ先生のお手配で、私の肩書きは一応プエルト・リコ大学医学部の上級研究員とし、ただし、実質は新しくサン・ファンに移された研究所で、動物を用いた心理学的実験を手伝うことになったのです。
周産期とは出産前後の期間を指しますが、母親の胎内にいる間には実にいろいろなことが起こっており、先にお話しした縄手小学校で教えたような子供が生まれてくることもあります。その当時、この研究所では専ら胎児の酸素欠乏や薬物の影響、特に母親が妊娠したことを自覚する前、すなわち、つわりが来る前に、胎内で起きているいろいろな生理学的異常が、出生後にどのような後遺症を起こすかという研究が進められておりました。
実は私自身が、両親の結婚10年目の子供で、難産の末に産れ出たときは全身が紫色、産婆さんが両足を持って盥のお水とお湯の間を行ったり来たりさせたら、やっとのことで息を吹き返した、という話を親からよく聞かされておりました。このようにお産のときが、これまた非常に重要な時期なので、その研究にサルを使用した訳です。具体的には、このサルの妊娠期間が平均159日と分かっていましたので、出産予定日の直前に帝王切開をして胎児を取り出し、いろいろな生理学的操作を加えた後、その後の成長発達に及ぼす影響を調べておりました。そこで、出生後の行動上の異常を分析させるために、心理学畑の私がプエルト・リコまで呼ばれた訳です。
ところが、ニクソン大統領の時代でして、ベトナム戦争で米軍側の旗色がだんだん悪くなると、政府の予算が大幅にカットされ、遂には海外の研究施設を全部本土へ引き上げさせることになり、そこで、私も仕事を中断してメリーランド州のNIH本部へ移りましたが、お陰でそれまでの研究が全部パーになり、早々に日本へ帰らざるを得ませんでした。幸いにも、その前に準備しておいた報告書の一部だけは、何とか当時の国際的な神経医学雑誌Brain Researchに、”Role of forebrain structures in emotional expression in opossum.” (1973)として発表することができました。
インB オポッサムを使われた比較心理学者は、それほどいないと思います。
原 はい、恐らく何処にもいないでしょうね。しかし、情動の研究には必要でした。というのも、プエルト・リコというところは、昔スペインの海賊たちがやってきたとき、船底からネズミが逃げ出して島中の農作物を荒らしたので、ネズミ退治にインドからマングースを連れてきました。ところが、このマングースには天敵がなく、今度はマングースが民家の鶏やブタまで襲うことになり、何とかして退治する方法はないか、それには先ず、その凶暴性を研究しようという訳でした。しかし、野生のマングースはなかなか捕らえることができないので、代わりに脳の構造が非常によく似ているオポッサムを使うことにしました。この動物も人間にはなかなか慣れ難く、刺激を与えると毎回同じような攻撃的態度を示します。そのように非常に獰猛であり、しかも脳の構造がよく似ているということから、あえてオポッサムを被検体に選んだのです。
この研究も、元はと言えば、新皮質とその下に隠れた古い脳組織との関連性に興味があったからです。ただし、当時研究の主流は、専ら連合野における機能的局在の問題で、BrocaやWernickeによる失語症の研究などを皮切りに、新皮質の中で運動野でも感覚野でもない、昔はsilent areaと呼ばれていた、すなわち、evoked potential が取り難いが、何か心理学でいう「連合」が起きているに違いないとの仮定から、「連合野」という名前の方が先に付けられた領域の解明でした。
先ず、前頭葉の連合野が高次の認知機能に関連するのではないかということから、真っ先に研究が進められました。ところが、後部の連合野については研究が大分遅れていましたので、私が学位論文の課題に採り上げることもできました。話が前後しますけれども、そのようにして知覚認知に関する後部連合野の役割と、更にそれらと視床(thalamus)との関連については少し解りかけていたものの、いわゆる辺縁系(limbic system)や、もっと脳の古い部分と情動との関係については、研究がさほど進んでいなかったので、あえてそれを取り上げようとしたのです。今では誰もが知っている海馬(hippocampus)や、脳の話で流行りっ子の扁桃核(amygdala)、更にそれに加えて梨状葉(pyriform lobe)などと情動との関係、特に凶暴性についての神経生理学的機序を調べようとしたのです。
このような関連性は、以前から「ロボトミー」によってもそれとなく示唆されていたことです。今では話題になることがほとんどありませんが、戦争中のこと、いつ何時鉄砲玉が飛んで来るかも分からない戦場では、恐怖心に耐えられなくなった兵士が発狂して、後方から味方を撃つ者まで出たのです。何とかして彼らを母国へ送り返さねばならないと、すなわち、無理やり「おとなしく」させる手段として、脳にメスを入れて前頭葉を切り離す「ロボトミー」と称する手術を、何と連合軍側でも同盟軍側でも、両方が行っていたのです。
ところが、この手術を受けると、内地へ帰ってからその人の性格がだんだん変わってしまうのです。アメリカでは「ハッピー・ベジタブル」というあだ名がつけられていました。つまり、もはや動物的欲求すら失われた状態なのです。後には施術部位を前額部眼窩回に来ている神経の最少部分に限定して、なお且つ同じ効果を示す「ロベクトミー」が開発されましたが、それでも、そこまで人格を侵害するような手術が、果たして倫理的に許されるのだろうかと問題になりました。この前頭葉の役割について早くから研究を手がけていたのが、先ほどお話しをした、チューリッヒ大学のアカート先生でした。後にウォーレン先生との共編で、The Frontal Granular Cortex and Behavior(1964)が出版されています。このように前頭葉の研究はどんどん先へ進んでおりましたが、後頭葉については研究が少し遅れてしまいました。
そこで、実験課題に視覚弁別学習と迷路学習とを採り上げました。ネコに明るさと大きさと形、それぞれの弁別学習をさせますと、どの個体でも正常なときは明るさの区別が一番やさしく、次が大きさ、最も困難なのが形と順序があり、後頭葉連合野を損傷すると、回復する順序もまた同じなのです。そして、明るさの弁別などは、術前よりもむしろ術後の閾値がより低く、刺激に対して一層鋭敏に反応しておりました。よって、連合野の新皮質は、興奮系よりも、むしろ抑制系の働きをしているという仮説を支持するわけです。
その頃、スタンフォード大学では毎週木曜日の夕方に教授と院生たちが集り、公開の研究会を開いておりました。招待講師のいないときには、学位論文の口述試験(defense oral exam.)を前にした院生たちに、練習のためにと研究発表の場が与えられておりました。ちょうど私の番のとき、フォード財団研究所に滞在中のウイリヤム・エステス(William Kaye Estes)教授がお顔を出して下さり、ネコの弁別学習が術後に回復していく割合と私なりの予測値推定式をご覧になり、「私のprobability theoryとよく似ているじゃないか。おまえは脳の中のどんな仕組みによって正解率が増えると考えているのか」と質問して下さった覚えがあります。通常の手続きではまだ弁別学習が成立していない場合、すなわち、反応率50%以下のサブリミナルな刺激でも、幾つかを組み合わせると、あたかも弁別ができているかのように見えるのですが、果たして脳内のどのようなメカニズムによるものか、と問われたのです。先生は、「研究室の窓からキャンパスの芝生を眺めていたら、ある年にタンポポが一つ咲き、次の年にはその数が増え、またその次の年にはと、タンポポがだんだん広がっていく姿から、あの公式を思いついたのだ」と内輪話を明かして下さいました。
なお、Journal of Comparative and Physiological Psychology に掲載された ”Visual defects resulting from prestriate cortical lesions in cats”(1962)をご覧になれば、先ほどの話がお分かりいただけるかと思います。要するに、脳は何も異常がないときに何ができ、損傷の結果、機能が一時的にどれだけ失われるのか。また、再度元の水準へ戻すことが可能なのか。そして、これらは決して脳の表層、新皮質だけの問題ではなく、脳全体のバランス、すなわち、深い部分との関係がどのように変化したかの問題ではなかろうか。今では大方の教科書が、また、テレビの講師たちも、脳を神経のネットワーク・モデル、つまり、神経回路説だけでしか説明しておりませんが、私にはどうしてもまゆつばものとしか聞こえません。もう少し違った見方ができないかという疑問から始まったのが、私の一連の研究でした。
またまた話が脱線してしまいましたが、妊娠から出産までの胎児期の役割については、古くからヘッケル(E. H. Haeckel)の法則、すなわち、「個体発生は系統発生を繰り返す」という反復説がありましたし、他方の発達の最終段階には、オルポート先生のいう「成熟したパーソナリティ」、すなわち、「人格の統合」という重要な課題があり、そこの最後に出てくるのが「価値志向」の問題です。この両端をうまくつなげて考えてみたいというのが、かねてからの私の願望と言ってもよいでしょう。したがって、片方で動物の実験をしながら、やはりもう一つの課題への関心からも抜け出すことができませんでした。
原谷達夫先生の訳本から、オルポート先生がハーバード大学におられることを知りましたので、Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality(1955)が出版されたときには、早速翻訳をさせていただきたいと先生に申し出で、ご承諾を得て訳しておりました。そして、サンフランシスコのAPAにお見えであった佐藤幸治先生にお話ししましたら、「その翻訳を貸してくれないか。京大の学生たちに見せて討議させたいから」と、日本へお持ち帰りになりました。ところが、しばらくしたら、何時の間にか他の人の訳書が出てしまったのです。そのことをオルポート先生にお伝えしたら、「日本の出版社が、あなたに翻訳権のあることを無視したのだろう。そのお詫びにこれを」と、サイン入りの新刊書 Personality and Social Encounter (1960)が贈られてきました。そこで、帰国後早々に、星野命先生や学生たちと一緒に翻訳にとりかかり、「日本版への序」を加えた『人格と社会との出会い』(誠心書房1972)を出版しました。後にオルポート先生を一度ICUへお招きしようとしましたら、「ハーバード大学の学部長職最後の年なので、今は海外へは出かけることが無理だ」とのことで、非常に残念に思いました。その後、しばらくして、奥様から先生がお亡くなりになられたとの報せを受け、渡米中の星野先生がボストン郊外のお墓へお参りして下さいました。
まだスペリー先生に関連する話が少し残っておりました。最も高次の心理学的機能として、言語の問題があります。そして、それが不思議と脳の左半球に限られている。では、右半球は一体何をしているのか。私も脳波やタキストスコープを使ってこの種の研究をしてみたのですが、研究方法がつたなかった所為か、それとも実験装置が悪かったためなのか、スペリー先生や東京医科歯科大学の角田忠信氏の言うような結果がなかなか出ないのです。
角田さんの研究がアメリカでも話題になり、日米共同でシンポジュームを開こうではないかと、私にも企画委員の声がかかってきました。しかし、「私自身には追試がうまくできなくて困っている」と伝えましたら、向こうの連中も皆、「自分たちもそうなのだ」と言うのです。それで結局、この案はおじゃんになりました。
持論を繰り返して恐縮ですが、私にはどうしてもモザイク流の脳モデルが納得できず、もしも生き物が何かの障害にぶち当たれば、仮に一時は退行しても、必ず再びバランスを取り戻し、更に一層伸びようとする力が生み出されるに違いない。そして、そのことが説明できるようなモデルを基にしてこそ、障害児に対する実践的な支援活動の方法を工夫することが出来るのではないだろうか、と考えていたとき、ジェーソン・ブラウン(Jason Brown)教授の Mind, Brain, and Consciousness : The Neuropsychology of Cognition(1977)という本に出会い、早速著者に許可を求め、訳書『認知と言語の神経心理学』(新曜社1979)を出すことになりました。彼は精神科の医者で、アルツハイマー病やピック病などの患者を診察しながら、それらの症状を新皮質の機能が障害を受けて、古い部分の脳の働きが表に現れた姿としてとらえ、そこから治療の方法を工夫していた人なのです。
また、ちょうどこの頃、宇宙工学の専門家であるカール・セーガン(Carl Sagan)博士の The Dragons of Eden(1977)が出版され、それが私の背中を強く後押ししてくれました。脳の進化を基に人間の知性を論じており、両者には共通点をたくさん見出すことができます。そのような本を訳させてもらいましたが、実はその前まで、私も一時は分離脳の話を真に受け、ヒトの脳半球の左右差についてまで、得意になって盛んに本に書いたり、ビデオの教材を作ったりしておりました。
インB ええ、それは、大内先生や金子先生が監修されたビデオですね。
原 はい、「文映教育映画社」のものです。(『大学講座用 現代心理学編 第一部 第5集 大脳機能の側性化』)
インB はい、入っています。これはまた、確か最近新しいDVDで見られるようになったと。
原 そうですか、本当ですか。しかし、もう一度見たら、恐らく冷や汗たらたらでしょう。人様の話も自分の目で確かめてみませんと、何時までも悔いが残ります。
インB ええ。一つ二つ、よろしいですか。どこかにあったと思うのですが、Corsiniのencyclopediaに、先生のお名前がありますね。
原 はい。しかも、ハウロー先生の記事の直ぐ前に載せてもらえたので、大変うれしかったです。
インB 私も、これに載っている日本人というものをずっと調べたことがあるのですが、それで、書いてあるところには名前があるのですが、あるところとないところとありまして、つまり、かなり上の方で選ばれているのですが、これは先生に、この文書自体はこれでいいのかという、校正のようなものが来るのですか。
原 確か編集者からの誘いに応じて、まずこちらの言いたいことを箇条書きにし、向こうからの素稿に手を加えて送り返しました。ですから、多分に自画自賛のところがあると思います。その上、当時は、自分の専門領域を社会心理と生理心理の二つに分けておりました。
インB つまり、これはご本人がきちんとチェックしているのですね。
原 はい。ゲラが届き、目を通して最後にオーケーをした覚えがあります。
インA ありがとうございました。では、続いて、学会でのお仕事について、何か他にありましたら。
原 私は学生時代を海外で過ごしましたので、日本の学会とはご縁がなく、原谷達夫先生以外には誰も知り合いがおりませんでした。しかし、いずれ将来帰国したときには、何とか心理学者のお仲間入りをさせてもらいたいものと、図書館で時たま届く『心理研究』を見ることを楽しみに、また、お小遣いを溜めては目に入る図書をせっせと日心の事務局へお送りしておりました。当時の学会誌は縦書きで、巻末の会務報告の中に寄贈本のリストが載せられており、その中に見覚えのあるタイトルを見つけると、会員でもないくせに何かしらお役に立っているような気持ちになり、内心大層嬉しかったものです。帰国後に事務局長の八木冕先生へ「本を送っていた者ですが」と申し上げたら、先生にはご記憶が全くなく、大変がっかりいたしました。でも、後になって、これらの本を借り出して読んだことがあると言う方に出会い、やっと救われた思いをしたものです。
話を戻して、この学会での仕事として最も誇りに思うことは、大山正先生の下で会誌の編集委員を務め、そして、『執筆・投稿の手びき』の改訂に2度も参加させていただけたことです。ご存知のように、投稿論文は、まず編集委員長が課題に関係の深い領域の委員へ配り、その方から最初の審査者が複数推薦され、もしもその人たちの評価が異なれば、更に次の審査者へ回すことになります。もちろん、評価は全て匿名でなされるものの、どうしても審査者の人選が編集委員の考え方に近いところへ固まりがちです。そこで、「公平を期するために違った見方の人を加えるように」、また、「英文アブストラクトやJPRの英語がアメリカ流なので、英国流のスペルも許容するように」とか、私自身の似たような苦い経験から、いささか苦情めいたことをしばしば申し上げ、委員長の大山先生を悩ませたのではないでしょうか。このことが、編集委員時代の想い出として、今でも強く私の心に残っております。
そして、『手びき』改定のときにも、委員の一人に加えていただけたことは、非常に光栄で何よりうれしく思いました。当時、内外の学会で、この種の変革が起きておりました。アメリカではAPA方式と、もう一つはChemical Abstract誌の方式とが張り合っており、どちらのマニュアルで学生たちにレポートや論文を書かせるのかが議論されていた時代です。理系では後者を選ぶ方が多かったのですが、APA方式にも学ぶべきところが幾つもありました。最も強調されていた点は、会員の納める会費で出版費がまかなわれる以上、いかにして限られた紙数の中にできるだけ多くの重要な情報を載せ、その効用を広く読者に還元すべきかということが、編集委員たちの責務と言われておりました。したがって、まず論文の長さを、ショート・ペーパーなら何ページ、ロング・ペーパーなら何ページと定め、「イントロダクション」をやめ、論文の最初の節にできるだけ簡潔に、しかし、その研究課題がどのような流れの中から生まれたものか、問題点の意義について必ず明記するように。すなわち、読者に内容を正確に把握させた上、更にその研究を発展させることが可能になるように、と指示していました。そこで、多くの大学が、心理学専修以外の学生たちへもAPA方式を基にレポートの書き方を指導しておりました。
ちょうどその頃、技術革新の波が押し寄せ、心理学の実験でも、ナノメーターなどの細かいスケールが必要になってきたので、大山先生は一生懸命、それへの対応にご尽力下さいました。そして、吉田正昭先生は常にカメラを持参され、事ある度に資料や関係者の顔を写真に撮っておられました。先生の記録写真は、学会として真に貴重な資料ではないかと思われます。そして、会誌の編集作業に当っては、裏方として事務局の久野洋子女史に大変お世話になり、今でも深く感謝しております。
それから、学会に関連して必ず思い出されるのは、1972年に品川のプリンスホテルで開催された第20回国際心理学会議(ICP)に、プログラム委員の一人として加わったときのことです。実はその前に岡部先生がICUを退職なされ、代わりに東大から梅津八三先生を研究室にお迎えしておりました。何分にも先生は、独自の手法で三重苦の障害児を訓育なされ、その実践的経験を基に比類なき壮大な理論体系を構築なされた方です。その梅津先生が、この国際会議の間際になって、日本人では唯お一人の特別招待講演者に選ばれました。そこで、そのための原稿をお借りして翻訳をし、夏休みの間に何度か鎌倉のお宅へ伺っては、訳文をチェックしていただきました。先生独特の言葉遣いや難しい用語が随所に出てきましたが、例の『心理学事典』にも、また、他の辞書の何処にも載っていなく、素養のない私は大変苦労しました。しかし、この時に垣間見た先生の真摯な研究者としてのお姿には、本当に深い感銘を覚えました。そして、ご自宅へお邪魔する度におそばをご馳走になり、実は先生ご自身が打たれたものだと奥様から教えていただいたことも忘れられません。
いよいよ、特別セッションでご講演をなさるに際には、私が拙い英語で通訳をさせていただきました。先生はお話しの冒頭で自作の映画をご披露され、「見えない・聞こえない・話せない」子供がどのように手探りでおもちゃの弁別をしていくのか、その学習のプロセスをご自分の理論に添って克明に説明なさいました。そのために時間が大層かかり、予定の時間が大分過ぎてしまいましたので、甚だ失礼なことを承知の上、「先生、そろそろ終りにしていただけませんか」と申し上げ、大切なお話しの最後を尻切れとんぼにさせてしまったのです。国際会議の場であったとは言うものの、あの時の私の杓子定規な振舞いは、想い出す度に今でも本当に申し訳なく思えてなりません。
後日、先生の納骨式のお墓まいりの折に東大の方から、そのときに通訳するため用意した英文の原稿が、先生を学士院会員にご推挙する際に必要とされた外国語の論文として使っていただけたとお聞きし、あのひと夏の努力は決して無駄ではなく、多少なりともお役に立てたということが判って、やっと自分を慰めることができました。
インB はい。鳥居修晃先生が梅津先生のお弟子さんで、前に、「梅津先生は、なぜ戦前に日本語でもあまり発表しなかったのでしょうか」とお伺いしたことがあるのです。そうしたら、鳥居先生のお答えは、「あの先生の哲学で、心理学者がそんなことよりもデータを集めるべきである」とおっしゃったということを聞きました。
原 そうでしたか。いかにも、梅津先生らしいお言葉ですね。
原 そのような思い出深いICPですが、このときに参加者へ配られた英文案内資料 A Guide to Psychological Institutions in Japanの冒頭には、‛We may say that Japanese people traditionally are psychologically oriented.’ と書かれてありました。それが外国人たちの目に留まり、事務局にいた私を捕まえて、「ここに書いてある『万葉集』や『古事記』と心理学との関連を詳しく話せよ」と説明を求めるのです。いやはや、日本人でありながら即座にうまく答えられず、大層恥ずかしい思いをさせられました。日本人特有のメンタリティーについては、私自身が大きな関心を抱いていた筈でしたのに。
実はサンノゼの学生時代にも、一般教育科目で「哲学」を受講した折、テキストの中に鈴木大拙氏の「Zen(禅)」が出てきたので、「おまえは日本人だから説明をしろ」と言われたものの、何も話すことができなくて顔を赤くしました。これから留学を志す人々には、是非とも私たちの文化が宿す psychologically orientedな特質とは何か、人前で話せるようになっていて欲しいものです。
この品川のICPの後、1974年には犬山と名古屋の両市で国際霊長類学会が催され、サルの実験をしていた関係から、ICUの教え子たちが大いに活躍をしてくれました。そして、1975年には、日本学術会議の企画で国際環境保全科学会議が京都宝ヶ池の国際会議場で開催され、内外の生物学者や都市工学などの人々を前に、私にも心理学を代表して発題の機会が与えられました。「このかけがえなき地球環境を保全していくためには、すなわち、当時の流行り言葉『ハッチなき宇宙船』の中で、われわれ人類は今後どのような営みをなすべきか」という課題です。そこで、あのヒルガード先生の宇宙飛行士のストレスを軽減させる研究や、サンノゼの人種偏見の調査を思い出しました。そして、しばらく後の1985年には、アリゾナ大学で開催された日米環境学共同会議に参加するため、早稲田大学の相馬一郎先生や建築学の研究者たちと一緒に、相互交渉心理学(transactional psychology)のイッテルソン(W. H. Ittelson)教授のところへも出かけました。
さて、私が学術会議の連絡委員をしていたときに痛感させられたことは、よその分野の学会とならばまだしも、恥ずかしいことには、心理学と名の付く学会の間で、仲があまりよくないのです。そこで出来ることなら近い将来、APAのように、日本心理学会の大きなアンブレラの下に臨床心理や教育心理や社会心理などなど、諸々の学会を招き入れたい。今直ぐに実現させることが難しくても、来年のICPを絶好の機会と捉え、学会幹部の方々のリーダーシップによって若い会員たちの意識を是非ともそちらの方向へ向けさせられないものだろうか。これは私の長年の夢であり、大げさに言えば学会への遺言です。
そして、同じく気に懸けてきた問題は、カリキュラムのことです。昨年『大学教育の分野別質保証のための 教育課程編成上の参照基準 心理学分野』という文書が公開されましたね。すなわち、学部における心理学の授業について、どのような配慮が必要か、ということです。今の認定心理士の資格を決める際には、最低38単位、五つの領域から必ず三つ以上について学ばせました。もう一度、じっくり検討する必要があるでしょう。
先ほどお話ししたように、私が在籍していた頃のスタンフォード大学では、六つの領域から主専攻と二つの副専攻を選ばせられましたが、もしも心理学の全分野について勉強しておきませんと、最後の口述試験の折に、あたかも指導してきた教授の手落ちのように、その先生を前にして他の審査者からうんと油を絞られるのです。これは大学院での話ですが、学部の学生たちへも、似たようなガイダンスが行われておりました。
ところが、私自身は、これまで教養課程の「一般心理学」、またはそれに類する授業科目の中で、果たしてそのような配慮を充分してきたのかどうか。既に手遅れながら、大いに反省しています。ついつい自分の得意なことばかりを講義してこなかっただろうか。専攻生がお相手ならば、それも許されるでしょう。しかし、一般の受講生の中には、心理学に二度と接することのない者も少なくないのですから、下手をすると彼らに、「心理学とはこんなものだ」と偏った見方を与えて一生を過ごさせてしまいます。そこで、授業についても、もっと工夫をしなければなるまいと、ついついカリキュラムの問題にまで口を出してしまいました。これは決して学生たちにおもねる気持ちからではありません。大学教員の多くは学生たちを教えることによって、自分の好きな研究活動が許されているのだから、もう少し彼らのことを念頭に置かねばなるまいと云うことです。
ところで、何もわざわざ「心理学」と呼ばなくても、生き物について勉強している中学生や小学生たちに、もっと早くから「こころ」の問題へ関心を持たせてもよいのではないでしょうか。実は私が最初に「こころ」について多少とも考えたのは、確か4歳の頃でした。叔母の葬儀の後、彼女に会いたいと、布団の中で一生懸命鼻をつまんで息を止めようとしたことがあります。とうとう苦しくなって諦めましたが、理科の授業で魚やカエルの解剖をした際には、必ずこの時のことを思い出しました。その後いろいろと紆余曲折を経ましたが、きっとそのときの体験が後に私を心理学へ進ませたことへの原点だったかも知れません。
心理学の授業で私が真っ先に学生たちへ尋ねることは、果たして単細胞の生物に「こころ」があると言えるのかという問いです。心理学ではゾウリムシの行動があまり話題にされませんね。プラナリアについてはどうでしょう。あれは体の構造がもっと複雑で、上下半分に切り離せば、それぞれが再生し、どちらに記憶が残っているかを問うことができますが。
私の学生時代、シカゴ大学にゾウリムシの研究している若い心理学者が一人おりました。シャーレーの中にゾウリムシを入れて虫眼鏡で観察すると、最初はガラスの壁にぶち当る度に同じ角度で反対側へ泳いで行きますが、その内にだんだんと壁に当たらなくなる。まだ神経組織のない単なる単細胞が立派に「行動の変容」、すなわち、「学習」をしているように見えるのです。このように外部のものに触れたとき、生物学では細胞膜の物理的・化学的反応として説明するでしょう。もしもその物質と同化できるなら、膜が薄くなり、よって中の細胞液が移動して周りを取り囲み、最後は細胞液が分解する。言い換えれば、刺激に「なじみ」があれば触れ合い、あるいは食い物にし、さもなければ避けて遠ざかる。これは決して唯物論や還元論を主張するわけでなく、心理学用語の「感覚」「知覚」「認知」「性格」「態度」「価値観」などなど、ひいては「いのち」と「こころ」の源、およびその働きの本質を、先ずは単細胞から学ぶことができないかと言う訳です。そして、このような質問をする理由は、後に、受精卵から胎児期を経て、更に出生後の長い長い生涯に亘る成長発達の過程を繋げて考えるための布石に他なりません。
もちろん、フロイトの「無意識」は、ダーウィンの「進化論」と並んで20世紀の二大発見の一つと称せられるくらいですから、私たちは大いに敬意を表すると共に、彼が描いた「イド、エゴ、スーパー・エゴ」の図が、もともとは女性の子宮や脳の形を模したものだったということからも、心理学はもっともっと生物科学と一緒になって「ヒトの特性」を研究せねばならないし、そのような授業ができないものだろうか。そうすれば、子供たちにも理解され易いし、世の中の心理学に対する関心がもっともっと高まるだろう、ということです。繰り返しになりますが、大半が心理学以外の専攻生たちを相手に授業をしてきた人間の正直な感想なのです。本当に心理学を専門にしたいと考える学生は、放っておいても自分で勉強してくれますからね。
もう一つ付け加えてお話ししたいことは、これは心理学に限らず、大学の先生たちがどのように教えるのか、いわゆる「教員の資質開発(faculty development:FD)という課題です。1981年の1月、中曽根内閣のとき、臨時教育審議会の公聴会へ私が呼ばれた際に、「このような言葉がアメリカにはあるのだが、日本の大学の先生たちへ、立派な『研究者』への意欲と共に、『教育者』としての自覚をもっと高める必要があろう、と提言しました。なぜなら、小学校・中学校・高校の先生たちは、そのような訓練をきちんと受けているのに、教員免許状なしに教壇に立っているのは、大学の先生たちだけなのです。そこで、私たちが自発的にそのような場を作ろうではないか、というのがこのFD活動です。今から30数年も前のことですが、これがまた物議をかもしました。
実はその少し前に、かつてヨーロッパ旅行でお供した早稲田大学の村井資長総長先生が、私立大学連盟の大学問題検討委員会で「大学の自己点検」を研究課題に取り上げ、私をその主査に指名して下さいました。これまで教育改革の名の下に数々の試みがなされてきたけれども、一度大学の活動全般について自分たちでじっくりと点検し直す必要があろう。それは今までのように外から視学官が来て評価するのではなく、私たちが自ら進んで日頃の仕事振りを顧み、同僚の教職員や学生たちへも協力を求め、そして、更に学外の人々、特に私学の場合には後援者たちへもレポートできるような、実践的な手法を考えようということでした。ところが、それが教育学者からは「胡散臭い」と言われたり、また、国立大学協会あたりへ伝わると、何時の間にか「自己点検」が「他者評価」になってしまったりするのです。それは決して私の本意に添うものではありません。
インB 一ついいですか。いろいろ前後することもあるのですが、ぜひお聞きしたいことがありまして、一つは、先生の所属学会です。資料には,日心、基礎心、生理心理などの学会の役職が書かれていますけれども、心理関係の学会ですと、それ以外にどこか入られていましたか。
原 岡部先生がいらっしゃいましたから、当然のこととして、日本に帰ってきたときには応用心理学会にも、また、教育心理学会にも入らせていただきました。
インB そうなのですか。APAは会員でいらっしゃる。
原 今はforeign affiliateです。その他に、数理心理学会にも一時入っておりましたが、そこでは私たちの用いる数値が一体どれだけの心理学的リアリティを秘めているのか、ということに拘りました。最も多く口出ししていた事柄は、テストの妥当性と信頼性の検証だったと思います。相関係数にはどこまで誤差を入れて検討すべきかなど、むきになって詰まらぬ議論を何度かいたしました。それから、小数点何桁までが有効な数字なのか。5桁も、6桁も、コンピュータが打ち出す数字をそのまま論文に載せている人がいるでしょう。心理学で用いる検定法ならば、それぞれが何桁までの数値で十分か、学生たちにきちんと説明しておきませんと、市販の計算プログラムが出す数字をそのまま平気でペタペタ貼り付けてしまいます。
私が指導を受けたマッケンマー先生は、因子分析の権威でもあり、私の就職推薦状には、彼の下でそのような勉強をしたとわざわざ書いて下さいました。その先生がAPAの会長に選ばれた折、就任講演の中で、幾つもやたらと数多くの因子を並べることに一体どのような意味があるのか、と疑問を投げかけ、大きな波紋を呼び起こしたことがあります。あのチャ―ルス・オズグッド(Chares E. Osgood)教授も、語彙分析法(semantic differential method)では「力量(potency)」「活動(activity)」「評価(evaluation)」の3次元に留めました。これなら誰にでも容易に意味空間のイメージが作れます。因みに一言付け足しますと、オズグッド先生が国連の平和親善大使として来日された理由は、仮に言語が異なっていても、この意味空間の上でコミュニケーションをすれば、世界中の人々が互いに理解し合えるだろう、ということでした。また、大山正先生のご研究では、日本人の色彩感覚がただ一つの評価因子には収まりきれないので、どうしても下位尺度(subscales)を設ける必要があるということから、国際的に大きな注目を浴びたのでした。計算機任せにやたらと数多くの次元を並べ立てるのはいかがなものかと、数理心理学会の研究会で言ったことがありましたが、マッケンマー先生の受け売りと云いますか、私もその血を引いてしまったようです。
思い出したのでついでに申し上げると、岡部弥太郎先生が東大からICUへ移られたとき、真っ先に丸善を通して、いわゆる古典的な実験器具一式をお揃えになられました。いわゆる、ブラス・インスツルメントの類です。たとえば「ダルトン・スティック」、あれは単なる真鍮の棒に過ぎませんが、縦にして一箇所を握らせて、次にまた握り返させ、棒の落下した距離で反射速度を計ります。これなら誰にでも眼で見て肌に感じることのできる測定値です。その棒も今回の話題にできないかと思い、研究室の許可を得て昨日倉庫を覗いてみましたが、残念ながら見当たりませんでした。
もう一つ思い出すことは、話が戻りますけれども、入学試験の採点についてです。最初の年は学内の寮生たちに徹夜で採点作業を援けてもらいましたが、何回チェックしても、なお間違いが起こり得るのです。そこで、次の1962年には、人事院の地下室にあった磁気式採点機を使わせてもらい、芯に鐡粉の入った鉛筆でマークシートへ回答させる方法を導入しました。試験の終った後で、こっそりと解答用紙をタクシーに積み込み、深夜に三鷹から霞ヶ関まで急行して、一晩中読み取り機械を回しました。次に採用したのがIBMのパンチ・カードでした。あれは普通の鉛筆でマークしても、自動的に穴を開けてくれます。それで、先ず水道橋にあったIBMの本社で採点した後、日本橋のコンピュータ会社で受験者個人個人のプロフールを印字させました。それは1965年頃のことで、これが一つのモデルとなり、あちらこちらの大学が真似をするようになりました。
なお、高木貞二先生の能力開発研究所には大型の採点用機械がありましたが、あれは私がシカゴの米国科学研究協会(ASRA)とプリンストンの教育検査サービス(ETS)を訪問したときにカタログを手に入れ、ICU出身の中山和彦氏が能研所員に採用されたとき日本へ取り寄せたものです。それが後に入試センターへと受け継がれました。以上が数理心理学会に関連する事柄でしょうか。
インB 先生も最初の頃、知能検査をしていたというお話を聞いて興味を持ったのです。大体、結構一般的に、学校の生徒を対象に知能検査をやるということは、心理学者は、それを取って、どうしたのですか。
原 テストをする側として、採点の結果はそのまま依頼された学校へお返しをし、利用の仕方はその学校にお任せしました。多くの場合、普通の授業についていけそうにない子を見つけ出し、どのような手当てをすればよいか考えるためでした。ただし、昔の偕交社、追手門学院などにはお金持ちの子弟が多かったですから、将来の進学に備え、早くから特別な教育をするためのクラス分けを考えていたのではないでしょうか。ついでにもう一つ、岡部弥太郎先生について付け加えますと、先生は戦時中、海軍兵学校の入試に性格検査を使おうとなさいました。それは、「淡路円次郎・岡部弥太郎式向性検査」として名が残っている内向性・外向性の検査です。海軍兵学校では、学力のみならず、将来の海軍士官としての望ましい人格特性を検査するため、岡部先生に性格検査の開発を依頼し、そこで、戦時中も「淡路・岡部式向性検査」の改良を続けておられたそうです。これは私が帰国して間もなく、先生から直々お伺いした話です。「ああ、君は海兵にいたのか。私もあそこではそんなことを考えていた。しかし、そのうちに他の検査が出たので止めにした」とのこと。矢田部ギルフォード性格検査が出てきた時点でしょうか、確かあの中には向性尺度が二つ入っていましたね。それで、「もう私のものは必要がなくなったと思った」と、極めて淡々としたお口振りでした。これは小田原の温泉プールで先生と一緒に泳ぎながらお聞きした話しです。
インB すみません。ヒルガードはどのような人なのですか、アーネスト・ヒルガードは。
原 はい。先ほどの写真のように、それからご自分でヒプノーシスをなされていたような方なので、非常に温厚な先生でした。ゼミなども極めて和やかな雰囲気で、多元的な見方を大事にされ、学生たちが主張する、ときには突拍子もない考えをも、一応は聞き入れて下さいました。そして、最後に、「おまえは、それと他の考えとをどのようにインテグレートしたいのか」と訊ねて下さるような指導を受けました。ですから、当時はスキナリアンが幅をきかせてきた頃ですけれども、古典的条件付けも、またゲシュタルト的な意見も交わされており、トールマン先生のところの院生たちまでも指導しておられました。そのトールマン先生は、バークレーの構内にあるライフ・サイエンス・ビルの上の階におられて、私たちの出入りも許して下さいました。スタンフォード大学とカリフォルニヤ大学の間では、カリキュラム上の交換ばかりではなく、私の在籍中たった一度だけでしたが、共同でテストを行ったこともありました。教授同士が相談して共通のテストを作り、両校の院生全員が受けさせられました。どちらの研究室が、どの面で強く、どの面で弱いのかを調べるためでした。そこで、私は、ヒルガード先生に、「今回のテストが全然できなかったので、私のためにスタンフォードの平均点が落ちてしまい、誠に申し訳ありませんでした」とお詫びしたことがあります。あの当時もスタンフォードとバークレーとは、交流しながら互いに強いライバル意識を持っていました。
インC ヒルガードの教室の催眠の話がでましたが、ヒルガードの催眠の誘導の仕方について、何か覚えていらっしゃいますか。
原 被験者のタイプによって、非常に入りやすい人と、なかなか入れない人がいましたね。いや、申し訳ないことに、細かいところまではよく覚えておりません。けれども、要は最初に、「気持ちのいいものだ」ということを納得させることに努力しました。「決して怖いものではない。本当に気分の良いもので、素直になれば自然と誰にでも起こるものだ」ということを充分納得させてからです。もちろん、場合によっては危険が伴うことも重々承知の上でしたが。その当時、私はあまり頼りになる学生ではなかったようです。あの学習心理のヒルガード先生が、まさか、そのようなことをなさっておられるとは夢にも考えておりませんでしたので。
インA では、長い間、どうも、ありがとうございました。
原 はい。そもそも、私は最初、数学と物理の教員になろうと考えていた人間です。終戦の時は海軍兵学校の舞鶴分校(旧海軍機関学校)というところにおり、8月6日に広島へ「ピカ・ドン」が落された翌日、京大出身の教官からウラニューム92の原子核構造について学び、どうやらこれが今度の爆弾に使われたらしいということを聞かされました。
間もなく終戦の日を迎えましたが、あの玉音放送も雑音に紛れて何のことやら全く分からず、その日の午後は「もっと頑張れ」と言われたものと思って一層訓練に励んでおりました。ところが、夕方になって「どうやら日本が負けたらしい」と判り、「それじゃあ、私の命も助かった!」と、悲喜こもごもの複雑な思いで復員しました。
家庭の事情もあり、他の友人たちのように横滑りに旧制高校へ入ることができず、1年半ばかりゴム工場で職工をしておりましたが、どうしても勉強したい気持ちを抑えることが出来ず、授業料が要らなくて、逆に毎月給費がもらえた天王寺師範(後に大阪第一師範学校と改称)に入り、数学と物理の中等教員免許状を取るつもりで勉強しておりました。最初の年に何方からどのような授業を受けたか、ほとんど記憶にありません。ところが、2年目に男女共学となり、理系の学生は平野にある元の女子師範へ転校することとなり、そこで原谷達夫先生という東大出の若い心理学の先生に初めてお目にかかりました。
この原谷先生は非常に進歩的なお考えの方で、教職員代表をなされており、学生委員長の私とは何度か議論を交わしました。ところが、ある日突然、「大阪城の隣にある追手門学院より知能検査を依頼されたから、原君、やってみないか」とお声を掛けて下さいましたので、早速友達を誘い、全校の生徒に対して「鈴木ビネー式知能検査」をやらせてもらいました。他にもう一つ「大伴式」がありましたが、田中寛一先生のものは未だない時でした。
実はこのテストを引き受けるまで、心理学と数学がこれほどまでに縁の深いものとは一度も考えたことがなく、大変驚きました。ちょうど数学の演習で、正規分布の公式は(2分の1+2分の1)のN乗を無限大に積分すれば出てくると知り、「公式なんかを覚えるのは馬鹿のすることで、必要なときに自分で作ればよい」などと生意気にうそぶいていた頃でした。このときから、原谷先生とは急に親しくなり、先生のご推薦によって付属中学で教育実習をし、また、就職の内定までもいただいておりました。
ちょうどその頃に、30年前に日本を飛び出して行方不明になっていた母方の祖父が、戦時中はワイオミング州の強制キャンプに収容され、戦後はコロラド州に住んでいるということが、進駐軍を通してやっと分かりました。その途端に、是非ともアメリカでもっと勉強をしたいと思うようになりましたが、市民権を持っていなかった祖父には、孫の私を呼び寄せる資格がありません。そこで、アメリカ人の「保証人」を探してもらうことになりました。
ところが、どうやら私の留学の意志が大阪府の教育委員会へ伝わったらしく、卒業後は付属中学へ就職できる筈だったのに、実際に手にした辞令には「中河内郡縄手町立小学校教諭」と書かれていたのです。そして、受け持った児童50余人の中に、二人の障害児がおりました。一人は知恵遅れで鼻の欠けた女の子、母親が梅毒だと聞かされました。もう一人の男の子は、両親がアル中で、片時もじっとしておられない、今で言う多動症の子でした。私の前の担任は、児童たちへ「二人は『お客さん』だから一切構わないように」と躾ていたらしいのです。
当時は養護学級などありませんから、障害のある子も、ない子も、同じ教室で教えねばなりません。そこで、いずれこの子の親たちが死んだとき、いったい二人はどうやって生きてゆけるだろうか。もしも今の内に、少しでも自分に出来ることを探してやれないものだろうかと、他の児童たちと一緒の小さなグループに入れ、そこの班長に「今日はあの子に何ができたか、教えてほしい」と毎日尋ねておりました。そうこうしている内に、ようやく私の渡航に必要な保証人が見つかり、領事館からビザも降りましたので、「皆には申し訳ないけれど、先生にもっと勉強をさせてくれないか」と子供たちに詫び、アメリカへ向かいました。
それは1950年の11月、ちょうど朝鮮戦争の最中で、北側の軍隊がいつ何時九州へ上陸するか分からない時で、プレジデント・クリーブランド号という大きな客船でしたが、潜水艦の攻撃を避けて灯火管制を敷き、真っ暗闇の中を神戸港から出航しました。次の日に横浜港へ立ち寄り、ドラの音と共に初めて大声で「さようなら」を叫び、五色のテープを投げることができました。16日間の船旅の後でやっとサンフランシスコに到着し、そして、上陸した直ぐ次の日から保証人の親戚の家に引き取られることになりました。そこはサンフランシスコの南、サンノゼという町の高校の先生の家でしたが、皿洗いと庭掃除をしながら昼間は学校に行かせてもらえる「ハウス・ボーイ」、すなわち、住み込みの書生として働きました。
通学したサンノゼ州立大学は、実は西海岸で最初に建てられた師範学校(normal school)が州立大学(state college)へ昇格した学校で、先生たちがとても授業に熱心、私にとっては非常にラッキーでした。そこで初めて「アメリカの心理学」に接し、心理学と数学をダブル・メイジャーに選んで、1953年6月に卒業しました。卒業式の翌日には、戦後日本から来た最初の卒業生ということで、地方の新聞にも写真が載りました。
この頃、私は目に留まった本を何冊か、師範時代にお世話になった原谷先生にお贈りしました。そうしたら、先生が訳されたゴードン・オルポート(Gordon W. Allport)著、 The individual and his religion.(1950) の翻訳書『個人と宗教』(岩波現代叢書 1953)がアメリカに届いたのです。そして、「あとがき」の最後には、「原著と参考文献とを送ることにより機縁を与えられた在米中の原一雄氏・・・」と、私の名前が初めて活字にされていたのです。それを見た途端、これではますます本気で心理学を勉強せねばならないと改めて思いました。ところが、更にこの本の序文に、今田恵先生が著者のオルポート博士について詳しく解説をされておられたのです。そのような訳で、日本には今田先生という私の恩師の原谷先生が最も尊敬している方がいらっしゃることを知りました。そして、1961年に帰国し、日心の会員となった翌年1962年度の学会大会が、何と幸運にも、今田先生の関西学院大学で催されましたので、そこで初めて先生に直々にご挨拶をする機会が得られたのです。
しかし、その前のアメリカ滞在中、佐藤幸治先生にお会いいたしました。それは1955年にサンフランシスコで催されたAPAの全国大会の折でした。私はスタンフォード大学の院生たちと大会の事務局で受付係をしておりましたら、一人の日本人がお見えになり、「京大の佐藤幸治だ」とおっしゃられ、会期中は私のオンボロ車で送り迎えをして差し上げました。また、学会の後でバークレーのカリフォルニヤ大学やミルス・カレッジにお出掛けのときには、私が運転手を勤めました。佐藤先生はお話を始める前に、カバンの中から木魚を取り出して「ポクポク・ポクポク」と叩かれるので、関係者の間では大変評判になりました。この時はまだ、佐藤先生がどのようなお方か全く存じ上げておりませんでしたが、後になり、ご著書の『人格心理学』(創元社 1951)の最終章で、最も理想的な人格像、すなわち、ゴードン・オルポートのいう「成熟した」パーソナリティとして、「菩薩」を挙げておられた方だということが分かり、お知り合いになれたことを今でも深く感謝しております。
それから、私が在米中に親しくしていただいた方の中には、音楽心理学で著名な、同じく京大の梅本堯夫先生がおられます。先生はピアノが大層お上手でした。恩師の矢田部達郎先生の奥様が宝塚のご出身だそうで、その伴奏を引き受けておられたとのこと。ですから、スタンフォード大学の構内に住む教授たちやそのご夫人方から「是非一曲聴かせて欲しい」と引っ張り凧でした。それでもお寂しかったのか、時々私の家でお茶漬けやおにぎりを所望されておられました。
少し脱線しましたが、私自身の心理学の勉強についてお話ししましょう。先にも申したように、私は元々心理学を専攻する心算はなく、途中から障害児の発達や心理統計に興味を持つようになりながらも、世の中の人間関係には極めて関心の薄い人間でした。ところが、アメリカ人の家庭に住み込むと、主人は高校の教師でも息子たちは、「日本人は卑怯者でずるがしこい」と私を詰るのです。「宣戦布告なしに真珠湾を攻撃した。だからジャップは・・・」と、ステレオタイプでもってしか私を見てくれませんでした。そして、同年輩の二世や三世の人たちは、自分たちを「バナナ」と称しておりました。「肌は黄色だが、中身は白い」という意味です。このように日系アメリカ人たちが己のアイデンティティを保たんがために大変悩んでいる姿を見て、私は修士論文の課題として、マイノリティ・グループの抱く民族的偏見を採り上げました。あのような社会では、誰しもが偏見を持たざるを得ません。マジョリティがマイノリティに対するのと同じように、マイノリティもまたマジョリティや他のマイノリティに対して偏見を抱くメカニズムが、私の眼には非常におもしろく映りました。そこで、解決の鍵が社会心理学にあるのではと思い、ジョセフ・クーパー (Joseph Cooper) 先生の下で、「少数民族の社会的態度」につき調査研究を行った訳です。
後で判りましたが、この先生はクルト・レヴィン(Kurt Lewin)教授の門下生で、したがって、行動の全てをライフ・スペース内におけるgoal seeking behaviorと考えます。そこで、少数民族集団がどのように心理的バランスを保とうとしているのか調べるため、私は三つのスケールを用いました。一つはドイツのナチズムに染まり易かった人たちの性格特性を測るため、レヴィンが考案したEF(ethnocentrism‐fascism)スケール。二つ目はマズローの不安(anxiety)スケール。三つ目には、かつてゴードン・オルポートが性格特性の表記に選んだ数多くのタームの中から、アメリカ人の特性と、日本人ないし日系人の特性に合いそうなもの、それぞれ20個を選択項目に選び出しました。そして、これら相互の関係から、民族集団間の偏見(prejudice)、すなわち、判断以前に働かす色眼鏡(pre - judgment)の特質を検討しようと試みました。そこで、『北米毎日』という新聞社を通して、シアトルからロサンゼルスまでの西海岸に住む日系二世たちへ、質問紙への回答を依頼したのです。
調査の結果は、EFスケールの値が高い、すなわち、エスノセントリックな人たちほど、それから、不安度が増せば増すほど、アメリカ人と日系二世に与えられるステレオタイプが、だんだんと似通ってくるのです。ところが、最も不安度が高く、直ぐにでも治療を要するような人々だけが、その類似度を逆にすとんと落し、自分たちはこれだけアメリカ人とは異なるのだと、世間で言われている民族的性格特性を容認しようとするのです。もしこれを解釈すれば、フロイトの云う抑圧(repression)、投射(projection)、反動形成(reaction formation)、転移(displacement)などなど、心理的なバランスを保つための、いわゆる自我防衛機構(ego defense mechanism)の表れではないか。このようなことを修士論文に纏めましたら、ファイ・デルタ・カパー(ΦΔΚ)からもこの年度の新メンバーに選んでもらえました。
その後で幾つかの大学院へ願書を出したところ、ミネソタ大学とスタンフォード大学の両方から入学許可の通知が届きました。しかし、ミネソタ大学の方は奨学金付きながらも西海岸からは大層遠いので、働きながらでも何とかやっていけそうな、多少とも様子の分かっている近くのスタンフォード大学を選び、追手門学院での知能検査や縄手小学校で接した子供たちのことを再び頭に蘇らせて、何とかして彼の有名なルイス・ターマン(Lewis M. Terman)教授のご指導を仰ぎたいと思ったのです。
この年に入った院生20名の内、ターマン先生から指導を受ける予定の4名の中に加えてもらえて大喜びしておりましたら、9月の入学式の日に先生が既にご入院中と聞かされ、その年の暮れには大学こぞっての盛大なご葬儀が大学教会で営まれ、私も参列することとなりました。ですから、先生にはとうとう一度もお目にかかることができませんでした。そして、私たち院生の指導はクイーン・マッケンマー(Quinn McNemar)先生、日本ではマクニーマーと訳されており、スタンフォード・ビネー知能検査(1937年度版)の改訂を担当した統計学者に引き継がれ、学内でアルバイトを探していた私に、「今度、ウィスコンシン大学のハリ―・ハウロー(Harry F. Harlow)教授のところから来たマイク・ウォーレン(J. M. Warren)准教授が動物飼育室で人を探している」と教えて下さいました。多変量解析のゼミに出ていたので、お声を掛けていただけたのでしょう。
このマッケンマー先生は、ターマン教授が最初の1916年版スケールを作成したときの「ジーニアス・グループ」の一人で、同僚のアーネスト・ヒルガード(Earnest R. Hilgard)先生も、また、ロバート・シアース(Robert R. Sears)先生も、そのメンバーだと聞きました。実はハウロー先生もスタンフォード大学の先輩で、在学中の名前は「何とかヴィスキー」と云って違っており、大学の図書館で先生の修士論文を探し出すのに一苦労した覚えがあります。先生の指導教授が、「もしこの名前だと直ぐにユダヤ人と判ってしまうから、将来学会で活躍するためには今の内に変えろ」と改名させたそうです。そのハウロー先生が、愛弟子のウォーレン先生を母校に送り込み、有り難いことにその実験室で私がアルバイトをさせてもらえることとなり、この時に初めて生理心理学の世界へ本気で首を突っ込むこととなりました。
この頃、ヒルガード先生にも大層お世話になりました。かねてよりご本の Theories of Learning(1948)でお名前だけは存じ上げておりましたので、当然「学習」についてご指導をいただけるものと思い、先生のゼミに入りました。
その前に、少し余談になりますが、当時のスタンフォード大学の心理学研究科について述べますと、そこは「統計」「実験」「学習と発達」「人格と社会」「比較と生理」「臨床」の六つの部門に分かれており、そして、doctorial candidate(博士候補)になる前にはqualifying exam(資格認定試験)があり、主専攻と二つの副専攻、および心理学以外の副専攻と外国語の五つの筆記試験を後期課程1年目の終わりまでに通らせないと、続けて在籍することが出来なかったのです。
そこで、これまで余り勉強してこなかった「学習理論」を学ぼうと、ヒルガード先生のゼミに入りましたら、何と討議や演習の課題は専らhypnosis(催眠)についてなのです。何故かと思ったら、アメリカ航空宇宙局(NASA)からの要請で、委託研究を引き受けておられたのです。宇宙飛行士を月に送り出すには、長い時間をカプセルの中で過ごさせねばならず、大きなストレスがかかるので、その間は催眠状態にしておき、月に到着する直前にそれを解けば、心理的負担が少なくて済むだろう。そのためのマニュアル作りだ、ということでした。
そこで、私たち受講生は、先ずあの5本の指を組む手法でもって、どれだけ催眠にかかり易いかの検査を受けました。私の名は「一雄」ですが、「キャーズ」と呼ばれていたので、先生が申されるには、「キャーズ、おまえはなかなか催眠にかかり難いようだ。しかし、そのブロークン・イングリッシュは催眠をかける方に向いているから、そっちの役へ回れ。」すなわち、「呪文のように聞こえてよく効くだろう。」そんな冗談を言って下さる、大変思いやりのある先生でした。
もうお一人、この頃にお世話になった先生には、認知的不協和理論で人気の高かったレオン・フェスティンガー(Leon Festinger)先生がいます。しかし、教室での指導はなかなか厳しくて、時々意地悪をなさる先生でした。ところが、ゼミの後で、「キャーズ、おまえは後に残れ」と言われるのです。それで、「何のご用でしょうか」と訊ねたら、「日本から来たのだから、俺に碁を教えろ」とのこと。そこでやむなく碁の手ほどきをして差し上げたところ、一月も経たぬ内に私を負かしてしまうのです。後で判ったことですが、先生は高校生のときにヨーロッパでチェスのチャンピオンになったそうです。後にフルブライト交換教授として東大に来られた際、日本囲碁連盟から初段を授与されて、得意なお顔で帰国なさいました。このような先生方のお陰で、学位論文の最終審査、すなわち、私の最も苦手とした口述試験も何とか切り抜けることが出来ました。
そして、これらの恩師の中にもうお一人、コムラド・アカート(Komrad Akert)教授を是非とも加えねばなりますまい。この方はスイスのチューリッヒ大学にある脳研究所の所長で、私が初めてお目にかかったのは、ウイスコンスン大学でハウロー教授との共同研究をなさっていた時でした。夏休みにはスタンフォード大学へもお出でになり、医学部の手術室で、ウォーレン先生と一緒に、ネコとアカゲザルの脳皮質損傷および切除手術の手ほどきを授けていただいた方なのです。
前後してしまいましたが、この当時に私がやっていた研究の概略を述べますと、先ず被検動物の正常時の行動、例えば、どれだけの精度で弁別学習ができるのかなどを個体毎に検査しておき、次に脳のある特定部位を破壊して、術後に機能がどれだけ脱落したのか、また、再訓練でどこまで回復させることが可能かを気長に観察し、最後には動物たちに甚だ申し訳ないけれども、いわゆる安楽死をさせて脳を取り出し、皮質に施した損傷が他の部位、中でも特に視床(thalamus)の中継核に、どのような変性が起きていたかを組織学(histology)的に調べるものでした。
ご存知の通り、神経線維が一旦切断されますと、終末ボタン(terminal button)が接続していた次の細胞体の周辺に「グリオーシス」(gliosis)と呼ばれる症候、すなわち、そこを取り囲むグリア細胞が増殖し、徐々に細胞体を食い潰していくような病変が起こります。この二次的変性を詳細に検出することにより、初めて脳内のある部位と他の部位、例えば新皮質と視床核や、古皮質と脳幹部との関係などが追跡できるのです。もちろん、神経細胞と神経線維の分布密度や配置の状態は、既にいろいろな染色剤を用いて解剖学的に調べられておりましたが、機能的な関係を明らかにするためには、裏付けとなる組織学的データが是非とも必要で、それが論文に付いていないと、この領域の学会誌へは載せてもらえませんでした。ですから、後に私はヨーロッパへの視察旅行の帰り道、スライド標本を片手にチューリッヒへ立ち寄り、顕微鏡による二次的変性の判定に間違いがなかったかどうかをアカート先生に確認していただきました。
何度も脱線して申し訳ないですが、ハウロー先生の研究室を訪れた時、先生のお顔が大きく腫れ上がっていたので、「何故か」とお訊ねしたら、「コバルト60にやられた」とのお返事でした。サルを使って放射能の影響を調べる実験をされている最中だったようです。当時のアメリカでは、国策に従って、また、研究費獲得のために、「学習理論」の大家であるヒルガード先生が催眠に、「学習セット」や「スキンシップ」で高名なハウロー先生がコバルト60を用いた研究に関わっていたような時代でした。
次に、また元に戻って日本での恩師について話を続けますと、1963年の秋に文部省と民主教育協会(Institute for Democratic Education:IDE)の主催で、国・公・私立大学の学長先生方総勢14名がアメリカ・イギリス・ヨーロッパ諸国の大学を視察旅行することになり、私にカバン持ち(書記)の役が命ぜられました。ところが、その一行の中に、あの今田恵先生も入っておられました。お陰で二ヶ月ばかりの旅行中、先生とはいろいろなところへご一緒させていただき、親しくお話を伺うことが出来ました。その中でも一番強く記憶に残っていることは、ちょうど大西洋を渡る飛行機の機内でのことでしたが、「原君、世の中にはICUのことを何かと批判する人が大勢いるけれども、一つ徹底的にアメリカ流の教養教育を試みて欲しい。その成功例も、また失敗例も、共に日本の大学教育にとって貴重な事例となるのだから、しっかり頑張るように」と励まして下さったことでした。
この視察旅行中に今田先生とご一緒に撮影した写真では、羽田空港の出発時とデューク大学を訪ねた折のものがあります。デューク大学には、嘗て創立当初にイギリスから迎え入れたウイリヤム・マックドーガル(William McDougall)教授が、彼の有名な Social Psychology (1916)を書いたときの机がそのままに残されており、今田先生が大層感慨深く手のひらで何度も撫でておられました。また、スタンフォード大学のキャンパスで、ヒルガード先生と今田先生と息子さんご夫妻の並んだ写真も残っています。これは寛先生がアイオワ大学で学位を取られて帰国の途中、ヒルガード先生の研究室で恵先生と何年振りかに親子の対面をなされたときのものです。
このように、今田恵先生と原谷達夫先生とのお二人こそが、数こそ少なく、しかもいずれの方からも教室で直接ご指導を仰ぐ機会はなかったものの、私にとっては掛け替えなき「恩師」とお呼び申し上げたい日本人の心理学者なのです。
インB 貴重なお話をありがとうございました。ところで先生をICUに呼んでくださった方は。
原 それは、形の上では岡部弥太郎先生です。しかし、帰国して初めて新任のご挨拶に伺いましたら、いきなり「その内に古畑和孝君がイリノイ大学から帰ってくるから、講師の契約が切れるまでに次の就職先を探しておくように」と告げられ、寝耳に水と大変びっくりいたしました。幸い次の年には助教授へ昇格することができ、いわゆる「終身雇用」(tenure)の権利が得られたのですが、しかし、既にかつてお世話になったウォーレン先生へ仕事口を頼んでおいたものですから、3年後の1964年にはペンシルベニア州立大学の動物行動研究所へ客員研究員として異動しております。
インB客員というものは、イメージとしては、何か月間か行けるという感じ、今のサバティカルのような感じなのですか。
原 はい。ただし、この時は休職扱いでした。ICUには既にサバティカルの制度があり、6年教えると7年目にはまるまる1年間の有給休暇がもらえましたので、後にはアメリカの国立衛生研究所やプエルト・リコ大学の医学部、あるいはコロラド大学へも2度ばかり、7年毎に出掛けることができました。
ここで少しICUの心理学研究室の創設について経緯をお話ししますと、この大学はもともと大学院大学を目指しておりましたが、当時の「大学設置基準」によれば、学部なしには大学院を置くことができないと言うことで、「それならば、卒業生がどのような分野の大学院へも進められるように、学部4年間を教養学部(リベラルアーツ・カレッジ)にしよう」と、元同志社大学の総長だった湯浅八郎先生を学長に、そして、アメリカのシラキュース大学で教育研究所所長をしていたモーリス・トロイヤー(Maurice E. Troyer)先生を副学長にお招きしました。
甚だ乱暴な言い方かも知れませんが、そもそも日本が戦争に負けた原因は、軍人たちが判断を誤ったばかりでなく、良識を持つべき教師も役人も共にだらしがなかった。そして、金持ちは優遇されても、貧乏人が無視されたからではなかったか。よって新しく生まれ変わるべき日本の人材育成のためには、大学院に「教育」「行政」「社会福祉」という今までになかった三つの専攻科を設けよう。ところが、当時は「教育学」を英語で「ペダゴジィ―」(pedagogy)と呼び、「教育」(education)という専門分野はまだ一人前の学問として認められていなかったので、大学院で教育に関する理論と実践の両方をしっかり研究するために、戦後に進駐軍のGHQと難しい折衝を重ねながら新しい「学校教育法」を制定したときの文部次官であった日高第四郎先生を大学院部長に、そして、カリキュラムの最も要となる教育心理学の主任教授として岡部弥太郎先生をお迎えしたのです。
ところで、私自身はと云えば、トロイヤー先生がロックフェラー財団からの助成金で「大学生の価値観研究」を始めるに当り、統計的処理を受け持つようにと言われて日本へ帰ってきた者です。この研究の目的を簡潔に述べますと、学生たちに自分自身の価値観と在学中における変容とを顧みさせ、卒業後の進路選択の参考に供するという趣旨のものでした。そこで、入学した直後の春学期と2年生最後の冬学期、そして、4年生の冬学期は就職活動で忙しいからその前の秋学期にと、在学中の3回に亘って1+1+1単位の必修科目を取らせ、授業中に質問紙を用いて「人生観」「政治経済観」「宗教道徳観」「芸術観」などを調べ、その結果を討議の時間に本人たちへフィードバックして、自分の価値観の全貌を明らかにさせようというものでした。
インBスタンフォードで学位を取得されて、先生はすぐにお戻りになったのですか。
原 いいえ、最初はカナダのブリティッシュ・コロンビア大学へ行く予定でした。既にそこの心理学研究室へ就任が内定しており、それまでの間をスタンフォード大学の医学部の生理学教室で副手(Research Associate)として勤務していたのですが、突然ICUからお呼びの声が舞い込んできた訳です。
実は、このICUとは、その創立以前から妙にご縁がありました。渡米した翌年の1951年にサンフランシスコ市のオペラ・ハウスで連合国との間で講和条約の会議が開かれたとき、私は夏休みのアルバイトを辞めて毎日傍聴人として通い続け、9月4日の最終日には吉田茂首相が条約にサインするのを2階のバルコニー席から見ておりました。そして、高揚した気分のまま帰り道にパイン・ストリートの日本人教会へ立ち寄りましたら、「今夜の献金は、近々日本に新しく建てられる大学へ贈られるものだ」と聞かされ、そのときは未だ大学の名前すら知りませんでしたが、「アメリカとカナダのキリスト教徒による共同プロジェクトなら、大変結構なことではないか」と、サンノゼへ帰るためのバス代1ドル50セントを残し、僅かでしたが財布の底をはたいて献金袋へ入れたことを覚えております。
それに加えて、スタンフォード大学から学位の取れることが分かった頃、かつての保証人が私に内緒でこの新しい大学に寄付をし、併せて「キャーズを雇ってみてはどうか」と湯浅学長宛に手紙を書いてくれたらしく、「それならば、丁度トロイヤー先生が統計の出来る人間を探しているから来い」ということで、教育心理学研究室の岡部先生の下で働くことになった訳であります。当時、この研究室には先任者の星野命先生とガイダンス専門の都留春夫先生がおられ、そして、肥田野直先生と池田央先生が、毎週非常勤講師として東大からお出でになっておられました。
ですから、私は4年目に一旦ペンシルヴァニヤ州立大学へ出て行きましたが、休職中であったにもかかわらず、「この度行政部の中に新しく入学志願者の選考を担当する専門部局を設けたから、その責任者になれ」と、1966年の夏休みに急ぎ帰国するよう命じられました。些か自慢げに聞こえますが、日本の大学で「入学事務部長」(Director of Admissions Office)という公式の肩書きを与えられたのは、多分私が最初の人間と言えるでしょう。
ここで是非、入学志願者の選考方法にかかわる岡部弥太郎先生のご功績についてお話しさせて下さい。恐らく皆さん方もよくご存知のことと思いますが、戦後間もなく、確か1946年から、大学の入学試験には文部省が作成する「進学適性検査」が使用されました。ところが、6年間は続けられたものの、7年目に中止となりました。多くの学会や日教組、そして、特に国立大学の人々が、「入試問題は学生を受け入れるそれぞれの大学が作るべきものであり、文部省が作るようなテストは・・・」とこぞって強く反対し、遂に廃止へと追い込んでしまったのです。そのとき、「受験生の能力を測る道具として如何ほど有効なものかがまだ十分解っていないのだから、追跡研究をするためにも中断してはならない」と、テストの継続を主張したのは、岡部先生が会長をなさっておられた応用心理学会のみであったのです。
しかし、岡部先生はICUへ来られた後も、この「適性検査」の必要性を唱えられ、「高校で身に付けた『学力(achievement)』を測ることはもちろん大切だが、将来大学に入学してから今までに学んだことのない新しい学問に挑戦することができそうかどうか、是非とも志願者たちの『適性(aptitude)』をも同時に測るべきだ」というお考えでした。しかし、アメリカのカレッジ・ボード(CEEB)が施行するSATには版権が付いており、日本でそのまま翻訳して利用することはできません。幸いにもSATの原型を作成したミラー博士という心理学者がトロイヤー先生のお友達でしたので、ご了解を得てその方が作成した「ミラー・アナロジー・テスト」を日本語に訳し、「一般能力検査」と称して判定資料の一つに加えました。部外へは極秘でしたが、心理学研究室の教員たちが、毎年このテストの改訂作業、すなわち、古い問題の項目分析と新しい質問項目の開発に関与しておりました。因みに付け加えれば、その手法は、将にマッケンマー先生からの受け売りです。
他方の「学力」評価については、高校間に格差があるのは致し方ないけれど、それでも志願者の能力は内申書で一応の見当をつけることが可能であろう。さほど教育環境に恵まれない学校にいても、クラスのリーダーをしていたような生徒には、やはりどこかに見所がある筈だ。したがって、一先ず内申書の記述を信頼し、積極的に審査の参考資料に利用すべきであろう。そして、大学側で作る適性検査、すなわち、「一般能力検査」と、更に、高校生がこれまでに眼にしたことのない教材を基に、どれだけ正確に内容を把握し、記憶し、そして新しい場面へ応用できるかを測るところの、自然科学・人文科学・社会科学それぞれの「学習能力検査」三つを加え、個人毎のプロフィールを眺めて総合的に判断する、というのがこの大学の入試方法でありました。私も少しは教育心理学の勉強をしたことのある人間でしたから、ただ単に教室で教えるだけでなく、学内での実践的奉仕活動として何が出来るかと問われれば、やはり、入試問題の作成や志願者選考のお手伝いが最も身近なものと言えましょう。そこで、この仕事にすっかりのめり込んでしまった訳です。
この時はちょうど池田内閣の時代で、東京女子大学の学長だった高木貞二先生が、新しく創設された能力開発研究所の所長に就かれました。そこでは、かつての「進学適性検査」やアメリカのカレッジ・ボード・テストのように、全国の高校生が何処にいても受けられるテストを作り、採点の結果は大学側が自由に入試へ利用できるもの、という案でした。その中の一つ、「適性検査」の開発に、私にも参加するようにと肥田野直先生からお声を掛けていただいたのです。
ところが、世間からは、「池田内閣の所得倍増計画のお先棒を担いでいる」と、さんざん悪口を言われました。「18歳人口を輪切りにして、進学組と就職組とに仕分けするためのテストだ」というのが彼らの解釈です。そのような雰囲気の中でICUが真っ先にこの「能研テスト」を採用すると公表したところ、直ちに学園紛争の火種となり、よその大学の学生たちまでが「わっしょい、わっしょい」と私の研究室へ押しかけてきて、遂には建物までも封鎖し、運悪く机の上に出しておいたフォルマリン漬けの脳切片やスライド標本を全部駄目にしてしまいました。そして、このスト騒ぎの責任を取らされて入学事務部長の職を首になり、更には2度目の学園紛争、すなわち、1969年に東大紛争の余波で学内が又もや荒れたとき、新しい学長の行政部から「キャンパスの中におられては困る」と、謂わば停職命令で出かけた先がアメリカ国立衛生研究所だったのです。
インB 少し戻りますけれども、先生が帰ってこられてから動物実験を続けることに当たっては、ICUには施設はなかったのですか。
原 はい。この大学には、そのような施設が全くありませんでした。ですから、同僚からは「もしも動物実験をやりたければ、外から研究費を稼いで来い」と言われ、そこでせっせと科研費を申請したり、アメリカの知人に寄付を頼んだり、足りないところは自分のポケットマネーでネコやサルなどを飼育しておりました。自動式のウィスコンシン学習実験装置(WGTA)も作りましたが、いよいよ資金が乏しくなり、サルの飼育と機械の維持管理が困難になったときには、甚だ残念ながら、当時東京女子大学から阪大に移られようとしていた南徹弘先生(現在甲子園大学副学長)に、動物と器具共々引き取っていただいたこともありました。なお、東京女子大学といえば、白井常先生がラットの実験をなされておられましたので、私も度々見学にお邪魔をし、また、先生にICUへお越し願って、学生たちに報酬用チーズの切り方を教えていただいたこともありました。
インB そうなのですか。ICUの中にも自然科学をやっておられる先生方が、当然いらっしゃったわけですけれども。
原 生物学研究室の先生たちとは領域が大分違いました。開学以来、遺伝学の泰斗でメンデル賞授賞者の篠遠喜人先生が東大から移られて自然科学科科長(後に学長)をなされておられましたし、モグラの生態学者もいましたが、生理学や神経学の研究者はいなく、私がこれらに関心を持つ学生たち、特に他大学の医学部へ進学を考える学生たちの相談相手を務めたこともありました。
インB では、もっぱら昔ながら心理の中に、心理と言いませんか、普通の文科系の大学の中に、その研究室があったのですか。
原 いいえ、赴任してきたときには、心理学研究室の中に生理学関係の設備は何もなく、全て一から始めねばなりませんでした。幸いキャンパスの中に、今は「富士重工」と名を替えた元「中島飛行機製作所」の社長さんの別荘があり、競馬用の馬を飼っていた小屋が残っていましたので、それを日曜大工でネコ小屋に、後にはプレハブのサル小屋へと改造しました。
インB当時のサルはどこから、買っていらっしゃったのですか、それとも。
原 輸入業者を通してインドからです。その前に、なぜ最初にネコを使ったかと申しますと、ネコは一種の国際的な規格品なのです。進化の途中で食肉類が分かれた後、イヌやオオカミなどはそれぞれがなおも進化を続けましたが、ネコはそこでストップしてしまいました。ですから、シャムネコと三毛猫とでは外見が大違いですが、世界中どこへ行ってもネコの頭は大きさも形も同じなので、手術に必要な脳の解剖図鑑は一つで済むのです。
ところがサルは、同じアカゲザル系統のニホンザルとインドのアカゲザル(Rhesus monkey)とでは、脳の形が少し異なります。ですから、犬山の京大霊長類研究所で分離脳(split brain)の手術をするときには、いつも苦労しました。ニホンザルの場合には、少し角度を変えてアプローチしないと、脳幹部の深い場所へメスが入らないのです。よく脳梁(corpus callosum)を切ると言いますが、実は脳梁だけでは不十分で、それが進化する基になった前交連(anterior commissure)も一緒に切らないと、本当の分離脳にはなりません。そこで、ニホンザルにこの手術を施すときは、通常のアカゲザルの脳図鑑に頼ることができません。このように、脳の組織解剖学的な知見を加えた研究をする場合には、インド産のアカゲザルを使用することが、医学や生理学では当時の慣習とされておりました。
さて、このアカゲザルは、もともとインド半島に生息している動物ですが、戦時中にあるアメリカ人の心理学者がカリブ海のプエルト・リコにある離れ島を買い取り、このサルを放して群れ同士の縄張り争いや、食糧不足の際のサバイバル方策などを観察していました。後に人が餌を与えるようになると、サルの数が増え過ぎてしまったので、国立衛生研究所(National Institute of Health : NIH)がその一部門の周産期生理学研究所(Laboratory of Perinatal Physiology)を移転させて、実験用の動物に利用することとしたのです。
ところで、なぜ私がNIHへ行くことになったかと申しますと、そこにドナルド・マイヤ―ズ(Donald Myers)先生が周産期生理学研究所の所長をしておられたからです。話はまた前に戻りますが、私がまだ院生の頃、ウォ―レン先生の紹介でロサンゼルス郊外のカリフォルニヤ工科大学(Cal. Tech.)にロジャース・スペリー(Roger Wolcott Sperry)教授をお訪ねしたことがありました。私が用いた実験装置も、実は「スペリー・ボックス」に手を加えたものだったからです。さて、心理学者のスペリー先生は手術があまりお得意でなく、後にノーベル賞を受賞された大脳半球の機能的左右差の研究も、分離脳手術は全てシカゴ大学の医学部でインターンをしていた若手医師のマイヤ―ズ先生に任されたそうです。そのマイヤーズ先生のお手配で、私の肩書きは一応プエルト・リコ大学医学部の上級研究員とし、ただし、実質は新しくサン・ファンに移された研究所で、動物を用いた心理学的実験を手伝うことになったのです。
周産期とは出産前後の期間を指しますが、母親の胎内にいる間には実にいろいろなことが起こっており、先にお話しした縄手小学校で教えたような子供が生まれてくることもあります。その当時、この研究所では専ら胎児の酸素欠乏や薬物の影響、特に母親が妊娠したことを自覚する前、すなわち、つわりが来る前に、胎内で起きているいろいろな生理学的異常が、出生後にどのような後遺症を起こすかという研究が進められておりました。
実は私自身が、両親の結婚10年目の子供で、難産の末に産れ出たときは全身が紫色、産婆さんが両足を持って盥のお水とお湯の間を行ったり来たりさせたら、やっとのことで息を吹き返した、という話を親からよく聞かされておりました。このようにお産のときが、これまた非常に重要な時期なので、その研究にサルを使用した訳です。具体的には、このサルの妊娠期間が平均159日と分かっていましたので、出産予定日の直前に帝王切開をして胎児を取り出し、いろいろな生理学的操作を加えた後、その後の成長発達に及ぼす影響を調べておりました。そこで、出生後の行動上の異常を分析させるために、心理学畑の私がプエルト・リコまで呼ばれた訳です。
ところが、ニクソン大統領の時代でして、ベトナム戦争で米軍側の旗色がだんだん悪くなると、政府の予算が大幅にカットされ、遂には海外の研究施設を全部本土へ引き上げさせることになり、そこで、私も仕事を中断してメリーランド州のNIH本部へ移りましたが、お陰でそれまでの研究が全部パーになり、早々に日本へ帰らざるを得ませんでした。幸いにも、その前に準備しておいた報告書の一部だけは、何とか当時の国際的な神経医学雑誌Brain Researchに、”Role of forebrain structures in emotional expression in opossum.” (1973)として発表することができました。
インB オポッサムを使われた比較心理学者は、それほどいないと思います。
原 はい、恐らく何処にもいないでしょうね。しかし、情動の研究には必要でした。というのも、プエルト・リコというところは、昔スペインの海賊たちがやってきたとき、船底からネズミが逃げ出して島中の農作物を荒らしたので、ネズミ退治にインドからマングースを連れてきました。ところが、このマングースには天敵がなく、今度はマングースが民家の鶏やブタまで襲うことになり、何とかして退治する方法はないか、それには先ず、その凶暴性を研究しようという訳でした。しかし、野生のマングースはなかなか捕らえることができないので、代わりに脳の構造が非常によく似ているオポッサムを使うことにしました。この動物も人間にはなかなか慣れ難く、刺激を与えると毎回同じような攻撃的態度を示します。そのように非常に獰猛であり、しかも脳の構造がよく似ているということから、あえてオポッサムを被検体に選んだのです。
この研究も、元はと言えば、新皮質とその下に隠れた古い脳組織との関連性に興味があったからです。ただし、当時研究の主流は、専ら連合野における機能的局在の問題で、BrocaやWernickeによる失語症の研究などを皮切りに、新皮質の中で運動野でも感覚野でもない、昔はsilent areaと呼ばれていた、すなわち、evoked potential が取り難いが、何か心理学でいう「連合」が起きているに違いないとの仮定から、「連合野」という名前の方が先に付けられた領域の解明でした。
先ず、前頭葉の連合野が高次の認知機能に関連するのではないかということから、真っ先に研究が進められました。ところが、後部の連合野については研究が大分遅れていましたので、私が学位論文の課題に採り上げることもできました。話が前後しますけれども、そのようにして知覚認知に関する後部連合野の役割と、更にそれらと視床(thalamus)との関連については少し解りかけていたものの、いわゆる辺縁系(limbic system)や、もっと脳の古い部分と情動との関係については、研究がさほど進んでいなかったので、あえてそれを取り上げようとしたのです。今では誰もが知っている海馬(hippocampus)や、脳の話で流行りっ子の扁桃核(amygdala)、更にそれに加えて梨状葉(pyriform lobe)などと情動との関係、特に凶暴性についての神経生理学的機序を調べようとしたのです。
このような関連性は、以前から「ロボトミー」によってもそれとなく示唆されていたことです。今では話題になることがほとんどありませんが、戦争中のこと、いつ何時鉄砲玉が飛んで来るかも分からない戦場では、恐怖心に耐えられなくなった兵士が発狂して、後方から味方を撃つ者まで出たのです。何とかして彼らを母国へ送り返さねばならないと、すなわち、無理やり「おとなしく」させる手段として、脳にメスを入れて前頭葉を切り離す「ロボトミー」と称する手術を、何と連合軍側でも同盟軍側でも、両方が行っていたのです。
ところが、この手術を受けると、内地へ帰ってからその人の性格がだんだん変わってしまうのです。アメリカでは「ハッピー・ベジタブル」というあだ名がつけられていました。つまり、もはや動物的欲求すら失われた状態なのです。後には施術部位を前額部眼窩回に来ている神経の最少部分に限定して、なお且つ同じ効果を示す「ロベクトミー」が開発されましたが、それでも、そこまで人格を侵害するような手術が、果たして倫理的に許されるのだろうかと問題になりました。この前頭葉の役割について早くから研究を手がけていたのが、先ほどお話しをした、チューリッヒ大学のアカート先生でした。後にウォーレン先生との共編で、The Frontal Granular Cortex and Behavior(1964)が出版されています。このように前頭葉の研究はどんどん先へ進んでおりましたが、後頭葉については研究が少し遅れてしまいました。
そこで、実験課題に視覚弁別学習と迷路学習とを採り上げました。ネコに明るさと大きさと形、それぞれの弁別学習をさせますと、どの個体でも正常なときは明るさの区別が一番やさしく、次が大きさ、最も困難なのが形と順序があり、後頭葉連合野を損傷すると、回復する順序もまた同じなのです。そして、明るさの弁別などは、術前よりもむしろ術後の閾値がより低く、刺激に対して一層鋭敏に反応しておりました。よって、連合野の新皮質は、興奮系よりも、むしろ抑制系の働きをしているという仮説を支持するわけです。
その頃、スタンフォード大学では毎週木曜日の夕方に教授と院生たちが集り、公開の研究会を開いておりました。招待講師のいないときには、学位論文の口述試験(defense oral exam.)を前にした院生たちに、練習のためにと研究発表の場が与えられておりました。ちょうど私の番のとき、フォード財団研究所に滞在中のウイリヤム・エステス(William Kaye Estes)教授がお顔を出して下さり、ネコの弁別学習が術後に回復していく割合と私なりの予測値推定式をご覧になり、「私のprobability theoryとよく似ているじゃないか。おまえは脳の中のどんな仕組みによって正解率が増えると考えているのか」と質問して下さった覚えがあります。通常の手続きではまだ弁別学習が成立していない場合、すなわち、反応率50%以下のサブリミナルな刺激でも、幾つかを組み合わせると、あたかも弁別ができているかのように見えるのですが、果たして脳内のどのようなメカニズムによるものか、と問われたのです。先生は、「研究室の窓からキャンパスの芝生を眺めていたら、ある年にタンポポが一つ咲き、次の年にはその数が増え、またその次の年にはと、タンポポがだんだん広がっていく姿から、あの公式を思いついたのだ」と内輪話を明かして下さいました。
なお、Journal of Comparative and Physiological Psychology に掲載された ”Visual defects resulting from prestriate cortical lesions in cats”(1962)をご覧になれば、先ほどの話がお分かりいただけるかと思います。要するに、脳は何も異常がないときに何ができ、損傷の結果、機能が一時的にどれだけ失われるのか。また、再度元の水準へ戻すことが可能なのか。そして、これらは決して脳の表層、新皮質だけの問題ではなく、脳全体のバランス、すなわち、深い部分との関係がどのように変化したかの問題ではなかろうか。今では大方の教科書が、また、テレビの講師たちも、脳を神経のネットワーク・モデル、つまり、神経回路説だけでしか説明しておりませんが、私にはどうしてもまゆつばものとしか聞こえません。もう少し違った見方ができないかという疑問から始まったのが、私の一連の研究でした。
またまた話が脱線してしまいましたが、妊娠から出産までの胎児期の役割については、古くからヘッケル(E. H. Haeckel)の法則、すなわち、「個体発生は系統発生を繰り返す」という反復説がありましたし、他方の発達の最終段階には、オルポート先生のいう「成熟したパーソナリティ」、すなわち、「人格の統合」という重要な課題があり、そこの最後に出てくるのが「価値志向」の問題です。この両端をうまくつなげて考えてみたいというのが、かねてからの私の願望と言ってもよいでしょう。したがって、片方で動物の実験をしながら、やはりもう一つの課題への関心からも抜け出すことができませんでした。
原谷達夫先生の訳本から、オルポート先生がハーバード大学におられることを知りましたので、Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality(1955)が出版されたときには、早速翻訳をさせていただきたいと先生に申し出で、ご承諾を得て訳しておりました。そして、サンフランシスコのAPAにお見えであった佐藤幸治先生にお話ししましたら、「その翻訳を貸してくれないか。京大の学生たちに見せて討議させたいから」と、日本へお持ち帰りになりました。ところが、しばらくしたら、何時の間にか他の人の訳書が出てしまったのです。そのことをオルポート先生にお伝えしたら、「日本の出版社が、あなたに翻訳権のあることを無視したのだろう。そのお詫びにこれを」と、サイン入りの新刊書 Personality and Social Encounter (1960)が贈られてきました。そこで、帰国後早々に、星野命先生や学生たちと一緒に翻訳にとりかかり、「日本版への序」を加えた『人格と社会との出会い』(誠心書房1972)を出版しました。後にオルポート先生を一度ICUへお招きしようとしましたら、「ハーバード大学の学部長職最後の年なので、今は海外へは出かけることが無理だ」とのことで、非常に残念に思いました。その後、しばらくして、奥様から先生がお亡くなりになられたとの報せを受け、渡米中の星野先生がボストン郊外のお墓へお参りして下さいました。
まだスペリー先生に関連する話が少し残っておりました。最も高次の心理学的機能として、言語の問題があります。そして、それが不思議と脳の左半球に限られている。では、右半球は一体何をしているのか。私も脳波やタキストスコープを使ってこの種の研究をしてみたのですが、研究方法がつたなかった所為か、それとも実験装置が悪かったためなのか、スペリー先生や東京医科歯科大学の角田忠信氏の言うような結果がなかなか出ないのです。
角田さんの研究がアメリカでも話題になり、日米共同でシンポジュームを開こうではないかと、私にも企画委員の声がかかってきました。しかし、「私自身には追試がうまくできなくて困っている」と伝えましたら、向こうの連中も皆、「自分たちもそうなのだ」と言うのです。それで結局、この案はおじゃんになりました。
持論を繰り返して恐縮ですが、私にはどうしてもモザイク流の脳モデルが納得できず、もしも生き物が何かの障害にぶち当たれば、仮に一時は退行しても、必ず再びバランスを取り戻し、更に一層伸びようとする力が生み出されるに違いない。そして、そのことが説明できるようなモデルを基にしてこそ、障害児に対する実践的な支援活動の方法を工夫することが出来るのではないだろうか、と考えていたとき、ジェーソン・ブラウン(Jason Brown)教授の Mind, Brain, and Consciousness : The Neuropsychology of Cognition(1977)という本に出会い、早速著者に許可を求め、訳書『認知と言語の神経心理学』(新曜社1979)を出すことになりました。彼は精神科の医者で、アルツハイマー病やピック病などの患者を診察しながら、それらの症状を新皮質の機能が障害を受けて、古い部分の脳の働きが表に現れた姿としてとらえ、そこから治療の方法を工夫していた人なのです。
また、ちょうどこの頃、宇宙工学の専門家であるカール・セーガン(Carl Sagan)博士の The Dragons of Eden(1977)が出版され、それが私の背中を強く後押ししてくれました。脳の進化を基に人間の知性を論じており、両者には共通点をたくさん見出すことができます。そのような本を訳させてもらいましたが、実はその前まで、私も一時は分離脳の話を真に受け、ヒトの脳半球の左右差についてまで、得意になって盛んに本に書いたり、ビデオの教材を作ったりしておりました。
インB ええ、それは、大内先生や金子先生が監修されたビデオですね。
原 はい、「文映教育映画社」のものです。(『大学講座用 現代心理学編 第一部 第5集 大脳機能の側性化』)
インB はい、入っています。これはまた、確か最近新しいDVDで見られるようになったと。
原 そうですか、本当ですか。しかし、もう一度見たら、恐らく冷や汗たらたらでしょう。人様の話も自分の目で確かめてみませんと、何時までも悔いが残ります。
インB ええ。一つ二つ、よろしいですか。どこかにあったと思うのですが、Corsiniのencyclopediaに、先生のお名前がありますね。
原 はい。しかも、ハウロー先生の記事の直ぐ前に載せてもらえたので、大変うれしかったです。
インB 私も、これに載っている日本人というものをずっと調べたことがあるのですが、それで、書いてあるところには名前があるのですが、あるところとないところとありまして、つまり、かなり上の方で選ばれているのですが、これは先生に、この文書自体はこれでいいのかという、校正のようなものが来るのですか。
原 確か編集者からの誘いに応じて、まずこちらの言いたいことを箇条書きにし、向こうからの素稿に手を加えて送り返しました。ですから、多分に自画自賛のところがあると思います。その上、当時は、自分の専門領域を社会心理と生理心理の二つに分けておりました。
インB つまり、これはご本人がきちんとチェックしているのですね。
原 はい。ゲラが届き、目を通して最後にオーケーをした覚えがあります。
インA ありがとうございました。では、続いて、学会でのお仕事について、何か他にありましたら。
原 私は学生時代を海外で過ごしましたので、日本の学会とはご縁がなく、原谷達夫先生以外には誰も知り合いがおりませんでした。しかし、いずれ将来帰国したときには、何とか心理学者のお仲間入りをさせてもらいたいものと、図書館で時たま届く『心理研究』を見ることを楽しみに、また、お小遣いを溜めては目に入る図書をせっせと日心の事務局へお送りしておりました。当時の学会誌は縦書きで、巻末の会務報告の中に寄贈本のリストが載せられており、その中に見覚えのあるタイトルを見つけると、会員でもないくせに何かしらお役に立っているような気持ちになり、内心大層嬉しかったものです。帰国後に事務局長の八木冕先生へ「本を送っていた者ですが」と申し上げたら、先生にはご記憶が全くなく、大変がっかりいたしました。でも、後になって、これらの本を借り出して読んだことがあると言う方に出会い、やっと救われた思いをしたものです。
話を戻して、この学会での仕事として最も誇りに思うことは、大山正先生の下で会誌の編集委員を務め、そして、『執筆・投稿の手びき』の改訂に2度も参加させていただけたことです。ご存知のように、投稿論文は、まず編集委員長が課題に関係の深い領域の委員へ配り、その方から最初の審査者が複数推薦され、もしもその人たちの評価が異なれば、更に次の審査者へ回すことになります。もちろん、評価は全て匿名でなされるものの、どうしても審査者の人選が編集委員の考え方に近いところへ固まりがちです。そこで、「公平を期するために違った見方の人を加えるように」、また、「英文アブストラクトやJPRの英語がアメリカ流なので、英国流のスペルも許容するように」とか、私自身の似たような苦い経験から、いささか苦情めいたことをしばしば申し上げ、委員長の大山先生を悩ませたのではないでしょうか。このことが、編集委員時代の想い出として、今でも強く私の心に残っております。
そして、『手びき』改定のときにも、委員の一人に加えていただけたことは、非常に光栄で何よりうれしく思いました。当時、内外の学会で、この種の変革が起きておりました。アメリカではAPA方式と、もう一つはChemical Abstract誌の方式とが張り合っており、どちらのマニュアルで学生たちにレポートや論文を書かせるのかが議論されていた時代です。理系では後者を選ぶ方が多かったのですが、APA方式にも学ぶべきところが幾つもありました。最も強調されていた点は、会員の納める会費で出版費がまかなわれる以上、いかにして限られた紙数の中にできるだけ多くの重要な情報を載せ、その効用を広く読者に還元すべきかということが、編集委員たちの責務と言われておりました。したがって、まず論文の長さを、ショート・ペーパーなら何ページ、ロング・ペーパーなら何ページと定め、「イントロダクション」をやめ、論文の最初の節にできるだけ簡潔に、しかし、その研究課題がどのような流れの中から生まれたものか、問題点の意義について必ず明記するように。すなわち、読者に内容を正確に把握させた上、更にその研究を発展させることが可能になるように、と指示していました。そこで、多くの大学が、心理学専修以外の学生たちへもAPA方式を基にレポートの書き方を指導しておりました。
ちょうどその頃、技術革新の波が押し寄せ、心理学の実験でも、ナノメーターなどの細かいスケールが必要になってきたので、大山先生は一生懸命、それへの対応にご尽力下さいました。そして、吉田正昭先生は常にカメラを持参され、事ある度に資料や関係者の顔を写真に撮っておられました。先生の記録写真は、学会として真に貴重な資料ではないかと思われます。そして、会誌の編集作業に当っては、裏方として事務局の久野洋子女史に大変お世話になり、今でも深く感謝しております。
それから、学会に関連して必ず思い出されるのは、1972年に品川のプリンスホテルで開催された第20回国際心理学会議(ICP)に、プログラム委員の一人として加わったときのことです。実はその前に岡部先生がICUを退職なされ、代わりに東大から梅津八三先生を研究室にお迎えしておりました。何分にも先生は、独自の手法で三重苦の障害児を訓育なされ、その実践的経験を基に比類なき壮大な理論体系を構築なされた方です。その梅津先生が、この国際会議の間際になって、日本人では唯お一人の特別招待講演者に選ばれました。そこで、そのための原稿をお借りして翻訳をし、夏休みの間に何度か鎌倉のお宅へ伺っては、訳文をチェックしていただきました。先生独特の言葉遣いや難しい用語が随所に出てきましたが、例の『心理学事典』にも、また、他の辞書の何処にも載っていなく、素養のない私は大変苦労しました。しかし、この時に垣間見た先生の真摯な研究者としてのお姿には、本当に深い感銘を覚えました。そして、ご自宅へお邪魔する度におそばをご馳走になり、実は先生ご自身が打たれたものだと奥様から教えていただいたことも忘れられません。
いよいよ、特別セッションでご講演をなさるに際には、私が拙い英語で通訳をさせていただきました。先生はお話しの冒頭で自作の映画をご披露され、「見えない・聞こえない・話せない」子供がどのように手探りでおもちゃの弁別をしていくのか、その学習のプロセスをご自分の理論に添って克明に説明なさいました。そのために時間が大層かかり、予定の時間が大分過ぎてしまいましたので、甚だ失礼なことを承知の上、「先生、そろそろ終りにしていただけませんか」と申し上げ、大切なお話しの最後を尻切れとんぼにさせてしまったのです。国際会議の場であったとは言うものの、あの時の私の杓子定規な振舞いは、想い出す度に今でも本当に申し訳なく思えてなりません。
後日、先生の納骨式のお墓まいりの折に東大の方から、そのときに通訳するため用意した英文の原稿が、先生を学士院会員にご推挙する際に必要とされた外国語の論文として使っていただけたとお聞きし、あのひと夏の努力は決して無駄ではなく、多少なりともお役に立てたということが判って、やっと自分を慰めることができました。
インB はい。鳥居修晃先生が梅津先生のお弟子さんで、前に、「梅津先生は、なぜ戦前に日本語でもあまり発表しなかったのでしょうか」とお伺いしたことがあるのです。そうしたら、鳥居先生のお答えは、「あの先生の哲学で、心理学者がそんなことよりもデータを集めるべきである」とおっしゃったということを聞きました。
原 そうでしたか。いかにも、梅津先生らしいお言葉ですね。
原 そのような思い出深いICPですが、このときに参加者へ配られた英文案内資料 A Guide to Psychological Institutions in Japanの冒頭には、‛We may say that Japanese people traditionally are psychologically oriented.’ と書かれてありました。それが外国人たちの目に留まり、事務局にいた私を捕まえて、「ここに書いてある『万葉集』や『古事記』と心理学との関連を詳しく話せよ」と説明を求めるのです。いやはや、日本人でありながら即座にうまく答えられず、大層恥ずかしい思いをさせられました。日本人特有のメンタリティーについては、私自身が大きな関心を抱いていた筈でしたのに。
実はサンノゼの学生時代にも、一般教育科目で「哲学」を受講した折、テキストの中に鈴木大拙氏の「Zen(禅)」が出てきたので、「おまえは日本人だから説明をしろ」と言われたものの、何も話すことができなくて顔を赤くしました。これから留学を志す人々には、是非とも私たちの文化が宿す psychologically orientedな特質とは何か、人前で話せるようになっていて欲しいものです。
この品川のICPの後、1974年には犬山と名古屋の両市で国際霊長類学会が催され、サルの実験をしていた関係から、ICUの教え子たちが大いに活躍をしてくれました。そして、1975年には、日本学術会議の企画で国際環境保全科学会議が京都宝ヶ池の国際会議場で開催され、内外の生物学者や都市工学などの人々を前に、私にも心理学を代表して発題の機会が与えられました。「このかけがえなき地球環境を保全していくためには、すなわち、当時の流行り言葉『ハッチなき宇宙船』の中で、われわれ人類は今後どのような営みをなすべきか」という課題です。そこで、あのヒルガード先生の宇宙飛行士のストレスを軽減させる研究や、サンノゼの人種偏見の調査を思い出しました。そして、しばらく後の1985年には、アリゾナ大学で開催された日米環境学共同会議に参加するため、早稲田大学の相馬一郎先生や建築学の研究者たちと一緒に、相互交渉心理学(transactional psychology)のイッテルソン(W. H. Ittelson)教授のところへも出かけました。
さて、私が学術会議の連絡委員をしていたときに痛感させられたことは、よその分野の学会とならばまだしも、恥ずかしいことには、心理学と名の付く学会の間で、仲があまりよくないのです。そこで出来ることなら近い将来、APAのように、日本心理学会の大きなアンブレラの下に臨床心理や教育心理や社会心理などなど、諸々の学会を招き入れたい。今直ぐに実現させることが難しくても、来年のICPを絶好の機会と捉え、学会幹部の方々のリーダーシップによって若い会員たちの意識を是非ともそちらの方向へ向けさせられないものだろうか。これは私の長年の夢であり、大げさに言えば学会への遺言です。
そして、同じく気に懸けてきた問題は、カリキュラムのことです。昨年『大学教育の分野別質保証のための 教育課程編成上の参照基準 心理学分野』という文書が公開されましたね。すなわち、学部における心理学の授業について、どのような配慮が必要か、ということです。今の認定心理士の資格を決める際には、最低38単位、五つの領域から必ず三つ以上について学ばせました。もう一度、じっくり検討する必要があるでしょう。
先ほどお話ししたように、私が在籍していた頃のスタンフォード大学では、六つの領域から主専攻と二つの副専攻を選ばせられましたが、もしも心理学の全分野について勉強しておきませんと、最後の口述試験の折に、あたかも指導してきた教授の手落ちのように、その先生を前にして他の審査者からうんと油を絞られるのです。これは大学院での話ですが、学部の学生たちへも、似たようなガイダンスが行われておりました。
ところが、私自身は、これまで教養課程の「一般心理学」、またはそれに類する授業科目の中で、果たしてそのような配慮を充分してきたのかどうか。既に手遅れながら、大いに反省しています。ついつい自分の得意なことばかりを講義してこなかっただろうか。専攻生がお相手ならば、それも許されるでしょう。しかし、一般の受講生の中には、心理学に二度と接することのない者も少なくないのですから、下手をすると彼らに、「心理学とはこんなものだ」と偏った見方を与えて一生を過ごさせてしまいます。そこで、授業についても、もっと工夫をしなければなるまいと、ついついカリキュラムの問題にまで口を出してしまいました。これは決して学生たちにおもねる気持ちからではありません。大学教員の多くは学生たちを教えることによって、自分の好きな研究活動が許されているのだから、もう少し彼らのことを念頭に置かねばなるまいと云うことです。
ところで、何もわざわざ「心理学」と呼ばなくても、生き物について勉強している中学生や小学生たちに、もっと早くから「こころ」の問題へ関心を持たせてもよいのではないでしょうか。実は私が最初に「こころ」について多少とも考えたのは、確か4歳の頃でした。叔母の葬儀の後、彼女に会いたいと、布団の中で一生懸命鼻をつまんで息を止めようとしたことがあります。とうとう苦しくなって諦めましたが、理科の授業で魚やカエルの解剖をした際には、必ずこの時のことを思い出しました。その後いろいろと紆余曲折を経ましたが、きっとそのときの体験が後に私を心理学へ進ませたことへの原点だったかも知れません。
心理学の授業で私が真っ先に学生たちへ尋ねることは、果たして単細胞の生物に「こころ」があると言えるのかという問いです。心理学ではゾウリムシの行動があまり話題にされませんね。プラナリアについてはどうでしょう。あれは体の構造がもっと複雑で、上下半分に切り離せば、それぞれが再生し、どちらに記憶が残っているかを問うことができますが。
私の学生時代、シカゴ大学にゾウリムシの研究している若い心理学者が一人おりました。シャーレーの中にゾウリムシを入れて虫眼鏡で観察すると、最初はガラスの壁にぶち当る度に同じ角度で反対側へ泳いで行きますが、その内にだんだんと壁に当たらなくなる。まだ神経組織のない単なる単細胞が立派に「行動の変容」、すなわち、「学習」をしているように見えるのです。このように外部のものに触れたとき、生物学では細胞膜の物理的・化学的反応として説明するでしょう。もしもその物質と同化できるなら、膜が薄くなり、よって中の細胞液が移動して周りを取り囲み、最後は細胞液が分解する。言い換えれば、刺激に「なじみ」があれば触れ合い、あるいは食い物にし、さもなければ避けて遠ざかる。これは決して唯物論や還元論を主張するわけでなく、心理学用語の「感覚」「知覚」「認知」「性格」「態度」「価値観」などなど、ひいては「いのち」と「こころ」の源、およびその働きの本質を、先ずは単細胞から学ぶことができないかと言う訳です。そして、このような質問をする理由は、後に、受精卵から胎児期を経て、更に出生後の長い長い生涯に亘る成長発達の過程を繋げて考えるための布石に他なりません。
もちろん、フロイトの「無意識」は、ダーウィンの「進化論」と並んで20世紀の二大発見の一つと称せられるくらいですから、私たちは大いに敬意を表すると共に、彼が描いた「イド、エゴ、スーパー・エゴ」の図が、もともとは女性の子宮や脳の形を模したものだったということからも、心理学はもっともっと生物科学と一緒になって「ヒトの特性」を研究せねばならないし、そのような授業ができないものだろうか。そうすれば、子供たちにも理解され易いし、世の中の心理学に対する関心がもっともっと高まるだろう、ということです。繰り返しになりますが、大半が心理学以外の専攻生たちを相手に授業をしてきた人間の正直な感想なのです。本当に心理学を専門にしたいと考える学生は、放っておいても自分で勉強してくれますからね。
もう一つ付け加えてお話ししたいことは、これは心理学に限らず、大学の先生たちがどのように教えるのか、いわゆる「教員の資質開発(faculty development:FD)という課題です。1981年の1月、中曽根内閣のとき、臨時教育審議会の公聴会へ私が呼ばれた際に、「このような言葉がアメリカにはあるのだが、日本の大学の先生たちへ、立派な『研究者』への意欲と共に、『教育者』としての自覚をもっと高める必要があろう、と提言しました。なぜなら、小学校・中学校・高校の先生たちは、そのような訓練をきちんと受けているのに、教員免許状なしに教壇に立っているのは、大学の先生たちだけなのです。そこで、私たちが自発的にそのような場を作ろうではないか、というのがこのFD活動です。今から30数年も前のことですが、これがまた物議をかもしました。
実はその少し前に、かつてヨーロッパ旅行でお供した早稲田大学の村井資長総長先生が、私立大学連盟の大学問題検討委員会で「大学の自己点検」を研究課題に取り上げ、私をその主査に指名して下さいました。これまで教育改革の名の下に数々の試みがなされてきたけれども、一度大学の活動全般について自分たちでじっくりと点検し直す必要があろう。それは今までのように外から視学官が来て評価するのではなく、私たちが自ら進んで日頃の仕事振りを顧み、同僚の教職員や学生たちへも協力を求め、そして、更に学外の人々、特に私学の場合には後援者たちへもレポートできるような、実践的な手法を考えようということでした。ところが、それが教育学者からは「胡散臭い」と言われたり、また、国立大学協会あたりへ伝わると、何時の間にか「自己点検」が「他者評価」になってしまったりするのです。それは決して私の本意に添うものではありません。
インB 一ついいですか。いろいろ前後することもあるのですが、ぜひお聞きしたいことがありまして、一つは、先生の所属学会です。資料には,日心、基礎心、生理心理などの学会の役職が書かれていますけれども、心理関係の学会ですと、それ以外にどこか入られていましたか。
原 岡部先生がいらっしゃいましたから、当然のこととして、日本に帰ってきたときには応用心理学会にも、また、教育心理学会にも入らせていただきました。
インB そうなのですか。APAは会員でいらっしゃる。
原 今はforeign affiliateです。その他に、数理心理学会にも一時入っておりましたが、そこでは私たちの用いる数値が一体どれだけの心理学的リアリティを秘めているのか、ということに拘りました。最も多く口出ししていた事柄は、テストの妥当性と信頼性の検証だったと思います。相関係数にはどこまで誤差を入れて検討すべきかなど、むきになって詰まらぬ議論を何度かいたしました。それから、小数点何桁までが有効な数字なのか。5桁も、6桁も、コンピュータが打ち出す数字をそのまま論文に載せている人がいるでしょう。心理学で用いる検定法ならば、それぞれが何桁までの数値で十分か、学生たちにきちんと説明しておきませんと、市販の計算プログラムが出す数字をそのまま平気でペタペタ貼り付けてしまいます。
私が指導を受けたマッケンマー先生は、因子分析の権威でもあり、私の就職推薦状には、彼の下でそのような勉強をしたとわざわざ書いて下さいました。その先生がAPAの会長に選ばれた折、就任講演の中で、幾つもやたらと数多くの因子を並べることに一体どのような意味があるのか、と疑問を投げかけ、大きな波紋を呼び起こしたことがあります。あのチャ―ルス・オズグッド(Chares E. Osgood)教授も、語彙分析法(semantic differential method)では「力量(potency)」「活動(activity)」「評価(evaluation)」の3次元に留めました。これなら誰にでも容易に意味空間のイメージが作れます。因みに一言付け足しますと、オズグッド先生が国連の平和親善大使として来日された理由は、仮に言語が異なっていても、この意味空間の上でコミュニケーションをすれば、世界中の人々が互いに理解し合えるだろう、ということでした。また、大山正先生のご研究では、日本人の色彩感覚がただ一つの評価因子には収まりきれないので、どうしても下位尺度(subscales)を設ける必要があるということから、国際的に大きな注目を浴びたのでした。計算機任せにやたらと数多くの次元を並べ立てるのはいかがなものかと、数理心理学会の研究会で言ったことがありましたが、マッケンマー先生の受け売りと云いますか、私もその血を引いてしまったようです。
思い出したのでついでに申し上げると、岡部弥太郎先生が東大からICUへ移られたとき、真っ先に丸善を通して、いわゆる古典的な実験器具一式をお揃えになられました。いわゆる、ブラス・インスツルメントの類です。たとえば「ダルトン・スティック」、あれは単なる真鍮の棒に過ぎませんが、縦にして一箇所を握らせて、次にまた握り返させ、棒の落下した距離で反射速度を計ります。これなら誰にでも眼で見て肌に感じることのできる測定値です。その棒も今回の話題にできないかと思い、研究室の許可を得て昨日倉庫を覗いてみましたが、残念ながら見当たりませんでした。
もう一つ思い出すことは、話が戻りますけれども、入学試験の採点についてです。最初の年は学内の寮生たちに徹夜で採点作業を援けてもらいましたが、何回チェックしても、なお間違いが起こり得るのです。そこで、次の1962年には、人事院の地下室にあった磁気式採点機を使わせてもらい、芯に鐡粉の入った鉛筆でマークシートへ回答させる方法を導入しました。試験の終った後で、こっそりと解答用紙をタクシーに積み込み、深夜に三鷹から霞ヶ関まで急行して、一晩中読み取り機械を回しました。次に採用したのがIBMのパンチ・カードでした。あれは普通の鉛筆でマークしても、自動的に穴を開けてくれます。それで、先ず水道橋にあったIBMの本社で採点した後、日本橋のコンピュータ会社で受験者個人個人のプロフールを印字させました。それは1965年頃のことで、これが一つのモデルとなり、あちらこちらの大学が真似をするようになりました。
なお、高木貞二先生の能力開発研究所には大型の採点用機械がありましたが、あれは私がシカゴの米国科学研究協会(ASRA)とプリンストンの教育検査サービス(ETS)を訪問したときにカタログを手に入れ、ICU出身の中山和彦氏が能研所員に採用されたとき日本へ取り寄せたものです。それが後に入試センターへと受け継がれました。以上が数理心理学会に関連する事柄でしょうか。
インB 先生も最初の頃、知能検査をしていたというお話を聞いて興味を持ったのです。大体、結構一般的に、学校の生徒を対象に知能検査をやるということは、心理学者は、それを取って、どうしたのですか。
原 テストをする側として、採点の結果はそのまま依頼された学校へお返しをし、利用の仕方はその学校にお任せしました。多くの場合、普通の授業についていけそうにない子を見つけ出し、どのような手当てをすればよいか考えるためでした。ただし、昔の偕交社、追手門学院などにはお金持ちの子弟が多かったですから、将来の進学に備え、早くから特別な教育をするためのクラス分けを考えていたのではないでしょうか。ついでにもう一つ、岡部弥太郎先生について付け加えますと、先生は戦時中、海軍兵学校の入試に性格検査を使おうとなさいました。それは、「淡路円次郎・岡部弥太郎式向性検査」として名が残っている内向性・外向性の検査です。海軍兵学校では、学力のみならず、将来の海軍士官としての望ましい人格特性を検査するため、岡部先生に性格検査の開発を依頼し、そこで、戦時中も「淡路・岡部式向性検査」の改良を続けておられたそうです。これは私が帰国して間もなく、先生から直々お伺いした話です。「ああ、君は海兵にいたのか。私もあそこではそんなことを考えていた。しかし、そのうちに他の検査が出たので止めにした」とのこと。矢田部ギルフォード性格検査が出てきた時点でしょうか、確かあの中には向性尺度が二つ入っていましたね。それで、「もう私のものは必要がなくなったと思った」と、極めて淡々としたお口振りでした。これは小田原の温泉プールで先生と一緒に泳ぎながらお聞きした話しです。
インB すみません。ヒルガードはどのような人なのですか、アーネスト・ヒルガードは。
原 はい。先ほどの写真のように、それからご自分でヒプノーシスをなされていたような方なので、非常に温厚な先生でした。ゼミなども極めて和やかな雰囲気で、多元的な見方を大事にされ、学生たちが主張する、ときには突拍子もない考えをも、一応は聞き入れて下さいました。そして、最後に、「おまえは、それと他の考えとをどのようにインテグレートしたいのか」と訊ねて下さるような指導を受けました。ですから、当時はスキナリアンが幅をきかせてきた頃ですけれども、古典的条件付けも、またゲシュタルト的な意見も交わされており、トールマン先生のところの院生たちまでも指導しておられました。そのトールマン先生は、バークレーの構内にあるライフ・サイエンス・ビルの上の階におられて、私たちの出入りも許して下さいました。スタンフォード大学とカリフォルニヤ大学の間では、カリキュラム上の交換ばかりではなく、私の在籍中たった一度だけでしたが、共同でテストを行ったこともありました。教授同士が相談して共通のテストを作り、両校の院生全員が受けさせられました。どちらの研究室が、どの面で強く、どの面で弱いのかを調べるためでした。そこで、私は、ヒルガード先生に、「今回のテストが全然できなかったので、私のためにスタンフォードの平均点が落ちてしまい、誠に申し訳ありませんでした」とお詫びしたことがあります。あの当時もスタンフォードとバークレーとは、交流しながら互いに強いライバル意識を持っていました。
インC ヒルガードの教室の催眠の話がでましたが、ヒルガードの催眠の誘導の仕方について、何か覚えていらっしゃいますか。
原 被験者のタイプによって、非常に入りやすい人と、なかなか入れない人がいましたね。いや、申し訳ないことに、細かいところまではよく覚えておりません。けれども、要は最初に、「気持ちのいいものだ」ということを納得させることに努力しました。「決して怖いものではない。本当に気分の良いもので、素直になれば自然と誰にでも起こるものだ」ということを充分納得させてからです。もちろん、場合によっては危険が伴うことも重々承知の上でしたが。その当時、私はあまり頼りになる学生ではなかったようです。あの学習心理のヒルガード先生が、まさか、そのようなことをなさっておられるとは夢にも考えておりませんでしたので。
インA では、長い間、どうも、ありがとうございました。